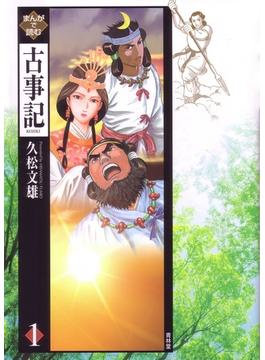まだまだ知らないことばかり
2010/02/13 18:55
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kumataro - この投稿者のレビュー一覧を見る
まんがで読む古事記(こじき) 久松文雄 青林堂
古事記は、西暦712年につくられた書物となっています。神話という扱いなので、読む前にとっつきにくさを感じたため、まんがで読むことにしました。しかし、予想に反して、最古の写本が先日訪れた名古屋市にある大須観音に保管されているとか、神がつくった最初の島が淡路島とか、内容はたいへん身近なもので楽しめました。日本国土の形成過程では、古事記にこんなことが描いてあるのかと「へーえ」と感心した次第です。
物語が壮大に広がっています。そして素晴らしい創造力です。男女の性別は、人間を語るうえで切っても切れない項目なのでしょう。
神さまがいっぱい。神さまだらけです。
やまたのおろちを退治したのは、ヤマトタケルノミコトだと思っていました。天照大神(あまてらすおおみかみ・女性)の弟である建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)でした。この本はあらすじなのでしょうが、新鮮でした。50年間生きてきて、まだまだ知らないことがたくさんあります。仕事ばかりをしていると仕事以外のことは知らない人になります。何でも知っているような顔をして、結局、何も知らずに死んでゆく。そんな人生は送りたくはない。最近そんなことを考えるようになりました。
まんがで読む古事記 1
2012/06/16 14:23
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のんびり屋のカユ - この投稿者のレビュー一覧を見る
3巻まとめた上での評価。残りの2巻はこちら。
http://www.junkudo.co.jp/detail.jsp?ID=0111456514
http://www.junkudo.co.jp/detail.jsp?ID=0112559217
原典に忠実であることを目指して書かれた古事記のマンガ。
故に性的描写が特に1巻は多い。
スサノオの扱いが、他よりもかなり酷いのも気になる。
2巻は主に大国主に関わる話で
3巻は大和朝廷が勢力を拡大していく話
この辺りは鉄板で、特に優劣がつけにくい
原典に忠実で、話の繋がりがよくわかるように描写されているが
内容から考えて読者の対象年齢は少し上げざるを得ないのが現実か。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:666 - この投稿者のレビュー一覧を見る
特別変な改訂もなく、伝わっているとおりの古事記を読むことができると思います。原典を読む前に参考になる本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
@yonda4
日本人のルーツって何?
古事記を読んだら少しはわかるだろう、と。
でも、いきなり原文なんか読めないよな~、という軟弱ものは漫画から入りました。
それにしても、八百万の神々とはよく言ったもので、色々な神様がでてくるでてくる。
最近では、トイレにも神様いるんやでって歌ってるからね。
入門書としてはいい本ではないかと
投稿元:
レビューを見る
子供の頃、松谷みよ子さんの「日本の神話」を読んだ。同じ本を本屋で見付け、40年前の本がそっくりそのまま出版されていることに感激しつつ、子供のために購入。
ところが、我が家の凡児は良く判らなかった、と云う。イザナギ、イザナミ、アマテラス、スサノオ、オオナムチなど、主要な神様さえ押さえれば良いんだからと云ってもピンと来ない様子。
このマンガ、本屋の昔のマンガ家コーナーで見付た。スーパージェッタ―やガボテン島も描いている人らしい。でもそのマンガを読んだ記憶は無いなあ。テレビマンガを雑誌用にリライトしたのかな。後で、もう一度確認すると、風のフジ丸も描いたらしい(原作は白土三平)。それなら、読んだ記憶がある。
絵は子供にも分かりやすく、すっきりした印象。沢山の神様を手を抜かず、判り易く描き分けている。3巻まで買った。ヤマトタケルはまだ登場しないので、4巻目の発売を待っている。
投稿元:
レビューを見る
古事記は正史ではない。
古事記を学校で教わったような記憶はないのだが、読んでみると以外にしっているところが多かった。
「国生み」伊耶那岐神と伊耶那美神が矛をどろどろとした大地に突き立て、引き抜いたときに矛から落ちたものがはじめて出来た日本の島。
「神々の誕生」女から声を掛けて交わったときに生まれたのが骨の無い蛭子。蛭子は海に流された。次に男から声を掛けて交わったとき神々が生まれた。神々を生み続けた伊耶那美神は火之迦具土神を産み、火傷をして死んでしまう。それに悲しんだ夫、伊耶那岐神は火之迦具土神を殺してしまう。
「黄泉の国へ」伊耶那岐神は伊耶那美神を追って黄泉の国へ行くが、そこでウジ虫のわいた伊耶那美神を見てしまい。恐ろしくなって逃げてしまう。そして伊耶那美神は日本に呪いを掛け、一日に千人の命を奪うといい、それに対し、伊耶那岐神は一日に千五百人の子を生むと返す。それから日本では一日に、千人が死に、千五百人が生まれている。
「天の岩屋戸」天照大御神は岩屋に引きこもってしまい、世に太陽がささなくなった。そこで八百万の神々は岩屋戸の前で楽しげな宴を行った。天照大御神は気になって外を覗いた。そこには自分と同じくらいの尊い神の姿があった。近寄ってみて見ると、それは自分が姿が八咫鏡に移っているだけだった。騙されたと思い岩屋に戻ろうとしたところ、ほかの神がその岩屋戸を占めてしまった。それから八百万の神々は騙したことを詫び、また世に治めて下さるように
懇願し、今日も太陽の日は日本に行きわたるようになった。
「山俣の大蛇」高天原を追い出された須佐之男は下界で山俣の大蛇に苦しんでいる人に会い、その生け贄である櫛名田比売に恋をする。そして、須佐之男は山俣の大蛇を倒すことを決意する。生け贄の周りに酒を用意し、山俣の大蛇が酔いつぶれたところを頭を一つ一つ潰して行った。そのとき、山俣の大蛇の体内から出て来たのが天叢雲剣。別名草薙剣といわれる。
学校などで教わったことはないが、子供の頃に見ていたNHK教育の人形劇などで見た記憶がある。
正史ではないため、重要視されないところはあるだろうが、日本のルーツがあるのがこの古事記だと思う。
しかし、改めて古事記をみると、奇形児が生まれたから海へ流したり、妻を殺されたからと我が子を殺したりと、そういった単純に美しいとは言えない行動もあるんだな。
投稿元:
レビューを見る
古事記編纂1300年なので、漫画で読んでみました。出雲のほかに野洲川、淡路島など行ったこと、住んだことがある場所が出てきて親しみを感じました。黄泉の国への入り口とされる黄泉比良坂に行ったことがないので行ってみます。
投稿元:
レビューを見る
こんなときだから日本の国の成り立ちの神話を読んでみた。
たくさん名前がでてきて一つ一つは覚えられないけど流れは理解しやすい。
なかなか美しい神話で読みやすい。
たくさんの神々がうまれ、あらゆるものに神が宿っている考えはこれが起源なのかな?
それにしても昔から山、川、海、木、岩、火、水、日、月、鉄、稲、雷などなど身近なものひとつひとつそれぞれに神がいたとは驚き。
いまでも日本的な和の心は遺伝子に組み込まれているんだろうな~。
学校の歴史で年号覚えたりするんじゃなくってこういう歴史的な背景をちゃんと教育したほうが日本人にとってためになると思う。
子供のときに民族の神話をまなばなかった民族は必ず滅びるとも言われるし。
まじで。がんばろう日本!
投稿元:
レビューを見る
お試し読んで買ってみたのですが。
イザナギ、イザナミは美形で言うことなし、死者になってもイザナミは美人(笑)
(人見先生版はなぜか山姥でしたが・・・w)
人見版とどちらが好きか、と聞かれると迷うんですよね。
久松先生は、あくまでもコミックとして描いてますし。
それよりもスサノオのごつさが生理的に受け付けません・・・。
おもしろいんですがねw
投稿元:
レビューを見る
古事記の漫画の中では詳しく書いてある。神道文化賞を受賞している。神様の名前が1回しか読み仮名が付いていないのが残念。他は良い。