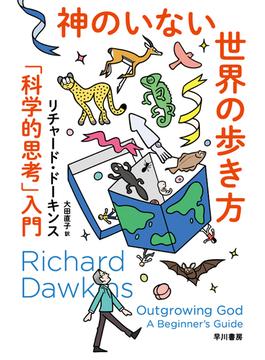攻撃的な無神論のすすめ
2023/05/29 13:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:R - この投稿者のレビュー一覧を見る
一神教的な神をゆるく信じている人への説得の書。
著者は非常に攻撃的な無神論なので、人を選ぶだろう。
信仰心の厚い人が、この本を手に取り、納得するかは疑問ではある。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
超自然的な神と宗教の否定を、不可知論と無神論、カーゴカルト、神の妬み、時代の空気、自然淘汰による進化と経済的バランスといった話題を通して、人間が善良であるために神は必要ない、決める権利は我々にあると断言している。
投稿元:
レビューを見る
リチャード・ドーキンス(1941年~)は、英国の進化生物学者・動物行動学者。一般向けの著作を多数発表しており、存命の進化生物学者として、最も知名度の高い一人。
1991年発表の『The Selfish Gene(利己的な遺伝子)』で、「生物は遺伝子によって利用される"乗り物"に過ぎない」という比喩的表現を使って、「自然選択の実質的な単位が遺伝子である」とする遺伝子中心視点を提唱したダーウィニストであり、科学的合理主義の推進者である。また、科学的合理主義の推進者であることと表裏一体ともいえる、徹底した無神論者・反宗教主義者であり、科学的精神の普遍性と反宗教を説く啓蒙書として2006年に出版された『神は妄想である』は、30を超える言語に翻訳され、最も有名な一冊となっている。
本書は、『Outgrowing God:A Beginner‘s Guide』、即ち、「神を卒業するためのビギナーズガイド」の全訳として2020年に出版された『さらば、神よ』を、改題の上、文庫化したもので、上記の『神は妄想である』のコンセプトを、世界の将来を担う若者向けに書いたものとも言える。
ドーキンスが、無神論者・反宗教主義者の立場からの発信を強め、宗教との対決姿勢を明白にするようになったのは、2001年3月11日の米国同時多発テロがきっかけだというが、それは、人の心を救うはずの宗教が、怒りと憎しみを煽り、多くの人の命を奪うテロや戦争を引き起こすことに気付き、「宗教は有害である」という結論に達したからである。それまでも、科学的合理主義と反宗教は同一線上にあったが、3.11により立ち位置が変わったのだ。
本書では、第1部「さらば、神よ」で、神を信じるべき理由の正当性を徹底的に覆し、第2部「進化とその先」で、生きものの複雑さや美しさをつくり出した自然の仕組みを明かしているが、第2部の進化論に関する研究・解説については、『進化とは何か』(ファラデーが1825年に英国王立研究所で始め、その後も毎年行われている“クリスマス・レクチャー”において、ドーキンスが1991年から5回に亘って行った内容を編集したもので、2016年、日本語版文庫化)に、平易かつ興味深く書かれている。
私も基本的に、この世界(宇宙を含む)のあらゆる事象は科学的に説明し得ると考える(現在は超常現象と言われる現象が仮に実在したとしても、いずれそれは科学的に解明される)科学的合理主義者であり、本書の内容に得心するが、何より重要なのは、科学的合理主義が導く無神論(特に、扇動的な一神教に対する)が、世界の平和に大きく貢献するということであり(世界の争いの全てが宗教に起因するわけではなく、様々な面での格差の是正も大事なことであるが)、その意味において、ドーキンスのスタンス・主張に強く共感を覚えるのである。
投稿元:
レビューを見る
開始:2022/8/22
終了:2022/8/26
感想
神のいない世界。人間はわからないこと、空白を恐れるが救いの神はいない。あるのは科学の進歩の可能性のみ。勇気をもって空白へダイブしたい。
投稿元:
レビューを見る
神様はいないんだよってことを論理的、科学的に説明した本。
日本ではあまり感じないし、自分自身もキリスト教信者じゃないので、人間含めこの世は神様が作ったんだとか、聖書は事実とかピンときてないんだけど、世界にはそう信じてる人もなかなかの数いて、ドーキンスがこの本含め、神様はいないだろって言いたくなる気持ちはわかる。信じるのはいいんだけど、他の人の生活に干渉するのはまずいと思うから。
んでもってこの本は、解説でも書いてあったけど、どうやらティーンエイジャーが対象で、「神は妄想である」の入門編らしく。言われれば口調とかそんな感じだなと思った。私は科学がめっちゃ苦手で、後半のDNAだのなんだのの話になったところは飛ばし読み気味になってしまったけど、前半は興味深く読みました。
みんなが住みやすくお互いを思いやれる世界になるといいな。
投稿元:
レビューを見る
とても面白かった。
神様を持ち出さなくても科学で説明できること、をていねいに説明するだけでなく、なぜ人が神様を信じたくなるのかも説明している。
さらに、倫理的にというか道徳的にというか、そういう面でも神様は必要ではないこと、つまり信仰が善人を作るわけではないことも説明している。統計的な調査からも、他人に親切にする方向に進化が働いた可能性からも。
納得するかはまた別の話だけど、説得力はあるし、面白い見方だと思う。
とりあえず、狂信的な人に攻撃されないように祈る。
投稿元:
レビューを見る
ドーキンス博士の無神論者としての良心の書だと思う。宗教に関しては、どうしても及び腰になってしまう科学者が多い中で、しっかり科学者としての立場を貫いている。
投稿元:
レビューを見る
前半パートでは、神の存在を歴史的な視点から暴いていく。神や経典を信仰する人に対して、いろいろな矛盾を指摘していく。
後半パートでは、神の存在を信じる人に対して、地球上のさまざまな創造物や地球・宇宙などが「それを作ったのは神の仕業ではない」ということを科学的に解説する本。
投稿元:
レビューを見る
はじめてのドーキンスさん著作。
『利己的な遺伝子』を読む前に…と思って。
丁寧に神様の存在や聖書のエピソード、有神論を科学的に否定していくので、大丈夫かこれ…と思いながら読み進める。後半はちょっと疲れていた。
ただ説得力はあるというか、道徳の涵養に宗教が強く影響しない人生を送ってきた人は、受け入れやすいんじゃないかなぁと思った。(自分がそうなので)
『利己的な遺伝子』を読むかどうかは迷ってるけど、いつかは手を出すと思う。
投稿元:
レビューを見る
【感想】
神は存在するのか?神を信じる必要はあるのか?神は人間の道徳や生命の起源に関係しているのか?
「進化論」を否定する人が4割近くもいるアメリカ社会において、科学的な根拠や論理的な推論を用いる、という行為は意外にも難しい。そうした中、「無神論者」「科学者」という立場から、明快かつ挑戦的な回答を提示するのが、筆者のリチャード・ドーキンス及び本書『神のいない世界の歩き方』だ。本書は、ドーキンスの代表作『神は妄想である』の続編とも言える一冊で、若い世代を対象に書かれた現代の無神論についての入門書である。
本書は12の章から構成されている。おおまかには、
第1章~第2章:古代から現代まで、さまざまな宗教や神々の歴史を概観し、人間がなぜ神を創造したのか、神の概念がどのように変化してきたのか、聖書やコーランなどの聖典がどのようにして書かれ伝えられてきたのかを考察する。
第3章~第12章:神の存在は科学的にも哲学的にも立証できず、生命の起源、目的、自然現象、人間の心、意識、感性、想像力、文化といったあらゆる自然的・人間的要素は「神によって定められたものではない」と、繰り返し検証していく。
となっている。
副題に「『科学的思考』入門」とあるとおり、筆者が軸足を置くのはサイエンス、中でも「進化論」だ。
進化論は神や宗教に対する無神論の立場を支持するための重要な科学的理論である。当たり前のことだが、進化論は生命に目的や意味を与えていない。対して「創造論」――神がそのようにデザインした――という立場であれば、「神は何故そのような器官を?」「神はどうしてもっと便利な形状にしなかったのか?」という「神の意志」に疑問を呈さざるを得なくなる。一方で、進化論は生命の多様性や複雑性、適応性や美しさなどを「自然選択」というメカニズム一つで説明する。一応、進化論も「なぜその形に?」という疑問が残るような形態進化はあるものの、「共通の祖先から複雑化していく過程」を説明する進化論のほうが、格段に説得力がある。そうした基本的な科学理論から神の存在や聖書の記述を否定し、世界の見方を捉え直そう、というのが本書のあり方である。
本書は、「進化論を信じていない&神と聖書を信じている」アメリカ人向けに書かれた本である。そのため、神の存在を証明しようとする論証や神の存在を否定する論証といった、日本人には耳馴染みの無い主張も出てくる。そうした未知の考え(間違ってはいるが)を、「進化論支持者」というスタンダードな立場から覗ける、という意味でも面白い一冊だ。
投稿元:
レビューを見る
うーん、相変わらずドーキンスの語り口は楽しく読める。
生物学におけるダーウィンの進化論が揺るがされる現代アメリカにおいて、多様な生物が分岐し、DNAを自然淘汰のうちに自由自在に枝を伸ばしてきた、地球上生きとし生けるものすべての生物の歩みを、論理的かつ実際的な見地でもってドーキンスは神のいない世界を肯定的に再度捉えなおす。
神への攻撃の仕方が有無を言わさない理詰め感で容赦ない。
YouTubeの動画は全部見ましたよ。
投稿元:
レビューを見る
ふむふむふむ。なかなかグッドでした。
読む人が読んだら大炎上しそうな内容でしたが、根拠を明示しながらの説明は首尾一貫としており、こういうスタンスもありだよね、と私は思えました。
特に最後の結論には納得感があり、非常に勉強になりました。
宗教が良い方向へ働いているうちは神はいてもいいと思いますが、悪い方向へ働いてしまったとしたら、それは神のいない世界を歩き始めるべきではないかと思います。
日本人は無神教的で、海外の宗教問題への意識が希薄であるという話を聞いたことがあり、私もその自覚はあるので、他者が大切にしていることを踏みにじりたくはないなあと思っていましたが、戦争やテロまで繋がって実害が出ている場合は、話が違います。
しっかり勉強して冷静に価値判断してほしいものです。
投稿元:
レビューを見る
神または宗教批判の書だが、聖書などの聖典の古文書分析(主に科学的批判)の考古学として読める。ただしターゲットの読者は主に英語圏または西欧になっている。基本的にアメリカ人に多いインテリジェントデザイン主義者のことを批判対象にしている。そのため日本人としては当たり前のことが書かれているとも言える。
私たちは勇気をもって大人になり、あらゆる神に見切りをつけるべきだと思う335
物々交換は課税出来ないので違法でさえある298
進化、生存競争は軍拡競争に例えると分かりやすい223
道徳哲学において、
「絶対主義者」⇒世の中は善か悪かしかない。悪いものはどんな理由であれ悪い。「殺人は悪」だから、たった一個の受精卵を潰すことも「殺人」と考える絶対主義者もいる。
「帰結主義者」⇒最終的な「結果」が大事。中絶の結果として「誰が苦しむ」のか?あるいは中絶を禁止することにより「誰が苦しむ」のか?173
旧約聖書のモーゼの十戒の第二の戒めには「あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水のなかにあるものの、どんな形をも造ってはならない。」とあり、ユダヤ教徒だけでなく、キリスト教徒もこれを理由に貴重な芸術作品を打ち砕いた。最悪の破壊者だったのは、ローマ帝国でキリスト教が認められた後登場した聖アウグスティヌスだった。140
「カーゴカルト(積荷信仰)」第二次対戦中、太平洋の島々はアメリカ、イギリス、日本などに占領された。占領軍には本国から、食料、冷蔵庫、ラジオ、電話、車などが供給され、それらは原住民をも魅了した。しかし原住民は不思議だった。このような魅力的な物資である食べ物や車を占領軍は島で育てたり、作ったりしない。それらは空から飛行機で彼らの空港に届く。まるで「神による天からの恵み」だ。終戦後、各国軍は引き払い魅力的な物資は枯渇した。そこで原住民は「恵みを再び」と行動を起こす。森を開拓してニセの滑走路を作り、ニセの管制塔を作り、ニセの待機航空機を作った。それらは「神に祈りを捧げる行動」だと認識したからだ。このカーゴカルトの信仰はいまだに続いてるものがある(バヌアツの「ジョン・フラム信仰」など。ジョン・フラムは「ジョン・フロム・アメリカ」というアメリカ兵に由来)84
「キリストの復活」神話が生まれるプロセスは現代でも起こりうる⇒「生きたプレスリーを目撃した!」82
ノアの方舟が事実ならば、カンガルー夫婦はトルコのアララト山から、子供を産むことなくはるばるオーストラリアまで跳び跳ねて行った79
旧約聖書の「ユダヤ人はエジプトで捕囚され、神に約束され、イスラエルを手に入れた」の歴史的しょうこは無い74
1917年に大勢の人の前で「太陽を動かした」奇跡を「ファティマの聖母」が起こした。暗殺にあったが、一命をとりとめたヨハネパウロは「ファティマの聖母に救われた」と言った。どうやらキリスト教は一神教ではなく、聖母マリアや、精霊など多数の神を崇めるだけでなく、「聖母マリアも複数いる」とするようだ66
聖書の聖典は4つあるが、これはローマ時代に決まったもの。本来は他にも沢山キリストの話を記した書がある。そのひとつ『トマスによるイエスの幼時物語』には年少のイエスは道で肩にぶつかった少年に腹をたて、魔法の力で彼を殺した。それはひどいと抗議した彼の両親はイエスによって失明させられた60
「携挙(けいきょ)」とは、近年一部の作家や牧師が聖書の特定のくだりを根拠に、「善良さで選ばれた幸運な信者が、じきに突然空へと舞い上がって天国に消える」という奇跡が起こると言った。これをアメリカを中心に大勢が信じた。
しかし、これが起こる場合、携挙されるオーストラリア人はヨーロッパ人とは逆の方向に舞い上がることになる42