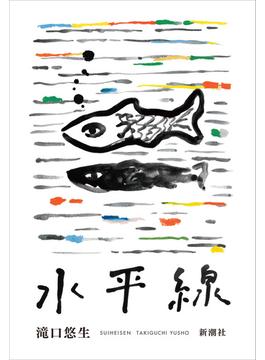遠い時間と場所を超越した世界
2023/01/07 12:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GORI - この投稿者のレビュー一覧を見る
太平洋にある硫黄島。クリンストウッド監督映画が話題になって名前は知っていた。
硫黄島で戦前暮らしていた人たちは内地に疎開させられたが、16歳から60歳の男子は島に残され全員戦死した。
祖父母が硫黄島出身の三森来未は墓参で2005年に硫黄島を訪れたことがあった。その15年後に祖父の弟からメールが届く。
また来未の兄横多には祖母の失踪して行方不明の妹から電話がある。
亡くなった者と現在生きている者が混在して触れ合うことで、過去の島の生活や亡くなった者たちの姿が生き生きと浮かび上がる。
過去の島の生活、兄弟の暮らし,友達の思い、仕事が現代と行き来して混在する。その鮮やかな生命感に今を生きる読者は熱い思いを抱かざるを得なくなる。
投稿元:
レビューを見る
1982年生まれの作家が、生まれる40年近く前の戦争を描くには、相当な覚悟も根性も要ったのではないか。2020年の感染症が広がりオリンピックがどうかという現代に生きる来未たちと、その60年前を生きる忍ら。
中上健次を思い出すようでもあり、『想像ラジオ』や『フィールド・オブ・ドリームス』を思い出すようでもあり。たまにクスリと笑ってしまうような地味なユーモアも。
死者と生者が繋がるということが、たぶん時にはあるんだと思うよ。
投稿元:
レビューを見る
滝口悠生さんの新作出たなら読むしかないでしょ!ってことで発売日に買ってすぐ読み始めてひと夏かけて読了。日本の夏の読書としてこれ以上ふさわしいものはないのでは?くらいにハマってどこへ行くでもない夏休みにゆっくり楽しむことができた。
第二次世界大戦中に激しい戦闘地となった硫黄島をめぐる時間と場所をクロスオーバーした群像劇。戦時中、近過去、現在と悠然と行き来するし、登場人物も非常に多くて一体自分がどこにいるのかふわふわした気持ちになるのだけど、それは著者が得意とする人称を自由自在に行き来するスタイルであり、船に乗って海でふらふらしてるような感覚があった。人称の変化具合は時代の横断を伴っていることもあり過去作の比ではなくフリーキーになっている。映像作品でいうところのカメラスイッチが立て続けに起こっていくので読んでいて飽きないし楽しい。整合性という「正論」の話をすると、そのあたりは完全にビヨンドしており、それはあれだすべて海のせい、的な展開で回収されていくのも興味深かった。
戦争に関する小説をそこまで読んだ経験がないものの、本作がスペシャルだなと思うのは膨大な量の生活描写だと思う。戦時中の生活について史料を読んだり、ドキュメンタリーを見たりすれば知識としては身につくのだろうけど、人が生きていた感覚を実感できるのはフィクションのいいところ。さらに映画ではなく小説だからこそ微細な描写、描き込みが可能となるのだなと500ページ超の本著を読んで感じた。その人がまるで生きているように感じるからこそ、戦争の理不尽さが浮き彫りになっていくのが良かった。戦争はクソだなと思う理由の一つが明確に書かれていたので引用。真剣に考えることの否定ではなく、ふざけられることの大切がよくわかる。ふざけて生きていきたい。
----------------------------------------------------------------------
幻想だ。真剣さは毒だ。真剣になっているうちに、自分じゃなく誰かべつの者のよろこびが自分のよろこびであるかのように思ってしまう。他人のよろこびを俺がよろこぶのは俺の自由だが、他人から、そいつのよろこびが自分のよろこびであるかのように惑わされて騙くらかされるのは御免だ。だから俺はあれからずっと真剣さを疑っっている。なるべくふざけていたい。大事な話や、大事なものについて考えるときほど、真剣さに呑みこまわれてしまわないように。
投稿元:
レビューを見る
太平洋戦争末期と現代。
物語は時空を行き来しながら進む。
70年以上の時間を隔てた人物から届く電話、メール。
今を生きる若者が導かれるように縁ある地に足を運ぶ。
不思議な物語。だが、この構成だからこそ強く伝わるメッセージが確かにある。
これまでの滝口作品とは一線を画す作品。
傑作。
投稿元:
レビューを見る
時代や人が章ごとに入れ替わり、今誰の何の話か?を考えながら読むのが楽しかった。結局誰なのか?何だったのか?わからないまま終わる。現代でさえも時間軸がズレてる?
投稿元:
レビューを見る
なかなかの力作!
うん?誰のパートだ?と最初は戸惑うが、人物像がはっきりしてくるとすぐに自分の頭も切り替わる。こんなファンタジーもありだと思う。知り得ぬ世界のことに思いを馳せて心を通わせていくところが良い。秋山くんと西武の秋山の話をするくだりがほのぼのしていて好き。
投稿元:
レビューを見る
クリント・イーストウッドの映画で有名になった硫黄島。戦前は住民がいたなんて知らなかった。
硫黄島に残り亡くなった家族、そして本土に疎開して生き残った家族とその子孫の物語。リアリズム小説なら並行世界的に描かれるところだが、この小説では超常現象的に両者が交わり、そしてそれはとても自然に書かれる。またリアルに表現されているはずの現代パートも微妙にズレて両立する。
最初はその荒唐無稽な内容に違和感を覚えるんだけど、だんだんその世界に馴染んできて、世代的に遠く離れた人々が身近に、逆にリアルに感じられるようになる。不思議な話だ。
硫黄島の砂糖工場で使われる牛フジに最も共感を覚えるというのは、自分としてどうか。
「真剣さは毒だ。真剣になっているうちに、自分じゃなく誰かべつの者のよろこびが自分のよろこびであるかのように思ってしまう。他人のよろこびを俺がよろこぶのは俺の自由だが、他人から、そいつのよろこびが自分のよろこびであるかのように惑わされて騙くらかさせるのは御免だ。だから俺はあれからずっと自分の真剣さを疑っている。なるべくふざけていたい。大事な話や、大事なものについて考えるときほど、真剣さに呑みこまれてしまわないように。」
投稿元:
レビューを見る
親が離婚したことにより苗字の異なる兄妹である横多平と三森来未。平には祖母の妹から、来未には祖父の弟から、すでに亡くなったはずの人からなぜかメールや電話がくる。さらには平がいる2020年はコロナがなく東京オリンピックが開催されているが、来未のいる2020年はコロナが蔓延していてオリンピックも延期された。
海の水平線の向こうには見えなくても島や大陸が確かに存在しており、ということはすでに亡くなっいて目には見えなくてもその人の思いが残っていたり会話したりもできるのでは…というのが著者の言いたいことだったのかな?
皆子が突然失踪した理由が最後まで明かされず、平が大島まで行ったがそこに皆子が住んでいたのかどうかもわからずじまいで消化不良な読後感だった。
投稿元:
レビューを見る
夏の季節に読めて良かったです。複数の本を同時並行で読み進める癖があるから、読み終わるのに1ヶ月くらいかかってしまったけど。
たとえば長い一日などで感じた、日常の中の些細なことの自分・他者の拡がりや、茄子の輝きで感じた、過去の自分の記憶の漂いみたいな、滝口さんの哲学たちが、時間軸や物理的にも拡張された壮大なスケールで展開されてゆきます。
壮大なスケールと言っても、SFみたいなあり得ない世界というわけではなく、まぁ見方によってはそうかもしれないけど、なんだか本当にあるような、ファンタジーとかって分類する意味がないような、日常のものとして語られていく。その語りが、悲哀に満ちた劇的な最期ではなく、硫黄島で死んでいった人たちの生活そのものを私たちの生活の地続きとして感じさせます。
過去の遠い出来事として薄れつつある戦争も実際にはあって、私たちと変わらない、語られない、残らない人たちが、それぞれあっけなく簡単に死んでいったということを実感として持っておきたい。
ただ目の前のことを受け入れる、理解しようとせず、疑おうとせず、そのまま受け入れる自分を受け入れたい。なにせ、確かなものなど、本当の一つもないのだから、と思いました。
もっといろいろなことを考え、想ったのだけど、すぐどこかへいってしまう。けど、そんなもんだよな、人の感情や記憶なんて。どこかにいってるだけで、確かにあって、確かに想ったことだけおぼえていれば、そのうち何かのきっかけでふわっと思い出すでしょう。
投稿元:
レビューを見る
とても読みでのある小説だった。読書好きの人には勧めたい本。
長いし、わりと時間はかかるのだが、どんどんページをめくっていきたくなる小説。
時空を超えたり、死者が語ったりするのはどちらかというと苦手なのだが、全く違和感なく、そんなこともあるだろうよみたいな感じで読めた。
硫黄島に人が住んでいたのは、映画「硫黄島からの手紙」等で知っていたし、その人たちが大変な思いをしたというのもなんとなくはわかっていた。そして戦後戻れないままであったことも理解していた。でもそこまでだった。この小説を読んで、生き生きとして暮らしていた人たちの様子、そこを去らなければいけなくなった悲しみ、家族との別離、新しい土地での苦労、島に残された青年たちの悲惨なその後など、知ることができた。
現代のパートはわりと楽しく読めた。こちらは自分も生きているのでリアリティがあり、それはそれで考えさせられるのだが、ちょっと息抜きもできた。硫黄島のパートも、別にずっと悲惨なわけではない。普通に暮らす日常があった。それを断ち切られてしまった、戦争のせいで。
「島」は大変だ。今現在も沖縄の島が将来犠牲にならないですむのかと心配になるような出来事が続いている。本島に住むものたちより先に犠牲になるようなことは絶対に避けなくてはならない。そんなことは一言も書いてないけど、そのことを改めて強く感じさせられた。
滝口悠生さんの小説は新刊が出るたびに「読みたい」と思うものの、読んだことがなく芥川賞受賞作以来だ。今回はしっかり手に取ることができてよかった。
"そこにはたしかに、よろこびもあった。(略)でもそんなのは作業に没頭している束の間の幻想だ。真剣さは毒だ。真剣になっているうちに、自分じゃなく誰かべつの者のよろこびが自分のよろこびであるかのように思ってしまう。他人のよろこびを俺がよらこぶのは俺の自由だが、他人から、そいつのよろこびが自分のよろこびであるかのように惑わされて騙くらかされるのは御免だ。だから俺はあれからずっと自分の真剣さを疑っている。なるべくふざけていたい。大事な話や、大事なものについて考えるときほど、真剣さに呑み込まれてしまわないように。" 308ページ
"いまは小さな濠のなかにいた。(略)生まれてこの方二十年以上も暮らした小さな島のなかなのに、いまいる場所がよくわからない。重ルには、そのことが違和とか焦りとかよりもまず悲しみとして感じられた。少し不思議だが、この悲しみはいったいどういう悲しみなのかと考えを追う気にならない。子どもの頃、意のままにならず泣いてみせるときみたいな、わからなさのなかで弱くなるような気持ちだった。" 317ページ
"いっけん規律に厳しい軍の仕事も、よく見ればあちこちにぼろがあって、いい加減さが露見しそうになれば無理くり封じ込めようとする。ないものもあるし、あるものもないことになる" 329ページ
投稿元:
レビューを見る
太平洋戦争の激戦地、硫黄島を巡る物語。人々の声が現代に届く。水平線っていう言葉の響きが歌のように体の中を通り抜けていく。
投稿元:
レビューを見る
現在と過去、今を生きている人と昔を生きた人、それが対比されるわけではなく、緩やかに気がつかないうちに、交わって物語が進んでいく。
最初は戸惑うが、次第にその時間が混ざる感覚というか、頭の中、もしくは夢の中でとめどなく考えていることが現実となるような感覚が文字化され、自分もこの物語に漂っている気分になった。
投稿元:
レビューを見る
読み終えて、ぽろぽろぽろとしばらく涙が止まらなかった。
完璧に本の世界に入り込み、読んだ後もあれこれと考えを巡らせてしまう小説は、ああ、本当に読んでよかった、と心から思える小説で、まさにこれはそんな1冊だった。かつて硫黄島で暮らした人々の声を聴き、平穏だった日々を共に懐かしく想い、辛くて悲しくてたまらなくなった。そして、本の中の彼らは今、どうしているんだろう、と思っている。
恥ずかしながら硫黄島については、ニノが出ていた映画も観ていないし、激しい戦場だった、くらいのことしか知らなかった。
この分厚い本の1/3ほどを読み終えた時、私の伯父が亡くなった。たぶんこの本を読んでいる最中でなかったら、こんなに伯父のことを思い出すことはなかったかもな、というくらい、幼い頃の鮮明な記憶をたどった。(硫黄島に住んでいた祖父母やその兄弟たちを思う登場人物たちの思いが重なっていたからかもしれない。)伯父は優しくていつもニコニコしていて、おしゃべりではないが、小さな冗談を言う人であった。90歳だった。
告別式の朝、持ち歩くには重たいな、と一度は薄い文庫本を黒いバッグに入れたのだけど、いや、やっぱり続きを読みたいな、と入れ替えた。久しぶりの新幹線で移りゆく景色を横目にぐんぐんと読み進めた。
伯父は両手では収まりきらないほどの理数系の資格を持っていて、体調を崩すまで現役で仕事をしていた。勤勉で人望が厚かったのだろう、両手が2つあっても足りない程の見事な献花が並べられていた。
私の従姉妹の息子でもある伯父の孫、Sくんが「じいちゃん、」と遺影に語りかけるように、何のメモを見ずに弔辞を述べた。じいちゃんの血を濃く受け継いだと言う彼と伯父の想い出は、羨ましくなるようなアカデミックなものばかりで、あまりの立派さにクラクラしそうになったが、その中で「じいちゃんがいなかったら硫黄島に行くこともなかった」という言葉を聞いた時、声が出そうになった。戦争のこと、歴史のことを伯父から多く学んだという。式が終わりロビーへ出ると、入る時には気づかなかった、受付横に並べられた写真が目に飛び込んできた。伯父が大切にしていた品々と共に並べられたその写真には「日米硫黄島戦没者合同慰霊顕彰式」とあった。Sくんを見つけて、これ読んだ?とバッグの中から本を取り出して見せた。「読みました」と嬉しそうに言ったように見えたSくんとは、いい小説だよね、と軽い会話を交わすことしかできなかったけれど(私がその時全部読み終えてなかったせいもある)、なぜ伯父が硫黄島へ行っていたのか、近々きいてみようと思う。
そんな偶然みたいなこともあって。硫黄島のこと、そこで暮らした人々が確かにいたことや、親戚付き合いがあまり盛んではない家系だけど私にも祖先がいて、彼らにも暮らしがあり、ご飯を食べ、笑ったり泣いたりしながら誰かを想い、生き、死んでいったことを思った。
中学や高校の国語や総合の時間は、1年を通じて『水平線』を読む、みたいなことをしてもいいんじゃないかしら。ホントに。
忘れてはいけない大切な過去を、素晴らしい作家さんの手腕で私たちの身近な物語として届けてくれる。小説を読む醍醐味だ。
投稿元:
レビューを見る
硫黄島の島民の記録を軸に,敗戦前に疎開した人々とその家族を少しオカルト交えて描いている.そして軍隊に徴用された人々が全員死んだ事実には,改めて胸が塞がれる思いがする.硫黄島からの疎開者の孫である来未に死んだはずの祖父の弟忍からかかってくる電話と横多兄に行方不明の祖母の妹からのメール.夢ではなく現実に過去が混ざり合ったような場の異空間の表現が自然で,読みながらも受け入れていて,でもそれはおかしな事.
硫黄島といえば,戦争の激しさばかりが強調され兵隊さんたちの悲劇がクローズアップされるけれど,島中犠牲になった人々のことを思うと,どこかサバサバと綴られた物語の中に深い哀しみを感じました.
投稿元:
レビューを見る
作者の思いや調査結果が削ぎ落とされることなくここでもかと盛り込まれていると感じた。
同じエピソードが繰り返し挿入され、語る人物は違えど語り口が同じなのでずいぶん退屈してしまった。
中編くらいに纏まってるともっと濃い物語になったように思う。