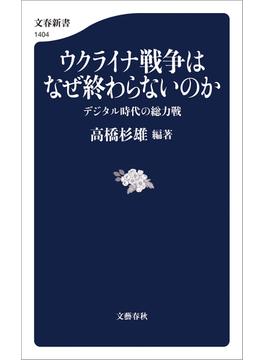始まった戦争はなかなか終わらせられない
2023/11/02 08:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシアのウクライナ侵攻のことをとりあげている本だが、そのことだけではなく、現在の国際情勢の中での戦争の性格やその抑止のことなど、より広い範囲のことを理解できるような書き方になっていると感じる。始まってしまった戦争を終わらせるのは難しいということ、そのため、抑止をしっかりときかせていくことが大事ということも納得がいく。ただ、抑止以前に、そもそも戦争を始める動機や意思をもつような国や組織をどうなくしていけるか、ということも考えることができないだろうか。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タタ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ウクライナの戦争がなかなか周旋しない原因は何なのかニュースだけでは、わからなかった点が理解できました。
投稿元:
レビューを見る
【米中の覇権争いでは終わらない。世界は戦争の世紀に突入した――】ウクライナ戦争以後、戦争はどう変わったのか。台湾有事を見据え、戦争抑止の視点から「終わらない戦争」の終わらせ方を考える。
投稿元:
レビューを見る
現在も継続するウクライナ戦争に関して、①なぜ生起したのか、②なぜ抑止できなかったのか、③戦争における宇宙利用、④ハイブリッド戦、⑤この戦争が終結するシナリオについて、懸念される台湾有事と関連づけて、読みやすく論じられている良書。分析も論拠をしっかり提示したうえでなされており、非常に納得のいくものだった。
特に、戦争の原因について、ロシアがウクライナに侵攻した原因としてよく語られるNATO東方拡大は、最もそうではあるが何か違和感があるなぁと漠然と考えていたところ、ロシアの独立以降の政策方針の変遷から、ロシアが大国としての「一極」をなすことを選んだというアイデンティティに原因を分析しているところが興味深かった。その際、一見関係ないと思われる中国が「あや」としてロシアの意思決定に作用していたという指摘も興味深い。構造的リアリズムへの批判つきで、腹落ちが良かった。
その他のテーマも事実ベースですら知らなかった事項もあったので、是非研究の参考としたい。
ただ、高橋先生が執筆されている章で、若干重複が気になる箇所が散見されたほか、なぜ2022年2月なのかという問いについて、地上戦力の展開限界時点という説明をしているが、(一般の人が疑問に思っているのは)そんな短期的な話でなくて、なぜ2020年でも2021年でもなかったのかという長期的な観点からの問いだと思うので、若干肩透かしを食らった気分。とはいえ、それ以外は大変素晴らしいので、これらが全体の質を下げているとは思わない。
投稿元:
レビューを見る
本書の題名を見た際、「読むべき?」と思ったのだが、読了に至ってその思い付きは間違っていなかったと確信できる。これは「読まなければならない」と言って差し支えない。言葉を換えると「必読書」に挙げるべきかもしれない。
「前史」というような展開は長いのだが、とりあえず“戦争”ということになったのが2022年2月であるから、既に1年4ヶ月間も続き、直ぐに1年半になってしまう。こうなると「何故終わらない?」という表現が口を突くというものだ。
本書は複数の執筆者による論考を纏めているのだが、論考を綴ると同時に纏める作業を担当した編者は、テレビ番組等でコメントを求められ、「何故終わらない?」または「落としどころ?」というように尋ねられる場面が在り、そんな中で考えを色々と整理することを重ね、本書という形に纏まったということであるようだ。
本書の各論考は、旧ソ連諸国や欧州の地域事情等を専門とするということではなく、所謂“安全保障”全般や、技術と社会というような事柄等、地域事情に拘泥しない論点を有する人達が手掛けている。それが凄く面白い。
たった一言で“結論”を敢えて言えば、目下のウクライナとロシアとの戦争は「簡単に終わるようには見えない」ということに他ならないかもしれない。それは「何故?」ということを本書では説いている。
ハッキリ言えば、ウクライナとロシアとは、経済規模や開戦当初の軍隊の規模等が「10倍以上の差」であった。そういう情況にも拘らず、ウクライナが善戦して持ち堪え、戦闘が膠着する場面も生じて、長期化している。その辺りの技術的なことも判り易く纏めているのが本書だ。
一言で言えば、“成功体験”から「詰めが甘い?」という感で開戦に踏み切ったロシアに対し、苦心しながら備え、必死に抵抗し、効果的な反撃で持ち堪えるウクライナという図式になるであろうか。「国の一部に組み込んでしまえ」と攻めるロシアに対し、「それは断る」と守るウクライナで、両者の“自己同一性”を賭しているような情況になっていて、目下の戦いの“終わり”は見え悪い。
「戦争」というような様相は、“外交”、“情報”、“軍事”、“経済”という諸要素が複雑に絡み合っている。そんな様相を、新しい意味で「総力戦」とでも呼ばなければならない筈で、目下のウクライナの戦争もそういう例に入らざるを得ないとしている。
そして「戦争」は、或る1国で勝手に決断すれば起こしてしまうことは出来る。が、その結果として「交戦相手」が生じてしまう以上、少なくとも2国以上で何とかしなければ、簡単には終わらない。要は「始めてしまわないように…」としなければならないのが「戦争」なのかもしれない。
このままであれば「厭戦ムード」が高まる迄の「更に数年?」というような時間が「終わり」に必要ではあるかもしれない。が、それは早ければ早い方が善いことは疑い悪いとは思う。国土が荒廃―通常兵器の激しい交戦の結果、「原爆??」という程度に破壊されてしまった都市も既に在る訳だ…―し、人々の生命が擦り減らされるばかりなのだから。
この戦争の件に関しては、「考える材料」を怠りなく集めるべきだと思う。��ういうことで、この種の本は積極的に読まなければならないと思う。
本書の好さは、地域事情等でもない「外交や軍事や技術の全般」という視座でウクライナで起こっていることを説こうとしている点で、それ故に「非常に判り易い」という辺りだ。広く御薦めしたい。
投稿元:
レビューを見る
ロシア・ウクライナ戦争の開戦から現在に至るまでの戦争の経過からわかる現代の戦争の特徴(&従前の戦争との共通点)や、戦争を終わらせるに至るシナリオについての検討がされている。それぞれの国家の論理からすれば、落としどころを見つけるのは極めて困難で、戦争を始めさせないこと(つまりは抑止力を高めること)が最も重要であろう。
投稿元:
レビューを見る
第1章:
クリミア半島とル人共、ド人共を分離してしまったばかりに、ウクライナ国内に親露派のお橋頭堡がなくなり、ウクライナがロシアとの対決に世論が集約されたのは、皮肉である。
第2章:
残念ながら本章で取り上げる八つの知見を台湾海峡有事の事例に適用してみると、台湾海峡においても今後、抑止が破綻する可能性は高いと言わざるを得ない。
第3章:
初の商業宇宙戦争。(ニュースペース)
双方が宇宙資産を利用する初の戦争
第4章:
ウクライナ戦争におけるロシア軍のハイブリッド戦争の具体例と、ウクライナの新領域戦争
第5章:
アイデンティティ戦争において、「落としどころ」はない。(これは中国の台湾侵攻にも言える)
終章:
戦争を終わらせることは、戦争を始めることよりもはるかに難しい。増して、アイデンティティ戦争に置いては落としどころはない。→中国に台湾侵攻を起こさせないことが重要であり、そのための戦略三文書の改定と防衛費の倍増は必要な平和のコスト
投稿元:
レビューを見る
ロシア・ウクライナ戦争を終結させることは、なぜ難しいのか。その理由・背景について一般読者向けに解説した新書である。この戦争はロシアとウクライナの双方がアイデンティティを懸けた戦いとなっている。ゆえに「落としどころ」を見つけることがきわめて困難であり、戦争終結のシナリオを考えることを難しくさせている。いつだったか小泉悠氏が「この戦争の終わりは悪い選択肢のなかからもっともよい選択しを選び取ることに等しい」みたいなことを言っていたが、その内実がよくわかるようになっている。また宇宙利用の話やサイバー空間におけるハイブリッド戦争の様相は、私自身理解ができていない部分だったので大変勉強になった。5章、終章は台湾海峡有事を起こさないようにするために何が必要かを考えるきっかけとなった。本書は特定の地域を専門とする識者が執筆した性格の本ではないため、ロシアの軍事が専門である小泉氏の著作や、欧州が専門の鶴岡氏の著作などを合わせて読むことで、より立体的な理解が可能になるはずだと思う。ともあれ、2023年のいま読むべき本であることは間違いないだろう。
投稿元:
レビューを見る
2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻で始まったロシア・ウクライナ戦争は、「ヨーロッパの一部」となることを選択したウクライナに対し「旧ソ連的な勢力圏」を形成するためにウクライナ(の領土)を必要とするロシアが一方的に攻め込むという構図であるが故に、ロシアがその意図を充足するか、断念しない限り終結しない。
前者はウクライナに妥協を強い、後者はロシアの宗旨変えか物理的な無力化を意味するために、短期間での終結は見通せない。
本書の本筋は1章と5章の編著者による論考であり、挟まれた他著者による論考は補足的なものなので、1+5章を読んだ後に2〜4章を読むのも勉強としてはあるが、各論にも同等の重みを置き、結論(書名の命題に対する回答)を最後に配置する本書の構成が落ち着きが良いのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
非常に読みやすい。ウクライナ-ロシア戦争の本質はアイデンティティの問題(ウクライナを旧ソ連の一部としてロシアに併合すべきというロシア側の考えと独立した存在としてヨーロッパの一部でありたいウクライナ)。その為、一度開戦してしまえばお互いに落とし所が無く、長期化しているのが現状。アメリカがヨーロッパに積極的に介入していないのはアジア戦略を優先している為であり、アジアのリソースを欧州に割いた結果、パワーバランスが崩れ、台湾有事を引き起こしてしまうことを恐れている。発生してしまえば台湾有事もアイデンティティの争いとなる為、大切なことは戦争を始めさせないということである。
投稿元:
レビューを見る
開戦原因、抑止や宇宙、ハイブリッド戦争などの観点から、戦略や安全保障の専門家によるウクライナ戦争の分析と台湾有事へのインプリケーション
投稿元:
レビューを見る
ロシア・ウクライナ戦争について、なぜこの戦争は始まったのか、この戦争はどのような戦争なのか、この戦争は終わらせることができるのか、という3つの論点について考察し、最後に日本の安全保障への影響についても論じている。
1つ目の問いについては、この戦争はロシアとウクライナのアイデンティティをめぐる戦争であり、抑止はほぼ不可能に近かったと結論付けられている。
2つ目の問いについては、この戦争は、「古さ」と「新しさ」が同居しているところに特徴があり、「デジタル時代の総力戦」と捉えられると論じられている。
3つ目の問いについては、3つのシナリオが考えられるが、どれも相当の時間がかかることが見込まれたり、蓋然性が低かったりして、いずれも早期実現の可能性は低いという悲観的な結論となっている。
そして、日本の安全保障への示唆として、中国による台湾海峡有事を念頭に置き、ロシア・ウクライナ戦争の最大の教訓は「戦争は始めるよりも終わらせることが難しい」ことであるとして、中国に「戦争を始めさせない」ために軍事的な抑止力の強化が必要であると指摘する。
ロシア・ウクライナ戦争の来歴と性格、今後の見通しについてとてもよく整理されている良書である。DIMEという概念や構造的リアリズムにおける「バンドワゴン」と「バランシング」という概念など初めて知る概念も少なくなく、ロシア・ウクライナ戦争の分析を通じて、安全保障論全体の勉強にもなった。
本書の結論はかなり厳しいものであるが、納得性の高いものであった。支援疲れが言われているが、ウクライナが占領地を奪回できるように国際社会が支援を継続していくことが大切だと改めて認識した。
アイデンティティを巡る争いという点では、懸念される台湾海峡有事は、ロシア・ウクライナ戦争以上ともいえ、本書が指摘するように中国に戦争を始めさせないために日本としても最善を尽くすことが必要だと感じた。その点で、賛否両論あるが、日本の防衛力強化は重要だと再認識した。
投稿元:
レビューを見る
国家としてのアイデンティティがロシアの考え方や感じ方を規定して、クリミア併合とロシア・ウクライナ戦争を選択させた。
これまでロシアの行動の理由の根本に何があるのかがわからなくて、ロシア・ウクライナ戦争勃発当初まことしやかにささやかれていたように、狂った独裁者にロシアが巻き込まれたという話が事実なのかどうか、いまだにいぶかしく思っていたけれど、国家としてのアイデンティティという考えを含めて考えると、すとんと納得できた。
考えてみれば当然だ。日本を含めた西側諸国だって、自由な民主主義国家というアイデンティティのためにウクライナを支援してきた。
この本の中でも盛んに論じられている、ロシアがウクライナで核兵器を使用する可能性についてだけれど、ソ連はチェルノブイリ原発事故でとどめを刺されたようなものだったし、核による被害についてのトラウマは旧ソ連国内にはまだ根強くあるんじゃないかと思う。
ロシアの目的はウクライナの国土強奪のはずだし、手に入れたい国土を核兵器で汚染させるだろうかと思う。
でも、手に入れたいはずのウクライナ人をブチャで虐殺したことを考えると、ロシアの核兵器使用に関する私の考えは、使わないでほしいという願望だけに基づいたものかも。
冷戦時代はイデオロギーをめぐる対立だった。ソ連が崩壊して冷戦が終わってから、イデオロギーの害悪について盛んに語られるようになった。
いま起きている戦争がアイデンティティの対立によるものなら、争いが終わった後にアイデンティティの害悪が語られるようになるの?そんなことになったら、誰も自分がだれかわからなくなってしまうので、そんなことにはならないはず。でも、一瞬だけそんなことも起きてしまうのかもと思った。
ロシア・ウクライナ戦争以前は軍事力が存在しなければ戦争も起きないと夢想していた。もうそんな夢は見られない。日本にも防衛力が必要だ。最低限、中国共産党が台湾有事をためらう程度の防衛力が。
高橋杉雄がロシア・ウクライナ戦争について、さまざまな媒体で非常に理解しやすく解説しているのを見て、著書も読むようになったけれど、文章でもやはり理解しやすい。
投稿元:
レビューを見る
なんで戦争が終わらないのか、なんで侵攻したのか戦争が始まって2年ほど経ってるはずなのに全く知らなかった自分を恥じました
なんかほんとに面白くて興味深すぎてあーー国際政治とか国際法とかもっと学びたいてなりました
投稿元:
レビューを見る
本書は、高橋杉雄編著であり、高橋氏の他にも3人の研究者の章もある。このことで、より客観的に分析ができているように思える。
内容は難しいものではなく、日頃ニュースを聞いてぼんやり思っていることを丁寧に文章化した感じなので、そうそうと納得しながら読める。
このような丁寧な分析に基づく考察はとても説得力があり、かつ大事な現状説明である。一部分を取り上げてセンセーショナルに報道するマスコミやSNSを見ていると、いつの間にか見落としが出てくるのだ。
決して派手な言論に与せず、冷静で慎重な文章・意見で一貫している本書はとても信頼できるものだと思う。