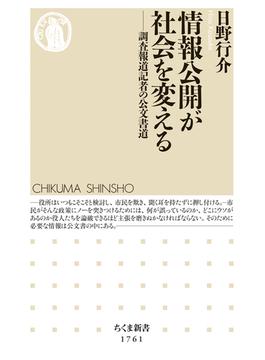読割 50
電子書籍
情報公開が社会を変える ――調査報道記者の公文書道
著者 日野行介
行政が押し進める理不尽な政策。そこに共通するのは、意思決定過程が不透明で結論や負担だけを市民に押しつける点だ。真実を知り、民主主義を守るためには、私たち一人ひとりが行政を...
情報公開が社会を変える ――調査報道記者の公文書道
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
情報公開が社会を変える 調査報道記者の公文書道 (ちくま新書)
商品説明
行政が押し進める理不尽な政策。そこに共通するのは、意思決定過程が不透明で結論や負担だけを市民に押しつける点だ。真実を知り、民主主義を守るためには、私たち一人ひとりが行政を監視し、政策をチェックすることが求められる。役所の不正に立ち向かうとき、強力な武器となるのが情報公開制度だ。これまでに千件もの情報公開請求を行い、数々のスクープを伝えてきた調査報道記者が、長年の経験をもとに、そのしくみとテクニックをわかりやすく伝授する。
目次
- はじめに/第1章 報道は期待できない──市民が自ら情報公開請求すべし/突然の建設計画/役所に騙されないために/情報公開請求したことがない記者たち/コロナで仕事がなくなった/緊急事態宣言下でひたすら下調べ/情報公開請求は誰でも使える「正攻法」/第2章 はじめての情報公開請求/プレスリリースを見てみよう/実は肝心なことが書かれていない/情報公開と公文書管理の基本知識/一連の「公文書スキャンダル」が示したもの/冤罪事件の弁護に似ている/第3章 意思決定過程を解明する──狙いは非公開の「調査」と「会議」/隠された政策のテーゼを言語化する/「公表」と「公開」の違い/狙うのは非公開の「調査」と「会議」/非公表「調査」の探索法/見つけるのに苦労した調査/チェルノブイリ法を否定するアンチョコ/非公開会議の目的はシナリオのすり合わせ/いじめ自殺問題で市教委に情報公開請求/市教委と学校が隠したかったこと/第4章 「不存在」を疑う──役所のごまかしをどう見抜くか/情報公開と公文書管理は民主主義を支える車の両輪/「不存在」の文書があった/公文書と「個人メモ」の境界は/「保存期間一年未満」の文書/決裁文書が付いたものだけが公文書?/「決裁文書がないから不開示」/請求取り下げの要求には要注意/特例延長について/期限の定めがない特例延長/第5章 請求テクニック──目的の情報にたどり着くために/議事録は一つではない/録音データも公文書/電子メールも公文書/独立行政法人にも情報公開請求できる/情報公開請求は挑戦状/開示の決め手は気迫と見識/第6章 黒塗りに隠されたもの──役所の「痛点」を見つける/黒塗りから透けて見える真意/「知られたら勝手に避難されてしまう」/会議のマトリョーシカ人形/役所のアピールと矛盾するファクトを見つけ出す/途中で葬られた選択肢を探す/密かに確保していた除染費用/消化不良の理由/第7章 審査請求のススメ──「不開示」がきたらどうする?/市民でもできる/「のり弁」と審査請求/審査請求書の書き方/過去の開示事例を探す/他の役所の開示事例を探す/審査請求後の流れ/情報公開審査会の答申/元委員が語る審査請求のススメ/おわりに/参考文献/あとがき
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
国や自治体の公表と情報公開請求は意味が違う
2024/01/15 11:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は元新聞記者であり、ジャーナリストが行政に対する情報公開請求について書かれたものである。行政全般に対してというものでなく、福島第一原発事故、茨城県の東海第二原発の事故や避難計画を中心に情報公開請求した経験を踏まえて展開されている。現在の新聞社は、行政や警察からの情報が欲しいという点で従属的になってはいないか、新聞の定期購読者が減り、記者等の人員削減が進み、テーマごとに追跡する余裕を失っているとか等で報道より市民の活動に期待するという面がある。目次を見ると、
はじめに
第1章 報道は期待できないー市民が自ら情報公開請求すべし
第2章 はじめての情報公開請求
第3章 意思決定過程を解明するー狙いは非公開の「調査」と「会議」
第4章 「不存在」を疑うー役所のごまかしをどう見抜くか
第5章 請求テクニックー目的の情報にたどり着くために
第6章 黒塗りに隠されたものー役所の「痛点」を見つける
第7章 審査請求のススメー「不開示」がきたらどうする?
おわりに
参考文献、あとがき となっている。
以上のように展開される。原発に限ると、老朽原発の再稼働、新増設を巡っての問題があるが、原発周辺地域の避難計画の策定は自治体が行うことになっている。しかし、策定する力がない、策定してもおざなりというのが通り相場である。しかし、原子力規制委員会が原発再稼働の可否判断では、避難計画は安全審査対象外なので、差し止め請求となると自治体の避難計画が重要となっており、ホームページ等で公表されている以外での情報公開請求で出てくる資料が重要となっている。具体的には本書を参照されたい。自治体は国との関係、関係団体とのつながりで住民に見られたくないという側面がある。福井県の高浜町の助役みたいに電力会社と利権で結びつき、資金還流まで出ている。政党のパーティー券の裏金と同じに見えることもある。情報公開と共に公文書管理にも触れている。原発以外にもいじめ自殺問題での情報公開請求のくだりが出てくる。公開請求し、文書があっても「不存在」としたり、公文書の範囲を勝手に狭めたりする例が紹介される。国や自治体、独立行政法人等が情報公開請求の対象となるが、そこで働いていると顔の見える人がチラついたり、自己保身に走ったりするするのはサラリーマンの宿命であろうか。しかし、制度としてある情報公開請求で請求されたら、出すのが当たり前となれば言い訳もできるだろう。これを活用する人が多ければ、裏で動く利権屋といわれる人も動きにくくなるだろう。原発に限らず、多くの面で活用されれば、本書の価値も変わってくる。一読してほしい本である。
電子書籍
のり弁
2023/12/19 16:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
公にすると率直な意見交換を不当に妨げる恐れがあると公表されない策定根拠資料は地方自治体の国策への盲従や及び腰にある。何もわからず納得できないまま進められるのが嫌ならば、市民の正当な権利である情報公開請求及び審査請求をしようと公文書道を説いている。