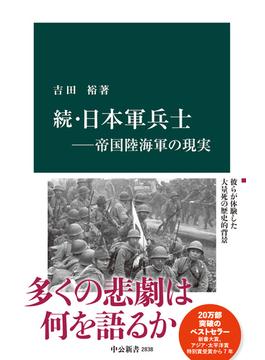0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
残っている資料が少ない中真の姿を浮き彫りにしようとしている姿勢は前作と変わらない。手記的なものよりも構造的な実態をあらわにしている。補給や衛生、制度など多角的にこれまであまり注目されてこなかった点を重視している。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次世界大戦時の日本の軍隊の実情が、わかりやすく解説されていて、よかったです。多くの悲劇が、教訓になりそうです。
投稿元:
レビューを見る
「帝国陸海軍は兵士には、必要以上の負担を強いる特性があった」
”はじめに”にある夏目漱石の『それから』の引用の通りで
「貧乏国は戦争なんかやってはいけない」
読めば読むほどにそう思いました。
もちろん金持ち国ならやってもいいわけでもありませんが。
本書の主題とは違いますが本書内のコラム
”戦争の呼称を考える”によって
「太平洋戦争」という呼称すら十分な市民権を得ていない、
という指摘に驚きの五〇代です・・・。
投稿元:
レビューを見る
2019年新書大賞を受賞した前作の「日本軍兵士-アジア・太平洋戦争の現実」から待望の続編が出版された。アジア・太平洋戦争では、日本人310万人が死亡し、推計230万人の兵士と80万人の民間人が犠牲となった。230万人の軍人・軍属を喪った6割は戦闘による戦死ではなく、戦病死であった。著者が引用し、著者の恩師である藤原彰氏のバイブル的書籍「飢え死にした英霊たち」でも詳細な推計が行われている。大量死の背景には、第2次世界大戦における機械化部隊に対する日本軍の精神論重視、下級兵士に犠牲を強いる組織機構の問題、兵士の生活や衣食住を無視した兵站軽視、日清戦争や日露戦争で露呈した栄養失調による脚気の再燃。アジア・太平洋地域に戦端を広げすぎたツケが、兵士を無謀な戦争へ追い込んだ軍上層部の無謀な作戦立案と撤退の遅れ。本書は帝国陸海軍の歴史を追い、兵士達の体験・エゴドキュメントを通して、日本軍の本質を描く。本書を読んで、戦争とはいかなる事態に陥るのかを多くの若い人たちに知ってほしい。(428字)
【雑感】
著者は、「おわりに」で続編発行までに長い月日が経ってしまったと回顧するが、7年の月日で著者が様々な書籍出版に関わり、一橋大学の退官記念書籍も発行し、故早乙女勝元氏の後を受けて東京大空襲・戦災資料センターの館長を歴任しながらの労作であることは間違いない。著者は、一橋大学において日本近代軍事史、日本近現代政治史の専門家として、ここ10年のNHKの夏の戦争特集では、毎年時代考証者として解説していることも付け加えておきたい。
投稿元:
レビューを見る
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。
https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01436559
投稿元:
レビューを見る
日本における未だに続く人命、補給、責任軽視の姿勢がはっきりと見られた。戦争には歴史そのものがよく現れると思う。
投稿元:
レビューを見る
前作に続く続編ではあるが、前作を読んでいなくても内容に関しては全く理解できるので問題ない。寧ろ、筆者が述べるように過去の戦争を原因や勝敗の分析をする書籍が大半を占める中、本書のように定量的な事実や環境、兵士の実態などの側面から捉える内容の物は少なく、戦史の一つとして理解を深めるのに大変役立つ。
近代の戦争、それは要は総力戦である。兵士の数や兵器の良し悪しなどは分かり易い指標ではあるが、実際にはそれを成立させるための国力が全てであり、過剰な兵員数、バランスの取れていない軍隊が戦争に勝利するのは難しい。日本は明治維新以来の重工業化を経て、近代的兵器や艦船を作ってきた。だがその供給力に於いてはアメリカやイギリスには未だ未だ及ばない。自動車の生産力や生産量を見てもアメリカのそれには全く及ばないし、エンジンも他の部品もアメリカの模倣品、それもかなりの粗悪品のレベルだ。工業力だけではない。兵員数は太平洋戦争の経過年数と共に増加し続け、食糧生産に支障をきたす程に伸び続ける。全体のバランスの観点で見れば、国家全体、特に地方における食糧生産は女性や若年層に頼らざるを得ず、結果的には国民の消費カロリー低下に繋がっていく。ましてや戦地に供給するには、太平洋を股にかけ闘う兵士達には海を越えて届ける輸送力も必要だ。それらのバランスが崩壊した時、十分な食事と娯楽すらも戦地で得られる米軍兵士に勝てる訳が無い。本書はそうした食事事情や兵站、兵士たちの使用する軍靴など、あらゆる視点で数値化を試み、戦闘力以前の問題点として捉えていく。
現代社会では身体や知能に障害を持つ人であっても、活躍の場は多く、正に多様性の掛け声の中で、あらゆる人々が働ける時代になった。未だそうした社会的な環境が充分に揃わない戦時中に於いては、そうした人々にまで召集が及び、十分な戦闘が出来ないまま戦地に送られ命を落とす。一方では病歴詐称などにより召集逃れをするもの、金品を渡して軍医から「兵士として不適切」の免罪符を得るものもおり、結局は金持ちは死に辛く、そうで無いものとの間に「命の格差」が生まれていく。当時も今も経済的な格差が生存率に影響していた実態が多くあった様である。更には戦地で十分な医療を行うことが出来ない日本と、充分過ぎる医療機材、薬品が揃う米国とでは兵士の損耗率を見ても、叶う訳が無い。そうした時に日本が得意とする精神論で押し通すのも、やはり限界はある。
あらゆる面で及ばない日本が、順当に戦争に敗北していくのを、本書は数値的に理解していくことができる。そこから学び取れるのは、やはり「バランス」に尽きるのでは無いか。この考え方自体は「国家総力戦」として従来から叫ばれてきたものではあるが、そこは「神国日本」の何か強力な加護に軍上層部さえも支配されていたのでは無いだろうか。人間軽視、機械化不十分、バランス崩壊、それら負の皺寄せは全て戦場に生きる兵士達に押し寄せていく。最前線の兵士は勇敢に戦いながらも、アメリカ兵だけではなく、蚊や餓えとも戦わざるを得ず、やがては敗北につながる虚しさも理解しつつ戦い続けたのでは無いだろうか。その様な兵士達の心の内を想うと涙が溢れて���る。
二度と戦争は起こしてはならず、今、正に世界で起きている戦争は直ぐに終わらせるべきである。どの様な理由があり、終わらない終わらせられない理由・状況があるにせよ、1番悲惨な最前線の兵士を思わなければならない。一刻も早く世界から戦争・紛争を無くすために、今は平和にある日本であっても一人一人真剣に考えるべきでは無いか。きっかけを与えてくれる一冊だ。
投稿元:
レビューを見る
「戦場の真実を直視する:『続・日本軍兵士 帝国陸海軍の現実』を読む」
吉田裕氏の『続・日本軍兵士 帝国陸海軍の現実』は、前作『日本軍兵士 アジア・太平洋戦争の現実』に続き、アジア・太平洋戦争における日本軍兵士の実情を克明に描き出した衝撃的な一冊です。
組織としての帝国陸海軍:構造的な問題点
前作が兵士個々の視点から戦争の実態に迫ったのに対し、本書では帝国陸海軍という組織に焦点を当て、その構造的な問題点を浮き彫りにしています。
兵站と衛生:戦場の悲惨な現実
特に深く印象に残ったのは、兵站と衛生に関する記述です。戦地における物資の欠乏、劣悪な衛生環境、そしてそれらが兵士たちに与えた絶望的なまでの影響。著者は豊富な資料と証言をもとに、日本軍の組織的な欠陥を冷静に分析し、それが兵士たちの命をいかに軽んじたかを痛烈に批判しています。
「戦場の花と散る」という美辞麗句とは裏腹に、実際には多くの兵士が飢えや病に苦しみ、誰にも看取られることなく命を落としていったという事実。その悲惨な現実に、私はただただ言葉を失いました。
日米の組織文化の差異:命の重さ
本書を読むと、アジア・太平洋戦争における日本とアメリカの戦い方が、いかに異質であったかがよく分かります。アメリカ軍が兵士の命を最大限に尊重し、潤沢な物資と医療体制を整えていたのに対し、日本軍は兵士の精神力に依存し、補給や衛生を軽視する傾向がありました。
この違いは、両軍の組織文化や価値観の根本的な違いに起因するものと考えられます。アメリカ軍は兵士を「人的資源」として捉え、その能力を最大限に活用しようとしたのに対し、日本軍は兵士を「消耗品」として扱い、精神力さえあれば物資の欠乏や劣悪な環境も克服できると考えていたのではないでしょうか。
もちろん、アメリカ軍にも問題点はありました。しかし、日本軍の組織的な問題点は、それを遥かに凌駕するものであったと言わざるを得ません。
現代に通じる教訓:組織とリーダーシップ
本書は、単に過去の戦争を批判するだけでなく、現代の組織にも通じる教訓を与えてくれます。組織の目的と手段、リーダーシップのあり方、そして何よりも「人」を大切にするということ。これらの普遍的なテーマについて、改めて考えさせられました。
戦史に興味がある方はもちろん、組織論に関心がある方にも、ぜひ本書を手に取っていただきたいと思います。今までとは異なる視点からアジア・太平洋戦争を捉え、そして現代社会にも通じる深い洞察を得ることができるでしょう。
投稿元:
レビューを見る
1. 戦争における病気の影響
- 日清戦争からアジア・太平洋戦争まで、戦病死が重要な要因であったことを強調。
- 戦争中に発生した感染症(赤痢、マラリア、コレラなど)が兵士の健康に及ぼした影響。
2. 戦病死者の統計
- 日清戦争では、戦死者と戦病死者の合計で一万二千六百四名に達し、戦病死者が占める割合が高かった。
- 日露戦争では、戦病死者の割合が戦死者の割合を下回ったが、依然として重要な問題であった。
3. 脚気と栄養失調
- 脚気の流行が戦争中の兵士に多くの死者を出した原因であり、栄養失調が深刻な問題として浮上。
- 栄養失調症の多発が、戦中の兵士の体格の劣化や戦闘能力低下に繋がった。
4. 兵力動員と兵士の質
- 戦争の長期化に伴い、後備役兵や補充兵が投入され、戦闘経験の少ない兵士が多数派となった。
- 中年兵士の増加が、兵士の士気や出生率に影響を与え、戦争遂行能力に悪影響を及ぼした。
5. 給養と生活環境の悪化
- 戦争末期には、兵士の給養状況が著しく悪化し、栄養不足が深刻化。
- 軍隊の装備や生活環境の劣悪さが、兵士の健康や戦闘能力に悪影響を与えた。
6. 戦争栄養失調症の定義と影響
- 戦争栄養失調症は、長期的な栄養不足によって引き起こされる病であり、治療が困難であった。
- 兵士の心身に深刻な影響を与え、戦闘意欲を低下させる要因となった。
7. 医療体制の問題
- 医療体制が整備されていなかったため、病気の治療や兵士の健康管理が不十分であった。
- 軍医や医療関係者に対する批判が存在し、戦死や病死を減少させるための具体的な対策が不足していた。
8. 戦争の結果と教訓
- 戦争の結果、兵士の健康や生活環境の悪化が明らかになり、今後の戦争における医療や給養の重要性が再認識された。
- 日本の戦争体制における構造的な問題が、戦争の悲劇を招く要因であったという反省。
投稿元:
レビューを見る
帝国陸海軍の欠点や問題点をあげつらったところで当時の日本はアメリカ合衆国のような工業化や自動車化が進んでいないのは習知の事なのに、この本はアメリカを持ち上げて日本をダメだと繰り返しているだけだ。それこそ日本軍が敵手の捕虜になる事を暗黙のうちに禁じたり人命軽視に関したりはドイツ軍の捕虜になって協力しなくても強制収容所や懲罰部隊に送った労農赤軍との対比は必要ではないか?
著者は秦郁彦の「日本人捕虜」を使っているなら昭和16年に英軍の捕虜となった少年飛行兵二期の李根晳准尉は知っているはずだ。彼は昭和10年に入隊しているのに著者は植民地出身者は昭和13年に朝鮮人に対する陸軍特別志願兵令以降しか入隊出来ないかように書いているのは前著と同じで簡単だ。おそらく「戦後責任」とか「戦後補償」とかいった観点からでも植民地出身者がいつから日本軍に入隊出来たか、朝鮮人なら王公族は大正15年の王公家軌範制定前から皇族のように軍人になる事が決まっていて昭和3年に王公族附陸軍武官官制が制定されたように昭和18年まで海軍は植民地出身者には門戸を閉ざしていたか、台湾人なら高砂義勇隊の位置づけはどうなるの等といった点について細かく関心自体を持っていないのだろうか?と思ってしまう。
投稿元:
レビューを見る
読んでる途中だけど、ここに書いてあることを学校で学ぶ(現)近代史の中心にしたらどうかな、生徒は少し興味を持つかも
俺が学校で教えられた年号と出来事の羅列には全く興味がわかなかった
その後自分で興味を持った歴史は本を読んで多少学んだ
兵士は戦うだけでなく自分達と同じように、食べて、寝て、排出して、病気になって、という事実と、そこに全く目が向けられてこななかったという事実に唖然とする
無謀な戦いだったことをこれほど的確に表した本に出会ったのは初めて
続く(かも)
投稿元:
レビューを見る
尊敬する吉田裕先生の新書。
「日本軍兵士」では、戦死よりも、海没死・餓死・特攻死などが多いことを
指摘したものの、掘り下げることができなかったことから
新しい視覚からその理由を読み解く。
図書館から借りるのではなく、手元に置いて、じっくり読みたい一冊。
投稿元:
レビューを見る
戦争の犠牲者と言っても戦病死が多いことを実証する。特に戦局の悪化による栄養失調などを具体的な数値により指摘。日本政府が明らかにしない戦争の実態に踏み込んだ一冊。
投稿元:
レビューを見る
続けて『続・日本軍兵士』を読む
前作と重複する箇所がかなり多く、辟易する
だがしかし、前作から8年を経ており、復習しながらさらに深掘りする内容で、しかも冒頭で断りを入れている
完全に続けて読む方が悪い
ごめんねごめんねー
で、である
掘れば掘るほどダメダメである
帝国陸海軍、ダメダメである
全くなってない
そりゃ負ける
必然
もう全てに於いて人間軽視が貫かれいる
兵士は消耗品
だから戦術は突撃一辺倒
食料は自分たちでなんとかしろ
装備も貧弱、病気はほったらかし
全く居住環境に配慮しない艦船
アメリカ軍は最も貴重なのは「人」という考え
よく分かった
そして今大切なことは、最も貴重な「人」はこっち側にもあっち側にもいるということではないのかね
投稿元:
レビューを見る
皇軍と言われ、勇猛果敢と言われた日本軍兵がいかに虚像であるかを一点の愛情も同情もなく記録と数字に基づき淡々と描く。ただ、その記録に関しての出版がはっきりしなかったり、残された数字をどのような根拠に基づいて変換したのかがはっきりしなかったりするのが気になる。さらに「非売品」というおそらく「自費出版」が多く見られることもその信憑性が心配である。何よりも一番の原因は敗戦前後に関係文書のほとんどを焼却した日本政府にあるのだが…。