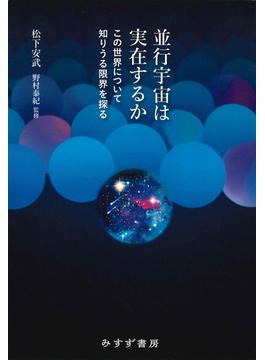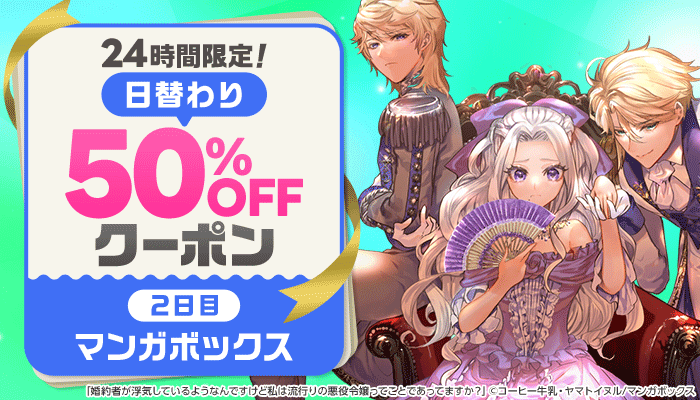投稿元:
レビューを見る
1. マルチバース宇宙論の基本的な考え方と種類
マルチバース宇宙論とは: 私たちの宇宙以外にも多くの並行宇宙が存在するという理論体系。
英語の「universe」は「uni」(一つ)と「verse」(宇宙)を組み合わせた言葉だが、マルチバースは「multi」(多くの)に置き換えた言葉である。
これらの並行宇宙全体をまとめてマルチバースと呼ぶ。
複数のマルチバース宇宙論:
量子力学の多世界解釈: 量子力学の実験結果を説明するために提唱された解釈で、観測が行われるたびに宇宙が分岐し、無数の並行宇宙が存在すると考える(P. 158, 226)。
観測できない世界は確率的に消え去ると考えるコペンハーゲン解釈に対し、多世界解釈では、観測が行われた世界以外の並行世界も存在し続けると考える(P. 213, 226)。
ただし、多世界解釈に基づくマルチバースは、「確率空間」の中に存在するものであり、私たちの世界と地続きではない(P. 159, 164)。
多数の粒子から構成されるマクロな存在である人間が観測を行った場合、異なる実験結果を観測した並行宇宙と干渉する確率はほぼゼロになり、事実上無視できる(P. 226)。
インフレーションに基づくマルチバース: 宇宙誕生直後の急激な膨張(インフレーション)が、無数の泡宇宙(並行宇宙)を生み出したと考える(P. 58, 61, 158, 213)。
インフレーションを引き起こす正体は「インフラトン場」と呼ばれる「何か」だと考えられているが、その正体はまだ分かっていない(P. 58)。
永久インフレーションと呼ばれる現象によって、親宇宙の中で無数の真の真空の泡が発生し、それぞれが独立した泡宇宙として膨張し続ける(P. 61)。
これらの泡宇宙は、外から見ると有限の大きさだが、中から見ると無限の大きさであると考えられうる(P. 79)。
この理論に基づくと、物理定数の値が異なる宇宙や、生命にとって都合の良い物理定数を持つ宇宙など、多様な宇宙が存在すると考えられる(P. 86, 88, 227)。
ブレーン宇宙論: 高次元空間に複数の膜宇宙(ブレーン)が存在し、それらの衝突がビッグバンを引き起こしたと考えるモデル。複数のブレーンが互いに影響し合って重力を及ぼしている可能性も示唆される(P. 210, 211)。
2. 宇宙の膨張と観測可能な宇宙
ハッブル・ルメートルの法則: 銀河までの距離と遠ざかる速度には比例関係があるという法則(P. 50, 108)。比例定数はハッブル定数と呼ばれる。
ルメートルはハッブルよりも先にこの法則を発見していたが、ハッブルがその功績を独占しようとした可能性が指摘されている(P. 50)。
宇宙の年齢: 観測可能な宇宙の年齢は約138億年と考えられている(P. 10)。
観測可能な宇宙の果て: 望遠鏡で観測できる範囲には限界があり、これを「宇宙の果て」と表現することがあるが、それは宇宙に壁があるわけではない(P. 10)。
観測可能な宇宙の果てまでの距離の表し方にはいくつか考え方があり、「138億光年先」とする場合と、「470億光年先」とする立場がある(P. 10)。これは、光が旅してきた時間で距離を表すか、宇宙の膨張を考慮した距離で表すかによる違いである。
観測可能な宇宙の領域はほぼ平らだと考えられているが、わずかに曲率を持っている可能性も残されている(P. 26, 112)。
宇宙の加速膨張: 20世紀末のIa型超新星の観測により、宇宙の膨張が加速していることが発見された(P. 112)。これは、ダークエネルギーと呼ばれる未知のエネルギーの存在が原因と考えられている(P. 113)。
3. 宇宙の構成要素と物理定数
宇宙の基本的な力: 自然界には、強い力、弱い力、電磁気力、重力の4つの基本的な力が存在する(P. 92)。
電磁気力と弱い力はワインバーグ・サラム理論によって統一されている(P. 56)。
これら4つの力を統一する理論の候補として超ひも理論などがある(P. 56)。
素粒子: 物質を構成する最小単位であり、フェルミ粒子とボース粒子に分けられる(P. 128, 186)。
フェルミ粒子には電子、ニュートリノ、クォークなどが含まれる。
ボース粒子には光子、グルーオン、ウィークボソン、重力子などが含まれ、力を伝達する役割を担う。
原子核: 陽子と中性子からできており、陽子と中性子はクォークからできている(P. 92)。
原子核がバラバラにならないのは強い力による(P. 92)。
ビッグバン元素合成: 宇宙誕生直後、水素やヘリウムなどの軽い元素が作られた(P. 94, 95)。
トリプルアルファ反応により炭素原子核が合成される(P. 95)。
物理定数: 自然界の様々な法則を記述する上で使用される定数であり、生命の誕生に必要な元素が存在するためには、これらの物理定数が生命にとって都合の良い値を取っている必要がある(P. 86, 88, 95, 103, 227)。
物理定数の値がわずかにでも異なれば、多様な元素は生まれず、生命も誕生しなかったと考えられている(P. 95)。
これは「微調整問題」と呼ばれ、人間原理によって説明されることがある(P. 103, 227)。
4. 宇宙の形と次元
宇宙の曲率: 空間の曲がり具合は、宇宙スケールの三角形の内角の和を測ることで調べられる(P. 19)。
内角の和が180度なら平らな空間(曲率ゼロ)、180度を超えるなら正の曲率、180度未満なら負の曲率となる。
宇宙全体で曲率が一定だと仮定した場合、曲率が正なら有限の宇宙、ゼロまたは負なら無限の宇宙となる(P. 19)。
高次元空間: 超ひも理論では、この世界は実際には9次元空間であり、私たちが見えている3次元空間の他に6つの隠された次元が存在すると予言している(P. 130)。
余剰次元がなぜ見えないのかについては、小さく丸まっているためと考えられている(P. 130)。
5. トンネル効果と宇宙の始まり
トンネル効果: 量子力学において、粒子が本来越えられないはずの山をすり抜ける現象(P. 44)。
「無」からの宇宙創成: 物理学者ビレンキンは、宇宙が「無」からトンネル効果によって生まれたと考えた(P. 44)。
ここでいう「無」は完全な無ではなく、物理学の法則が適用できる何らかの状態を指す(P. 45)。
ビレンキンは、このシナリオは「量子重力理論」によって説明されるとしている(P. 44)。量子重力理論は未完成である(P. 45)。
6. ブラックホールと宇宙の進化
ブラックホール: 非常に高密度な天体であり、強い重力によって光さえも脱出できない(P. 208)。
ブラックホールの中は別の宇宙につながっている可能性があるという説もあ���(P. 208)。
サイクリック宇宙論: 宇宙が膨張と収縮を繰り返しているというモデル。ビッグクランチと呼ばれる宇宙の終焉の後、再びビッグバンが起きると考える(P. 208)。
エキピロティック宇宙モデルでは、ブレーン同士の衝突がビッグバンを引き起こすと考える(P. 210)。
7. マルチバース宇宙論の検証
直接検証の難しさ: マルチバース宇宙論の多くは、観測可能な領域の先の世界に関するものであり、直接検証することは困難である(P. 212)。
インフレーションの証拠: インフレーション理論が提唱した現象、宇宙の膨張速度の加速や宇宙背景放射の温度の均一性などは観測によって確認されている(P. 56, 57, 112, 168)。
宇宙背景放射の温度のわずかなムラや偏光パターンから、原始重力波の存在を検証しようとする研究も行われている(P. 58, 168)。
超対称性粒子の探索: 物理学者は、超対称性粒子と呼ばれる素粒子を探索しているが、まだ発見されていない。超対称性粒子は、インフレーションの引き金になったインフラトン場と関係している可能性がある(P. 187)。
余剰次元の探索: 余剰次元が存在する場合、短い距離での重力の振る舞いがニュートン力学からずれることが予言されており、実験によって検証が行われている(P. 188)。
8. 宇宙の「幸運」と人間原理
宇宙の微調整: 私たちの宇宙の物理定数は、生命の誕生にとって非常に都合の良い値を取っており、これは「微調整問題」と呼ばれている(P. 86, 88, 95)。
人間原理: 観測者である人間が存在するためには、宇宙は生命が誕生可能な環境でなければならないという考え方(P. 103, 227)。
微調整問題は、人間原理やマルチバース宇宙論によって説明されることがある(P. 103, 227)。もし無数の宇宙が存在し、それぞれの物理定数が異なるとすれば、その中には生命が誕生可能な宇宙が存在する可能性が高まる。
9. 相対性理論と時間の遅れ、空間の曲がり
光速不変の原理: 光の速さは誰から見ても一定である(P. 79)。
時間の遅れ: 相対性理論によれば、運動速度によって時間の進み方が遅くなったり速くなったりする(P. 10)。
空間の曲がり: 質量の大きな物体の近くでは空間が曲がる(P. 20)。
地球の表面のような曲がった面での「直線」は、球の中心を通る大円の一部となる(P. 20)。
望遠鏡で遠くの宇宙を見ることは、時間の遡りにつながる(P. 10)。
10. 量子力学と不確定性原理
量子力学: ミクロな世界の素粒子や原子などの振る舞いを説明する理論(P. 187)。
不確定性原理: 量子力学において、粒子の位置と運動量を同時に正確に知ることはできないという原理(P. 86)。
観測と量子の状態: 量子力学によれば、観測するまで粒子の位置は決まっておらず、観測によって初めて決まる(P. 187)。これは、マクロな人間には奇妙に聞こえる現象である(P. 187)。
コペンハーゲン解釈では、観測によって重ね合わせの状態が収縮すると考える(P. 158)。
多世界解釈では、観測によって宇宙が分岐すると考える(P. 158)。