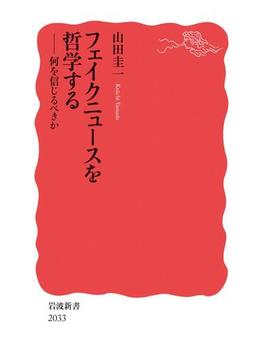タイトル通り、フェイクニュースを哲学的に分析しています。
2024/10/20 14:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
正にタイトルにある通り、当書はフェイクニュースに対して、哲学的に分析した1冊です。
実に冷静に分析されているためか、いつの間にか話に引き込まれ、気が付いたら読み終えていました。
投稿元:
レビューを見る
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1887694678184894579?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
投稿元:
レビューを見る
配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。
https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01433911
投稿元:
レビューを見る
フェイクニュースとは:
定義ではない明確化
真理の価値
他人の言っていること:
リアルとネット
可謬主義と不可謬主義
還元主義=証言だけでは不十分
非還元主義=証言だけで十分
ネット空間での人格の同一性
うわさ;
オルポートの実験
認知的な歪み
コーディの反論
ワンクリックで伝わる功と罪
うわさを楽しむ条件
専門家:
専門家不信
3つの困難ー前提・支持関係・反証
利害関心とバイアス
メタ専門家による同意
査読制度
知的謙虚さ
マスメディア:
情報の門番
フィルターバブル・エコーチェンバーの認識論
陰謀論:
ポパー、ピグデン
歴史学・心理学の陰謀論
カッサムによる批判
反証不可能性
3つの対処法ー反駁・暴露・教育
真偽への関心
投稿元:
レビューを見る
「フェイクニュース」「陰謀論」を突き詰めて考えるとこうなる。分かりきったこと、という自分の常識に自信がある人も常にそれを意識しろということか。
投稿元:
レビューを見る
フェイクニュースという言葉を聞いたのは、2016年の米国大統領選挙の時のトランプ候補の発言だった記憶がある。インターネット時代で、真偽が分からないニュースが飛び交うようになっていた時代だからだと思うが、考えてみれば関東大震災の時の朝鮮人虐殺がそれによるものだったし、太平洋戦争における大本営発表もそうだった。昔から行われていたものだった。それがネット時代になるとともに、大きく注目を浴びたわけだ。しかしタイトル通り、フェイクニュースとは何ものなのか?必ずしも嘘ではなくても、真偽に拘らずに流すニュースが確かにあるし、その理由もさまざま。そして信じるとはどういうことか、噂は信じて良いのか、「専門家」は信じられるのか、マスメディアは信じられるのか、そして陰謀論とは何なのか?なぜ陰謀論を信じてしまうのか?陰謀論の定義は?など深みのある論説の集大成だった。カント、デカルトの言葉までが引用されるほど、哲学的な論証と言って良いだろう。
投稿元:
レビューを見る
書店で気になったもの。哲学的観点で、フェイクニュースの定義から語り起こされる。信用できる専門家の条件として、過去の証言の記録、利害関心とバイアス、同意する専門家の多さ、信念形成ルートの独立性ってのは、なるほど納得。全く目新しいって内容ではないけど、リテラシーの再確認にもってこいの一冊。
投稿元:
レビューを見る
「そもそもフェイクニュースや陰謀論とは?」という哲学的、言語学的な解説がおもしろかった。まさに読者(非専門家)と筆者ら専門家と前提知識を共有するということだろう。結論も単に「情報の取捨選択をしましょう」というような良い子ちゃん風なものではなく好感を持てる。
投稿元:
レビューを見る
哲学するということはあれこれ考えることであるからして、フェイクニュースについて時間をかけることを求めるものになるのは当然なんだけど。だんだんめんどくさくなってくる。ので、引っ掛かるのだろうなあ。
投稿元:
レビューを見る
いつも利用している図書館の新着本の棚で目につきました。
“フェイクニュース” にしても “哲学(する)” にしても、とても気になるキーワードですね。
期待どおり興味深い指摘が多々ありましたが、「自律的に考えるための作法」を丁寧に紹介した良書だと思います。
投稿元:
レビューを見る
インターネット、テレビ、新聞、ラジオ、うわさなど多くの情報が氾濫しています。
その膨大な情報を、どうやったら信じてもいいものなのか、信じるのはよくないものなのか、その判断基準を考えていく本です。
インターネットでXやインスタグラムなどをリツイートして拡散する人の中には、それが真実だろうが嘘だろうが気にしていない人が多数いる、ということが、薄々は感じていましたが、改めて文章で掲示されると衝撃的なものがありました。
常に自分が知的な徳を忘れないで、情報に接し、発信しなければ、と思いました。
投稿元:
レビューを見る
フェイクな情報がもたらす影響論は、歴史をひもとけばカントやデカルトの時代から現代まで様々な形で論じられてきたわけです。インターネットというメディアの登場、社会の変化によって私たちの日常生活にまでフェイクな情報が影響を及ぼす現代、「そもそもフェイクニュース」ってどんな問題なのか、より広範な「知識」における嘘(誤り)の問題、陰謀論の問題、言葉の問題といった視座から論じる本書は、問題そのものというより、問題を理解するためのアングル(視点)、道具を本書はいろいろと紹介してくれます。
本書の帯のことば:
何が真実なのか
結論を急がない
本書も「フェイクニュースとは何か」安易に結論を提示するスタンスでは書かれていないので。
投稿元:
レビューを見る
インターネットが発達して、良くも悪くも情報の扱い方が難しくなった気がします。
たしかに、結論を急がないことが大事なのかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
タイトルに魅力を感じて購入したが、インターネット上の言説を批判的に見ている人には当たり前のことばかり。
目新しい内容は特に無く、“哲学的に考察した“と思しき部分も特には無い。
同じことを違う表現を使って何度も繰り返して書いたり、適切とは思えない例示をしていたり…一つ一つ書いていたらキリが無い。当たり前のことばかりの内容なのに、言葉の使い方のせいで疑問符ばかりが残る。
「序章」に書いてある以下の文が最後まで読めば理解できるのかと思ったのだが…
『…これはフェイクニュースがどういう場合に、許容され、逆にどういう場合に許容されないのかに関わっており、本書全体で考えていきたい。』
『許容されるフェイクニュース』に関しては分からず仕舞いになった。
投稿元:
レビューを見る
まず個人的な印象として、件の兵庫県知事選挙の後に読んだので、その内容に戦慄すら覚えた。
また、"陰謀論"に囚われて抜け出せない人に関する記事等もちょうど最近目にすることが多かったので、そちらも実にタイムリー。
序章から極力平易な言葉遣いで鋭い考察を飛ばしている。
決して革新的で真新しい提唱が為されているというわけではないが、私たちが日常、虚実ない交ぜとなった情報過多社会に生きる中で、なんとなく感じ取っていた曖昧模糊とした焦燥や煩悶を一つ一つ拾い上げて明瞭に言語化し、説明してくれている。
フェイクニュースという言葉自体は比較的新しいものだが、ここで展開されている論法は、例えば"人はなぜ占い(あるいはオカルトでも)を信じるのか"を考察する際に古来繰り広げられてきたそれと重なる部分が大きく、哲学や心理学と相性が良いことが理解できる。
政治的なポピュリズムに対し、"知的なポピュリズム"という概念を打ち出してきたことには、なるほどと深く頷いた。
一方でマスメディアの末端に身を置いてきた一人としては、第4章に差し掛かり神妙な面持ちとなる。
著者による客観的な分析がそこでは行われており、口を極めてオールドメディアの有り様を非難するようなものでは決してないが、これまでと比して劣化してきている面があることは否めない。
期せずして背筋がぴんと伸びていることに気付いた。
人文学に関する専門的な素養を持たない人にとっても分かりやすくしたためられた本書は、カオスのような世の中で意識的あるいは無意識的に"哲学"を用いて思弁する道への格好の入口となり得る。
答えは本の中ではなく、あなたの、私の、一人一人の中にある。
余談ながら著者は私の大学時代のクラスメイトであり、鬱蒼とした森に覆われた彼の下宿にぞろぞろと集まり、夜通しあれやこれやと口角泡を飛ばしていた日々が読みながら思い出された。
と言ってもほぼすべてが何の社会的意義もない単なる与太話であったが…。
「現在、多くの国や社会では、住民投票や選挙等の直接的・間接的な民主的手続きを通じて意思決定が行われている。しかしこのプロセスは、それぞれの社会の成員が政治的な問題に対する判断能力を具えていることを前提にするだけでなく、一人ひとりにある程度正しい情報が共有されていることをもまた前提にする。したがって、もしもこの前提が崩れるとすれば、民主的なプロセスそのものの信頼性が揺らぐことになり、決定された結果の正統性にも疑いの目が向けられることになる。」