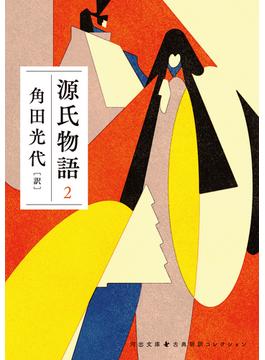投稿元:
レビューを見る
なんといっても葵の上が亡くなってしまうところが悲しいところ。この時代では物の怪が取り憑くとか普通にあったことなのかな。
葵の上と仲良くなってほしかった。
それにしても光源氏は本当に女性が好きだな。こんなに簡単に好きだなと思ったりするのかなーと不思議です。
ついに都を離れて須磨に行く光源氏。残された紫の上が一番不安だと思う。
読み始めたらおもしろいです、源氏物語。
投稿元:
レビューを見る
源氏物語を読むのは教科書以外ではこの文庫本が初めてで、訳の本も初めてです。
なので他の作品がどんな訳になっているのかが分からないので比較できないですが、角田さんの訳なので割と淡々として読みやすかったと思います。
ただ登場人物の名前や続柄や身分などが当時の物などが
よく分からないので相関図を何度も見ながら読んでいました。
現代と時代背景が全然違うし身分や倫理観など全てが違う時代だったので、
それぞれの立場で見てみると「はて?」ということも多々ありました。
それにしても光君の女性に対しての想いや行動力は凄いなと思いました。
華やかなな京を離れて心が穏やかになるかと思ったら、
またそこでも物思いにふけたり、あちらこちらで気持ちがそぞろになるのでかなり繊細な性格の持ち主なのかとも思いました。
女性だけでなく、人生に対しての考え方も垣間見えたのは良かったです。
小難しい所が所々ありましたが、
物語としては面白かったと思うので、
やはりそれだけ引き付けられる文芸書だと思いました。
もっと現代風の訳してもらったら面白味も増すかなとも思いました。
投稿元:
レビューを見る
慣れてきたものの…
光くんは自分から様々な女性に手を出してるのに
「何でこんなに悩んでしまうのだろうか」とか
言っててイラッと来た。
当時読んでいた女性たちは「アイドル」として光源氏を読み、登場する女性達に自分を重ねたり、こんな人いるわぁみたいな感じだったのだろうか…
それはさておき、出会いや別れ歌や言葉を交わすことの重さ、出会いことの一期一会さを深く感じ合いながら他の人々と接している文化が垣間見えて良かった。
明石のあたり紫の上のことも思いつつ、あっさり他の女性へと手を出す…ちょっと怖い。
投稿元:
レビューを見る
文庫版2巻読み終わりました。
あっちこっちで逢瀬を交わし、怖いもの無し絶好調の光君。女性たちの感情は生々しく、しかし優雅に描かれており、その人間描写が味わい深いです。
大切な人との別れがあったり、咎めによって須磨へ流されたり、波乱万丈な巻で、中盤は特に悲壮感に満ちていました。でも左遷された先でも女性と関係持ってるし、なんかだんだんと「そうでなくっちゃ!」って気分になってくるから不思議。
登場人物はさらに増え、各々の人物に厚みが増しています。登場するどの女性もそれぞれに個性が光っており、話の都合上から配置した記号的役割になってはいないので、すべてのシーンにおいて深みのある読書体験ができました。光君が女性を振り回してるようにも見えますが、おそらく逆もまた然りで、女性たちも駆け引きによって光君を振り回している。その男女間、そして人物間での違いは読んでいて本当に面白い。
相変わらず角田光代さんの訳は流暢で読みやすく、次巻以降も楽しめそうです。
んで、前回の読書中に書いたメモ書きが一部の方に好評だったので今回もそのまま掲載しておきます。
【紅葉賀】
頭中将の説明が「光君と立ち並ぶと、桜の花の隣に立つ名もなき木のようである」は笑う。
光君の読み方がたまに"ひかるきみ"じゃなくて"ひかるくん"に見えることがある。だからどうと言うこともないけれど。
こきでん女御
P.18「光君の人形に同じように着飾らせ」本人の人形が作られてるの!?
うつ伏せになってふさぎ込む姫君かわいい。
典侍周り入り乱れとる。
【花宴】
草子地好き。
この顔も名前もよく知らないのに……って文化(文化と言っていいのかはわからないけど)、やっぱりいまの感覚からするとお互い豪胆というか何というか、すごい。
おお、変なところで終わるなこの話。
【葵】
暦の博士?タイムキーパーみたいな職の人ですか?
めのわらわって声に出したくなる、めのわらわ。
光君色んな女性と仲を持ったせいで、ちょっと変わったことが起きないかと退屈してるように見える。
あー、葵の上……。
頭中将いいやつ……けど、でないしのすけ(典侍)のことネタにすんのはどうかと思う……。
あ、ていうか頭中将からすれば葵の上は妹なのか、なるほど。
悲しみと喪失感につつまれてるな『葵』。
【賢木】
登場人物系図が複雑になってきた。
P.130「光君は、それほど深く思っていない時でも、恋のためにはいくらでも言葉巧みに書き綴ることのできる男である」ははは、わかってんじゃん。
光君をクズだとは思わないけど、今でいうところのクズ男の才能はあると思う。
面倒な恋に惹かれがちなのは、光君の癖だし、退屈だからだろうな。
の割に気移りが激しいし、すぐ出家したがるのよくない。よくないわ〜。
頭中将は大事。色んな意味で。
【花散里】
光君の逢瀬を交わした女性のことを忘れないのがだんだん美徳に思えてきた。
って短!この話。
【須磨】
この世は無常。
四季の変化を桜の花��散っていく様子で綴っていたり、こういう部分に風情を感じますね。
入道出てきてようやく話が愉快な方向に転がり始めた。
全体的に悲壮感強いよ2巻。
言われのないって言ってるけど、言われはあるでしょ。
やっぱり頭中将は大事。
【明石】
物の怪のたぐいはたまに出てくるけど、海で嵐にあっても簡単に晴れたりしないあたり、"奇跡"には頼ってないんだなと感じる。
紫式部って明石の浦とか住吉神社まで行ったことあるのかな。それとも伝聞でここら辺は描かれたことなのかな。気になる。
P.272「入道は、それからも数えきれないくらいの多くを光君に語り尽くしたのだけれど、ここに記してもうるさいだけでしょう」よくわかっていらっしゃる。つかここら辺はの塩梅って初の長編小説なのになんで出来ちゃうんだろ。
ってまた詠んだ歌を省略してる笑
身をば思はず
【角田光代によるあとがき】
光君からの愛を拒み続けることで、人生の安定と愛される喜び、あるいは人生のままならなさどちらも拒む姿勢を見せた朝顔は非常に現代的とのこと。なるほどー、早く出てこないかな朝顔。
投稿元:
レビューを見る
「紅葉賀」から「明石」まで。一番好きな女君は花散里なのですが、後書きまで読んで六条御息所の印象が変わりました。読むタイミングや訳によっても異なるとは思いますが。それにしても光君の体力と気力、財力はどれほどのものなのか計り知れない。「須磨帰り」せずにこの先に進めるのは角田さんの訳のおかげです。
投稿元:
レビューを見る
二巻になって断然面白くなった。これは紫式部たちがいろんな集まりでの歌会をそのまま劇にしたような気がする
投稿元:
レビューを見る
"紅葉賀"から"明石"まで。
近江に旅行し、三井寺と石山寺に詣でた時に携帯して読む。
子が生まれ、正妻が死去し、保護者たる父帝も崩御、そして藤壺の出家と、源氏を取り巻く環境が大きく変化し、ついに左遷される。
「葵」の帖のなかで紫の上と契る場面を持ってくるのに衝撃。なぜこのタイミング!?
また訳者も書いていたが、ちゃんと読むと、六条御息所に対するイメージが変わるな、と。
投稿元:
レビューを見る
葵の上の死、須磨への退居など物語が大きく動く。田辺聖子の『光源氏ものがたり』を併読すると簡単におさらいできてとても助かる。こうなると田辺聖子の『新源氏物語』も読みたくなってくる。
投稿元:
レビューを見る
「紅葉賀」から「明石」までを収録。
正妻である葵の上よりも紫の上の元にばかり通う光源氏。藤壺との間に不義の子を成し、六条御息所を等閑にし、朧月夜と逢瀬を重ねる。現代人の感覚からするとあまりに多情で不誠実、一方で“家”に囚われず己が心のままに恋愛できる自由な男にも映る光源氏の姿が、なんとも滑稽で哀れ。光源氏に通われる嬉しさと、通わぬ彼への恨めしさ・彼に通われぬ己(中には明石の君のような、彼に見初められた身分違いの己)への惨めさに翻弄される女君たちの描写も巧み。マザコンでヤリ◯ンの美男子と振り回される女たちの話、とだけでは言い尽くせぬほどの奥行きある物語として読めるは、作者と訳者のおかげだろう。
投稿元:
レビューを見る
疾走感ある今に息づく訳文で、物語の醍醐味が味わえる角田源氏。あどけない紫の姫君が成長していく中、藤壺の宮は光源氏との不義の子を出産する。正妻・葵の上も出産し光源氏の気持ちが寄り添うが、六条御息所の生霊で命を落とす。その後光源氏は朧月夜との情事が発覚し、須磨へと退居することになる・・・。「紅葉賀」から「明石」までを収録。
前半は光源氏の素晴らしい姿が目一杯描かれるだけに、後半の涙に暮れる描写が悲しい。作品としては山あり谷ありで飽きないけれど私はやっぱり光源氏苦手だな・・・。あっちにもこっちにも良い顔するわりに、お前がうろうろ落ち着かないから皆不幸になるんだよバカ!と言いたくなる。紫の上なんてショックすぎる展開。こんないきなり女として扱われるの?いきなり近親相姦されるようなもんじゃん・・・。六条御息所は以前読んだときは本当に怖い怨霊のイメージだったけど、こんな本人もコントロールできない形なら可哀想だなと思った。これも元はと言えば源氏・・・()いよいよ須磨から都に戻って、というところで3巻へ。するすると読みやすい訳で素敵。
投稿元:
レビューを見る
今回は第6帖「花宴」のみ。桜の花の宴が開催され光君は美しい舞を披露する。酒に酔った光君は藤壺に会えないかウロウロするが扉はぴったり閉まる。しかし弘徽殿の扉は開いている。光君が動く!朧月夜(あとで判る)も光君だと思い、夜を共にする。互いに名前を明かさずに扇を取り換えた2人。どうやら弘徽殿女御の妹らしい。今回は光君の行動力が素晴らしい。果敢にチャレンジする(でもストーカー?)。弘徽殿女御の妹ということは、、、(帝の寵愛を受ける)藤壺を憎む弘徽殿女御VS.光君という構図になりかねないのでかなりえぐい状況かな?⑤
投稿元:
レビューを見る
光の君に瓜二つの皇子がうまれ、葵の上、桐壺院の死、藤壺の出家など、どの帖もとても面白い。
車争いや、葵の上にとりつく物の怪など、六条御息所の悲しさをはじめ、紫の上、花散里、明石の君らの深い悲しみも非常に印象深く語られていて、あっという間に読んでしまいました。
やっぱり角田光代さんの翻訳でも光の君にはもやもやします。
投稿元:
レビューを見る
お相手の女性が色々出てくるので、この方はどういう方だったかなと、見返したりして読んでいる。が、今、角川書店のビギナーズクラシックス日本の古典 源氏物語も並行して読んでいるので、これを読み終えて、そちらも明石まで読んで、頭に入れようとしているところです。
投稿元:
レビューを見る
男女の関係が手紙で始まるの素敵だなと。
紙にも気を使い字も評価され…昔の人すごいな(語彙力欲しい)。
六条御息所の生き霊の話好き。
投稿元:
レビューを見る
二巻目が終わった時の素直な感想は
「男の人もよく泣くな」
悲しみの表現として「泣く」なのか、
平安男子はよく泣いたのか気になるところ。
一巻と違い話が急展開。