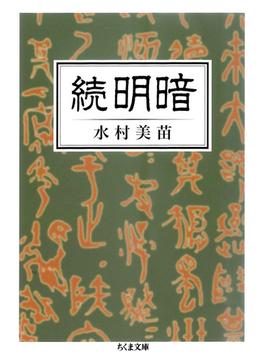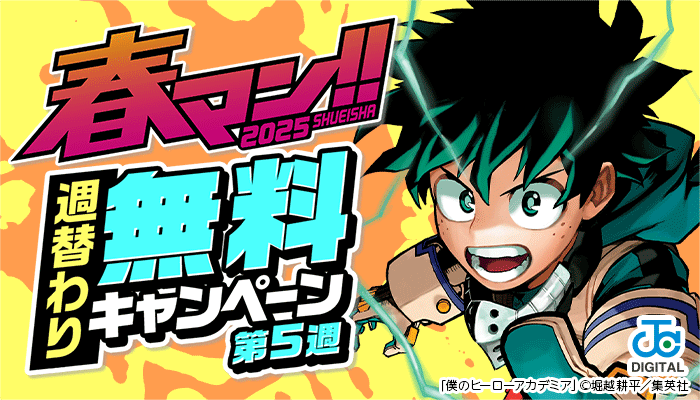自立した小説であり批評ともなっている
2023/01/25 13:27
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る
未完に終わった夏目漱石の『明暗』の続きを書く、夢想しつつもおそれおおいと感じていた人が多いであろうこの作業を見事に成し遂げている。とりわけ後半は単なる漱石の模倣ではなく、自立した小説であり批評ともなっている。
投稿元:
レビューを見る
非常に読み応えのある作品だった。
主人公津田はいつまでも自分の人生を正面からぶつかろうとしない態度、
素直な感情の発露よりそれと同時に現れる下らない理性による体面ばかりを気にする態度によりどうしようもない人間となってしまう。
津田の妻であるお延も初めはそんな主人を無理やり信じながら(心のどこかで疑っていたが)生きてきたが、津田の元恋人の存在に気づき、
半狂乱におちいる。しかしながら、最後には生きていく決意を見出す。
漱石は女性を描くことに関してはあまり評判は良くなかったが、水村氏はとても肌理細かく女性の揺れる心を表現したと思う。
漱石の『明暗』のあとを引き継ぐ名作であった。
投稿元:
レビューを見る
おのぶと吉川夫人の場面では、本当に自分が侮辱されたかのように、胸がカッとなった。
清子の津田への怒り、おのぶの津田への失望、
自分の中にある津田が、えぐられるような思いで読んだ。
投稿元:
レビューを見る
図書館。
「明暗」を読むならこちらも、と欲張ってみました(09.12.14)
こういうのもアリ・・・かなあ。
昼ドラマっぽい展開だと思ったら
著者が意図的にドラマチックにしたらしい。
投稿元:
レビューを見る
漱石の「明暗」と比べると文体に違和感を少し感じますが、物語としてはとても面白いです。
自分がどんな考え方をしている人間なのかを、津田は清子に振られるだけでは気づけなかった。もし婚約破棄という状況になった場合、わたしは自分のことをどれだけ見つめ直すことができるのか。
投稿元:
レビューを見る
日本語で小説を書く、ということを独自の視角から提示しつづけてくれる水村さんが漱石の未完作品を書き継いだ、という意欲作だけに、いつか読んでみたいと思っていました。
漱石の「明暗」から違和感なく、しかも漱石の世界にもともと内包されている激しい心理劇をきちんと展開してくれて、読んでよかった、なんか得したなぁ~という気分。「本格小説」も合わせて、小説好きには広くおススメしたい一冊です。旅行のお供にもなんだかふさわしい!
投稿元:
レビューを見る
異彩を放つ本歌取り―― 2005.10.19記
漱石の「明暗」を読んでもいないくせに水村美苗の「続 明暗」を読んでみた。いわば本歌取りを鑑賞して未知の本歌を偲ぶという、本末転倒と謗りを受けても仕方のないような野暮なのだろうが、それなりにおもしろく楽しめた。
本書冒頭は、漱石の死によって未完のまま閉じられた「明暗」末尾の百八十八回の原文そのままに置かれ、津田と延子の夫婦と津田のかつての恋人清子との三角関係を書き継いでいく、という意表をついた手法が採られている。
換骨奪胎という言葉があるが、過去の作品世界を引用、原典を擬し異化し、そこに自己流の世界を構築するという手法は、古くは「本歌取り」などめずらしくもなく、今日では文芸に限らずあらゆる表現分野に遍くひろまっているとしても、本書の成り立ち方はとりわけ異彩を放つだろう。
著者は文庫版あとがきで「漱石の小説を続ける私は漱石ではない。漱石ではないどころか何者でもない。「続明暗」を手にした読者は皆それを知っている。興味と不信感と反発のなかで「続明暗」を読み始めるその読者を、作者が漱石であろうとなかろうとどうでもよくなるところまでもっていくには、よほど面白くなければならない。私は「続明暗」が「明暗」に比べてより「面白い読み物」になるように試みたのである」という。
小説細部は晦渋に満ちた漱石味はかなり薄らいでいるとみえるも、なお漱石的世界として運ばれゆくが、延子の夫津田への不信と絶望に苛まれ死の淵を彷徨った末に、新しき自己の覚醒にめざめゆく終章クライマックスにおいては、もはや漱石的世界から完全に解き放たれて作者自身の固有の世界となった。
投稿元:
レビューを見る
「漱石未完のあの傑作の続きを書く」という時点で非常に面白いテーマであったし、現代に於ける創作の一つの根幹をついていると思う。それを抜きにしても非常に楽しめた。
あとがきを読むだけでも漱石文学批評として明晰で興味深かった。それは、自らを漱石として創作するという態度によって獲得される批評であり、その上で自身の作家としての本質も浮き彫りになっているように思う。もっと早くに読んでおけばよかったと思った。
「『続明暗』を読むうちに、それが漱石であろうとなかろうとどうでもよくなってしまう — そこまで読者をもって行くこと、それがこの小説を書くうえにおいての至上命令であった。」
「『続明暗』では漱石のふつうの小説より筋の展開というものを劇的にしようとした。筋の展開というものは読者をひっぱる力を一番もつ。・・・さらに心理描写を少なくした。これは私自身『明暗』を読んで少し煩雑すぎると思ったことによる。・・・漱石の小説を特徴づける、大団円にいたっての物語の破綻は真似しようとは思わなかった。漱石の破綻は書き手が漱石だから意味をもつのであり、私の破綻には意味がない。反対に私は、漱石の資質からいっても体力からいっても不可能だったかもしれない、破綻のない結末を与えようとした。」
— あとがきからの引用
そういった意図の中で、少し展開がドラマチックに過ぎる感じが俗っぽい印象を受けてしまうことは否めない。逆に言えば、煩雑な心理描写や広範多岐にわたる脇道が、漱石の小説の魅力であることに改めて気付かされた。
小説を読むという行為やその中で自分が受けている印象、心理の変化について多くのことを教えていただいた様に思う。その意味で、単純な小説作品ではない文学批評作品としても楽しめた。
ものをつくる人間にとっては必読の一冊。
投稿元:
レビューを見る
著者自身があとがきで述べているように、「漱石もこう終えたであろうと万人が納得できる『明暗』の終え方もなければ、漱石に比べられて小さく映らずにすむ現存の作家もいない。」
『明暗』の終わりかけでやっと登場した清子は、謎めいた雰囲気を醸し出していて、本当に良いところで絶筆になったことが残念だった。
『続・明暗』では、清子というキャラクターが、あまり魅力的に映らなかった。その理由は、物語全体から通俗的な匂いを醸し出しているからで、なんて言ったらいいかわからないけれど、清子と津田という物語のキャラクターが薄味すぎて、その上に男女のいざこざが重なっているから、「あー、結局こういうかんじかぁ」と、「昼メロ」的なステレオタイプな印象を受け取ってしまった。
文体は一緒なのだけれど、津田の思想みたいなものが『明暗』に比べて少なくなっているから、「男女間の未練」みたいなものだけが浮かび上がってしまって、私は期待はずれだった。
清子という存在は、未完のままで、私の中では良かった。
投稿元:
レビューを見る
おもしろかった。漱石のことをよくわかっているというわけじゃないから当然かもしれないけど、「明暗」を読んだあとすぐに読んで、まったく違和感なかった。ときどきこれは「続」のほうだ、漱石じゃない、と思い出さないといけないくらい。で、「明暗」よりは後半に動きがあって展開が早くて読みやすかった。ええーそれでどうなるのー、という感じ。淡々としているのに、清子が津田をふったわけを話すところとか、いよいよ謎が明らかに、という気がして、なぜか読んでいてすごく盛り上がった。 でも、なんとなく、またこの先を読みたいような気がした。決着がまだ着かない感じというか。この先、みんなが日常に戻ってからのことを読みたい。 それと、津田って人は女たちに、最後のところで信じられない、とかひどい言われようなんだけど、なんか人間ってみんなこんなものじゃないだろうか、という気もする。よくわからない。そういってみると、小林も吉川夫人もよくわからないような。いろいろ考えてみたい気がした……。
投稿元:
レビューを見る
本の評価うんぬんの前に、漱石という日本を代表する文豪が手掛けた未完
の遺作に手を加えようとする試みを決心した水村氏にまず敬意を表したい。
これは、未だかつて誰もやろうとしなかったこと、あるいは過去に誰かが
やろうと思いつつも勇気を出せずに思いとどまったことであろう。
水村氏は本作がデビュー作ということだが、新人作家にしてこの決断力は
他に類を見ない。現代文学界の歴史に名を刻まれる偉業だと信じて
止まない。
それだけに、作品の出来が非常に惜しく思われる。
漱石の文体はうまく真似できており、雰囲気だけであれば漱石のそれと
大きく変わらない。問題は、心理描写のカットである。これは本人が
認めているように、実力不足から来る断念せざろうえない省略である。
清子が初めて登場するのは『明暗』の後半部分である。
そのため、漱石が描いた清子の心理描写はお延らと比べて圧倒的に
少ない。したがって、清子が何をどう考えているのかといった、清子の
人となりを決定づけるヒントがあまりにも少ない。水村氏はこの不利な
スタートラインから駆け出し、本作の鍵を握る清子を動かし、物語を
締めくくらなければならない。キーパーソンの清子が不十分な描写で
終われば、読者は皆本作に好意を抱かないであろう。
ストーリー自体は評価したい。
私の考えた結末とは異なるものの、水村氏の結末もまた一つアリだと
認めたい。
全体的に心理描写が足らず、特に清子に至っては思惑が読み取れず、
ある意味謎の人物のまま表舞台を去ってしまった印象を受けた。
これが物語を薄っぺらくしてしまっている大きな要因であると考えられる。
投稿元:
レビューを見る
何が哀しくて私は結婚(同居に限って言えば)半年で、
新婚半年の妻が自殺しにいく話をよまにゃならんのだ。
面白かったです。
さほど違和感なく続いています。
どことなく女手だよなぁと感じる箇所がないではなかったのですが(どこだったけかな。。)
三文ドラマにありそな劇的なる展開ではあるのです。
が、面白ければ良し。
関の病が何だったのか、関と清子がうまくいっていないように見えるのはなぜなのかなど気になる点はあるのですが。
信用できないから・・・という下りの女方のものの見方、心情には共感するところ大でした。
投稿元:
レビューを見る
続明暗を本屋で見たときにこれは読まなくてはならないと感じた。明暗を読んだかどうか記憶の無かった私はとりあえずその場で続明暗を購入。家に明暗の無い事を確認して明暗も購入した。
津田の思いや行動に苛立ちながらも終いの方では一緒になったような心持ちもあり不思議な感じがした。
漱石が書いたら、というのは自分にとって想像する必要のないこと。今水村さんが書いた続明暗がここに存在しそれを読めること、読めたことに感謝します。
投稿元:
レビューを見る
漱石はお延に対して、もう少し距離のある描き方をしていたし、それに比例して、吉川夫人のヒールぶりは本作で高まっている。
小説としては面白い。おそらく漱石が完結させていたよりも。
投稿元:
レビューを見る
さすが、ちくま。さすが水村美苗さん。
1990年に筑摩書房から出版された、水村美苗さんの初小説だそうです。面白い。大好き。
新潮文庫になっていたんですね。それが絶版になっていた。それをまた、ちくま文庫が出したんですね。まあ、新潮の方がメジャーですからねえ。でも、僕はちくま文庫さん、大好きです。ちくま文庫がそこそこの分量、置いてある本屋さんが好きです。
閑話休題。
水村美苗さんの本は、以前に「日本語が亡びるとき」(2008)、「母の遺産」(2012)、の二作を読んだことがあります。で、そのどっちも、大変に大変に、面白かったんですね。
感じとしては、丸谷才一さんの本が好きなヒト、夏目漱石や芥川龍之介とか本が好きなヒト、津村記久子さんの本が好きなヒト、などには、おすすめだと思います。違ったらごめんなさいですが。
他に、「本格小説」「私小説」などの本があって、僕はまだ未読です。楽しみです。
リアルタイムで新作が期待できる小説家さん、というのは実に嬉しいものです。
(個人的には、2014年現在では、他に「ほぼ必ず買う」レベルで言うと、小熊英二さん、津村記久子さん、伊坂幸太郎さん、原りょうさん、大沢在昌さん(の、「新宿鮫」シリーズ)…。くらい、でしょうか。一歩下がって、中村文則さん、池井戸潤さん、奥田英朗さん、萩原浩さん、内田樹さん、村上春樹さん…。少年時代に好きだった小説家さんの多くは(殆どが?)亡くなってしまったので。新作が楽しみにできるリアルタイムの、好みの小説家さん、もっと探さないと、愉しみが増えないなあ、と思っています)
という訳で。「續・明暗」。
夏目漱石さんの「明暗」は1916年の小説。
意志の弱いサラリーマンの津田。
上司であり恩人の吉川氏、そしてその強烈な奥さんの吉川夫人。津田は、この吉川夫人の言いなりになっている。
津田はかつて、吉川夫人の紹介で「清子」という女性と交際した。
結婚したかったが、振られた。
その後、お延という若い、うぶな女と結婚。
そんな津田が日々のお金のやりくりに苦労しながら。胃腸を病んで治療しながら。
吉川夫人の言いなりになって生きている。
新婚の妻・お延は、左程、吉川夫人に隷従しては、いない。
吉川夫人は、自分に精神的に服従しないので、お延を疎ましく思っている。ところが、初心なお延はそんなことは何も知らぬ。
なんとなく、吉川夫人がお延を精神的に貶めようとしている陰謀を感じる。
津田は吉川夫人に、「湯治に行け」と言う。
お金を出してあげる。仕事も休んで良い。
その湯治場には、人妻になった清子が、今湯治しているから、会ってこい、と。
会って、どうして自分は振られたのか聞いてこい、と。その代り、そのことを当然ながら、お延には黙っておけ、と。
そして、津田が不在の間に、
「お延は自分が教育しておいてあげる」
と。何だか怖い。
で、津田は湯治に行く。とうとう清子と会う。どうなるどうなる。お延の身には何が起こるのか。
で、漱石死没、未完。
水村美苗さんの「續・明暗」は、その続編。で、多分ですが、別段漱石のメモや遺稿があった訳ではなくて。水村さんの推測というか想像というか創造というか、のようですね。
漱石もそうですが、水村さんも、とにかく文章がすごいですね。
これ、なかなか一言で言うと安易ですけど、やっぱり凄いんですよ。
無駄がない。品がある。けど気取ってない。読み易い。率直。でも含意含蓄がある。うーん、もっと印象論で言うと、日本語への愛がある。技術がある。思索の積み重ねがある。
日本語と言う道具を、実に巧みに華麗に大胆に。
…なんていうか、新体操の選手さんがリボンとかそういう道具を扱うように。ため息がでるような捌き。
アートというのが芸術であったとして、それが技術なんであれば。成程、小説というのは畢竟、言葉の技術である訳ですね。
そして、「明暗」と変わらぬ味わいの、心理サスペンス。これが強烈です。
小心者の見栄っ張りの津田は、清子に言い寄るのか。
吉川夫人はどう、お延をいじめるのか。
無邪気に夫を信じていた若い女房お延は、プライドを汚されて、どうする。どのように壊れるのか。
犯罪サスペンスのように、津田の精神的倫理的犯罪が進行する。悪漢小説。ピカレスク・ロマン。罪は実際に犯されるのか。
そもそも、人妻になっている清子は、何を考えているのか。
ある意味、夫婦ともども、破滅にずるずると落ち込んでいく。そう、ボヴァリー夫人なんです。タマリマセン。オモシロイ。フローベール、大好きです。
ちなみに、フローベールの「まごころ」を漱石が読んだ、という批評文が残っているそうですね。「ボヴァリー夫人」は、フランスでの発表が1856年。日本語訳は、ネットの情報によると、1916年だそうです。漱石の死去は、その年の12月。明暗の連載開始が5月。漱石はボヴァリー夫人を読んだんですかねえ。フランス語は読めないにしても、ひょっとしたら日本語訳を待たず、英語訳で読んでいた可能性もありますよね。
と、考えたりするのは愉しいことですが。
まあ、ボヴァリー夫人のような、ある種の破滅していく粗筋で、漱石が考えていたかと言われると、違うような気がしますけど。水村さんが言及しているように、漱石の小説って粗筋、運びという次元で言うと、終盤に華麗に独特の破綻を起こすことが多いですからね。
そう踏まえると、水村さんがあとがきで、「意図的に漱石のタッチよりもドラマチックにした」。とても納得。ああ言う「味のある華麗なる破綻」を真似してもしょうがないですもんね。
と、いう訳で、「續・明暗」。終盤の怒涛の展開は、確かにドラマチック。僕は嫌いじゃないです。漱石の作品じゃない、水村さんの小説ですしね。堪能、脱帽、剛腕にして大胆、そして美味な文章を、ごちそうさまです。
未読の水村さんの本、また楽しみにしたいですね。そして、何より新作が待ち遠しいですね。2014年、2015年かな。もっと先かも知れませんが。
同時代を生きている水村さんが、何を書くのか。わくわくします。同時代進行形で楽しめるのが、いちばんの読書の快楽なのかも知れませんね。
まあ、そう思える物書きさんは、そうそう簡単には、見つけられないものなんでしょうけど。
####################
あらすじというか、備忘録で言うと。
津田は湯治場で、人妻となった清子と交流する。清子は積極的ではない。けれども津田は未練と執着があって、近づく。
お延は、吉川夫人から、「津田が独身時代に執着していた女と会いに行ってるぞ」とねちねち言われる。恥をかかされる。お延は精神的に打撃を受けて、湯治場に向かう。
津田は結局、再度ふたたび、清子に振られる。清子には見透かされていて、意思が弱い、自分が無い、己の醜悪さを全て指摘される。がーん、となってるところに、清子とふたり連れの場面を、やって来た女房お延に目撃されてしまう。
更に、お延の失踪に等しい湯治場への暴走が波紋を呼んで。東京の親族や関係者まで心配して湯治場に来る。夫婦は大恥をかくことになる。どうやら矢張り、全ては吉川夫人の自作自演の陰謀。自分の紹介なのに津田を袖にした清子。そして自分を尊重しない、お延。この二人を同時に辱めて、自らの優位を示すためなのか。
夜半、お延は最早、自死しようと。滝に身を投げようと宿を出る。津田が気づいた時にはもう、居ない。その上、津田は胃腸が壊れて下血する。そんな中でようやく津田は、吉川夫人の悪意を実感する。もう言いなりになるまい、と思う。お延は滝まで行くが、山の自然を感じて、なんとなく自殺を思いとどまる。以上、終わり。