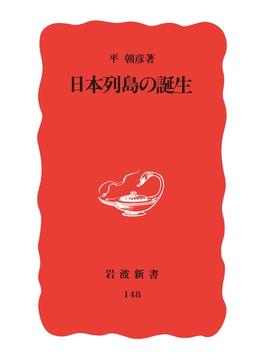地球は生きている!
2020/05/26 21:02
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岩波文庫愛好家 - この投稿者のレビュー一覧を見る
地震大国、日本。全国各地にある断層、数年話題になっている南海トラフ・・本書では地学をかなり専門的に解説しながら、日本列島の出来方について解説してあります。一読の価値あり、です。
日本列島は北海道の右半分を除いてアジア大陸、もう少し詳述すると、韓国と北朝鮮北部とロシアのエリアから離脱して生まれたというものです。確かに日本海側の地形を嵌め込んでいくと、ほぼそうなります。一方で伊豆半島は遥か南方から日本列島に衝突してくっつき、北海道東部は今よりも北東部から動いてきてくっついたという構造です。
普段経験する地震や、各地で見られる火山活動の映像を目にすると、地球はまだまだ現役の活動途中にあるのだと痛感せずにはいられません。でももしこの活動が終着すれば・・。おそらく地震はなくなり、火山活動もなくなる・・、但しそれは地球の死を意味するのだろうなぁ、と感じ複雑な思いにとらわれました。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トニー - この投稿者のレビュー一覧を見る
JAMSTECの理事長として名前は知っていたが、著作を読んだのは初めてだった。もちろん専門の論文を読む力は私にはないので、読む、といっても一般向けの入門書のようなものになってしまうのだが。この一冊は、研究者としても、文筆家としても素晴らしい!面白い本だ。
研究に対しては誠実で、飽くなき探究心が彼を真理の解明へと駆り立てる。こういう人が組織のトップにいればおのずと組織は活性化し、若手研究者の研究環境も整っていくであろう。
投稿元:
レビューを見る
この本は、付加体地質学や日本列島形成史などの基礎的なことを学ぶのには、非常に良い入門書だと思います。
投稿元:
レビューを見る
私たちにとって日本列島の誕生はとても凄いことである。日本列島がなかったら、もしかしたら日本人はこの世にいなかったと思う。そんな日本列島はどうやって誕生したのか。なぜ、日本は列島になったのか。そんな疑問を持っている人は居ると思います。この本は、日本列島の誕生がわかる本です。この本を読んだら日本列島の誕生のことがよくわかりました。みなさんもこの本を読んで自分たちの国、日本列島の誕生を是非知って下さい。
投稿元:
レビューを見る
正直言って、少し難しかった。地質やテクトニクスなど、いわゆる地学の分野の知識が十分でないためと思われるが、何しろ、日本列島の現在の形が骨の髄まで染み込んでいるので、シルル期だのデボン期だのといった大昔の状態はイメージすら難しい。
それでも、プレートの沈み込みによって付加帯が形成されていくこととか、そこに働く力によって様々な断層ができることなど、東日本大震災以降よく説明されるメカニズムが少しよく分かった。
元々は、八ヶ岳や南アルプスの山並みを見て、また、その近くのフォッサマグナに想いを馳せ、これらの山ができた原因を知りたいと思ったのが本書を読むきっかけであり、その目的はある程度達したが、もっと大きなことを知った。特に、中央構造線の北と南で形成プロセスが全く異なっていて、そもそもの場所も全然別であったというのは知らなかった。
誰にでも薦められる本ではないが、もう少しこの分野に詳しくなってから再読したい。
投稿元:
レビューを見る
日本列島の形成過程をデータを元に仮説検証しています。数々の試行錯誤の結果であると思いますが、ロジカルに形成過程が説明されており、現時点では(とは言え上梓されたのは20年前)もっとも信頼がおけると思います。
本書を読んで驚いたのが、プレートテクトニクスを始めとする地球物理学が比較的新しい学問なのではないかということでした。
宇宙の観察と比較して深海調査が困難なのか、地域色が強い学問であるため世界的な知恵が集中しにくいのか...
本書の中では、日本海が開いて行く過程が面白くワクワクしながら読む事ができました。日本列島形成の歴史を知ると、日本列島の形状そのものが愛くるしく感じますし、山脈の皺が寄っている方向にさえ楽しみを見出す事ができます。さらに、東名高速道路を厚木から富士川あたりまで運転するときに見える景色が今までとはまったく違って見えそうです。
時間軸を巻き戻し、古の海溝を走っていることを想像しながら、海底2万マイルの世界に入り込めるかも。くれぐれも事故に注意しなければ。
投稿元:
レビューを見る
現在の日本列島を特徴づける山地を始め,我々が今日立っている地面の基盤となっている岩体が,どのようにして形成されてきたかを,プレートテクトニクスにより説明した本.筆者が沈み込み帯や付加体といったテーマを専門に研究していることもあって,全体の構成もそうした部分が中心になっており,日本列島を形作ったテクトニクスそのものがどういう原理であったかという部分は深く扱わない.
高校~大学初頭レベルで習うような地学の専門用語は説明無しで使われていることも多く,一般向けというにはやや難しい本.一方地図や露頭の解説図などが豊富で,説明も丁寧なので,地学の前提知識のある人にとっては,日本列島の成り立ちを包括的に理解する一助になる.時々地図に記載のない地名が出てきたり,口絵の衛星写真では判別できないような特徴について言及していたりすることがあるので,インターネットの地図サービスを併用すると良い.
内容は1990年当時ということもあって,やや古いところもあるものの,大まかな流れをつかむには十分と思われる.
投稿元:
レビューを見る
1990年刊。著者は東京大学海洋研究所教授。◆日本列島の物理的形成過程を地質調査とプレート変動等の地質学的見地から解明しようとする書。個人的に難易度高いが、その理由は①地質年代の理解不足、②各地質年代の大陸模様の理解不足(超大陸パンゲアくらい)、③現在の各海嶺、海溝等地名の理解不足、④地層変動の基礎概念の理解不足等に基づくだろう。地球全体の大陸変動(平面図では歪みが出る)、それが現代の地域とどう結びつくのかも表しにくいかもしれない。ただ、北米、ユーラシア、フィリピン海、太平洋各プレートの集合する日本近域。
ユーラシア大陸の東端でインドが大陸を押している(ヒマラヤ山脈形成)こと等が影響している点、といった複雑な動きをする只中に日本が存在することはよく理解できた。
投稿元:
レビューを見る
日本列島の形成の歴史が、とてもダイナミックなものであることがわかります。
* 日本列島の大部分は、海洋プレートが沈み込む際に、プレート上の堆積物が大陸縁部で削り取られてできた(付加体)
* 元々中国南部にあった日本列島の太平洋側は、約1億3000万年前に北に移動して現在の日本海側に並んだ。中央構造線はその横ずれの名残り。
* 約1700万年前に日本海が拡大して大陸縁部が大陸から離れ、海が流れ込んだことによって日本は島となった。
これらが詳細に解説されており、図も多いので、とてもわかりやすいです。他にも、日高山脈や伊豆半島の形成などが解説されており、日本列島の成り立ちを様々な面から概観できます。日本列島の教科書的な内容と言えると思います。
また、研究の歴史を振り返りながら書かれているので、読み物として楽しめました。
投稿元:
レビューを見る
日本列島がどのようにして誕生したのか。
自分たちが生まれ育った場所だからこそ、興味が湧いたタイトルである。
投稿元:
レビューを見る
個人の研究の進行や発展の順序通りに書かれているので、四国四万十一帯の地層がどう形成されたかという局地的な内容から入り、そこから日本各地の地層の比較、そしてアジア各地との比較と移り、最後にまた自分の話に戻る。
内容は学術的だが話の展開はあまり学術的でないように思う。エッセーに近いかも。学術よりにいくなら本来はアジアの形成から入って日本列島の形成に入り、地方地方の成り立ちに細かく分け入るのが筋だろうと。
やはり個人的には新赤版よりも旧赤版のあの淡々と自分の専門を述べていくスタイルの方が好きかな。新赤版は読みやすさでも意識したのか、内容が薄い。文字が大きいのも正直却って頭に入らず困る。
投稿元:
レビューを見る
⚫︎日本列島の履歴
日本列島ってどうやってできたんだろうと知りたくなり、購入。地盤について、以前から興味があり、地層の構成や、地盤図等をみるたびに、これはなんでこうなっているんだろうと疑問を持っていたところ。
本書では、基本事項の説明はないが、四万十帯の事例から始まり、日本列島の成り立ちまで書かれており、後半になるにしたがってどんどん引き込まれていくような内容でした。
付加体、ダービタイトなどの動きを知り、地球の大きな動きを知ることで、地盤ってこうやってできていくんだなと、感覚的なものがわかりました。
日本海と太平洋はでき方や構造がまるで違う、東京湾の中には川があった、平野、山のでき方、インド大陸の衝突による歪みなど、驚きの連続で、興味がつきませんでした。