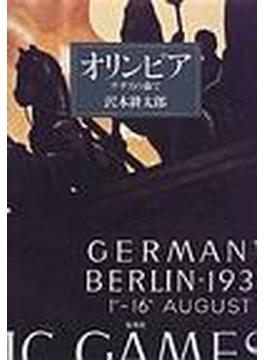「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発行年月:1998.5
- 出版社: 集英社
- サイズ:20cm/334p
- 利用対象:一般
- ISBN:4-08-783095-0
紙の本
オリンピア ナチスの森で
著者 沢木 耕太郎 (著)
1936年夏、ヒトラーの威信をかけて開催されたベルリンオリンピック。その「民族の祭典」の真実の姿とは。記録映画「オリンピア」の監督レニ・リーフェンシュタールをはじめ、日本...
オリンピア ナチスの森で
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
1936年夏、ヒトラーの威信をかけて開催されたベルリンオリンピック。その「民族の祭典」の真実の姿とは。記録映画「オリンピア」の監督レニ・リーフェンシュタールをはじめ、日本人選手等の証言から探求する。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
沢木 耕太郎
- 略歴
- 〈沢木耕太郎〉1947年東京都生まれ。横浜国立大学卒業。ノンフィクション作家。「テロルの決算」で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に「バーボン・ストリート」「敗れざる者たち」「深夜特急」ほか。
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
ベルリン・オリンピックにズーム・イン
2002/04/10 21:24
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読ん太 - この投稿者のレビュー一覧を見る
レニ・リーフェンシュタールが撮ったオリンピック映画『オリンピア』をベースにして、1936年のベルリン・オリンピックについて書かれたノンフィクションである。
昔のオリンピックの様子を知る楽しみと、ヒトラーのオリンピックへの関わり方も知る事ができて、なかなか内容の深いものになっている。 不況下のドイツでオリンピック会場を滞りなく整えることができたのは、皮肉なことにもヒトラーのおかげであったようだ。
オリンピックの様子は、現在とのあまりのギャップに驚くことがたくさんあった。シベリア鉄道を使って十数日、船を使うとおよそ1カ月かかってベルリンの会場に着いたことなど、当たり前のことだとは思いながらも驚いてしまった。
また、ベルリン・オリンピックを機にラジオが大普及したことを知り、「ラジオか!」としみじみした気持ちになった。大画面じゃ、高画質じゃどころか、人々は映像を見ることもかなわなかった時代なのである。ベルリン・オリンピックの映像は、レニが『オリンピア』というオリンピック映画を作って初めて世に出ることになるのだが、これでも、作成に2年という歳月を必要としており、今から考えると全く気の長い話に思えてくる。
選手の心情の違いも顕著である。「思いっきり楽しんできま〜す。」と笑顔で手を振りながら出かけていく現代の選手に比べて、当時の選手達には悲壮感が漂っている。「メダルを逃したら切腹もの」だとか、「負けたら日本に帰れない」あるいは、「家族や親戚が村八分」みたいな雰囲気があるのだ。 「前畑がんばれ」の前畑選手が金メダルを取ってくれたおかげで、水泳は命拾いしたようである。
マラソンで優勝した孫基禎は、日本人としてオリンピックに参加した。朝鮮は日本の属国であったのだ。「君が代」を聞きながら日の丸が掲げられるのを見上げる孫、オリンピックから帰還した孫を迎えた人々の歪み。国民をあげて喜べない金メダリストを出す状況にあった日本、その後の戦乱、流れるべきところに流れていく様子が理解できた。
オリンピック競技そのものについては、不完全がより楽しみを広げる要因になっていたのではないかと感じた。不完全ゆえに、今から考えるととんでもないレースが行われていたりするのだ。たとえば、バタフライ。ベルリン・オリンピックの頃に新種の泳法として現れたものだそうで、驚くことに大会では、平泳ぎのレースでバタフライをする選手が混じっていたのだ。
昨今のオリンピックは、世界新記録は出ているのだろうが、どうも「行き着くところまで行き着いた」という感じがしてならない。普通の人では理解できない域に入ってきているのではないだろうか? と思えてしまう。もしかしたら選手達にも理解できないものになりつつあるのかもしれない。ドーピング検査が厳しくなればなるほど、これを証明しているような気がする。
オリンピックももはや活字で楽しむものとなってしまったのだろうか。彗星のごとく現れた! と叫ばれる選手を出すには、ドーピング検査に血眼になっている前に、「不完全」をじっくり考えることではないだろうか。
紙の本
沢木耕太郎の中でせめぎ合うフィクションとノンフィクション。
2001/03/15 16:19
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
村上春樹の『シドニー』を読んで、「おお、そういえば沢木さんのオリンピックものをまだ読んでいなかった」と思い出した。
オリンピックをどう捉えるか、ルーザーたちの人生に対する温かな眼差しが含まれているに違いないことは、彼のこれまでの仕事ぶりから察して読み始めたが…なんと、これは!
わが敬愛するスーパーレディのレ二・リーフェンシュタール女史に対し、ベルリン・オリンピックのドキュメンタリー映画「民族の祭典」撮影背景について鋭いナイフの切っ先を向けた内容ではないか。
今はなき池袋・西武美術館のこけら落としだか第2回目の展示がレ二の写真展で、アフリカのヌバという民族を撮影したものだった。彼女の回顧録はどうやら版元絶版になってしまったようであるが、ナチス・ドイツの宣伝塔と呼ばれたレ二が、いかに旺盛な制作意欲をもったクリエイターであり表現者であるかが面白く熱中して読んだものだった。
「時代と寝た女」という表現があるが、ナチスに翻弄され誤解を受けながらも自分の美意識や感性の表現に忠実に生きようとするレ二の意志が毅然として美しかった。
ところが、ヒトラーの広告戦略として利用された偉大なる記録映画「民族の祭典」には、試合後の撮り直しという「リメイク」がいくつか含まれていたこと、彼女が競技の流れを迫力あるものにするために、確信犯的にフィルムの裏焼きを編集したことなどを沢木さんは指摘している。ドキュメンタリーではなく、修正を施したレ二のブロマイドのようではないか…と。
そのエピソードが巻頭と巻末にあり、世界の人々の心にベルリン・オリンピックのイメージとして強く焼きついたものの実態を追う流れが底流として置かれている。沢木さんは、その上で勝者となった選手や敗者となった選手はじめ役員・報道関係者など当事者へのインタビューを重ね、思いがけないエピソードをいくつも掘り起こしている。
西洋の行進曲に合わせて歩くのに慣れていない日本人選手団の入場行進がどんなものであったか、3000人の大合唱団による「ハレルヤ」が選手の心にどんなものを残したか、テレビがなく電送写真の技術が未熟な中での新聞報道やラジオ報道の苦労、2週間強に及ぶ9000キロを移動する選手たちの経験はじめ、体操競技の跳馬をどう演技したらいいのか、水泳競技の予選から決勝までどんなレース運びをしたらいいかなど、情報がほとんどなかった選手たちの当事の練習や本番への取り組みも書かれている。
そんなことはかけらも書かれていないが、シューズやユニフォーム、器具の技術開発が目まぐるしく、ルールの改定も多く、開催国や主催者を潤わせるための商業主義がはびこる現代のオリンピックに比べ、戦前のオリンピックが持っていた競技会としての素朴さ、その姿がくっきり浮き彫りにされていて興味深かった。
「オリンピア」というタイトルはレ二の映画のタイトルでもあるが、沢木さんは、これから彼がベルリン以外のいくつかのオリンピックについても文章を書いていくに当たり、彼女へインタビューで「仁義」を切っておきたかったのだと述べている。
「民族の祭典」を一つの土台にしたベルリン・オリンピックに続いて、他にどんなオリンピック像を見せてくれるのか、今後の展開が待たれてならない。