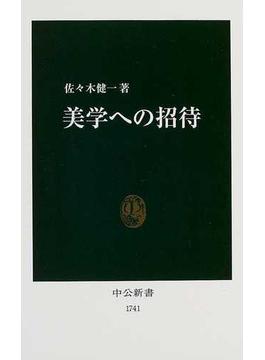紙の本
読みやすい
2016/02/02 11:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:onew - この投稿者のレビュー一覧を見る
東京大学の推薦図書サイトに紹介されていた本。美学に関する入門書、一般向けに書かれた本だけど、特に美大志望の高校生や美大1年生に良いと思う。
投稿元:
レビューを見る
教授に「授業受ける前に読むと良い」と薦められた本。初心者向けに平易な言葉で書かれていますが、重要なことを押えておりわかりやすく勉強になります。
投稿元:
レビューを見る
『現代の美学は、作者の「意図」を、証言によって確かめても無意味だ、と考えています。たしかに、作者が自作を誤解するということは、珍しくないようです。しかし彼が誤解している、と言いうるのは、少なくとも作品に固有の「意図」のようなものがあるからでしょう。わたくしはそれをin-tensionと呼ぼうと思います。作品には、内部に独特の緊張がみなぎっていて、それを捉えることが大切なのです。』
投稿元:
レビューを見る
僕のような美学について全く知識がない人には難解な本でした。
この本によると、美学とは「美と藝術と感性を論ずる哲学」、らしいです。
藝術が美しかったのは過去のことで、背後に精神的な次元を隠し持ち、それを開示することを真の目的としている活動が藝術、らしいです。
今日の美学では、作者の証言や人生に従って作品を理解するやり方は正当なものではなく、近代藝術はその藝術概念ゆえに藝術史を知らなければ分からないもの、らしいです。
僕に藝術が理解できる日はまだ遠いみたいです。
投稿元:
レビューを見る
講義の教科書として買ったんですけど面白そうなのでパパーっと読んじゃいました。
美学がなにか、っていう本じゃなくてほんとに招待の部分を重視したような内容でした。
エッセイ読むような気持ちで読めます。
著者の先生がちゃんと仕事を終えきったのかそれがきになります笑
投稿元:
レビューを見る
大学で教科書と指定されたため購入
タイトルの通り、難しい専門用語を使わずにできるだけわかりやすく用例を用いさわりの部分を説明してくれる本
アレクサンダーゴッドリブバウムガルデンからはじまり現代の美学に至るまで
それと、俺の美学に反する、とか私の美学に合わないなあという使われ方の美学とは異なるので読むときはそれに注意
投稿元:
レビューを見る
文字通り「招待」という感じだった。入門にはよいと思う。できることなら,ここからさらに思考を進めていければ。
投稿元:
レビューを見る
美とはつまるところ、センスの章でも書かれていたように、<言葉にならないもの>のうちの一つということですね。それは近代に知覚されるべきものから、考えられるべきものになり、芭蕉が説いた「不易流行」の概念のように、永遠で変化しない者があると同時に、新しさが必用であるもの。また、設計図では書ききれるものでもなく、作り出されるというよりは、恵みとして与えられるもの。それぞれ納得はできるが、良く分からないというのが本音。奥が深い。
投稿元:
レビューを見る
[ 内容 ]
二〇世紀後半以降、あらゆる文化や文明が激しく急速に変化しているが、芸術の世界も例外ではない。
複製がオリジナル以上の影響力を持ち、作品享受も美術館で正対して行うことから逸脱することが当たり前になってきている。
本書は、芸術が、いま突きつけられている課題を、私たちが日常抱く素朴な感想や疑問を手がかりに解きほぐし、美と感性について思索することの快楽へといざなう、最新の「美学入門」である。
[ 目次 ]
第1章 美学とは何だったのか
第2章 センスの話
第3章 カタカナのなかの美学
第4章 コピーの芸術
第5章 生のなかの芸術
第6章 全身を耳にする
第7章 しなやかな応答
第8章 お好きなのはモーツァルトですか?
第9章 近未来の美学
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
投稿元:
レビューを見る
美学の入門書として推薦されて手に取りました。
身近な問題から導入が話されていてわかりやすく、近現代の美学の課題について丁寧に論じられており、興味深い一冊でした。
「芸術とは何なのか」という現代アート出現による解釈学の全く根本的な問いの成立など、ざっくりと問題意識を提起されているような印象をもち、初学者としてためになる一冊だったように思います。
投稿元:
レビューを見る
美とは作り出されるものではなく、恵みとして与えられるもの。だからこそ人は美を追求するのであり、『美しい』という言葉は日常会話においてあまり語られない。
投稿元:
レビューを見る
音楽、美術などアートに関わる人には、アクチュアルな問題が並ぶ。もちろん鑑賞する人にとっても。
古典的な美学の説明は最低限で、現代芸術をどう見るか・評価するかに内容がさかれている。
投稿元:
レビューを見る
本書は美学の概説書ではない。「あとがき」で著者が、「この美学の入門書を、学説を紹介することなく、言い換えれば何も参照せずに、心のなかにあることだけでつづる、という方針を立てていた」と語っているように、ふだんの生活の中で出会う素朴な疑問や感想を取り上げて、わかりやすい言葉で考察を進めている。
著者は第1章は、そもそも美学という営みがどのようにして形成されてきたのかということを、簡単に論じている。近代になって、人間はみずからの力で社会を創造してゆくことができると考えるようになった。そこで、創造的な力を持った「天才」が求められることになる。そして、科学とともに芸術が、天才の活躍する領域だと考えられるようになった。こうした近代的な芸術館とともに、天才の創造性を把握する感性の学として「美学」が誕生する。その後、現代に入って芸術のあり方が多様化し、感性的で観照的な美的体験によっては理解できない作品が登場するようになると、知性による解釈や、幅広い美的概念を扱うことのできるような美学が現われてきた。
第2章以下では、美的な事柄にまつわる素朴な疑問が、美に関する本質的な問題につながってゆくことを示す考察が展開されている。たとえば、「センス」とは何か、カタカナで表現される「アート」は「芸術」とどのように違うのか、さらに、複製芸術の成立や、スポーツと芸術の接近、芸術と関わる身体のあり方といった観点から、私たちの芸術の鑑賞の仕方を問いなおしている。
ふだん見過ごしている美学的な思索の「芽」は日常の中にあるのだということ、そして、それを大切に育んでゆくことから美学の思索が生まれるということを学ぶことができたように思う。
投稿元:
レビューを見る
思った以上に専門的じゃなかった本。
現代アートや現代音楽と斬新な分野を扱った内容で、建築とかもあって面白い。
ただ、筆者の考えは年齢を感じます。
美学界でも権威っぽい筆者だけど、
読み終えても美学についてさっぱり分かりません 笑
そのぶんいろいろ考えさせられるので。。
もっと美学について読んでみようと思います。
投稿元:
レビューを見る
美学の問題について、自分で思考するヒントが沢山得られた。知りたい分野について本を読んでも知識一辺倒になりがちなので、手にとってよかった。次は美学の流れを外観できる本を読んでみたいと思う。