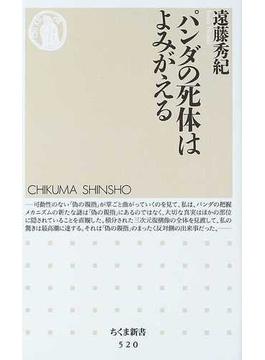「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
動物の遺体は人類共有の財産
2005/06/28 21:14
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゆうどう - この投稿者のレビュー一覧を見る
「遺体科学」を標榜する動物学者による、死体を素材にした動物エッセーである。死体(著者は、死んだ動物たちに敬意を表してあえて「遺体」と呼ぶ)を研究することで、さまざまな動物の謎が解明できる。その実例を著者の豊富な経験からいくつかピックアップして、動物学的な側面から解説を加えている。
例えば、タイトルにもあるパンダの「偽の親指」。著名な動物学者スティーブン・ジェイ・グールドの著書の標題にもなっているテーマだ(邦訳『パンダの親指』)。手先の不器用なクマ科のジャイアントパンダがタケの茎を握れるのは、本物の親指の根元に突き出た橈側種子骨(とうそくしゅしこつ)=「偽の親指」のおかげである、というのが学会の定説であった。しかし、上野動物園で死んだフェイフェイの遺体を分析し、実際にものをつかませるなどの実験を行った結果、この骨は固定されていて動かず、人間の手のように物を掴む機能はないことが判明。まさに「偽」の親指だったのだ。さらに観察を重ね、小指の付け根に「第7の指」、副手根骨を発見。この骨と掌の間にタケの茎を挟んで「持っていた」事実をつきとめる。まさに、「遺体」と向き合わなければ得られない発見である。
最近話題のレッサーパンダにも、「偽の親指」があるという。こちらは、手のひらの中で浮遊し、対象の大きさに合わせて移動し、物をつかむのに役立っているらしい。
上記のような動物たちの意外な真実を、遺体を調べることで明らかになった発見をもとに教えてくれる。ゾウ、ツチブタ、アリクイ、ニホンオオカミ……。皆さんは、渋谷駅の象徴である忠犬ハチ公の死因を知っていますか?
紙の本
死体を調べることで生きた動物をより深く理解できることを示す好著
2007/11/05 23:29
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Skywriter - この投稿者のレビュー一覧を見る
あの愛くるしいパンダは、熊の仲間である。そして熊の仲間であるということは、親指が他の指と対向していないことを示している。だとすると、パンダはどうやって竹を掴んでいるのだろうか。
パンダの手には人間の親指に相当する骨がある。そしてその周りを筋肉が取り巻いている。この偽の指のおかげでパンダは円筒形の竹を掴むことができるのだ。
と、信じられてきた。
この神話を打ち破ったのが著者である。パンダの遺体をCTスキャンにかけることで詳細な骨のデータを手に入れ、解剖することで筋肉の動きを理解することで、パンダをより深く理解する。本書はパンダの”親指”の謎を解明したことで一躍名を馳せた解剖医による、解剖学の魅力の解説書である。その立場について、著者はこう述べる。
「生きとし生けるものは、今日も遺体に変わり果てる。それを文化の源泉ととらえるか、それとも不要不急の”生ごみ”として廃棄してしまうか。いうまでもなく私は、人類の知を生み出す根源として遺体を大切にしていくのが正しいと信じるが、それは学者が社会を変革し、社会を説得し切って続けていくべき、アカデミズムの闘いなのだ。(本書P.216より)」
著者の信念は「すべての遺体は学問に、文化に、そして人類の知に貢献する」だという。実際に数多の遺体と格闘して知の世界を切り拓いてきた著者の言葉だから重みがある。
本書で取り上げられている例だけでもパンダ、象、レッサーパンダ、モグラ、ツチブタ、イリオモテヤマネコなどが挙げられ、それぞれがユニークな生物であることがとても分かりやすく表現されている。また、ハプスブルク家のコレクションにあるコウモリ、忠犬ハチ公、かわいそうな象、テディベアに名を残すセオドア・ルーズベルトなど面白い話題が目白押しだ。
扱っているのは遺体だとしても、本書に動物への愛と知への飽くなき探究心が込められているのは間違いない。科学博物館に行って知的好奇心を広げたくなる、そんな一冊。
紙の本
「遺体」に隠されている「情報価値」を熱っぽく語る本。
2009/07/21 17:44
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
パンダの手のヒミツを書いた絵本を読んだらとても面白かったので、もう少し詳しく、と読んでみました。絵本の話のもとになった研究者自身が書いた一般向けの本です。
パンダの話も詳しく出てきましたが、それも題材の一つで、全体のテーマは博物館や動物の遺体の扱い方についての著者の考えを述べた本、と言った方がよいでしょう。
研究者の立場から、著者は貴重な動物の情報を捨てずに利用すること、後世にも残すことの重要性を、著者は熱をこめて語ります。
解剖なんて血と内臓の匂いがしてきそう、と嫌な気分になるひとも少なくないでしょう。たしかに第一章のゾウの解剖の話などは、「腕まくりの科学」と言った感じの「血と汗」が感じられる、臨場感溢れる描写です。その中から、巨大なゾウの体の仕組みはどうなっているのか、実際に切り開いてみなければわからないことも確かにある、ということが熱をもって伝わってきます。
著者の語り口は、一寸熱すぎて苦手に思えるかもしれません。ある意味では科学者の典型のひとりかもしれないのですが、たとえばゾウの遺体を前にした想いがこんな風に書かれます:
「死は終りではない。私にとっては始まりである。・・・いまから取り組む相手が未だ人類が知り得ない秘密をどれだけその遺体に包み隠しているのかに思いをはせながら、これ以上はない学者としての幸せに震えているのだ。」
こんな文章は、もしかしたら「マッドサイエンティスト」のイメージに重なってしまうところかもしれないですね。
著者の分野の科学的手法も、他の分野とはかなり特殊なところもあるのではないか、という感もします。「動物が死んだ」という情報が入ってから、「その動物の遺体からなにができるか」を最大限考えるのが著者の仕事、といった表現は、きちんと実験計画をたてるだけでなく、「この研究にはこの生物」と「モデル生物」まで先に考えて進んでいくタイプの科学とはかなり違うようです。
パンダの手の話は第二章に詳しく出てきますが、骨や筋肉の名称など専門用語がかなりあるのでちょっと難しく感じるところです。骨の図だけで、筋肉を想像し、動きを想像するのは結構至難の業でした。素人には、この話を基に描かれた絵本(冒頭に書いたもの)の方が、ポイントだけおさえてあって大人にもわかりやすい、と言う気がします。専門家って、ついきちんと書こうとして伝わりにくくしてしまうところがあったりするんですよね。
動物の解剖を「遺体科学」と考えたい、という著者の熱い想いはこの本に充分書き表されているでしょう。
少し離れてしまいますが、以前読んだ「死因不明社会」を思い出したりもしました。病気で亡くなった人も、命を終えた後ににできることとして「どんなことが原因だったのか」や「治療は上手くいっていたのか」などを解剖やCTスキャンデータで残してもらうことができる。これも自分が生きている社会、人間への知識への貢献という点では「遺体科学」かもしれません。
動物の保存された標本、化石をたどると、様々な変化を知ることができる。今現在は調べる技術がなくても、保存してあれば未来に調べることができる。確かにそういうことはあります。そうなると、「火葬」習慣が続いた日本などは、ヒトの情報の欠落をつくっているのだろうか、と考えてしまいました。未来に「ヒトの変化」を調べようとしたら、「現代のヒト」のデータは未だ「土葬」の残っている地域のものに偏っていたりして・・・。「遺体科学」の立場からみるとどうなんでしょうね、遠藤さん?