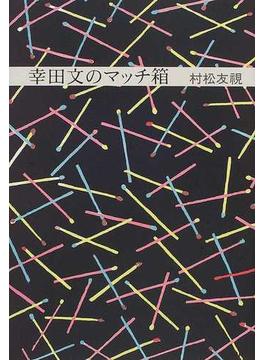「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
「幸田文」の旅をしてみよう−。母の死、父・露伴から受けた厳しい躾、弟の死、継母との関わり…。作家・幸田文はどのように形成されていったのか。その「作品」と「場所」を綿密に探りつつ、幸田文世界の真髄に迫る。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
村松 友視
- 略歴
- 〈村松友視〉1940年東京生まれ。慶応大学文学部哲学科卒業。出版社勤務を経て、文筆活動に入る。「時代屋の女房」で直木賞、「鎌倉のおばさん」で泉鏡花文学賞を受賞。著書に「永仁の壺」など。
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
なんて可愛らしい人でしょう、幸田文って。そう思います。でも、相手が文壇きっての2枚目、村松なら仕方がないかな
2005/10/10 19:19
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
幸田文のところに話をしにいくようになった村松がふと目にしたマッチ箱。それは幸田文が千代紙を貼ったものだった。訪問するたびにそれをもらい始めた経緯を語る第一章 幸田文のマッチ箱、七歳で母と死別した文の記憶の始まりは、第二章 母の死から、通いはじめた学校で知らされた父・露伴の再婚は第三章 継母のいる風景。
姉のように美しくなく、おとうとのように誕生を望まれていなかったと自分を見つめる少女の第四章 みそっかすの眼、読んでいて思わず顔が綻ぶ父娘の仲は第五章 露伴の躾、20歳を前に結核で亡くなってしまった弟への思いは第六章 〈おとうと〉の色、24歳で結婚した文の離婚までを第七章 結婚と性。
実家に戻り父の死を迎えるまでの9年の歳月は第八章 〈流れる〉季節、幸田文の作家としての自立と独特の文章について第九章 語り口と文体、文の中に生き続ける父・露伴の教え第十章 この世学問、法輪寺の三重塔再建に奔走する文と宮大工から見た老女の姿第十一章 斑鳩の渾身、72歳を越えた文が出会った『崩れ』、年齢を感じさせないエネルギーを第十二章 〈崩れ〉の宇宙、あとがき。
装丁は菊地信義、装画は菊寿堂いせ辰(竹久夢路筆 マッチ)
書き下ろし作品で、「みそっかす」の引用に際し、旧かなは新かな遣いにあらためられています。
ともかく伝わってくるのは、年老いた文のなんともいえない可愛らしさでしょう。少女めいた、とでも言ったらいいでしょうか。それが、よく若ぶって却って気持ち悪がられるお年寄りとは大きく違います。「みそっかす」に出てくる文章にもそれがよく出ていますが、私はまず第一章で、松村が幸田の作るマッチ箱に目を留め、それを欲しいと言われたときの文の表情、それが目に見えるようで好きです。
第九章に村松が清水でとれたばかりのしらすを、幸田邸に届ける場面があります。その玄関での文のしぐさ、あるいは第十章での自分の就職をめぐる割り切り、第十二章での、最後に残ったおにぎりに手を出す時の様子、若い人に背負われて山を登る老女の姿、どこか艶めいて、それが自然で、ああ、ご存命中にお会いしたかった、そう思わずにはいられません。
それから、第七章の絹を着ることのエロスをめぐる美輪明宏との話は、意外性があって面白かったです。私なんかは絹の着物を素肌に直に着る、という経験がないものですから、女はみんな感じる、と書かれてもピンとは来ませんが、もしかして祇園や銀座にお勤めの方たちは、そうそう、なんて肯いているかもしれません。その点、美輪さんは知ったかぶりもせず、男としてそういう感じがないことを断言します。ホントはどうなんでしょね。
気になる点が一つ。それは幸田文その人のことではなくて、彼女の作品に対して村松が「文芸」に分類し、「文学」ではないとする点です。日本人が明治期にいろいろなものに「学」とか「術」とかつけてしまい、本来の学ぶというものを捻じ曲げてしまった、というのはこの20年くらい、色々なところで言われてきたことです。
文学作品についても純文学だエンタメだという分類も、結果としてなされることはあっても、それが本質的なものかというと、所詮はジャンルだろ、見たいな認識が根付きました。でも、村松の中には、その区別、というか序列が歴然としてある、それを知ったことは驚きでした。お前、いつの時代の人間だ?みたいなものですね。
幸田が村松のそういう見方を知ったら、どう反応しただろうか、そう考えるだけでもワクワクしてきます。
紙の本
馬鹿なアホな。桑原武夫と幸田文。
2009/05/05 16:48
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:和田浦海岸 - この投稿者のレビュー一覧を見る
まずは、余談から。
雑誌諸君!の巻頭コラム「紳士と淑女」は徳岡孝夫氏が書かれていたのでした。その徳岡孝夫氏は1930年生まれ。ということで、昭和5年(1930年)生まれの列挙。
渡部昇一・岡崎久彦・日下公人・日高敏隆・上田篤・加藤秀俊・渡辺京二・松永伍一・佐々淳行・飯島耕一・平岡敏夫・竹村健一・半藤一利・小山内美江子・粕谷一希・田代慶一郎・米谷ふみ子・武満徹・大庭みな子・開高健・向井敏・上坂冬子・岸田今日子
こうして同じ年生まれの人たちを並べるだけでも、何か壮観な感じを受けます。さて本題、幸田文についてです。
桑原武夫と幸田文とは、ともに1904年生まれ。
ということで、お二人を結びつけて見たくなりました。
ここでは、上方弁と東京っ子言葉という視点で。
まずは、桑原武夫・司馬遼太郎対談から
「『人工日本語』の功罪について」と題された対談で、
司馬遼太郎は、こう語っておりました。
「・・いまの発言は、わたしが多年桑原先生を観察していての結論なのです(笑)。
大変に即物的で恐れいりますが、先生は問題を論じていかれるのには標準語をお使いになる。が、問題が非常に微妙なところに来たり、ご自分の論理が次の結論にまで到達しない場合、急に開きなおって、それでやなあ、そうなりまっせ、と上方弁を使われる(笑)。
あれは何やろかと・・・・。」
これに対して、私は「幸田文のマッチ箱」の第九章「語り口と文体」にある言葉を、重ねてみたいのです。
「幸田文が文机の前に坐り、原稿用紙の上を走らせている鉛筆を止め、ふと宙をにらんでいる貌・・・それは、ひとつの文章の流れの中に書き表すべき、次の言葉を宙から引っぱり出そうとしている貌だ。あれこれ思い浮かぶ言葉は、いずれも的の芯を射ていないような気がする。幸田文はその的の芯を射る言葉を、じっと待って、時の経過を忘れる人ではなさそうだ。そんなとき、幸田文はえい! と気合をかけて、もうひとつの抽出(ひきだし)を開けその中にうごめく江戸語の余韻をもつ東京っ子言葉のひとつをつまみ出す。そして空白にそれをポンと置いてみる。そうやってから、前後の文章を整え直す。そのようにして、幸田文流の文章と喋り言葉の結合というスタイルが紡ぎ出されていったのではなかろうか。・・・・」
さてっと、最後は桑原武夫氏に登場ねがいましょう。
桑原武夫対談集「日本語考」(潮出版社)には、各対談のはじめに、桑原氏による簡単なコメントが付けてあるのでした。先に引用した司馬さんとの対談には、どういうコメントがはいっていたか。それを引用しておきます。
「自然言語から文明言語に移るときに失われてしまうもののあることは否定できないが、この移行は歴史的に不可避なものである。そのさい混乱を少なくし能率をあげるために、人工的規制を加えることが多くの滑稽さを生むことは事実である。文学者ないし文筆にたずさわる者の任務は、機能化されたことばの組合せの中に、人間自然の美しさをどのようにして生かすかを工夫するところにある。」
う~ん。これだけじゃ、あまりにそっけないかなあ。
もうすこし、司馬さんの対談中の言葉を引用してみます。
「・・まあ、標準語で話すと感情のディテールが表現できない。ですから標準語で話をする人が、そらぞらしく見えてしょうない(笑)。あの人はああいうことをいってるが、嘘じゃないか(笑)。東京にも下町言葉というちゃんとした感情表現力のあることばがありますが、新標準語一点張りで生活をしている場合、問題が起きますね。
話し言葉は自分の感情のニュアンスを表わすべきものなのに、標準語では論理性だけが厳しい。ですから、生きるとか死ぬとかの問題に直面すると死ぬほうを選ばざるを得ない。生きるということは、非常に猥雑な現実との妥協ですし、そして猥雑な現実のほうが、人生にとって大事だし厳然たるリアリティをふくんでいて、大切だろうと思うのですが、しかし純理論的に生きるか死ぬかをつきつめた場合、妙なことに死ぬほうが正しいということになる。【そんなアホなこと】とはおもわない。生か死かを土語、例えば東北弁で考えていれば、論理的にはアイマイですが、感情的には『女房子がいるべしや』とかなんかで済んでしまう。なにが済むのかわからないけど(笑)。」
【そんなアホなこと】といえば、
最近出た平凡社の「幸田文しつけ帖」「幸田文台所帖」を読んでいると(これは、小説よりも随筆を中心に編まれたアンソロジーとなっておりより身近感があります)、露伴と幸田文との親子のやりとりが随筆中に再現されているのでした。さすがに「そんなアホな」いうのは出てきませんが、「馬鹿」というのは、もう潤滑油のようにして要所要所に出てきていたような感じがあります。