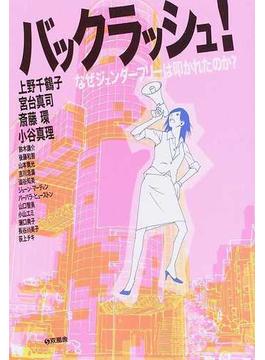「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発行年月:2006.7
- 出版社: 双風舎
- サイズ:19cm/441p
- 利用対象:一般
- ISBN:4-902465-09-4
紙の本
バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?
「ジェンダーフリー」が性差をなくす? 伝統文化を破壊する? なんでも男女混合? 豪華執筆陣が、ジェンダーフリー教育や男女共同参画社会に対するデマやバッシングを分析しつつ、...
バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
「ジェンダーフリー」が性差をなくす? 伝統文化を破壊する? なんでも男女混合? 豪華執筆陣が、ジェンダーフリー教育や男女共同参画社会に対するデマやバッシングを分析しつつ、「男女平等」の未来を描きなおしていく。【「TRC MARC」の商品解説】
収録作品一覧
| ねじれた社会の現状と目指すべき第三の道 | 宮台真司 著 | 10-99 |
|---|---|---|
| バックラッシュの精神分析 | 斉藤環 著 | 102-120 |
| ジェンダーフリー・バッシングは疑似問題である | 鈴木謙介 著 | 121-136 |
著者紹介
上野 千鶴子
- 略歴
- 〈上野千鶴子〉1948年生まれ。京都大学大学院博士課程修了。社会学者。東京大学大学院人文社会系研究科教授。著書に「家父長制と資本制」「差異の政治学」など多数。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
女に依存しない自己肯定の思想を構築しますか、
2006/07/11 12:23
10人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗山光司 - この投稿者のレビュー一覧を見る
《解消すべきは、生物学的な性を社会的・文化的な性のありようと同一のものとして結びつけるような考え方や社会構造であり、異なるジェンダー間の権力関係であり、差別構造であって、ジェンダーそのものでないはずだ。(山口智美 p259)》至極もっともなことを書いているし、何が問題なのか実のところよくわからない。
恐らく、ジェンダーフリーの言葉自体がそれぞれの論者で、それぞれの文脈で手前勝手に道具概念として装填されているもんだから、バックラッシュ言説と反バックラッシュ言説とが噛み合わないのでしょうか、小山エミの「『ブレンダと呼ばれた少年』をめぐるバックラッシュ言説の迷走」にしても小山エミの水も漏らさぬ論述は説得力があって僕なんか素直に頷いてしまうのですが、バックラッシュ側は見たくないもの、聞きたくないものを閉ざしてしまうのでしょうか、まあ、反バックラッシュ側の言説を体系的に読んだことのない、僕としてはそのことに対してとやかく言う資格がないのですが、恐らく理屈でなく「情」で読まなくてはいけないのでしょうが、「情」として読むためには発話者が強烈なキャラでもって僕にオーラを浴びせることが前提条件ですが、少なくとも僕にはかような光線を感じることが出来ないのです。
問題はバックラッシュをしている人々が本書をクールに読んでくれるかどうかで、編集者が再三、ブログでもまえがきにも書いているように次なるステージへの叩き台として読んでもらいたいと謙虚に書いて、第三の道を提示してはいるが、そのような啓蒙活動が彼らの神経を逆撫でバリアをより強固にするおそれがありますね。
それより、ジェンダーフリーという言葉を使わないでタダ単に「男女平等」の一点張りで運動として効果があれば、それでいいでしょう。憲法上、国際法上認められた差別撤廃は当たり前のことなのです。当たり前のことを当たり前にやる。その実践をそれぞれの人々が日常の暮らしの場で学習の場で働く場所で「男という抑圧」、「女という抑圧」から自由になってまず、自分の頭で考え抜くことでしょう。
その前提で僕の最低限の自明の一線は問題の解決を個人の意識に還元するのではなく、制度の問題として問いを立てる。運動が稼働すれば、その中でアイデンティティとしての「男らしさ」、「女らしさ」が骨格となってバーバラ・ヒューストンの言う(p213)“fredom from gender bias”の具体的な姿が個々に出現する。それは勿論、終りのない更新で問題解決をする。一つの解決が別の問題を生む。そんな連鎖に忍耐強く付き合うことでしょう。そんな運動の中でギリギリに個に落とし込んだ「男」、「女」、「それぞれの性」が立ち上げる。多様性こそ、豊饒の謂いであり、そのモラルは最低限手放したくありません。
僕が本書で宿題を負わされた気になったのは上野千鶴子さんの次の言葉です。
≪女についてはもっとあからさまに、男に認められることが女の価値だといわれてきました。それに対してフェミニズムは、「男に選ばれようと選ばれまいと、私は私」という思想の装置を提供してきた。「私の価値は私が決める。男に選ばれることによって、私の価値は決まらない」フェミニズムは、そのように女の自己解放のために思想を鍛えてきたわけです。いま、そのような自己解放のシステムを、男がつくれるかどうかが問われています。(p432)≫
そのような言葉をそっくり返して、「オレの価値はオレが決める。女に選ばれることによってオレの価値は決まらない」と男を鍛えますか?
歩行と記憶