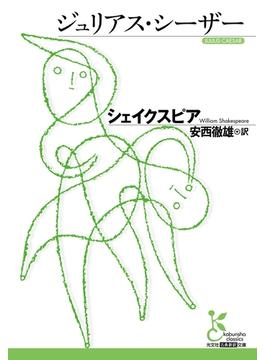ジュリアス・シーザー
著者 シェイクスピア (著) , 安西徹雄 (訳)
シーザーが帰ってきた! 凱旋する英雄を歓呼の声で迎えるローマ市民たち。だが群衆のなかには、彼の強大な権力に警戒心を抱くキャシアス、フレヴィアスらの姿があった。反感は、暗殺...
ジュリアス・シーザー
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
シーザーが帰ってきた! 凱旋する英雄を歓呼の声で迎えるローマ市民たち。だが群衆のなかには、彼の強大な権力に警戒心を抱くキャシアス、フレヴィアスらの姿があった。反感は、暗殺計画の陰謀へとふくらむ。担ぎ出されたのは人徳あるブルータス。そして占い師の不吉な予言……。耳をくすぐる言葉、卑しい媚びへつらいにも動じないシーザーに、死はとつぜん訪れた。息遣いが聞こえる演出家の名訳・第2弾。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む