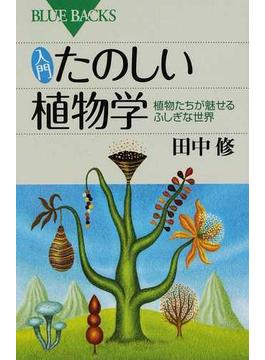「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
入門たのしい植物学 植物たちが魅せるふしぎな世界 (ブルーバックス)
著者 田中 修 (著)
電信柱に突如咲いた美しい花々、ガラスビーズで栽培したシイタケ、メロンとカボチャからできた怪しい「メロチャ」…。植物のふしぎな生態を紹介しながら、植物学の基礎をたのしく学べ...
入門たのしい植物学 植物たちが魅せるふしぎな世界 (ブルーバックス)
入門 たのしい植物学 植物たちが魅せるふしぎな世界
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
電信柱に突如咲いた美しい花々、ガラスビーズで栽培したシイタケ、メロンとカボチャからできた怪しい「メロチャ」…。植物のふしぎな生態を紹介しながら、植物学の基礎をたのしく学べる画期的な入門書。【「TRC MARC」の商品解説】
「ミスター植物学」が、植物のふしぎな謎に迫る!
植物学はおもしろい!
電信柱に突如咲いた美しい花々、ガラスビーズで栽培したキノコ、真っ赤な突然変異レンコンなど植物のふしぎな生態を紹介しながら植物学の基礎をたのしく解説します。まったく新しい植物学の入門書!
<植物たちのふしぎな生態>
●電信柱に美しい花々が咲いた
●根からいきなり芽が出ることがある
●枝の途中から新しい品種が生まれる「枝変わり」
●太鼓の音を聞かせて、シイタケをはやす
●花の色で、生まれる子孫(種)を守る
●メロンとカボチャからできた?「怪しいメロチャ」【商品解説】
目次
- 第1話 電信柱に咲く花の謎
- 第2話 赤色のレンコン
- 第3話 植物の光感覚
- 第4話 ガラスビーズでキノコを栽培
- 第5話 七色のプロトプラスト
- 第6話 遺伝子の組換え
著者紹介
田中 修
- 略歴
- 〈田中修〉1947年京都生まれ。京都大学大学院博士課程修了。農学博士。甲南大学理工学部教授。つぼみの形成や開花のしくみを研究。著書に「ふしぎの植物学」「つぼみたちの生涯」「緑のつぶやき」他。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
こんなに植物って、面白いのか!と思わず驚く一冊です!
2020/02/07 15:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、最新の科学的知識をと分かり易く解説してくれると大人気を誇っている「ブルーバックス」シリーズの一冊で、同巻は、植物学の入門書です。同書は「ミスター植物学」と呼ばれる田中修氏の執筆によるもので、実に楽しく、不思議な植物の生態について書かれています。例えば、同書には「電信柱に美しい花々が咲いた!」、「根からいきなり芽が出ることがある!」、「枝の途中から新しい品種が生まれる<枝変わり>」といった実例が示され、これらについて詳しく解説されています。読み始めるともう止まりません。「こんなに植物って、面白いのか!」と驚いてしまう一冊です!
紙の本
TVネタからの導入が多いのが気になりますが、
2007/05/22 16:26
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「なんでこんな植物ができたのか?」とか「なぜこんな栽培法が考案されたのか?」とか、その基礎になる知識をわかりやすく説明してくれる本です。さらにはちょっと踏み込んで、高校の教科書にも隠れている一寸した疑問などにも触れ、教科書も漫然と読むだけでは見落とすこともある、と教えてくれたりもします。
著者はテレビのニュース番組や科学番組にも出演し、ニュースに取り上げられるような植物の話題を解説している学者。ニュースで流れてくる話を「へえ!」「なるほど!」とただ聞き流すだけでなく、そこから科学の本質にちょっとでもつながるものを捉まえる手がかりを説明してくれるこういう本はたまにはあってよいでしょう。
なかなか楽しく読める、タイトルどおりの本でした。筆者の文章はリズムもあって気持ちもよいです。しかし、読み終わって少し複雑な思いも残りました。どこそこのテレビのニュースにでてこんな風な場面をとった、だれそれと対談した、という話がたくさん載っているのですが、本業への時間が削られてはいないのでしょうか、と。こういう活動も、昨今の大学研究者には要求されるのでしょうけれど、「リアクション芸人」一歩手前のような使われ方の扱いを喜んでいるような文章は・・・。「余計なお世話」ですが、バランスを大事にしてください、とつい、思ってしまいます。最近は「出すぎる」方が多いようなので。
ちょっとした面白い「テレビ的話題」から「植物学」の基礎知識へ。テレビを見るだけでなく、このような本でもう一歩正しい知識に歩を進めることは大事だと思います。でも、そこからもう一歩、面白いと感じたことに次は自分で歩み寄って欲しいとも。観察してみるとか、調べてみるとか、最後は自分で動いてみないことには、知識はなかなか「身につかない」ものですから。