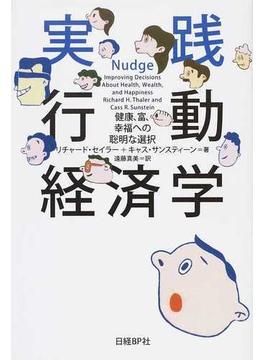紙の本
小さな政府/大きな政府の対立を超えて
2010/01/21 01:25
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:梶谷懐 - この投稿者のレビュー一覧を見る
邦訳のタイトルはややミスリーディングだと思う。確かに前半は行動経済学の説明であるが、むしろそれはツールとしての必要からなされていて、主眼は著者の政治的立場である「リバタリアン・パターナリズム」の内容とその実践に関する説明の方にある。そしてそこにこそ、小さな政府と大きな政府という古典的な対立では捉えられない、現代社会の変化をとらえた本書の重要な問題提起があると思う。
たとえば、学校の食堂カフェテリアのメニューの並び方は、学生たちの食事の選択に決定的な影響を与える。言うまでもなく、最初におかれたメニューほど選ばれやすいからだ。このメニューの並べ方を各種の政府による制度設計に置き換えてみれば、それはやはり必ず人々の行動に影響を与える。どうせならば、選んだメニューが子どもたちの健康を促進させるよう並べるべきではないのか?それがパターナリスティックな介入であり、「選択の自由」を奪うからといって、最初から全くのランダムにメニューを並べるべきだ、と主張するのはばかげているのではないか?
このような議論をするとき重要なのが、「エコノ(経済人)」と「ヒューマン(普通の人)」の区別である。一言で言ってヒューマンにとって「選択の自由」はそれほどありがたいものではない。ヒューマンが自由に振舞うとき、かならず感情や雰囲気、周りの人々の決定に左右される。カフェテリアでおいしそうだが高カロリーのメニューが最初に並べられれば、ついそれを手にとってしまう。その結果、時に自分にとって不利な選択をする。この点において、本書はエコノを前提として選択の自由の重要性を説いたミルトン・フリードマンを痛烈に批判する。
ここまでは、本書の立場はヒューマンの限定的な合理性ゆえに「大きな政府」を支持する立場と同じである。しかし、そこで政府がなすべきことは、直接的な所得の再分配や市場にゆがみを与える規制でなどではなく、あくまでも食堂のメニューの並べ替えのようなもの、つまりアーキテクチャ設計によってヒューマンによりよい選択のインセンティヴを与えること(=ナッジ)で実現しようというのが、リバタリアン・パターナリズムの立場である。そしてその制度設計には、従来の新古典派経済学ではなく、行動経済学こそが重要なツールとなる。
そこで、新たな問題点が二つある。一つ目は、本当に望ましいアーキテクチャを設計できるだけの人材をうまく調達できる仕組みを、政府部門であれ民間部門であれ持つことができるのか、ということである。もう一つは、かりにそれができたとして、アーキテクチャの設計から排除され、自らは導かれるだけになった人々が、そのこと自体に不満を漏らすことはないかのか、ということだ。本当に重要な決定から排除されているということに気づいた人々が、パターナリズムに対する「理由なき反抗」を起こさないという保証はあるだろうか。
いずれにせよ、ちょっと考えただけでもリバタリアン・パターナリズムは突き詰めていくと、民主主義の根幹に触れるような問題を含んでいるといえそうだ。「民意の反映であればたとえ愚かな選択であっても受け入れる」のが民主主義の精神であるとするなら、リバタリアン・パターナリズムは明らかにそれとは相容れない契機を持つからだ。そんな点からも、本書は小さな政府/大きな政府という対立を超えて、今後の社会にとっての重要な問題を提起している、といえるだろう。
紙の本
ノーベル賞を受賞したセイラー教授の代表作です!
2017/11/19 13:26
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
私たち凡庸人は、不合理な行動と自分自身の決断力の弱さに振り回される人生を送っています。こうした我々の人生をよりよくするには、社会に、若干の「ナッジ」を吹き込めばよいと筆者は言います。この「ナッジ」とは、強制やインセンティブに頼らず、人々を賢い選択へと向かわせるちょっとした工夫のことを指します。本書では、この「ナッジ」について丁寧な解説とともに、それをどう社会や制度に組み込むかが、非常にわかりやすい方法で書かれています。我々の人生を豊かにする人生の指南書です。
紙の本
Nudge
2021/01/12 10:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
原著の書名はNudge であるが、訳本では実践行動経済学としている。
Nudgeという言葉が適当な日本語訳に無く、ナッジというカタカナ表記にしても一般的でないということなのだろうか。本書全体に日本文として理解しにくい箇所もあり、こなれた訳文ということでもないようだ。
世の中の様々な場面に際して行う判断、意思決定について、アメリカの事例などを引き合いに具体的な説明が続く。個人の貯蓄や投資、借金問題、社会生活上の医療や環境問題、さらには婚姻制度についても言及している。
よりよい選択をするために、ナッジによる手助けを人々に提示してあげることが大切だと説く。自身の体験を考えてみても、貯蓄や投資、保険などについて契約の細部などよく把握せずに利用している事がほとんどである。電気製品なども取扱説明書をよく読まず、上手に使用しているとはいえない。PCやICTに至ってはよくわからない段階でも利用せざるを得ないものだが、日常生活上必須アイテムとなっている。
本書の終わりの部分ではナッジについて異論も含めて総括議論を展開する。
本書が出版された2007年頃はサブプライムローンによる金融危機に見舞われた時期である。このような経済危機対応としてナッジの利用についても言及している。ただ、ナッジがあれば解決すると言っているわけでもない。
金融危機の原因として、強欲と腐敗というものがあるとし、人間なら誰しも持っている弱さが大きく影響していた述べている。そして、このことを十分に理解することも非常に重要だと最後に述べている。ナッジも悪意を持った人間に悪用される危険性もあるということなのか。しかし、完全に防ぎきれないことだ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る
けっこう難しかったです。図書館でフラっと気になって読んだのですが、難しかった。しっかり学ぶ意欲のある人向け。
投稿元:
レビューを見る
経済学は、「合理的個人」を前提とし、行動経済学は、「限られた能力しか持たず、感情に突き動かされ、自制に悩む人間」を前提とする。
後期高齢者医療制度などは、「感情による判断が先行」した悪例ではないか。制度への悪評は、導入から一年経てかなり収まってきたという。「保険料が年金から天引きされるのはけしからん、75歳で区切るのは姥捨て山だ」という感情的反感が薄れたためだという。小泉劇場のひとつとして医療改革を感情的に排斥する動き(民主党の保険組合制度を一元化する政策など)が見られるが、『命の値段が高すぎる』(永田宏著)では、感情論を抑えて医療改革の背後に隠された意図に注目せよと警鐘を鳴らす。
(著者の関連議事録、資料を読みこなし、そこから含意を引き出す手法も、直接取材を省きながらも、ジャーナリスティックな筆致が感じられる)
さて、本書の主張はこうだ。
「欠陥のある人間は、自由意志に任せたのでは幸福にならず、その人にとって本当にためになることを強制する家父長的政策をとるべきなのではないか」
家父長的選択か、自由意志か・・。本書は、、できる限り選択の自由を残しつつ、人々をよいより選択に導くという中庸の立場を選択した。「学校の食堂で生徒の体によいものを食べさせるには、目に留まりやすいところに置くことだ。食事をランダムにおくことも、食堂からよくないものを排除することも望ましくない」、ユーモラスにエッセンスを伝える本書から、具体的に生活に役立てる方法を学べそうだ。
投稿元:
レビューを見る
ヒューリスティック(経験則)
- アンカリング
- 利用可能性 (事例をどれくらい簡単に思いつくかによって可能性を評価する)
- 代表性(AがカテゴリBに属する可能性がどれくらいあるかの判断を、AがBに対する自分のイメージや固定観念にどれくらい似ているかを自問して答えを出す)
自分に対する過度の楽観主義と自信過剰
ものを失う痛みは喜びの2倍(そのため損失回避的になる)
現状維持バイアス(注意力のなさが原因のひとつ(はいはい、なんでもいいよ))
フレーミング(100人のうち90人が生きている。100人のうち10人が死ぬ。年間350ドル得をする。年間350ドル損をする)
システム1とシステム2
腹と脳
自動システムと熟慮システム
ヒューマンとエコノ
狭量な「実行者」と、先を見通す力のある「計画者」
ホットとコールド
自制心の問題(ホットな状況の影響)を解決するために
- 外部装置を使う
- 心理会計を採用する
投稿元:
レビューを見る
行動経済学をベースとした社会的システム構築についての本。
悪くないが個人が実践するわけではない(政府・企業レベル)ので、自分の行動での実践法を知りたい場合は注意(その場合こんな本は手に取らないと思うが)。
投稿元:
レビューを見る
Nugde=注意や合図の為に人の横腹を肘で優しく押したり、軽く突いたりすることが原題の行動経済学に関する本。人々がより良い生活を送るために、人々の行動を予測可能な形で変える環境を作る、選択的アーキテクトのこと。例えば、アムステルダム・スキポール空港の男性用トイレでは、便器に黒いハエの絵が描くことで、飛沫の汚れを80%減少させた等、社会福祉制度、貯蓄などあらゆる点でのナッジの有効性を説明する。経済学というよりも、広義の公共選択論として捉えた方が良いかも。
投稿元:
レビューを見る
どこかで読んだ内容だな。
デフォルトの話はなかなかだ。
デフォルトを悪用する商売ってあるよね。めんどくさい手続き踏んで解約しないと毎月小さい金額が自動で引き落とされていくみたいな。
デフォルトの罠と名付けよう。
投稿元:
レビューを見る
結構、誘導されて物事決めてるかも。何かを決断する際、よく考えて判断してると思いきや、些細なことに影響されているということ。でも怖い話ではなく、ちょいとしたこと、ナッジをするだけでみんながいい方向にいくと教えてくれます。
仕事でも他でも何かをするとき、こういう気を配っていこう。
投稿元:
レビューを見る
感想は、こちら → http://mdef.blog29.fc2.com/blog-entry-57.html
投稿元:
レビューを見る
via http://kashino.tumblr.com/post/1067323570/amazon-co-jp
投稿元:
レビューを見る
お勧め。
実験経済学でも、人々の行動のほとんどは積極的な選択の結果ではなく、習慣によって自動的に決まることが確かめられている。人々がそれを変えて意識的に選択するのは、今までの習慣ではうまく行かない新しい事態が生じたときだけだ。
投稿元:
レビューを見る
■心理
1.ものを失う痛みは得る喜びの2倍。
2.人はあなたが思っているほど、あなたを注意してみていない。
投稿元:
レビューを見る
nodge 注意や合図のために人の横腹を特にひじでやさしく押したり、軽く突いたりすること
リバタリアン・パターナリズム 個人の選択・拒絶の自由(リバタリアン)をみとめながら、選択アーキテクトにより人々の行動に影響を与える(パターナリズム)戦略
「ヒューマン」と完璧な経済人「エコノ」 現実にはエコノなんて少ない
エコノはインセンティブに主に反応し、ヒューマンはインセンティブとナッジの両方に反応する
現状維持バイアス 惰性 デフォルトの選択肢に強く従う傾向
パターナリズムへの反対
前提:「ほとんどすべての人が、ほとんどすべての場合に、自分たちの最大の利益になる選択をしているか、最低でも第三者がするより良い選択ができる」
誤解1「人々の選択に影響を与えないようにすることは可能である」
誤解2「パターナリズムには常に強制が伴う」
人はどうしてこれほど頭が良くて、これほど頭が悪くなれるのだろう。
バイアスと誤謬
脳の二つの認知システム
自動システム 本能的
熟慮システム 意識的
考え過ぎる危険性 時間をかけて自動システムに頼れるようになる
三つのヒューリスティクス
経験則ヒューリスティクスと体系的なバイアス
アンカリングと調整 アンカー(自分の知ってるもの)が意志決定プロセスに関わってくる アンカー≒ナッジ
利用可能性ヒューリスティクス
事例をどれだけ簡単に思いつくか≒現実に起こる可能性と考える 保険加入数
類似性ヒューリスティクス代表性representativeness
類似性と頻度のズレ=バイアス
リンダ 銀行の窓口係 銀行の窓口係でフェミニスト運動家
ホットハンド バスケ
「平均以上」効果 非現実的な楽観主義
損失は獲得満足の二倍 損失回避性
現状維持バイアス ∵注意力のなさ
フレーミング 言い回し
シカゴのレークショアドライブ
「誘惑」の先回りをする
誘惑と思慮の欠如
興奮の効果を過少評価している
ローウェンスタイン「ホット-コールド感情移入ギャップ」
心理会計 家計が予算を評価し、管理し、処理するシステム ハウスマネーは別会計
目的会計
言動は群れに従う 社会的影響力がなぜ、どのようにして作用するのか
エコノ:流行に左右されない
ヒューマン:頻繁に他社にナッジされる
社会的影響力=情報/仲間からの圧力(ピア・プレッシャー)
1950's 社会心理学者ソロモン・アッシュ 同調実験easy 線の長さ
1930'sムザファー・シュリフ 同調実験difficult 民間部門、公的部門問わず、首尾一貫した揺らぐことのない主張をする人は、集団や活動を自分の思い通りの方向に動かせる
集団的無知が集団的保守主義の問題となる
集団的無知:集団の全員あるいは大部分が他の人はどう考えているかを知らない状況
スポットライト効果 他人は自分が何をしているか注視していると考える
体重を増やす最も効果的な方法は他人と一緒に食べること
食事の相手が一人居る時は、一人で食事するときより35%食べる寮が多��なる 四人75% 7人以上96%
ロバート・シラー 2008年金融危機 不安定な市場における心理的要因「今回や過去の投機ブームを理解する上で最も重要な要因は、ブームがきているという見解の社会的伝染であり、株価の急騰が広く観察されることを媒介として広がる」
「投機バブルのあいだには、『株価−ストーリー−株価』のループが何度も繰り返される」結局のところ、バブルははじける運命にある。バブルは長期的に持続できない社会的判断に依存しているからだ。
同調性と納税協力 ミネソタ当局
珪化木の保護
非飲酒の社会科←利用可能性ヒューリスティクス モンタナ市民
笑顔としかめっ面と省エネ カリフォルニア州サンマルコス
プライミング ほんのわずかな影響を受けると、特定の情報を思い出しやすくなる アイデアや概念をそれとなくほのめかすだけで、連想が誘発されて、活動が促進されることがある。こうした「プライム(先行刺激)」は社会的状況でおこり、驚くほど強力な効果を生むことがある。
どうするつもりであるか質問するナッジ クルトン・レヴィン「チャネル効果」
ナッジはいつ必要なのか
ツケ 困難度 頻度 フィードバック 嗜好
選択アーキテクチャー
良い選択アーキテクチャーを作る6つの原則
iNcentives(インセンティブ)
Understand mappings(マッピングを理解する)
Defaults(デフォルト)
Give feedback(フィードバックを与える)
Expect error(エラーを予期する)
Structure complex choices(複雑な選択を体系化する)
刺激反応的合成 押し戸、引き戸と取っ手
「RECAP(価格の記録・評価・比較)」
選択を体系化する エイモン・トバスキー「属性値による排除」
価格とインセンティブ 「顕著性」が重要 選択者は自由市場ではインセンティブに気づくが重要なケースでは気づかない
第2部 個人における貯蓄、投資、借金
貯蓄/年金
社会保障 1889年ドイツ ビスマルク政権が初めて社会保障制度を整備
初期 確定給付型が多かった 登録しやすい 最低雇用期間働く必要がある
現在 多くが確定拠出型 登録が最初のステップ/掛け金が税控除、事業主の付加拠出(マッチング)から、ネックはそれほどない
SMarT(Save More Tomorrow)プログラム セイラー、シュロモ・ベナルチ 賃上げがあるごとにあらかじめ決めておいた拠出率の引き上げを行うことを約束させる 1998年中規模の製造会社に実施されたのが初めて
資産配分決定 「リスクに対する姿勢は、投資家がポートフォリオをモニターする頻度に左右される」
分散ヒューリスティクス:疑わしきは分散せよ n分の1ヒューリスティクス:n個の選択肢があるときには、資産を選択肢に均等に分けよ
借金
市場が複雑化すると、洗練されていない教育水準の低いローン希望者は特に不利になる
サブプライム・ローンの長所:他の手段では借り入れが出来そうにない人々に信用を供与して、貧しい家庭やリスクの高い家庭が住宅所有者(もしくは事業所有者)になれるようにすること 教育されていない 簡易表記による誤解 古く不適切な法律
クレジットカードに潜むデフォルトオプシ��ン
第3部 社会における医療、環境、婚姻制度
社会保障制度の民営化 スウェーデン・プラン プロチョイス(選択権尊重)
ホーム・バイアス:投資家は自国の株式を購入する
薬剤給付プログラム アメリカ国民 処方薬剤費を自費または主に事業主が提供する医療保険を通じて支払わなければならない
2003年ブッシュ・プラン メディケアを消費者のニーズに適応させるため、選択肢からチョイスする形に「パートD」外来処方薬剤費給付プログラム →簡素化を求める悲鳴
臓器提供の同意 ルーチン的摘出 推定同意 命令的選択(運転免許証への登録事項を一つ増やす)
環境保護 インセンティブとフィードバック
ヨーロッパではアメリカと違い、グリーン税制への関心が高い
「キャップ・アンド・トレード制度」(炭素排出量取引制度) 市場原理に基づいて汚染をコントロールするインセンティブが生まれる
EU ETS(排出権取引制度)EU域内の温室効果ガス排出量の約四割をカバーする
アメリカ 1990年改正大気浄化法の酸性沈着削減プログラム 排出権取引制度が酸性沈着(酸性雨)削減の柱に 汚染の削減を現金かできる
情報フィードバック 市場のメカニズム 指揮統制型APより低コスト
政治のメカニズム チェルノブイリ原発事故以後「有害化学物質排出目録制度(TRI)」連邦政府に企業や個人は潜在的な危険性をもつ有害化学物質の貯蔵量や環境への排出量を報告→排出量の大幅な減少
トヨタプリウス成功の理由 cf.カムリ ハイブリッドカーしか作らなかったこと 顕示できる
クライブ・トンプソン エネルギーは目に見えないため、たくさん使ってもそれがわからないことが問題になる エネルギー消費の”見える化”
1991年EPA「グリーンライト・プログラム」個人消費者ではなく大企業と小規模企業を支援する自主参加型プログラム 当局は誰にも何も要求せず、望ましい環境効果を与えると期待される一定の基準に従う意志があるかどうかを企業に問う 営利企業、非営利企業(病院、大学を含む)の両方と自発的に協定を結び、企業は照明のエネルギー効率を高めることを誓約 1992年「エネルギースター・オフィスプロダクツ・プログラム」プリンター、コピー、コンピューター、電気機器全般に的を絞る 参加企業にロゴ使用を許可
結婚を民営化する
結婚の便益 税控除 、権利の保障(家族医療休暇法など)、死亡時の相続などの優遇措置、所有権、意思決定の代行、秘匿権限
公的な結婚のメリット?シビル・ユニオンでもいいのでは。
第4部 ナッジの拡張と想定される異論
ナッジサイトの例示
異論
止まらない滑り坂
←メリット有無が抜け落ちる オプトアウト(拒絶の選択)による傾斜の軽減 ナッジは避けられないならば活用するべき
間違う権利
←注意を促す標識としてのナッジ
中立性(強者から弱者への再配分は不必要)
←選択しないことを選択する自由
公知性の原則とサブリミナル広告
←大義に反しないのならば タバコに汚れた肺の写真 ハンバーガーショップに痩せて見える鏡
民間部門、公共部門の中立性 私的な利益を図るリスク
ナッジを与えるものがナッジを受ける者とって何が最善であるかを上手く推測出来るか
リバタリアン・パターナリズムに留まる理由
目的:人々が可能な限り低コストで思い通りに行動出来るようにすること
----------
社会的状況の一見すると小さな特徴が人々の行動に非常に大きな影響を与えることがあり、私たちの目に見えなくても、ナッジはどこにでもある。選択アーキテクチャーは、良いものも悪いものも、広く浸透し、避けることができず、私たちの意思決定に強く影響する。
----------
----------
リバタリアン・パターナリズムは撞着誤報ではない。選択アーキテクトは、選択の自由を守りながら、人々の生活が良くなる方向にナッジ出来る。
----------