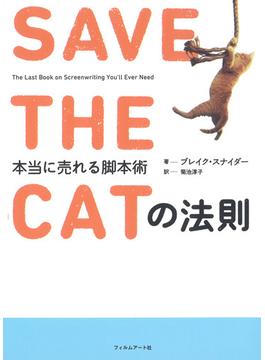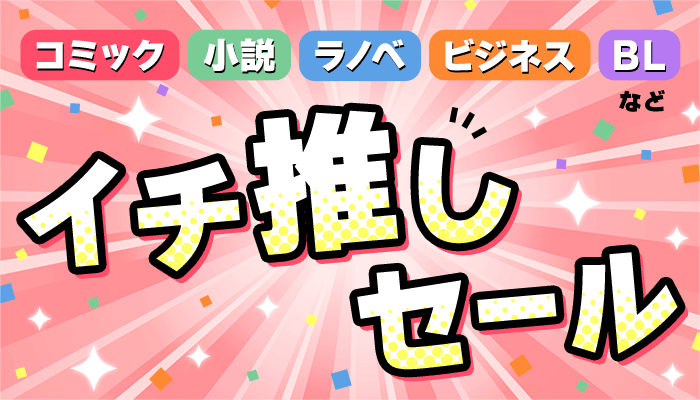売れ行きと名実共に最高峰の指南書
2015/01/28 01:47
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おっさそ - この投稿者のレビュー一覧を見る
物書きをやっている者です。
売れているということから、脚本術を知るとっかかりに買った本だったのですが、一年以上経った今でも愛用して、手垢がついてしまうほど使い込んでいる本です。
この本以降も、創作関係の様々な指南書を買って読みましたが、これ以上にわかりやすく、しかも役に立つ原則が書かれている本には今のところお目にかかっていません。
脚本術はシドフィールドが原点と言われていますが、彼の本よりも数倍わかりやすく、読みやすいです。
ぜひ、多くの物書きの方に読んでもらいたい。映画好きの方にもお勧めです。
そしてhontoさん、ぜひ電子版を発売してもらって、いつでもどこでも読めるようにしてもらいたい!
危機一髪の猫を助けろ
2015/10/23 07:34
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者のブレイク・スナイダー氏流に、この本のログラインを書くとすれば、「ハリウッドの人気脚本家が売れる秘訣を惜しげもなく披露した脚本術の本」となるだろうか。
もっともこのログラインで出版されるかどうかは別だ。
本を読んだり映画を観たりしたあと、それってどんな本? それってどんな映画? と訊かれて、うまく答えられるかどうか。きっとそこにも才能があるのだろうが、ログラインは作品にとって背骨のようなものだから、そこを巧く書けたら、「じゃあ、プロットでも書いてみて」ということになるのだろう。
ログラインと同じくらいに重要なものに「タイトル」がある。
スナイダー氏は「インパクトのあるタイトルとログラインが組み合わさると、ボクシングの連続パンチみたいにノックアウト確実」とまで書いている。
この本のタイトルは、いい。
「SAVE THE CAT」って何? って、つい手にとってみたくなる。それに「法則」がついているから、この「法則」を使えば、面白い脚本が書けるってこと?
こういう風に「?」がいっぱいつけば、読んでもらえる可能性が増加する。いいタイトルというのは、読者や観客を刺激するのだ。
では、「SAVE THE CAT」とはどういう意味なのか。
日本語に翻訳すると、「危機一髪 猫を救え!」となる。
これはドラマの主人公を観客に「好かれる人物」にする法則なのだそうだ。
スナイダー氏は映画『アラジン』の主人公が盗人で暴れん坊の青年なのに観客が彼に肩入れし応援したくなるのは、盗んだパンを食べようとする場面でお腹をすかした子どもにそれをわけてあげることで観客が主人公の味方になったと分析している。
つまり、危機にひんした猫を助けるだけで、観客が主人公に肩入れできるというわけだ。
こんな具合にこの本が「脚本術」として面白いのは、記述が具体的でわかりやすい(訳は菊池淳子)こと。さすがに実際に脚本を書いている人だけのことはある。
もし欲をいえば、参考例として紹介されている映画に日本映画があればいいのだけれど、さすがにそれは欲張りすぎだ。
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藍玉 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ハリウッド映画のシナリオを書いて競売にかけて売っていた著者。
読みやすい語り口で、シナリオに必要な要素をまとめてあります。
でもこれ一つで必ず書けるようになるわけではない。補完するためには別のアプローチからの勉強も必要。でも大切なことや使えるアイデアは書いてあるので、この手の本の中でも使える本です!
創作に関して、売れるモノを描くというのは媚びてることだろうという人がいますが、それは違うのであしからず。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:蒼依 - この投稿者のレビュー一覧を見る
前置きが長く回りくどいくせに、答えの部分があっさりしていて無駄が多い。紹介されている脚本術自体は良いと思うが、本としてはほとんど筆者の自己満足としか思えない。また、具体的な映画名を出して解説しているところが多く、その映画を知らない人にはわかりにくい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:自称ばか - この投稿者のレビュー一覧を見る
英語を無理矢理日本語に直した文章でとても読みづらかったです。コツなどを本から探しにくい点や例に出している元の作品を知らないと理解出来ないことが多くて全体的に難しい内容の本です。
投稿元:
レビューを見る
↓以下のように書きましたが、再読して印象変わりました。
わかりやすく注意点を指摘してくれる文章には
リマインダーとして学ぶべきものがあるとは思います。
作劇術関連の本は自分なりにこつこつと読んできた者としての感想。
うーん、正直言って新味のない内容でした。
この作者が語っていることは、今まで私が読んできた
脚本術の本ではほぼすべて書かれていたことでした。
妙に口語体風なのも日本語で読むと今ひとつですね。
なんかデーブ・スペクター的で。
興味深いのはチャプター2のタイトル
「同じものだけど、違ったものをくれ!」という言葉。
ハリウッド的だなーと思いました。
もっとほかにいい本があると思います。
初めて脚本を書こうと思ったひとなら
古いけど
新井一「シナリオの基礎技術」
シド・フィールド「映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと」
リンダ・シガー「ハリウッド・リライティング・バイブル」
などのほうがおすすめです。
この本に書かれていることがもっときっちりと書かれています。
あと翻訳ですが、ハリウッド式脚本術の書籍は
(フィルムアート社、フィルム メディア研究所が多くのものを出版しています)
おおむね誤植、意味不明の表現が多いのですが、
この本も同様でした。
人物表記もバーバラ・ストライサンドと間違えてるし。
古い映画をある程度見てる人なら、
バーブラと文字を打つと思うんですが。
訳者はあまり映画のことに詳しくないんですかね。
否定的なコメントばかりになりますが。。。
あと、この人は15のビート(局面、シークエンス、オオバコ、フェーズ)で物語を構成する考え方のようです。
それに基づく「デンジャラス・ビューティー」のオオバコの箱書きがあります。
結論としては読んで感心するようなことはありませんでしたが、
以前読んだことを再度思い出すみたいな効果はありました。
ただ、もしかしたら
この類の本を初めて読む人ならとっつきやすいからもしれません。
ちなみに
ここで語られているロバート・マッキーの著作は読みたいんですが、
ビジネス本以外の
単行本としての翻訳は出ていないようで残念です。
「Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting」
これは時間があれば頑張って読みたいんですけどねー。
翻訳出してほしいです。
脚本関係の本については厳しい純丘先生も絶賛していますし。
→この人のいう15のビートシートはハコガキとは微妙に違うものでした。
ハコ+ポイントとニュアンスからなるものです。
意外にこれはいいかも。
投稿元:
レビューを見る
いわゆるハリウッド式三幕構成をベースとしている脚本術の書籍。軽快な文章で独自の脚本術やルールを紹介している。なんにしても、書かなくちゃ、書こう! という気になる本。前半(1章~4章)の、ログラインやタイトル、BS2の話あたりは日本でいえば企画書作成に役立ちそう。
投稿元:
レビューを見る
脚本術指南もさることながら、私はブレイク・スナイダー本人に好感を持ってしまった。
故人であるのが惜しい。
脚本術指南書ではあるが、物語を紡ぐ指南書でもあると思う。
大変勉強になった。
しかし、勘違いしてはいけない。
ここで指南してくれているのは、ビジネスとしての物語術だ。
もし、大衆に何か迎合したくない、なんて反論を述べるようならお門違いだ。
これはあくまで、脚本家という職業に身を置いた一人の男の処世術だ。
図らずも本書のような口ぶりになってしまった笑
投稿元:
レビューを見る
Save the catの法則という名前からもわかるように、過度の一般化を避けている点がすばらしい。
そう、これは、学者が物語という生き物を解体した解剖学の本ではなく、ハリウッドという最前線で脚本を生業としてきた著者が売れている作品の良いところ、実際に脚本を書いた経験からわかったことを生かしながら、これから脚本を書く際に気をつけるべきことが、そして気をつけていることが書かれている虎の巻なのである。虎の巻て。
まず気の利いた(そして皮肉のある)ログラインを決めて、どんなジャンルの作品を書くか決めて(バカの勝利・難題に直面した平凡な奴・バディとの友情)、独自のテンプレートに従ってどんな事件を起こすかを決めて、場面をボードに貼ったりはがしたりして構成を練って、最後にちゃんと法則に背いてないかをチェックする(魔法は一回だけか・パイプを置きすぎてないか・氷山は遠すぎないか)。
物語の構造としては救済が、援助者が、どうこうなんて物語論じゃない。バカの勝利だの、氷山遠すぎだの、プールで泳ぐローマ教皇だの、中国の百科事典みたいな分類には、そういった意味がある。
すなわち、実際に作劇の際に使える方法論であるという意味が。
もちろん、本文でもしばし例外がでるように、これは物語すべてにスコープがあたってるわけじゃない。ハリウッドで売れている作品が主な焦点。しかしだからといって価値を損ねるものじゃないし、こういった本においてはむしろ有益だろう。
だってこれは本当に売れる脚本術なんだから。
そったら意味で、実際に脚本家を目指す人にとっても、他の物語を志向する人にとっても、物語論を読むのが好きな人にとっても、いろんな意味で有益な本。いいね!
投稿元:
レビューを見る
最初に断っておきたいのですが、僕の仕事は脚本家ではありません。俳優です。ではなぜこんなテーマで本を紹介するのかと言えば、この文章を書くために自分の本棚を眺めていたら、この手の本がたくさん並んでいることにあらためて気付いたからなんです。どうやら僕は「面白い脚本を書いてみたいという欲求がある」らしいのです。そして今からご紹介する「SAVE THE CATの法則」も、そんな僕の願望を満たすために購入した一冊です。
この本は、いわゆるハリウッド映画の脚本術について書かれているのですが、まず僕が面白いと感じたのは、この本の著者であるブレイク・スナイダー氏のキャラクターです。彼はいかにもアメリカ人的で、売れる脚本を書くための法則を次々に断定していきます。例えば「きっかけを書くのは12ページ、絶対だ」のように。なんて潔い文章なんでしょう。ここまで言い切られると、その通りに書いてみようという気になるってものです。この調子で、氏は1ページから最終ページまでになにをどこに書いたらいいのか、全て解説(断言)してくれます。
法則を知って驚いたのは、多くの有名なハリウッド映画の脚本が、この法則にピッタリ合致して書かれていることです。かなりの衝撃だったので、他のハリウッド式脚本術の本も調べてみたのですが、ほぼ語られている内容は同じでした。しかもそれは、ページ単位、時間単位で決まっているのです。それは、これらの法則が、ハリウッドの長い歴史の中で蓄積され、分析されてきた集大成なのだということを感じずにはいられませんでした。
ただ、この完璧に見える法則にも、弱点がないわけではありません。それは、一定の法則に従えば、どの作品もどこか似たテイストになるということでしょう。近年のハリウッド映画を観ていると、前に観たような話だと感じることも少なくありません。しかしながら、基本を知らなければ応用もありえません。この本に書かれている法則を知っていて損はないですし、この本を読んだあとにハリウッド映画を観ると、エンターテイメントの歴史が培ってきた優れた法則を作品の中に発見する喜びを得られますから、この先、脚本を書く予定がない方であっても充分楽しめるのではないかと思います。
投稿元:
レビューを見る
「それってどんな映画なの?」という問いから始まる、売れる映画の脚本の書き方。
これから映画の脚本を書くーその前に、この問いのきちんと答えられて、且つそれだけで「面白い」と思わせるものになっているかどうか。
それができないうちは、まだ書き始めてはいけない。
この本の中では、「どんな映画なの?」に対する答えを「ログライン」という言葉でいっていますが、これはもしかしたら、ビジネスでも同じ問いあてはまるかもしれない。
「それって、どんな会社なの?」「どんな計画なの?」と置き換えると当てはまるはず。
色々なヒントにもなるかもしれません。
噂ですが、今やこの本は映画の企画打ち合わせの場でも皆持っているとかいかないとか・・・
投稿元:
レビューを見る
園子温がハリウッドのプロデューサーに「こういうのが売れる脚本だよ」とこの本を渡されたというのをどこかで見てどれどれ試しに読んでやろうじゃないかと手にとった。
定形を提示するような本は好きじゃないののだけれど、この本は面白かった。
とにかく、売れる、という一点に絞っているのが潔い。
そして定形の命名が面白い。
「プールで泳ぐローマ教皇」「マジパン多すぎ」「家の中のモンスター」などなど。
映画を時間分節で区切るやり方も他の脚本術の本よりわかりやすい。
著者が売れる脚本の優れた例として挙げている映画の中には今までなら見ずに済ましていたものもあった(「キューティーブロンド」)が、この本をきっかけに見てみると確かによく考えられたエンターテイメント作品であることがわかった。
これは収穫だった。
とても優れた脚本術の本でシナリオ執筆に興味がある人なら誰にでも薦めたいところなのだが、唯一の懸念は著者が「刑事ジョー ママにお手上げ」の脚本家だということだ。
投稿元:
レビューを見る
所在:展示架
資料ID:11300616
請求記号:901.27||Sn
エンタメ映画の殿堂、ハリウッド仕込みの脚本術。
王道なエンターテイメント作品をつくるにはかかせない知識が盛りだくさんの1冊。
読みやすく、わかりやすい(海外の本だから、わかりにくい部分もある)。初めて、物語や脚本、小説を書こうと思っている方にオススメの一冊。
スランプのブレイクスルーになる可能性も。
とりあえず、何かを書いてみたくなる本。
また、とにかく形にすることを可能にしてくれる本。
この本の指示に従っていれば、ある程度のストーリーができるため、一発ネタ程度の構想しかない場合にも便利。
プロットの作り方から王道映画の類型、脚本の売り込み方まで書いてある。
脚本の売り込み方はハリウッド基準なので、日本人にはあまり関係ないかも。ただ、知識としては面白い。
ブレイク・スナイダー・ビート・シート(BS2)という独自のシートを使った創作法が紹介されている。
曖昧で固まってなかったネタでためしてみたところ、たしかにそこそこのプロットができた。
著者は、このシートにあたる部分は何ページ~何ページまでと厳密過ぎるくらいの指示をしているが、脚本基準であるから、小説や漫画などの制作では気にしなくていいだろう。
使いやすくシートをカスタマイズすると、よりスムーズな創作活動ができるはずだ。
このシートで数~十数作分のプロットを完成させれば、意識しなくても物語の流れを生み出す力が身につくだろう。
ログラインという考えた方は、エンターテイメント作品を作る上では必須だと感じる。
今まで、意識せずに似たようなことをやっていたが、もっと精錬されてやり方があると知った。
物語は感覚で作るのも大切だが、それ以上にいかに理論的に考えるかも大切であると再確認させられた。
「魔法は一回」(手元にないからうろ覚えの表現)という考え方も載っていた。これは作中に不思議な要素は1つでいいということ。
日本の漫画を読んでいると、そこかしこに「魔法」がちりばめられていることが当たり前だが、一作でまとまっていることが前提の映画の場合、「魔法」をちりばめすぎるのは危険なのだ。
小説も基本的には1冊に1つの物語をまとめなくてはいけない。
まとまった作品にするには必要な教えのように思う。
尖らせたい場合は(ラノベや漫画など)あえて、この教えをやぶるのも手だろうが、バランス感覚が必要なので、最初の内はこの教えを守ったほうがいいと思う。
とにかく、初心者の第一歩になりそうな本だった。
s.s.
投稿元:
レビューを見る
シナリオ作成関連本で個人的に最も分かり易かったです。
実際にシナリオを書いたことはありませんが。。。
投稿元:
レビューを見る
ハリウッド三幕構成のメソッドが、類書の中では最もシステマティックに解説されていると思います。
訳文も、ちょっとテンション高めなのがたまにひっかかりますが読みやすい。
個人的には恋愛とかアクションとかじゃなく、映画の根幹のテーマから作品をジャンル分けするところが興味深かったです。
ただ読みやすいぶん、引用などは少なめ、諸々の掘り下げもライトなので、シドフィールドなんかと合わせて読むと、より理解が深まるかもしれません。