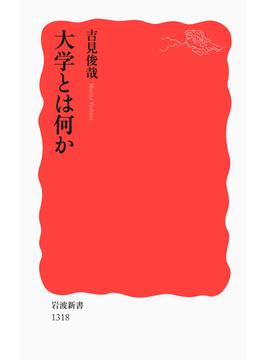紙の本
歴史的な認識の重要さ
2012/02/18 00:28
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kana - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本を読んでみると,最近の大学論のおおくがいかに近視眼的だったかがわかる. おおくの本がここ数 10 年のスコープしかもっていないのに対して,この本は中世からの歴史をひもとく. そして,現在すすめられている改革のおおくがすでに 1971 年の 「四六答申」 で提案されていることが指摘されている. 大学問題にかぎらず,現代がかかえる問題をかんがえるうえで歴史的な認識が重要であることを,あらためて感じさせる.
投稿元:
レビューを見る
中世の印刷革命において、大学での学問の幅は大きく広がった。
哲学であれ、人文学であれ、リベラルアーツであれ、自由の理性の場を大学の学部として制度的に確保した場合、果たしてそのような確保が自由の維持の自己目的化、つまり新しい大学で理性の自立性の組織的維持が自己目的化されるのか?
理性の大学から、文化、教養の大学に変貌しつつある。
文化=教養である。
感との哲学から、ニューマンらのリベラルな知への大学の理念のイングランド的展開において重要なのは、やがてこのリベラルな知の中核が哲学ではなく、むしろ文学へ移行していったことである。
投稿元:
レビューを見る
この新書版一冊で、中世の大学誕生から、アリストテレス、カントから・・・、またまた1960年代の大学紛争、さらに国立大学の法人化まで、なんと、すべてが網羅。これ一冊で、大学のことならわかる・・・という本。大学とはメディアである。これが著者の結論。共感を覚えますねぇ。
投稿元:
レビューを見る
大学の歴史をなぞるのに役立った。大学は普遍的なようであって実はそうではなく、時代や環境の変化とともに変わっていることは大事な事実だと思う。これからの大学がどうあるべきかは過去の延長上からは定義できないことだけはハッキリしたかも。
投稿元:
レビューを見る
「メディアとしての大学」をテーマにしたカルスタ的大学論.中世の大学から最近の日本での国立大学独法化まで,概説
投稿元:
レビューを見る
研究とも関連して興味あるテーマなので面白く読んだ。
ヨーロッパにおける大学の成り立ち(1章)から国民国家と大学の再生(2章)、舞台を日本にうつして帝国における大学(3章)、戦後日本の大学改革(4章)という今までの、最後の章では「それでも、大学が必要だ」とのタイトルで今後の大学のあり方に関する提言が書かれている。
今後の日本に置ける大学の形を考える時、既存の大学概念の中で中世の都市ネットワークを基盤にしたポスト中世的大学モデルが参考になるのではないかと提言している。その理由として、1、世界で多数の大学が国境を越えて都市間で密接に結びついていること、2、高等教育のアメリカ化の中で
学術言語としての英語の世界化がおきており、北東アジアなどの近隣諸国の学生と知的交流をすすめるのにも英語でのコミュニケーション能力が必須であり、それを単純な英語支配と捉えず共通言語以上の可能性を持ったものとして認識することが重要であること、3、今後人類が取り組むべき課題はすでに国民国家の枠組みを越えており、ナショナルな認識の地平を超えて地球史的視座から人類的課題に取り組む専門人材を社会に提供することが大学に求められていること、などを挙げている。(pp.240-243)
面白いのだが、取り立てて目新しいものではない。
それよりも、未来の完全なインターネット社会で大学が生き残ることができるのか、との懸念をぶっこんでたことには、その懸念は理解できるもの、もう少し大学がキャンパスをもち、人と人との直接的な交流が生まれることの意義を聞きたかったなあと思う。最近のキャンパスの国際化や、地域連携などの点についても触れてほしかった。そして、すべての大学教員がマイケル・サンデルのような「白熱」議論ができるわけじゃない、という部分には素直に笑ってしまった。
投稿元:
レビューを見る
本書は2つの読み手によって異なる印象を持つだろう。高等教育の入門の段階で読む場合は、「より抜いたポイントの集約」かなと。多少高等教育をかじってから読む場合は、「いつまで先行研究のレビューまで続くのか、と思っていたら終章になってしまった」と思うかもしれない。
新書1冊に日本大学史を総覧した価値はある。参考文献リストも学習者に役立つ。ただ、筆者の考える新しい主張が終章の一部くらしか見当たらないのは、少し寂しい。教育学を専攻としない情報学環の先生だからこそ、このような本が書けたのかとも思う。2時間で日本の大学の誕生から今日までをかけ抜けることができる意味は大きい。
印刷技術の発展に伴う書物の爆発的な出版、インターネットによる知の洪水という各メディアが大学に与えた影響に触れられている。メディア論としての大学論を今後期待したい。
投稿元:
レビューを見る
読むのに時間がかかりましたが大変勉強になる一冊でした。
大学4年である今更になって、もっと早くこの本に出会いたかったと思います。(もっとも、出版自体今年ですが)
なぜ大学に来たのか、なぜ今いる大学を選んだのか、なぜ今いる学部を選んだのか。
そもそも、なぜ大学はあるのか、大学とは何なのか。
そういったことを考えさせられます。
大学生必読の書だと思います。
投稿元:
レビューを見る
限られた紙幅のなかで大学の起源と変遷の歴史がコンパクトに概観された上で、深い洞察と重たい問題提起がなされている。「未来に向けて命がけの跳躍をしなければならない」(p239)との言葉には痺れた。大学関係者必読の書。
投稿元:
レビューを見る
岩波書店でこのタイトル。
しかも著者は教育学者ではない。
興味津々で読んだ。
目次だけ見ると「大学の歴史を振り返るのか」と思われたが、「メディアとしての大学」の視点があるため、これまで知らなかった大学像が立体的に浮かびあがってくる。
・キリスト教は、日本の大学システムの形成期と転換期の二度にわたり、ペリー提督やマッカーサー元帥以上に大きな役割を果たした (P186)
・(国立大の法人化について) 財務構造にすでに劇的な変化が生じているのに比べ、組織運営のあり方があまり変化していないように見える最大の理由は事務組織や職員の意識と能力が新しい体制に追いついていない点にある (P231)
・現在の状況に有効に介入しうるような新しい大学概念を、歴史と未来の中間地点に立って再定義していく (P239)
・ グーグルやアップル、フェイスブックといった新たなネット上の知識システムに対し、大学という相対的に古い知識形成の場が何を固有にできるのかを明らかにせざるを得ない時が来ている (P249)
など、多くの箇所を備忘録に留めた。
投稿元:
レビューを見る
中世から現代に至る高等教育の歴史を辿った本。
大学について語るためにまずは歴史から知りたい人にオススメ。
特に日本の現代史を綴った四章が面白かった。
投稿元:
レビューを見る
最初は非常に難しい(とわたしは感じた)昔の海外の大学の出来かたやいまの日本の基礎になった帝国大学のできかたなどについて非常に学問的に解説している。
戦後の大学改革について、筆者は「たくさんの分野を結びつけるのが真の教養主義」と言っていて、現在の日本の大学のもとになった部分を痛烈に批評している。つまり「大学は真の大学の体をなしてないのではないか?」ということを読み取った。
大学紛争と最近の大学改革についても言及している。
それでも大学は必要、でももっと頑張らなきゃね、という筆者の言葉には、もっと頑張らなきゃなと思わせてくれる。大学に関わる中級者向けかな。
投稿元:
レビューを見る
図書館で借りた。
大学という仕組みはどのように始まったかからスタートし、日本への導入、大学の置かれている状況を説明して、大学に求められていることや大学とは何かを考えている。
大学がもともと建物ありきの発想でないことを知り驚いた。師と弟子のような感じで先生のもとに学生が集まり、各都市を渡り歩いていたらしい。その後、学生が多くなり、学生の組合のようなものが先生を雇うところもあった。地元住民と大学との対立はこの時代からすでにあり、大学に建物がなかったため、全員別のところに移るという言葉で大学に有利な条件を得ていた。
大学は印刷革命が起きたときにうまく対処できず、学問の主体を本の著者に奪われたらしい。それが今のネットワークの発展した状況と似ていると指摘していた。
アメリカ型の大学、フンボルト型の大学というような各国の大学のあり方の歴史も概観できる内容だった。
投稿元:
レビューを見る
吉見俊哉『大学とは何か』岩波新書、読了。大学を知のメディアと捉え、中世における誕生と衰退、近代国家による再生、近代日本の移植と戦後の再編を概観することで、大学の理念を再定義する。懐古趣味的教養主義への回帰や社会へ阿る安易な対処療法を退け、見通しを提案する刺激的な論考。お勧め。
7割程度が大学史に当てられているが、200ページ程度でよくその概要をまとめたものだと感嘆。ヴェルジェやクリストフを紐解く時間がない人やざっくり概要を知る上では便利。知のコミュニケーション場=「メディア」として大学の歴史を俯瞰するのは現代的で面白い。
個人的に興味深かったのは、新制大学を創造するなかで、最大の抵抗勢力が、旧制高校を温存しようとする教養エリート。しかし教養エリートのひとり・南原繁がそれを退け、教養エリートの差別的「教養」主義ではない、新しい「一般教養」を立ち上げていくというところ。
付記。
吉見俊哉『大学とは何か』岩波新書、吉野作造への言及あり。かつて私学にあった「民権と出版の学知」が東京帝大に内在化していく象徴的人物として(大正デモクラシーと『中央公論』)。以降、出版と大学が相互依存へ、ただこの蜜月は治安維持法後、「自由の余地」は縮小していく。
投稿元:
レビューを見る
新書を読んで、知的好奇心を味わいたい人には
ぜひ読んでもらいたい作品です。
僕自信、新書を読んで久しぶりに興奮しました。
「大学」の歴史的な変遷を丁寧に辿りつつ、
いま現在抱える問題、その未来像まで語られた本書。
いわゆる「大学問題」自体はメディアを通じて得る程度の知識しかない
僕のような人間でも分かりやすく、かつ面白く読みました。
特に、中性以降、存在意義を見失ってゆく大学が
近代国家成立とともに価値を見いだされ、復活してゆくくだりや、
大学の没落と新しいメディアの誕生の関係性などの部分が
とても印象に残ってます。
また、僕はこれまで、なんとなく今自分達の目の前にある
大学のスタイルが古くから連綿と続いているイメージを
持っていました。なんの疑問も持たず。
本書を読んで、同じ「大学」という言葉でも
それが現す状況というものは時代・地域によっても
違うという、極めて当たり前なことに気付きました。
安易に言葉のイメージに流されてはいけない、
ということも、本書を読んで得た教訓でした。
今年読んだ新書の中では有数の面白さでした。
おすすめです。