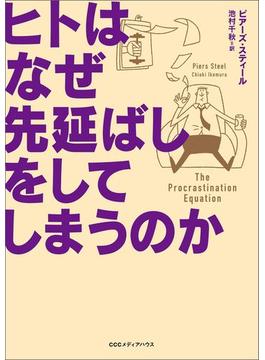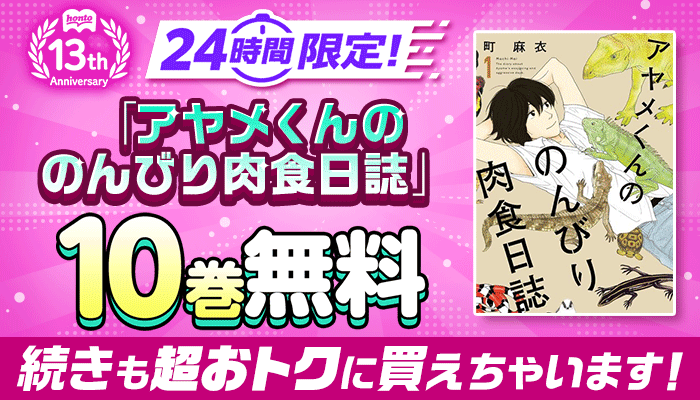気になるタイトル
2017/05/21 13:22
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:冬みかん - この投稿者のレビュー一覧を見る
常々なんでだろうと思っているそのもののタイトルだったので。ちゃんと研究データに基づいた裏付けがある内容なので説得力がありました。
投稿元:
レビューを見る
先延ばし界の権威?が書いた本。
この本自体が先延ばしされないよう配慮した構成でスラスラ読める。
先延ばし一つ取ってもタイプわけできる辺り興味深かった。
投稿元:
レビューを見る
先延ばしのタイプを課題がどうせ失敗する、退屈に感じる、目の前の誘惑に勝てないの3タイプに分類しそれぞれの特徴を分析し対策を講じている。
また課題に対するモチベーションを(期待*価値)/(衝動性*遅れ)で表しそれを如何に高く保つかが書かれている。
先延ばしの対策としては以下の13が示されている。
・成功の螺旋階段
・鼓舞される物語・仲間
・脳内コントラスティング法
・失敗を計算に入れる
・先延ばし癖を自覚する
・ゲーム感覚、目的意識
・エネルギー戦略
・生産的な先延ばし
・ご褒美効果
・情熱を燃やせる仕事
・プレコミットメント戦略
・注意コントロール戦略
・ゴールを設定する
どれも分かりやすく例が書かれているのですぐに実践することもできる。
投稿元:
レビューを見る
グズクズ、モジモジ、ウーン、ウーンと物事を先延ばしにする人がたくさんいる。著者は、先延ばしをライフワークにしているなかなか面白い人だ。
英語で「先延ばし」は、procrastinationという。著者は、語源に触れている。もともと、「前へ、優先させて」を意味するラテン語のproと、「明日の」を意味するラテン語crastinusからできている。今と違って、「慎重であること」といったように、「先延ばし」の意味はなかった。今の「先延ばし」の意味が登場したのは、16世紀。
本書の最初の方に、自己診断テスト1と2が用意されている。まあ、後でいいか思わずに早速やってみた。著者によると平均レベルの先延ばし癖の持ち主だった。買ってからすぐにテストしたのだから、先延ばしレベルが高いわけがない。
先延ばしを改善するには、日頃の行動を振り返って考えて見る必要がある。そこから、先延ばしをどうやって減らしていくかが重要だ。先延ばしは人生にはつきものだけにイカになくすか。しかし、先延ばしの起源は、9000年前にさかのぼると著者は述べている。それだけ昔から先延ばしは問題になっているわけだ。民主党だけではなかったのか。フムフム。
脳には、辺縁系と前頭前野と呼ばれる部位がある。著者によると、辺縁系は、脳の「野獣」の部分に相当して、本能に関わる反応をする。一方で、前頭前野は、遂行(=エグゼクティブ)機能を担っていると説明している。辺縁系は、「ワイルド」だけに反応が、前頭前野より早く、「先延ばし」にしたいという怠け心が優先される。辺縁系と前頭前野の使い方には注意する必要がある。辺縁系に左右されると、怠け心一色になってしまう。怖いなあ。
先延ばし克服の行動プランが紹介されている。これを是非読んだもらいたい人たちがいる。それは、無駄を削りもしないで、税金を上げたり、電気料金を上げている政府や東京電力の関係者によく読んでもらいたい。聞く耳なんて持っていないか。国民は、税金や使用料を払うだけの金づるという程度の認識だと想像がつく。
著者のウエブサイト
www.procrastinatinus.com (英語)
投稿元:
レビューを見る
ダメとわかっていてもやってしまうのが人間の弱いところなのである。
うんざりするような課題なら、なるべく小分けにし、進歩の度合いを記録に残し、成功を積み重ねてゆく。
新しいことを学び、小さな上達を確認し、それを自分の勝利と考える。
心を鼓舞される作品や仲間の力を借り、モチベーションを上げることも効果あり。
やはり、どんな小さな事でも、まずは行動に移してみることが大切なのだ。
投稿元:
レビューを見る
第1章 先延ばし人間の実像
第2章 先延ばしの方程式
第3章 さぼる脳のメカニズム
第4章 現代社会は誘惑の巣窟
第5章 私たちが失うもの、悔やむもの
第6章 企業と国家が払う代償
第7章 自信喪失と自信過剰の最適バランス
第8章 やるべきことに価値を吹き込む
第9章 現在の衝動と未来のゴールを管理する
第10章 さあ、先延ばしを克服しよう
投稿元:
レビューを見る
先延ばし方程式 モチベーション=(期待・報酬の確実性)x(価値・報酬の大きさ)/(衝動性・忍耐心)x(遅れ・時間の要素)
個人的責任の悪癖、ではなく、生物としての進化の賜物であり、普遍・必然のものなのだ。
そう言ってもらえると、ちょっと、罪悪感も軽減されます。
投稿元:
レビューを見る
先延ばしとモチベーション研究の第一人者による、先延ばしの科学的分析&克服法。
面白くて実証的でタメになる、なかなか素敵な本。
しかも心理学だけでない、経済学や生物学などの幅広い研究成果を取り込んだものになっている。
モチベーションは「(期待×価値)/(衝動性×遅れ)」によって求められる。この数字が小さくなればなるほどモチベーションは低下し、人は先延ばしをしがちになる。
このように先延ばしを方程式で表したうえで、あとはこの構成要素を如何にコントロールするか、という観点で克服法が語られる。
先延ばしに至る理由も克服法も、どこかで目にしたような記述も多いが、本書は理論が一本通っているので非常に理解しやすく腹落ちする。
さて、あとはここに書いてあることを先延ばしせずに実践できるかどうかだ。笑
投稿元:
レビューを見る
●モチベーション理論の方程式
(期待×価値)/(衝動性×遅れ)
1
期待=課題を成し遂げた場合にご褒美を得られる確実性
価値=ご褒美の大きさ
遅れ=時間
※遅れが大きくなる(手にできる時期が遅くなる)とモチベーションは下がる
衝動性=遅れに対する敏感さ
2
分子…期待×価値
確実に課題を成し遂げ、褒美も大きいとモチベーションは上がる
分母…衝動性×遅れ
課題の締め切りがずっと先で、成績が出るのも先の時にこの値が大きくなり、モチベーションは下がる
⇒これを利用してて、モチベーションを上げる
●れんが職人の話
3人のれんが職人がいました
旅人が何をしているのかと聞くと
一人目は「れんがを積んでいます」といい
二人目は「働いてお金を稼いでいます」といい
三人目は「町の大聖堂を建てているのです」といいました
って話なのだけど、金曜日に学校の授業で聞いたのがまた出てきてびっくり
⇒三人目の人になりたいね
投稿元:
レビューを見る
なぜ先延ばししてしまうのかという理由、豊富な事例、そして現実的な具体策まで書かれていて、それなりに好印象の本。
一部根拠が薄い部分も含まれるが、そこはご愛嬌かなと。
投稿元:
レビューを見る
即実践したい人は7章から読んでもいいと思う。先延ばししないためにも日常で取り入れられるノウハウが書かれてあります。
投稿元:
レビューを見る
先延ばしとはなにか、それによる悪影響、その原因と対策までこれまでの研究にもとづいてわかりやすく書いてあります。
やや長いですが、読みやすくてよかったです。
やるべきことを先延ばしにして悩んでる人には間違いなくおすすめです。
投稿元:
レビューを見る
タスクやTODOを書いても、つい先延ばししてしまうので読んでみた。中に自己診断テストがあって3要素のどれかを調べられるが、満遍なく当てはまった中レベルの先延ばしだった。やってみるとそんなに大したことではなくでも、つい放置して自分の中でどんどん苦しい負担になっていく。それを克服するにはちょっとだけでもこまめにやってみること。とりあえずなんでも ‘Try Everything’ 実行していこう。
投稿元:
レビューを見る
自分自身、昔から先延ばしの傾向はあったのだけれど、最近とみに先延ばしでそれなりに痛い目にあっているので、タイトルに惹かれて購入。
先延ばしと言えばエインズリーの『誘惑される意志』で語られた双曲曲線の理論が有名だが、基本的には先延ばしの原因の説明は本書でも同じだ。直前にすぐに得られる報酬(ゲームなど)があるとそちらを選択して、期限が先にあるものにはとりかからない。先にある大きな報酬や問題は、容易に小さいがすぐ目の前にある報酬のために先送りされてしまうことが示される。
本書では、先延ばし克服の行動プランが13個も提案される。小さなゴールに分割する、先にコミットメントする、失敗を想像する、など。すべてその理屈は理解できるし、そうすべきであることはわかっているのだが、やはりどれも実行は容易ではないなと思う。そういえば、このレビューもすぐ書けばよいのだけれど、先延ばしにして記憶が曖昧になって、内容も薄くなっている。それが、生物として組み込まれたものだと言われると、ますます克服への意欲が遠のくのだけれど。先延ばしはいいことない、先にやると実際には多くの報酬がもらえる、ということだけ覚えておくことにしよう。早起きは三文の得、をことわざとして覚えておくのと同じ程度かもしれないけれど。
投稿元:
レビューを見る
著者は産業心理学・組織心理学を専門とし、"先延ばし"やモチベーションについて10年以上にわたり研究をされています。
著者自身が「私はかつて相当な先延ばし人間だった」と自称しており、行動心理や脳科学などの科学的観点から、なぜ私たちが先延ばしをしてしまうのかを具体的な調査・研究結果に基づいて記しています。
先延ばしと聞いて「自分も当てはまる」とドキッとした方もいるかもしれませんね。
正直、私もそう感じました。
ですが、実は動物学的にヒトだけでなく、さまざまな生物が先延ばしの性質を持っているそうで、遺伝的な要素があるのだそうです。
先延ばしたくなる気持ちは、誰もが持っているものなのですね。
とはいえ、その先延ばしの特徴を顕著化しているのは、環境などの後天的要因が大きいのだそうです。
著者は典型的な先延ばしのパターンを、3人の人物の例を挙げて詳しく説明しています。
・「どうせうまくいかない」と決めつけて、大事な仕事を後回しにする営業マン
・「仕事(課題)が退屈だ」と感じてしまい、執筆が進まないライター
・楽しいことばかりを優先させ(「目の前の誘惑に勝てない」)、間際になってホテルの予約をする旅行者
ユーモアを交えた分かりやすい説明ではありますが、自分にあてはまると感じると冷や汗をかくかもしれませんね。
興味深かったのは、モチベーションの大きさは次の式で表せる傾向があるという点です。
モチベーション = 【期待】×【価値】/【衝動性】×【遅れ】
その課題に取り組むことで手に入れられるものへの【期待】や【価値】が大きければ、先延ばしにせずすぐに取り掛かります。
反対に、期限が遠かったり、見返りを手にするまでの時間が長ければ(つまり【遅ければ】)、行動を開始するまでの期間が長くなる傾向があるのだそうです。
また【衝動的】に動く人も、やるべき事に対する計画性が薄くて先延ばしをする人が多いのだそうです。
本書の後半では、先延ばしする癖を断って行動を起こすためのヒントが紹介されていますが、気になる方はぜひ読んでみてください。
私自身、「面倒だな」「退屈だな」という気持ちが全くないわけではありません。
それでも事業で欲しい結果と達成したい目標があるので、思い立ったらすぐにやる、経営仲間と集まって一緒に仕事をするなど意識して工夫してきました。
私のメンターの仕事のスピードやマメさにはいつも驚かされるばかりで、今でもその背中を追いかけています。
先延ばしが環境に因るなら、"先延ばししない"ような環境を整えることが大切だと感じ、誰と一緒にいるかをあらためて徹底します。