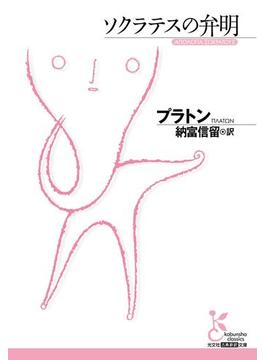ソクラテスの弁明
2016/10/18 22:44
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:NAOKI - この投稿者のレビュー一覧を見る
思想史を勉強中に、古代ギリシア思想の理解を深めたく手に取った一冊。“ソクラテス裁判”の様子が弟子プラトンによって描かれている。ソクラテスによる他者への論駁は、絶対的な神から与えられた「人間的な知恵」への探求活動であり、「不知」の認識によって為されるもの。現代で言う「知ったかぶりはダメ!ちゃんと(本質まで)知っていますか?」というもので、至極当然な問いではあったものの、ソクラテスのその真っ当なやり方が、無知蒙昧(言い過ぎ?)な市民の反感を買う。この対比が面白い。解説とプラトン対話編への案内も充実している。
投稿元:
レビューを見る
ソクラテスの弁論は素晴らしいと思わされた。
極めて理論的かつ戦略的に組み立てられた弁論で、実際に自分が訴えられていること(新しい批判)に対しては軽く論駁、古くからの批判、つまり自分が神の教えに従ってソクラテスは知者であるということはどういうことかを知ろうとした行為、その中で多くの知者とされている人を論駁してきたその恨みに対して弁明をする。
この行為は当時の裁判においては例外的で最後まで自己は悪くない、善き行ないを成したのだという自身に見た溢れた姿であった。
なるほど西洋ではこれほどの理知的な思考が古代の日本が原子文明であった時から脈々と受け継がれているのかと感動すら覚えた。
追記的に書いておくがこの本は非常に読みやすく、古典における翻訳が大変読みやすさに影響を与えているなぁと思った一作でもある。
投稿元:
レビューを見る
この作品は、プラトン作品の中でも、厳密な論理展開で相手を煙に巻く、ソクラテスの得意な対話・論駁の場面が少なく、その意味ではとても読みやすく理解しやすい。しかし、メレトスとのやり取りだけでも、ソクラテスがなぜ裁判にかけられて死刑に処されなかったのかわかるくらい、彼の底意地の悪さがわかる(あるいは、ソフィストは皆このような話しぶりであったのか)。
日本人がこの作品に格好良さを感じるのだとすれば、それは邪気眼的なものであって、善き生き方に対する共感ではないように思う。西洋においては特に、ペルソナの下に隠れた本音を見せるのは恥ずべきこととされており、社会においてふさわしい所作を身につけることが当然とされている。そのような文化においては、ソクラテスのやっていることは、社会的な身の振り方を意識するあまり、抑圧され無意識に追いやられてしまっている自分自身を知ろうと努力すること、ユング風にいえばアニマ・アニムスを発展させ、自己をよりよく知ることの指摘に他ならないであろう。そして、その指摘の重要性も明白である。
翻って、日本おいてはどうかといえば、建前と本音(実際は疑似本音)を使い分け、要領よく生きることが美徳とされている。本音を漏らす場面を設けてガス抜きし、無知のままに生きることが奨励される。無知という点では西洋と全く同じであるが、日本人の場合は、すでにして知らないと思っているのである。このような社会では、真っ向から真理探究の重要性を指摘することは、本音を語ることと混同され、子供の戯れごとと解され、苦笑のうちに、ここは建前をいう場であるから慎むようにと、諭されるのがせいぜいである。諭された側としては、道化に徹する他、道はない。本書を読んで、本気で怒りを感じる日本人がいるであろうか。したがって、ソクラテスのやっていることは、勘違いの正義感に基づくヒロイズムでしかなく、そうした行動に思いを馳せるのは強き者への追従による陶酔感に他ならない。
本書の内容は、良く知られるデルフォイの信託を受けて対話をして回っていた様子などがソクラテス自身によって語られる。前々から疑問に思っていたのだが、なぜソクラテスが追放刑を選ばなかったのかについて、今回ようやく疑問が解けた。ソクラテスを追放して、他のポリスで対話を続けさせることは、アテナイの人々の目を問題からそらすことであるし、それだけでなく、他のポリスに対して害悪をなすことでもある。それは悪に他ならない。また、一度問題が回避されれば、永久に回避し続けられることになりかねない。したがって、ソクラテスはアテナイの人々が自発的に真理の探究に取り組み、善く生きることを選択しない限り、自身が死ぬことで問題の不可避性を示さなければならなかったのである。
本書の日本語訳については、格別読みやすいかというと、プラトンの著書の場合、その読みにくさは論理の厳密さにあるのであって、判断が難しい。しかし、詳細な注釈と解説で、きちんと議論を追っていけば必ず内容を理解できるようになっている。また、巻末にはプラトンの著書の読書案内がついており、自身の関心と照らし合わせながらプラトンの他���諸作へ読み進む際の参考となる。
最後に、訳者のこだわりである「無知の知」が誤訳であるとの提起であるが、私は原語を解さないので本当のところはよくわからない。しかし、訳者のように「知っていること」を「明確な根拠をもって真理を把握している」と定義するならば、「知らないということを知っている」ことが、「知っていると思っている」と同様に「無知」に他ならないというのは、もっともであると思う。あくまで、「不知を素朴に自覚している」と解すべきなのであろう。
投稿元:
レビューを見る
解説がいい。見逃しがちなポイントが照らされている。
無知の知、なんてソクラテスは一度も言っていない。
無知の認識、あるいは無知の疑惑を自覚しているだけ。
自分は無知なのではないか?という疑いを抱いて、本当かどうか確かめるため、色々な人に尋ねて回る。
それが結果的に他者の無知を暴くことになり、嫌われ、疎まれる。
確かに、嫌われるでしょうねー。
弁明でも、全く主張をまげず、挑発的ですらある。
昔からの批判に対する弁明が今でも古びない主張。後はおまけで、時代背景を感じさせるピントはずれな弁明。神関係ないし、政治家にならない理由なんて知りたくはない。
投稿元:
レビューを見る
ソクラテスが裁判をかけられた時に語った文章。ソクラテスの考えに触れることで、自分の考えを見直すきっかけになる。
投稿元:
レビューを見る
・かつて岩波文庫の久保勉訳で読んだことがあるが、それよりも格段に読みやすい。もちろん格調高い久保氏の翻訳が果たした功績は尊重されるべきと思うが、教養主義の時代が終わった今、難解な哲学書を平易な日本語に訳しなおす時期にきているのだと思う。この新訳の誕生を素直に喜びたい。
・ただ、スラスラ読めてしまうだけに、ソクラテスの主張を「判ったつもり」になってしまうのが唯一の難点だ(「無知の自覚」を促したソクラテス先生に申し訳が立たない)。しかし、誤読・誤解しやすい箇所は訳者解説で丁寧に注意喚起されていて、訳文といい解説といい、本当に心が行き届いていると思う。
・原告からの死刑求刑に対して、被告人ソクラテスが「自分は何も悪いことはしていない。むしろ善いことをしたのだからメシを食わせろ」と放言するくだりなどは、とんでもなく滑稽な場面であり、喜劇的ですらある。思えば、ソクラテス裁判自体が、全体を通じて、ソクラテスが弁明すれば弁明するほど裁判員の反感を買って死刑に近づいていくという一種の喜劇的な構造を持っていることに、今さらながら気がついた。
・ソクラテスの死を単なる一面的な悲劇として取り上げるのではなく、多面的な悲喜劇として描き切ったプラトンの文学的力量は流石だ、とも思う。
投稿元:
レビューを見る
弁明の邦訳、解説のほか、プラトン対話篇を読むための手引きもついているので、プラトンやソクラテスに興味があるといった方には特にオススメします。納富訳の特徴としては、写本に忠実であり、プラトン研究者の指摘する語句の削除や追加、変更などにはあまり従わない傾向にある、といったところでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
友人からのお勧めで読みました。
ソクラテス文学(哲学)はまぁ有名なので常識的な範囲では知ってたけど実際読むのは初。
この本はソクラテス(プラトン)入門という感じですね。
新訳で読みやすいし、解説もしっかりしてて理解が深まります。
知とは
正義とは
善く生きるとは
西洋哲学のスタートであり根っことなった哲学的なテーマが扱われてますが、
裁判を舞台とした対話形式なので読みやすい。
面白かったのは、「無知の知」についての解説。
非常に有名な概念だし、意味するところはわりと理解しやすいと思ってたんだけど、この言葉自体が誤解を招きやすい、と。
ソクラテスが繰り返し表明するのは「知らないと思っている」ということであり、無知の知ということばから導かれるような「無知を知っている」とは態度がまったく違うという指摘。
けっきょく自分はあなたの知らないことを知っている、と言ってしまっては意味がなく、あくまでも「知らない」という謙虚な態度こそが「知」を求めるということである。
これはものすごい納得した。
「真実を語る」というソクラテスの言葉が、ただ語りの内容のみではなくその聴衆の態度反発やその結果導かれる死刑という判決まで含めた「真実」である、などこういう仕掛け的なすごさや気付きもあったけど、無知の知の捉え方の方が感動。
もう1個おすすめされてる「ゴルギアス」も面白そうなんで読んでみようかと思います。
投稿元:
レビューを見る
ずいぶん前に岩波文庫版を読んだが、その時は、ソクラテスの偉そうな物言いばかりにひっかかり、むしろ聴衆側に感情移入してしまった。それに比べてこの新訳は、現代の普通の語り言葉で訳されていて、ソクラテスのセリフを必要以上に尊大に感じさせたりしない。で、今回感じたのは、ソクラテスが市民の多くから反感を買われているのをひしひしと感じながら、飽くまで、ポリスの法の枠を守りつつ、自分の立場を人びとに必死に伝えようとしている姿である。今回はソクラテスに感情移入した。
投稿元:
レビューを見る
活字が大きく、文体も読みやすいです。他の訳の多くが「だ・である」調になっているのに対し、本書は「です・ます」調で書かれており、この違いだけでもソクラテスに対する印象がだいぶ違ってきます。また、本文の前にある「訳者まえがき」と本文のあとの「解説」も素晴らしく、読み方や考え方のヒントを提示してくれています。
一番印象に残ったシーンは一七の29A後半です。引用します。
「と言いますのは、死を恐れるということは、皆さん、知恵がないのにあると思い込むことに他ならないからです。それは、知らないことについて知っていると思うことなのですから。死というものを誰一人知らないわけですし、死が人間にとってあらゆる善いことのうちで最大のものかもしれないのに、そうかどうかも知らないのですから。人々はかえって、最大の悪だとよく知っているつもりで恐れているのです。実際、これが、あの恥ずべき無知、つまり、知らないものを知っていると思っている状態でなくて、何でしょう。」
これが世間一般に言われている"無知の知"の具体例なのか、こういうことなのかと。
(解説122ページでは"無知の知"という呼称は誤りだと説明されています。が、"無知の知"は一般的に浸透している言葉だと思ったのでそう書きました)
この部分ですが、「だ・である調」の訳で読むと、なんだか上から目線な印象を受けます。他の訳と読み比べてみても新たな気づきがあり、買って本当によかったと思っています。
投稿元:
レビューを見る
ソクラテスの裁判とは何だったのか?ソクラテス の生と死は何だったのか?その真実を、プラトン は「哲学」として後世に伝える。シリーズ第3 弾。プラトン対話篇の最高傑作。
投稿元:
レビューを見る
今から約二千五百年前、反感を買っていた人々から「ソクラテスはゼウス神を信じておらず、亜教の神々を信じるようにギリシャの若者をたぶらかしており、公衆秩序を混乱させている」という罪で裁判所での弁明を余儀なくされる。
そこでの語りを後に弟子だったプラトンが物語にしたのがこの本であるとのこと。
ソクラテスは「私は無知の智を知っている」と言っているが、果たしてそうだったのか?と疑問が浮かんできた。ソクラテスは対立する人々から怒りや恨みをかっていたのはわかっていたが、その心を理解できていないことに気づいていないように思う。確かに腐敗した政治家や権力者がいただろうし、生死を賭けて自身の正義を貫き通す姿に共感を覚える人もいるだろうが、私にはその弁明がさらなる亀裂を作るような痛々しさを増幅させているようにしか感じられなった。裁判員は500程。30票差で死刑が宣告される。もう一度智とは一体何なのかを考えさせられるきっかけとなった。
投稿元:
レビューを見る
私はあなたがたよりもむしろ神にしたがいます。息のつづく限り、可能な限り、私は知を愛し求めることをやめませんし、あなた方のだれかに出会うたびに、勧告し、指摘することをけっしてやめはしないでしょう。
恥ずかしくはないのですか、金銭ができるだけ多くなるようにと配慮し、評判や名誉に配慮しながら、思慮や真理や魂というものができるだけ善くなるようにと配慮せず、考慮もしないとは。
はい、反省。
ソクラテスの弁明自体はすごく短いんだな。
知らなかったよ。
投稿元:
レビューを見る
フィロソフィア:「智を愛する」とはどういうことか。ソクラテスはその命を懸けて証明した。わかりやすい。
ソクラテスも知識人らしく、他人の気持ちを読めない空気を読めないアスペルガーっぽい所があったっポイな。でも、他社に迎合しないその姿勢は、高潔で、勇気があるようで、強い意志を感じる。
しかし、それだけでもなかったんだろうな。やっぱり対人関係が不自由だったんだろうな。でもそれゆえに死ぬことになった。
ソクラテスが最も愚かと言ったのは、「無知の恥」
知ったかぶりの人間ほど醜い物はない。「智識は無限」である。どんな知者でも、何でもは知らない。知っていることだけを知っているのである。羽川翼もそう言っている。持てる知識の多少をひけらかすのは愚か。謙虚に自分の知識を増やし続けること、学びを愛することが正しい態度。
「無知の智」を自覚しよう。学び続けよう。
投稿元:
レビューを見る
岩波文庫版に親しんで、よく知っていると思っていたけど、それ自体がとんでもない間違い、まさに無知であったことがわかりました、この新訳と充実した解説を読んで。無限に続く真理の探究、知を愛し求める哲学の実践、飽くなき自己吟味と魂への配慮にまさに命を賭した一人の人間が、自己の生死のかかった裁判で、人々に人間として生きることの意味を問い続けます。
本書はまさに人類の宝というべき古典だったのです。