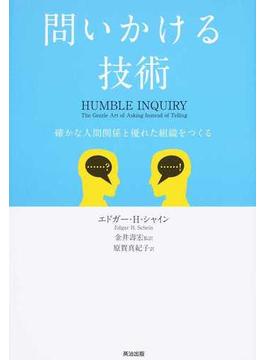紙の本
謙虚に問いかける
2022/05/15 09:30
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mk - この投稿者のレビュー一覧を見る
謙虚に問いかけるのが大切ということは、わかりました。思い込みで決めつけるのではなく、謙虚に問いかけていきたいと思います。
ただ、全体的に難しくあまり頭に入ってきませんでした。
投稿元:
レビューを見る
2015年59冊目。(再読)
自社本のため割愛。
====================
2014年113冊目。(初読:2014年11月19日)
投稿元:
レビューを見る
謙虚な問いかけをすることは、経験のある人ほど難しい。
後輩に、自分の経験値や固定観念を捨てて、謙虚な問いかけができるか。
上司や先輩に、遠慮することなく素直な質問ができるか。
個人の問題でもあり、組織文化の問題でもある。問いかけは本当に難しい。
でもちょっとしたことに気をつければ、いままでよりは良くなるはず。
易しく書いてありますが、本質的な本です。
投稿元:
レビューを見る
レビューはブログにて
http://ameblo.jp/w92-3/entry-11982124830.html
投稿元:
レビューを見る
2016年2冊目。
尊敬する先輩 Yさんの本棚にあったので、
迷わず購入・大好きな出版社 英治出版さんの本でも
あった。
【謙虚に問いかける技術】
問いかけるとは何か?をとことん深掘りしている一冊。
普段、後輩にどのような質問をしているのか?
自分の知識を引け散らかすような質問をしていないか?
改めて考える機会になった。
”自己表現”ばかりにこだわるのではなく、
あえて"問いかけることで、へりくだることで相手の考えを知る"
"技術"というよりも、
"相手を知るための心構え"の大切さを教えてくれた一冊。
○謙虚さは3種類存在する
1.基本的な謙虚さ(社会的な立場で生ずるもの)
2.任意に示す謙虚さ(優れた人を前に生ずるもの)
3.今ここで必要な謙虚さ
=>私があなたに対して抱いている思い
○質問するという行為
=>会話の相手に力を与えると同時に、
一時的に自分を弱い立場に置くことになる。
○問いかける行為
=>相手に対して興味や好奇心を抱くという立場から始まる
投稿元:
レビューを見る
現代社会は「話す」過多な社会だ。寡黙や聞き上手よりもプレゼン上手のほうが評価される。本屋にいけばプレゼン術のほんばかりだ。
シャインはそうした風潮に警鐘をならしほんとに必要なのは問いかける力だと指摘。現代の社会は複雑性をましていて、みんなで強調しながらダンスを踊るような精密なバランスが要求される。そんななかで大切なのは命令したり指示することえではなく、たえず相手を尊重し相手と自分をシンクロさせること、それが問いかけるということだ。
ーー
人間関係を築くかぎとして本書で語られるのが、「問いかける」という日常の行為である。コミュニケーションといえば、自分が「話す」ことや単に「聞く」ことに意識が向いてしまいがちだが、「問いかける」という行為は、時としてたった一言で場の空気を変え、人の視点や考え方を変え、相手との関係を変える力をもつ。よいリーダーもよいコーチも、指示・命令する以上に、いつも相手に問いかけをしているものだ。もっとも、ただやみくもに質問すればいいわけではない。よい人間関係の構築に役立つのは「謙虚に問いかける」ことだ。これが本書全体を通じてのキーワードであり原題(Humble Inquiry)でもある。
「自分が動き、自分が話す文化」がはびこっているということへの問題意識
われわれの社会は話す力を過大評価しているが、むしろ発言を控えて問いかける力を高めていくべきなの
米国の文化では、リーダーたる者は賢くなければならず、はっきりと方針を決め、価値観を明確に示すべきだと言われるが、どれをとっても質問することよりも自分が話すことに比重が置かれている。しかし、人の上に立つ者こそ、「謙虚に問いかける」ことが必要だ。なぜかというと、物事が複雑に絡み合い、人が協力し合わなければ進められない仕事こそ、信頼に基づく良好な人間関係が欠かせないの
リーダーのほうからチームに向かって「私のやり方は正しいだろうか。もし間違っていたら指摘してほしい」と折に触れて言っておく必要がある。
相手をとるか自分をとるかという選択を迫られた場合、二人にとってどうするのがいいかという視点で考えよう。互いの関係に焦点を当てること。(どっちかが我慢するではなく)
ほかの問いかけ方と「謙虚に問いかける」はどう違うのか
ある人との付き合いを始めようとして会話に臨むとき、あなたには問いかけ方の選択肢がいくつも用意されていることを認識してほしい。それともう一つ、自由に答えさせるような質問をしているようでいて、実は相手をかなりコントロールしてしまう聞き方がある。そのことも知っておくべきだ。なんとしても相手にすべてを打ち明けてほしいのであれば、うっかり自分が会話を支配してしまった、などという事態に陥ることは避けたい。
彼はよく社内を歩き回っては技術者の席で立ち止まり、「今、君はどんな仕事に取り組んでいるの」と話しかけてい
「あなたがその行動をとったとき、相手はどんなふうに感じたと思いますか」 「もしあなたが、自分が言ったことをそのとおりに実行したら、��の人はどう対応するでしょうか」 「もしあなたが自分の気持ちを伝えていたら、相手はどのように反応したと思いますか」
謙虚な問いかけ ②診断的な問いかけ ③対決的な問いかけ ④プロセス指向の問いかけ
相手との話が進むにつれて自分はなるべく聞くことに専念するように心がけよ、という
自分ばかりが話すことを控え、もっと相手に質問するように心がけたとしても、それだけでは互いに信頼できる人間関係を築くには不十分である。もしも自分のほうが相手よりも一段高い位置にあることを証明したいと心のどこかで思っているならば、その気持ちが態度に表れてしまう。
謙虚に問いかける」はどうしてこんなに難しいのだろう。この問いに答えるには、自分が話すことを奨励する文化的な影響力について考えなければならない。
投稿元:
レビューを見る
自己主張の国、アメリカならではのビジネス書な感じがした。ビジネスを主眼として書かれてる感じだけど、うまく「問いかける」というのは、仕事だけでなく人間関係では大事。しばらくしたら、もう一度読んでみよう。
投稿元:
レビューを見る
「謙虚に問いかける」
相手の警戒心を解くことができる手法であり、自分では答えが見い出せないことについて質問する技術であり、その人のことを理解したいという純粋な気持ちをもって関係を築いていくための流儀である。
まだ途中ですが、読み進めていく中で、「ふむふむ」と納得する箇所、初めて出会う考え方がたくさんありました。
続きは読んでからまた書きます!
投稿元:
レビューを見る
「自分が話す」のではなく「謙虚に問いかける」ことを心掛ければ、会社も家庭もうまくいく。組織心理学の観点から、「問いかける」ことの重要性とその手法、更には実行面での課題と対処法を明らかにした一冊。
特に多様な価値観を持ったメンバーとの相互依存によって、複雑性の高い仕事を行う組織では、「まずは自分が話すことで主導権を握る」といった「勝ち負け」の文化を脱却し、地位や立場を超えた人間志向の信頼関係を高めることが不可欠であり、そのためには自分の価値観や先入観を内省し、様々なスタイルの「問いかけ」を通じた、新しいタイプのリーダーシップを身につける必要があると説く。
このような姿勢は得てして「あいつは弱い」とか「やさしすぎる」というような評判に繋がり、舐められたりバカにされたりするリスクを感じる向きもあるかもしれない。ただ、そんな自尊心を優先することが、組織の生産性の低下や、家庭不和の要因になっているのも事実だろう。安易におもねるのではなく、勇気をもって「一段下がる」ことが、これからの時代を生き抜く"真の強さ"なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
謙虚にきくことで、人間関係が改善していくという例が、さまざまな角度から解説されています。
話すことではなく、きくことの重要性が説かれています。
問いかけるというよりも、きく技術です。
最後の監訳者の言葉にも書かれていましたが、きく技術とすると、聞く技術と捉えられる恐れがあるので、邦題を「問いかける技術」としたと書かれてあります。
単なるスキル本ではなく、理論的な背景から書かれていますので、理解しやすく、納得できるところが多々あります。
投稿元:
レビューを見る
自分でもよくある、そんなつもりで言ったわけではないのに、相手に不快な思いをさせることの防止法を示唆してくれる。ただし、これを実行するための前提として、自分自身にゆとりを確保する必要があると実感した。
投稿元:
レビューを見る
「謙虚に問いかける」はその人のことを理解したいという純粋な気持ちをもって関係を築くための流儀であり、質問する技術である。
目的を共有し、お互いを理解し、尊重することを意識し、自ら「謙虚に問いかけ」内省していきたい。
投稿元:
レビューを見る
まず訳がいけてなく、本の構成も悪いのが傷。。
・よい人間関係の構築に役立つのは「謙虚に問いかける」
・上に立とうとするのではなく、自分をあえて弱い立場に置くことを学べば、より良い関係が築けるはずだ。
・私は人からむやみに指図されたり、一方的にまくし立てられたりすることが苦手だ。とりあけ、自分が知っていることを聞かされると気分が悪くなる。
・つい自分の話をしたがってしまう。大抵の場合、自分では思い当たらなかったことを相手から教えてもらえるような質問をするという心掛けや好奇心と言ったものが会話のなかで忘れられているからだ。
・今ここで必要な謙虚さ。部下を始めとるす自分よりも地位の低いメンバーに自分は実質的に頼っているという事実を認識する。
・問いかける、という行為は相手に対して興味や好奇心を抱くという態度から導かれる。
・あなたが賞賛し尊敬する人たちのことを思い浮かべてみよう。彼らがもっている謙虚さとは?
・しかたなくお茶にでかけることにしたものの、心からそうしたわけではないので、会話がぎくしゃくして、互いに不満が残る。こうならないためには、2人で一緒に決める。
相手をとるか、自分をとるか、ではなく、2人にとってどうするのがよいのか、という視点で考える。
・自分がそのとき抱えている問題で手が離せなくても、相手に対する思いやりは示したいと思っているなら、ほんの少しだけ自分が変わればうまくいくことが多い。
・「ああしろ」「こうしろ」ではない。これをしなければならない理由を考え合うことで、コミットメントを共有し、責任感を持てる。
・たとえ一方的な話し方でも、相手に対する純粋な興味からだた言葉であればいかなる質問も「謙虚な問いかけ」になる。相手のことをもっと知りたいと思っていることは、しぐさや声のトーンなどで伝わるものだ。
・謙虚な姿勢で尋ねるときは先入観を排除し、頭のなかをすっきりとさせて会話を始め、相手に話をさせることに注力する。
・「信頼」は、相手が自分を利用したり侮辱したり恥をかかせたりすることはせず、自分のこと
投稿元:
レビューを見る
傾聴の派生。「謙虚に問いかける」humble inquiry ことをテーマに、幾つかの角度から解説した本。具体的な事例も多く、わかりやすい
投稿元:
レビューを見る
「人を助けるとはどういうことか?」につづく、組織行動論の大家シャイン先生の「人助け」シリーズの2冊目。
「人を助ける・・・」を読んだときには、なるほどと思いつつも、なんて、人間って、面倒くさいんだろう。そんなに相手に気を使わずに、率直に話せばいいじゃん的に思った。
今回の「問いかける技術」(humble inquiry: the gentle art of asking instead of telling)は、さらに面倒くさい感が高まった感じです。
たしかに、人間って、社会的な関係性のなかにあって、言いにくいこと、聞きにくいことがいろいろあったり、立場や言葉が作り出す微妙な上下関係みたいなのがあることはあるんだろうけど、ここまで、謙虚にならないと人間って、コミュニケーションできないんだろうか?これって、主張が強くて、相手の話しを聞いていると「負け」になってしまうアメリカなどの文化のなかでの話しじゃないの?などなどの思いがたくさんよぎった。
でも、日本で、こういう謙虚な問いかけというのがよくなされているかというと、そういうわけでない。「いやいや、私はそれほどのものではありません」と謙遜、卑下、自己否定(?)と「謙虚」することは多いとおもうけど、「私は知らないんです。もっと教えてください」と謙虚に質問することはそんなに多くはないかも。
なるほどと思いつつも、なんとなく、微妙にフィットしない本でした。