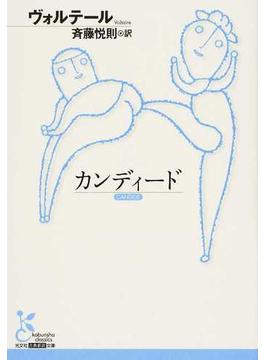紙の本
フランスの啓蒙思想家ヴォルテールによるピカレスク小説です!
2020/05/09 10:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、フランスの啓蒙思想家ヴォルテールによって1759年に発表されたピカレスク小説です。内容は、ドイツのウェストファリアを舞台に、そこの領主ツンダー・テン・トロンクの城館に領主の甥にあたるカンディードという若者がいました。家庭教師パングロスによる「すべて物事は、今あるより以外ではありえない」ことが証明されていて、「一切万事は最善である」というライプニッツの楽天主義を信じて幸福に育ったカンディードであったのですが、領主の娘キュネゴンドと接吻を交わしたために、生まれ育った城から追放の憂き目に遭ってしまいます。騙されてブルガリア連隊に編入させられたカンディードは、脱走を試みて捕まり、連隊中の兵士から鞭打ちの刑罰を喰らいます。ブルガリア(プロイセンのアレゴリー)とアバリア(フランスのアレゴリー)との合戦の際、戦闘の混乱に紛れて再び逃げ出したカンディードは、戦場の至る所で両軍の兵士により虐殺された市民の死体を目にします。血まみれの乳房を子どもにふくませたまま死んでいく女性や陵辱後に腹を裂かれて死んでいく娘たちを見たカンディードは何を想い、どうするのでしょうか? 続きは、ぜひ、同書をお読みください。
紙の本
文句なく面白いですよ
2019/01/27 20:37
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「最善説」というのは、例えその人生が悲惨を極めていたとしても、作中の言葉を使うと「すべては最善となるよう整えられております」と考えてられるというとんでもない考え方であって、ガンディードが生きていた時代には結構はやっていた思想であるようだ。その思想について、彼はこの作品を通じてくそみそに貶しまくる。強姦されても、八つ裂きにされても「こんな目にあっても、お前は最善だと言っていられるのか」と彼は罵る。さらに、彼は彼に批判的な人を物語に引きずり出して「三文文士とは低俗な雑誌に文を載せる〇〇〇」みたいに罵倒する。しかし、ガンディードは最後に「とにかく、ぼくたち、自分の畑を耕さなきゃ」と前を向いているのだ
紙の本
純真と名付けられた青年の苦難の遍歴!
2017/04/14 17:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sin - この投稿者のレビュー一覧を見る
純真と名付けられた青年の苦難の遍歴!その純真さ故に腹立たしいほどに他人の悪意に食い物にされていく様や、物語に散りばめられた作者の八つ当たり等、最早醜悪なコメディ!この苛立ちはなんだろう?次から次に現れる悪意ある人間達の有り様に、言い様もない不快感を覚える。ヨブは信仰の為に苦難に合い神に見出だされるが、カンディードは労働に己の存在理由を見つける。
投稿元:
レビューを見る
普段、ニュースに現れるものは事故や事件、災害など人々におこる不幸である。
というよりも、そういうものこそがニュースになるという面がある。
起こりうる「災害」や「不幸」を、その理不尽さをどのようにとらえるべきなのか。「カンディード」はまさにその「不幸」を引き起こすもの、つまりはこの世界を創り出した「創造主」に対する抗議、皮肉である。この世界は全能の「神」である創造主が創りだしのだから、間違いなど無い、「全て最善」である。毎日報道され、存在する無数の「事件」や「事故」も最善なのだとしたら、「そんなことはない」と反発を覚えるのではないだろうか。私は最初にそう感じた。ヴォルテールが本書で言いたかったこともそういうことなのではないか。
本書の解説は最初にこれがテーマだと感じたものをより掘り下げてくれた。それは「最善説」の解説である。「この世の全ては最善である」という説は、この世にあるものは全てに何らかの存在の理由があり、その理由を辿っていくと究極的にはこの世界の創造の原因に辿り着かざるを得ないという説だ。これは強力な存在の肯定論だ。実際、あらゆる「事件」も「事故」も「災害」もその背景や動機を辿っていくという行為は日々行われているものだが、その究極の原因については考えないものだ。そんなことを言い出したらこの宇宙の誕生という話から全てを行わなければならないからだ。「最善説」は現在ある世界を肯定する。それも強力に。存在の善悪ではなく、ただそこにあるものをあるというだけで肯定する。それが本来の「最善説」である。
本来の「最善説」とは、因果関係の果てにあるものは何か?という話だ。その問題意識は今でも通じるものだ。学者は「真理」を探究して学問や研究を追求するからだ。しかし、もし本当に理由や原因がはっきりとわかったとして、それで「不幸」にあった人々はその理由や原因に納得するのだろうか。例えば、地震の原因が完全に解明されたとしても、その地震によって何かを失ってしまった人は本当に納得するのだろうか。その理由がこの自然に存在する何らかの法則であったとして、それによる被害を受けた人々は救われるのだろうか。この世の理不尽に引き起こされ、現実に起こる苦しみや不幸が何か別のものに変換されてしまうような憤りを感じるのではないのだろうか。「苦しみ」や「不幸」もそれぞれの人が抱えるその人らしさの一部である。ヴォルテールは本書に収録されている「リスボン大震災に寄せる詩」においてそうした一節を書いている。彼は生の苦しみもかけがえのないその人のものであり、それを抱えて一歩を踏み出している人達を讃えようとする。新聞にはニュースが載る、それはだいたい良くない出来事の事だ。その裏には多くの「不幸」がある。まさにこの小説で描かれる事だ。その「不幸」を乗り越えるために、現実をコントのように描写し、皮肉に乗り越えていく。短く素晴らしい本である。
投稿元:
レビューを見る
レナード・バーンスタインのオペレッタ「キャンディード」は、この物語をベースにして作曲されたとのことである。確かに、その序曲からは主人公の波乱万丈の物語がよく表現されている。
この物語のキーワードである「最善説」とは、「性善説」と勘違しがちであるが、それとは少しく異なっている。「この世にある個別の悪は、ことごとく全体的な善である」という考えである。作者ヴォルテールは、どうやらカトリック教会が中心になって流布していた権威的な「最善説」をこの作品で批判したかったようだ。
投稿元:
レビューを見る
「最善説」についての是非。世界は最善にできているのか、できるいるとしたら、不幸な人はなぜいるのか。個人のせいなの?悪いことをしたから。全体としての善。主人公カンディードが遭遇する様々な出来ことを通し、隣人と対話しながら、考えていく物語。頭でごちゃごちゃ理論を考えるでなく、目の前にある畑を耕そうというラストシーンがプラグマティックな印象を受けた。ドイツの観念論、フランスの構造主義、イギリスの経験論、アメリカの分析哲学、プラグマティズム。これらのもとになっているような、なっていないような。啓蒙の時代の17、18世紀であり、近代合理主義というか科学発展の時代の始まりに書かれた本で、現代のように、高度に専門分化する前のところ。とても面白く読めた。再読しよう。今度は岩波で読んでみようかな。
投稿元:
レビューを見る
バーンスタインがミュージカル化しているこの作品。ミュージカルは観てないけど、気になっていたので読んでみた。登場人物が皆悲惨な目にあってるのに結構あっけらかんとしていて、コメディタッチで読みやすい。途中で著者の私怨も盛り込まれていたりしてもう何でもあり。机上の空論より身体を動かして働こう、と登場人物たちがオプティミスティックな思想が最後リアリスティックになるのがなるほどと思った。途中で出てくる登場人物ですべてを批判する人、一般の人が美しいと思っているものに欠点を見つける人は、それを楽しめないことを楽しんでいる、と分析しているのはとても腑に落ちた。
投稿元:
レビューを見る
こんなにも笑える古典は初めてだ。
たっぷりといたずらな皮肉が効いている。
不幸の域値を越えて爆笑となる。
だが中盤、あまりにも悲惨なので笑えなくなってくる。
だが、終盤はもはやめちゃくちゃで哲学コントと言われるのもよくわかる。
だが、ヴォルテールは至って本気でこれを書いているのだろう。
本書を通じて一貫してあるテーマは、
「人が生きるということは、善なのかそれとも悪なのか?」
という人や人生の本質への問い。
実は、ヴォルテールはルソーから批判の手紙を受け取っていた。
「君の考えには人間の原始状態への考察への配慮が足らないよ」と。
この『ガンディード』は、そのルソーへの暗黙の返答だったのだ。
それを踏まえて読むとさらに面白い。
ルソーとヴォルテールの議論を、この『ガンディード』という物語を通して垣間見ているようだ。
結論として、
ヴォルテールは議論している暇があったら働こう。なぜなら、退屈、堕落、貧困というのは不幸の元凶であり、働くことはそれらを退けることになるのだから、と。
この働くということを重んじる思想は、
聖書からの引用でもあるように、
庶民は働かなければ(主に農業)生きていくことができない時代を反映しているものであり、
それをそのまま現代に置き換えることは出来ないと思うが、
それだけではないより深遠なメッセージがそこにあることを感じる。
働かなければ生きていけない時代から
働かなくても生きていける時代の今。
働かざるもの食うべからず、から
働かなくても食っていいの現代。
人はパンのために生きてはいない。
だが、パンなしでは生きられない。
そして、ただ何もせず無為に過ごす(働かないというのをその意味で使うならば)ことは出来ないのだ。
投稿元:
レビューを見る
東浩紀が書いた『観光客の哲学』に本書が参照されていたので、読んでみた。梅毒にかかったり、絞首刑で死にかけたりしながらも、最後まで「最善説」を肯定するパングロス博士が滑稽で仕方がない。ところで、今の時代で最善説を信じている人はどれくらいいるのだろうか。もし私が災害などの不幸にあって苦しんでいる際に、「全体の善のために、あなたの不幸があるのだ」とか彼らに言われたら、間違いなくブン殴るだろうな(笑)
投稿元:
レビューを見る
リスボン大震災に寄せる詩を目当てに読んでみた。
あまりの惨事に、18世紀当時支配的であった最善説、すなわち、世界は神によって最善のものとして作られているのだから、いまここが不幸に見えてもより大きく見ればそれは最善なのだ、という考え方を疑うというもの。災害は天罰なのか、それともめぐりめぐって実は救済なのか、どう、この惨事を腹落ちさせればよいのか、という悩みは、現代もなお続いている。
地震そのものの描写も興味深い。
カンディードの方は、最善説を信じてよいのかと悩める冒険物語。理想郷としてのエルドラドの扱いや、ちらっと日本が出てきたりするあたり、スイフトのガリバー旅行記とも通じる感じがした。ほぼ同時代のもの(ガリバー旅行記の方が先)だし、影響があるのかも。
投稿元:
レビューを見る
個々の不幸が全体の幸せを作り出す
盲目的に信じるということの大切さ。
結果には必ず原因がある。結果は今を見ればわかるが原因は考えないと分からない。
全ては神によって決められている。全ては最善なのだ。最後には自分の心臓まで食べられてしまうのに人間は自分を飲み込む大蛇を愛おしそうに抱えている。
働く事は私たちを退屈、堕落、貧乏の3つの不幸から遠ざけてくれる。働こう。休むために生まれてきたわけではない。
素直に良さを引き受けよう。あまり批判を考えすぎない。
自分の身の回りの幸せに目を向けよう。
投稿元:
レビューを見る
読まなければよかった。
悪趣味の最たるもの。
滑稽さを笑い話にする手法で、当時の思想をおちょくっているにせよ、あまりに残虐。
受け入れられる人と、絶対無理という二つに分かれるだろう。
投稿元:
レビューを見る
面白かった。純粋で真面目で師匠の説く最善説をひたすら信奉するカンディード。苦難の旅で信じるものが揺らいでゆき、第二十三章では「この世界はいったい何なんだ」と悩むカンディード。第二十九章礼を尽くしてきた身分の高い恋人の兄を面と向かってとうとう「バカ殿」呼ばわりするカンディード(ここは笑いました)。人間について生きることについて現代でも解決できない同じことを、ずっと昔から人は悩み苦しんできたらしい。「リスボン大震災に寄せる詩」は素晴らしかった。よくも自分はカンディードとこれを読まずに今まで人生に悩んでこられたなと思う。詳しい解説がまた素晴らしく、目を開かされた思い。
パングロス先生を私は滑稽とは思わない。その生き方も尊重されるべきで、彼がカンディードの支えとなり読者の思考を深める。
解説でライプニッツ、ルソー等の本も紹介されている。本をめくりかえしながら、人生ってなんなのかを問うわたしの旅への出発はここからだなと気づく。
投稿元:
レビューを見る
ライプニッツの最善説、カトリックに対する痛烈な皮肉だが、そうならざるを得ない苛烈な現実認識があり、その元となった「リスボン大震災に寄せる詩」も収録されている。
カンディードは、どんな無体な現実の体験をしても、哲学の眼鏡を通してしか認識することができないが、最後になってようやく、目の前の畑を耕すことの方が重要である、と言う事実に気づくことになる。
カンディードのあまりに過酷な経験に目を覆いたくなったり、キリスト教的な道徳や、救いの少ない結末に違和感を持つ読者もあるだろうが、それが、リスボンの大震災の経験に基づいている、と思うと日本人としては途端に親近感を覚えることも事実。
投稿元:
レビューを見る
18世紀の啓蒙思想家ヴォルテールの哲学的小説。波乱万丈の冒険譚を通じて「最善説」に疑問を投げかける。
何やら哲学がテーマになっているというのでどんな小難しい話が出てくるのかと思ったら、冒頭からたたみかけるような災難・悲劇・試練のオンパレードで引き込まれた。息もつかせぬスピード感で波乱万丈の大冒険を繰り広げる主人公。彼はただ運命に翻弄されているだけにみえて、その胸には常に「恩師の教え『すべては最善である』は本当か?」という命題がつきまとっている。この「最善説」という考え方は、本書に反発したルソーのように色々な解釈ができ、多くの人を議論に巻き込んでしまう魔力のようなものがあるように思える。この物語の中でも主人公を中心に議論がたえない。悪や不幸を目の前にして、すべて神の創った最善といえるのか。それでは希望とは……。こちらも考え込んでしまうことしきりである。
若者カンディードの冒険譚というメインラインだけでエンタメとして十分面白い。その上で議題の哲学的テーマについて、同時収録の「リスボン大震災に寄せる詩」と合わせ、一通りの思索をめぐらせる機会となった。あらゆる苦難・辛酸を味わった主人公が最後にたどり着く結論が感慨深い。最後の一行……人間にはこれしかないよなぁ、と。