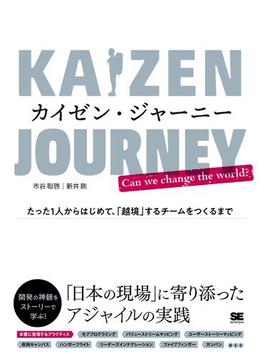- 販売開始日: 2018/02/15
- 出版社: 翔泳社
- ISBN:978-4-7981-5334-6
カイゼン・ジャーニー たった1人からはじめて、「越境」するチームをつくるまで
「日本の現場」に寄り添った、アジャイル開発の実践!現場のストーリーで、開発の神髄を学ぼう【本書の特徴】・現場のストーリーから、考え方とプラクティスを一緒に学べる・1人でも...
カイゼン・ジャーニー たった1人からはじめて、「越境」するチームをつくるまで
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
「日本の現場」に寄り添った、アジャイル開発の実践!
現場のストーリーで、開発の神髄を学ぼう
【本書の特徴】
・現場のストーリーから、考え方とプラクティスを一緒に学べる
・1人でも始められる業務改善の手法から、チームマネジメントの手法まで解説
・日本の現場を前提にしているので、実践しやすい
・アジャイルをこれから始める人だけでなく、もっとうまく実践したい人にも最適
【あらすじ】
ITエンジニアとしてSIer企業に勤務する江島は、
問題だらけのプロジェクト、やる気のない社員たちに嫌気が差していた。
そんな中、ある開発者向けイベントに参加したことがきっかけで、
まずは自分の仕事から見直していこうと考える。
タスクボードや「ふりかえり」などを1人で地道に続けていると、
同僚が興味を示したため、今度は2人でカイゼンに取り組んでいく。
ここから、チームやクライアントを巻き込んだ、現場の改革がはじまる。
チーム内の軋轢、クライアントの無理難題、迫りくるローンチ……
さまざまな困難を乗り越え、江島がたどり着いた「越境する開発」とは。
【筆者コメント(「あとがき」より)】
良い問いは人を立ち返らせてくれます。
そのような問いは人によって異なるでしょう。
読者のみなさんにとっての良い問いと出会えるよう、
江島(本書の主人公)同様、自分がいる場所から外に出て、
いろいろと見聞きしてみてください。
もちろんこの本があなたにとっての
良い問いになることを願っています :)
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
物語仕立ての社内のカイゼンストーリーです。
2018/07/04 11:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、「カイゼン」によって社内の業務を効果的、効率的にしていった一人の主人公を中心とした物語です。この物語を通して、業務の「カイゼン」の精神が学べるようになっています。少し内容を紹介しますと、ITエンジニアの主人公、江藤の社内はやる気がない社員と非効率な仕事の温床でした。江藤は、ある研修に参加したことをきっかけに一人で、振り返りやタスクボードへの書き込みなどを行っていると、やがて、それに興味を示した仲間が増えていき、社内は徐々に改善されていったというものです。物語として語られるので、非常に分かり易いと思います。ぜひ、自分の会社を「カイゼン」したい人には、読んでいただきたい一冊です。