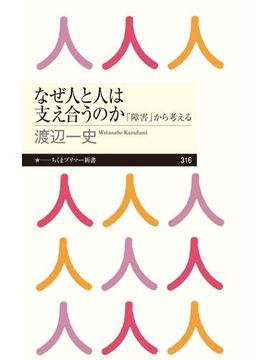「支えること」によって「支えられている」。ちょっとドキリとさせられる。
2019/02/14 16:38
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
2020パラリンピックも近づき「障がい」について考える本も増えてきた。きれいごとで終わるようなものも多いが、本書のような「ちょっとドキリとするが気づかされる」本もぜひ目を通してほしい。
2003年刊行の「こんな夜更けにバナナかよ」。映画化されたので聞き覚えのある人も多いかと思う。一見「わがまま」のようにだけ思えてしまうかもしれないこの「夜更けにバナナ」という障害者への感想もひとそれぞれだろう。著書の作者が、本を書いた当時からさらに積み重ねた言葉には気づかされることが多かった。
「障がい者に価値はあるのか」というところから2016年に起こった殺傷事件から始め、本書は「人間・人間関係」について考えていく。障がいを持つ人とはどういう人か。持たない人にとってどんなものと考えればよいのか。
例えば「ボランティアをする側の気持ち」。「なぜボランティアをするか」もつきつめていけば「自分も何かできる」という欲求を満たしている気持ちがあるだろう、というのだ。「自分の価値を見つけたい」欲求は誰にでもある。その欲求をボランティアで満たしているとすれば、お互いに与えあっているとも考えられる。
「自立」ということ。それは「他人の世話にならない」ことではなく「自分で決定できる」ことだと第3章にある。そう考えれば障がい者も「自立」できるはず。
こんなふうに、わかっていたつもりでもまだまだちがう見方もあるのだと思わされるところがたくさんあった。人間はどうしても自分自身の「あたりまえ」に沈んでしまう。何度かどきりとさせられた。
気づかされる場所は本書でも「ひとそれぞれ」だろう。今は「他人の世話など必要ない」人でも、事故や加齢でいつどうなるかわからない。若い人向けに書かれてはいるが、何歳の人が読んでも得るものがある(あってほしい)本だと思う。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽんぽん - この投稿者のレビュー一覧を見る
障害者に生きる価値はあるんですか?という意見はあるよね。その人も自分が言われたらとか障害者になったらと想像してみると…そんな感じでいろんなことを考えさせられた。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る
障害者のことを考えるお言うことは、じぶんにとってもとても大切なことだなということを、気付かされました。
投稿元:
レビューを見る
面白かった。こんな夜更けにバナナかよ、の便乗本だと思って手に取ったが、それを包括して、じっくり論じている。読者は何らかの意見を持つことが出来る。
投稿元:
レビューを見る
映画の『こんな夜更けにバナナかよ』の作者が書いた本。
相模原の事件犯人に反論することも含めて、障害者の価値
についても書かれてある評論。
とても有意義な内容だと思います。常々私自信も
障害者は、社会のリトマス試験紙というか、生きづらさに
悩む人たちに対する対応は、社会全員に有意義な対応になり
得ると思っています。
こういう考えというか、感じ方ができる人や社会が
作られていけば、本当にいいなあと思います。
皆さんに読んでほしいと思います。
投稿元:
レビューを見る
障害については色々あって、割と詳しいのだが、障害の社会モデルや、「役に立たない」論、障害者福祉政策の変遷など、分かりやすくまとまっていた。
同著者の「こんな夜更けにバナナかよ」も映画化され、今までの障害者観が変化しつつある現在、本書で多くの人に障害について知ってもらえたら嬉しい。
投稿元:
レビューを見る
著者は2018年に公開された、障害者とボランティアの交流を描いた映画「こんな夜更けにバナナかよ」の原作者。
障害者と社会について、著者の経験をもとに書いている。
「人は誰かの役に立つことによって存在意義を見出す。だとしたら困っている人であることが、誰かの役に立っていることになる。ゆえに介護する側もされる側も平等である。」という意見が印象に残った。
投稿元:
レビューを見る
あわれみの福祉感、まさに、自分の中にあった障がい者への気持ちを言い当てられた具合の悪さがあった。
確かに、かわいそう、気の毒、頑張ってる、24時間テレビ的な、きれいごとが私の中の障がい者に体する意識としてあった。
後半の海老原さんの人サーフィンして生きる姿はたくましい。
ものを頼むというのは、生きていく中でもっとも神経をすり減らす作業の一つです。という言葉が刺さる。
実際、健常であることは永遠ではない。自分や、身近なひとが障がい者になったとき、
健常でなくなっても、どれだけ同じように他者と関わって行けるか=自分と障がい者の関わり方として考えないと…。
投稿元:
レビューを見る
これだから、福祉の本はやめられないなあ、という本。
すごい人がたくさん出てくる。思いもよらなかった視点を持っていたり、行動力が半端なかったり、忍耐力もすごかったり。
私はいま、心に余裕がないが、社会福祉の最前線を知るたびに、不思議と生きていることへの無前提の肯定が得られる。
投稿元:
レビューを見る
駅のエレベーターも最初はコスト的にムリ、次に車椅子で来たら突き落とすぞ(すごい言葉…)、と言われていたものが、今ではすっかり普通に。求めなければ与えられない。「社会に生かされているだけでもありがたい…」と遠慮していてはダメなんだと。
障害者は生きる価値がない、というのであれば、あなたにどんな生きる価値があるのかを示してください、という問いがおもしろい。
誰かを支えることで、自分が幸せになれる。一億円積まれてもやらない人はやらないが、一億円積まれなくても「あ、やりますよ」という人間はいる。人間関係というのは単純なものではない、と思いました。
投稿元:
レビューを見る
津久井やまゆり園を例に出して、障害者の存在意義を書いたのだろうが、書かれている障害者の奮闘ぶりは、全て身体障害によるものというのが残念。
「なぜ人と人は支え合うのか」というタイトルなら、三障害を網羅してほしかった。
投稿元:
レビューを見る
障害者とその活動、関わり
意外と障害者にかかる税金は少ないこと
彼らが人を雇い経済を回していること
障害者はある点ではそう分類されるが、身体的個性でしかないこと
投稿元:
レビューを見る
1/29おはよう日本で紹介
『こんな夜更けにバナナかよ』原作者が、
障害者殺傷事件を受け問題に正面から挑む―!
投稿元:
レビューを見る
なぜ人と人は支え合うのかという大命題を解いていく。といっても答えは載っていない。ちくまプリマー新書だけに示唆的にいくつか障害者との事例を出したり、制度のことや「しょうがい」に当てる漢字についても取り上げている。ちょうど執筆時期(といっても5年かかっているらしいけど)と重なっていたこともあってか、津久井やまゆり園事件についても特に殺害を図った植松聖についても触れている。
私もかつて障害者の家で泊まり込み介助らしきことをやっていたから、渡辺さんと『こんな夜更けにバナナかよ』の鹿野さんとのつき合いの様子などは、当時のことを思い出し、うなずけたり懐かしく思うことが多かった。
「しょうがい」に当てる漢字については、私の今の認識は渡辺さんと似ていて、過剰に意識することなく使えばいいと思っている。何よりも障害者自身が、「障がい」という書き方をそれほど望んでいなかったとは。こういう似非配慮らしきものが世のなかと障害者をよけいに隔絶してしまうのだと思う。
それを思えば、植松さん障害者とかかわっていたわけで、その末の曲解であろうとも、それを障害者にやさしくとか口では言いながら、かかわることなく過ごしている人が非難するのってどうなのって思う。法治国家(?)の日本で人を殺したのだから刑は科されるものだろうけど、彼なりの実体験から導かれた障害者観は、間違った考えと一刀両断にできるものでもないと思う。……この件、この本の感想とは関係ちょっと脱線してしまった。
渡辺さんはたぶん考えはめぐらすけど答えはあえて出さない人のような気がした。答えを出すということは、言い換えれば決めてしまうことであり、その答えにとらわれてしまうと物事を見る目が不自由になってしまうと思う。優柔不断に思われがちだけど、そんなところに勝手にシンパシィを感じ、考えあぐねながら書いたであろう文章にやさしさを感じた。
投稿元:
レビューを見る
『なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える』渡辺一史
先日公開されていた映画『こんな夜更けにバナナかよ』(未見)の原作者であり、ジャーナリストの渡辺一史さんによるビギナー向けの新書。
映画の中で描ききれていなかった障害者の自立生活へ向けた運動の歴史、声を挙げる運動あってこそ駅のバリアフリーが普及し、ベビーカーや高齢者も恩恵を被っていること。「障害者・障がい者・障碍者」の表記の議論について。言葉を選ぶことで「いい人(ちゃんと配慮している人)に見られたい」自分を見破られ、戸惑う。
相模原の施設で起きた殺傷事件から、ネットでは見るに耐えない言動が撒き散らされる中、「その人に価値があるか無しかではなく、価値を感じられる人間がいるかいないかだ」とひとり一人に問いかけてくる。
この本についてはあれこれ書けば書くほど嘘っぽくなるので、読んでほしいとしか言いようがない。いろんな事件の中で「役に立つものしか認めない」風潮が見え隠れする、「今」の空気に、流されないためにも。
もう亡くなって数年経つが、直前まで元気だった義母が脳出血で倒れ、あっという間に人の助けがなければ生活を営めなくなった時、福祉が行き届いた社会を作ることは「明日の家族や自分のためでもある」と痛感した。
ゆる夫は、重度の障害を持つこどもたちのデイケアで勤めている。主体的に仕事をしようとしないまま生きてきた彼が、「俺がおらんと(職場が)回らへんねん」と自分の意志で仕事を続けている。
こどもたちの生活を支えると同時に、彼も支えられている。塾講師時代、何度も中学生に教えた吉野弘の詩『生命は』の1フレーズが浮かんでくる。
「生命はすべて/そのなかに欠如を抱き/それを他者から満たしてもらうのだ」
書き手自身が答えを模索する旅に、同行する気持ちで読んだ本だった。