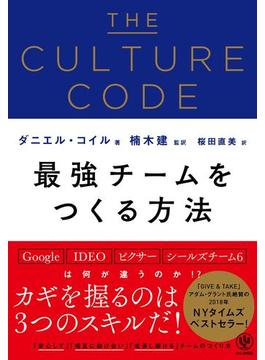ひとつの目標に向かって
2020/05/19 17:36
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
上下の関係よりも、横の繋がりを重視した組織運営が参考になります。ビジネスからスポーツまで、様々な分野で応用ができそうです。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kuni - この投稿者のレビュー一覧を見る
ダニエル・コイルさんの本は2冊目だと思います。良くも悪くもアメリカっぽいというか合理的な感じがします。ただそんな考えも嫌いじゃないですよ。経営、ビジネス、MBAなどに興味がある方はぜひ一読を!
投稿元:
レビューを見る
さすが監訳者が楠木先生だけのことはあった。面白かった。
・監訳者まえがき
「安全な環境」「弱さの提示」「共通の目標」という3つの条件に支えられた文化を持つチームには、以下のような行動様式が共通して見られる。お互いの物理的距離が近く、よく輪になっている。アイコンタクトが多い。握手やグータッチ、ハグなどの肉体的接触が多い。特定少数の人が長々と話すのではなく、短い言葉のやり取りが多い。仲のいいグループで固まらず、誰もがメンバー全員と話をする。人の話を熱心に聞き、さえぎらない。質問をたくさんする。ユーモアと笑いがある。ちょっとした礼儀や親切を忘れない。「ありがとう」と言う―。このように、本書の議論は、いたってシンプルかつポジティブな人間観に基づいている。
いずれも、ちょっとした習慣であり、振る舞いである。
・本文
ペントランドの研究によって、チームのパフォーマンスは、5つの計測可能な要素の影響を受けることがわかった。
1 チーム全員が話し、話す量もほぼ同じで、それぞれの1回の発言は短い
2 メンバー間のアイコンタクトが盛んで、会話や伝え方にエネルギーが感じられる
3 リーダーだけに話すのではなく、メンバー同士で直接コミュニケーションをとる
4 メンバー間で個人的な雑談がある
5 メンバーが定期的にチームを離れ、外の環境に触れ、戻ってきたときに新しい情報を他のメンバーと共有する
ジェフ・ディーンというグーグル社員が、そのメモ(ラリーペイジがキッチンの壁に貼った「こんな広告はクソだ」というメモ)を目にした。…
ディーンは自分のデスクに戻ると、アドワーズ・エンジンの修正を始めた。誰かから許可を得たわけでもなく、誰にも話さなかった。ただ「やってみた」だけだ。
ディーンのこの決断は、どの角度から見てもまったく意味がない。目の前には自分の仕事が山積みになっているのに、それを無視してでも、誰にも「やれ」と言われていない、難しい仕事にあえて手を出している。途中でやめても、誰もそれに気づかないだろう。
しかし、彼はやめなかった。それどころか土曜日にも出社して、アドワーズの改良に取り組んだ。そして日曜の夜、家族と一緒に夕食を取り、2人の幼い子供を寝かしつけると、午後9時ごろに車でオフィスに向かった。オフィスに着くとカプチーノをつくり、アドワーズの続きに取りかかった。
月曜の午前5時5分、ディーンは改良案をまとめるとメールで送信した。それから家に戻り、ベッドに入り、ぐっすり眠った。
グーグルでのコミュニケーションは、センテンスが短く、言葉が矢継ぎ早に飛び出す。お互いの目を見る、エネルギッシュなやりとりだ。グーグルは、まさに帰属のシグナルであふれている。お互いに近い距離で働き、誰もが安心して自分の仕事に没頭できる。
ポポヴィッチの本当のメッセージとは、世界にはバスケットボールだけでなく、もっと大きなものが存在するということ、そしてその世界の中で人はみなつながっているということだ。
この言葉をよく見て��ると、3つの帰属のシグナルがあることに気づくだろう。
1 あなたはチームの一員である。
2 このチームは特別であり、高いレベルが期待されている
3 あなたはそのレベルに到達する力があると信じている
この3つの明確なメッセージが無意識の脳を刺激し、「ここは安全な場所だ。ここなら私は頑張れる」という気持ちになるのだ。
彼ら成功したスポーツチームのリーダーたちは、ロッカールームの掃除という地道な仕事を選手たちに見せることで、チームワークと勤勉さという価値観をチームに植えつけているのだ。
私は彼らのような行動を、「強者の謙遜」と呼んでいる。シンプルな方法でチームに貢献しようという心構えだ。ゴミを拾うという行為はその一例であり、他の方法もある。
弱さを見せるために必要なこと
まずリーダーが弱さを見せる(1回だけでなく何回も見せる)
メンバーに期待されていることをしつこいぐらい伝える
ネガティブなフィードバックは直接会って伝える
新しいチームをつくるときは、2つのタイミングを重視する。
トランポリンのように効く
もっとも効果的な聞き手には4つの特徴
1 相手が「ここは安全だ」「私はサポートされている」と感じられるような対応をする
2 相手を助けたい、協力したいという姿勢を見せる
3 ときおり優しく質問し、相手の思い込みを変えさせる
4 ときおり提案をはさみ、別の可能性に目を向けさせる
「価値のあることを言いたい」という衝動を抑える
率直な意見交換のできる場を確立する
率直な意見と個人攻撃は違う
気まずい瞬間を大切にする
協力関係を強調する言葉を選ぶ
仕事の評価と能力開発を明確に区別する
「フラッシュ・メンタリング」を活用する
ときどきリーダーが姿を消す
投稿元:
レビューを見る
culture codeという英文タイトルに惹かれて手に取った本。
「安心して」「相互に助け合い」「成長し続ける」チームこそが最強であり、そんなチームの作り方を事例と共に紹介している。
個人的に学びになったものは下記
●シグナルを出し続け、距離を縮めること
●弱さをさらけ出すことで相互の助け合いを促進する
●創造的なチームに必要なことは奇跡のブレークスルーではなく正しい選択するシステム=創造的な人を支援するカルチャー
●習熟が必要な分野と創造が必要な分野を切り分ける
習熟=
「目標とする最高の姿」をわかりやすく伝える
「繰り返しとフィードバックを主体にしたトレーニングを行う」「行動の指針となる覚えやすい標語をつくる」「スキルの基礎を重視する」
創造=
チームの構成や力関係に最新の注意を払う
創造的な行動におけるチームの自主性を定義し、守り抜く
失敗を恐れない環境をつくり、フィードバックを与える
チームの自主的な行動を盛大に祝う
カルチャーは一朝一夕には作れないが、組織こそが、人を成長させるという当たり前のことに気づかされた。
投稿元:
レビューを見る
チームを作るとき大切なことを凝縮。自分がスクラムを知って以降、学んだりどこかで気づかされたりしてきたことが、分かりやすく書かれている。この本は全てではないかも知れない。でも、たまにほ読み直してみてもいいかも知れない。
投稿元:
レビューを見る
今までいろいろなビジネス書を読んできたが、本書は間違いなく自分の中でトップ3には入る良書。
「良い組織」を作るにはどうすればよいか?
誰しも、「風通しを良くする」、「なんでも言い合える雰囲気にする」、「家族的な雰囲気にする」。
こんな言葉を何となく誰もがイメージすることはできるが、どうすればこれを実現できるかは、誰も教えてくれない。
本書では、このぼんやりとしたイメージを実際に数多くの成功しているチームへのインタビューや実験を通して、実際にどうやったら良いかが誰にでも分かりやすく具体的に述べられている。
著者は「最強のチーム」つまり、「良い組織」を作るには、本書で以下の3つのことを実践しろと述べている。
1 安全な環境をつくる
2 弱さを共有する
3 共通の目標を持つ
特に最初の「1安全な環境をつくる」の中で述べられている「腐ったリンゴ」の実験は、非常に興味深かった。
この実験は、ある組織に一人の人物が送り込まれる。この人物は組織内で雰囲気を壊すようなありとあらゆる態度や言動をさりげなく行う。
例えば、会議の場で、「この会議、かったるい、やってられないよ」というような言葉を他の参加者にやっと聞こえるくらいの小声で言ったり、発表者を馬鹿にしたような態度を取る。さらに発言を求められられても、その場で取り繕ったような適当な発言をし、会議の雰囲気を壊す。(実際に、『こういうことする人、いるいる!』と読者の誰もが思うようなことだ)
このような「腐ったリンゴ」が一人でもいると、どんなに優秀な人が集められた組織であっても、生産性が落ちてしまう。これは、その人物の態度や言動が他の人の気持ちに影響し、「あんな感じでいいんだ」というイメージを他の人間も持ってしまい、潜在的に真面目に仕事に取り組もうという意識が無くなり、結果として組織全体の生産性が落ちてしまうのだ。
この「腐ったリンゴ」作戦は、ほとんどの組織で成功した(実際に生産性が落ちてしまった)が、ある組織だけは上手くいかなかった。
この生産性の落ちなかった組織には、「腐ったリンゴ」の言動を中和してしまう人物「おいしいリンゴ」がいたからだ。
この「おいしいリンゴ」は、カリスマ的チームリーダーでも、組織のエースでもなく、ごく普通の人物であった。ただ、この「おいしいリンゴ」は「腐ったリンゴ」が悪意を持った言動をすると、すかさず「君はそう思うんだね。僕はこう思うんだけど、(他の人物を指して)あなたはどう思う?」と「腐ったリンゴ」の悪意を持った言動が周りの人に伝染しないようにする。
「腐ったリンゴ」はさらに悪意をばらまこうとするが、ことごとく「おいしいリンゴ」に中和され、最終的には、「腐ったリンゴ」も「おいしいリンゴ」に協力的な気持ちになってしまったという。
この「おいしいリンゴ」がやっていることは、特別なスキルを持っていなければできないような難しいことではなく、あくまでも「この職場は安全である、何を話してもいいんだよ」というメッセージを周りの人たちに与えるだけだ。しかし、このような「���の職場は安全である」というイメージを与えることこそが「良い組織」を作る為には非常な重要なことなのだ。
この「腐ったリンゴ」の実験の他のにも、数多くの実例が述べられ、さらに「2 弱さを共有する」や「3 共通の目標を持つ」にも目から鱗が落ちるインタビューや実験結果が満載されている。
本書で登場するのはGoogle、デザイン企業IDEO、ピクサー、アメリカ海軍ネイビーシールズ、全米プロバスケットボールのサンアントニオ・スパーズなど、高度なチームワークを誇る組織や、さらにコメディ集団のアップライト・シチズンズ・ブリゲード、悪名高い宝石泥棒集団(ピンクパンサー)も登場する。こういった最強チームに対する取材内容だけでも本書は一読の価値がある。
本書は、いわゆるハウツーものでも、四番打者を数多く集めて運用するようなマネジメント本でもなく、「組織内で働く人たちがどうすれば100パーセントの力を発揮できるようになるか」を論じている組織論だ。
本書は、ビジネスマンだけでなく、あらゆる組織内で生活する人たち全てに役立つ本だと思う。今いる組織(もしかしたら学校、あるいは家庭であったとしても)がもっと良くならないかな?と考えている人には、ぜひ手に取ってみて欲しい1冊である。
投稿元:
レビューを見る
チーム作りにおいて
①安全な環境
②弱さの開示
③共通の目標
が必要である。リーダーは決断するだけではなく、周りに問いかける術も持たなくてはいけない。良いチームは短い言葉でコミュニケーションをとり、グループに分かれていない。チームメイトのことを家族のように思っている。
さまざまなチームを例として書かれている。とても勉強になる一冊であった。
投稿元:
レビューを見る
大切なことは3つ。
安心できる環境であるか、
弱さの開示をする、
共通の目標があるか、
難しいことではなく、日常でも行なっている行動をより習慣化させることが大事。
エネルギー、個別化、未来志向という帰属のシグナルを送り続ける。
チームにはぎごちない瞬間も必要。
共通の価値観を持てるようさりげなく、何度も伝えていく。
投稿元:
レビューを見る
文句なし、5つ星!
ビジネスに必ず役立つ知識だけど、フレームワークなんかの理論じゃない。チームづくりのやり方でいくらでもパフォーマンスは変わってくるというコトを認識させてくれる良著です。
「最強チームをつくる方法」という副題は全くもってそのとおりなのですが、本著の内容は実際のケースに基づいていて、物語として楽しみながら読めるので、なんか勿体ないなぁという印象を受けました。
読んで驚いたのは、過去読んで素晴らしいと思った本や題材が集まっていたこと。
アダム・グラントから始まって、ピクサー、ユニオン・スクエア・カフェのダニー・マイヤー、アメリカ海軍の駆逐艦ベンフォールドの艦長マイケル・アブラショフ。私がここ数年で読んで、4つ星か5つ星をつけてきた本たちの題材がここに集結してたとは。
そして、これらの本を取りまとめて抽象化している本があったとは!
読んでみると、確かに共通する要素があった。著者のキュレーション力と体系化する力には脱帽です。
内容には敢えて触れませんが(ネタバレにもなるので)、ビジネス…と言うか、人を動かしたい、物事を進めていきたいと思った時の「車輪」には、個人的には2つの側面があると思っていて、それは「理論」と「情緒」です。
理論については割と過去のビジネス書で語りつくされてきていた感があったのですが、本著は情緒の本です。
今まで、情緒側は何だかちょっと怪しげな印象の本ばかりだったのですが、本著では著者が上手くいった要因を分析して説明していて、「なぜか」がクリアなので、安心して人に薦められます。
つい日々で試したくなる、良い勉強をさせてもらった本です。
投稿元:
レビューを見る
成功しているチームには共通するスキルがある。それは、「安全な環境」「弱さの開示」「共通の目標」、この3つに集約される。
チーム論について書かれた本は数あるが、たったの3つにポイントを絞っているところが、この本の良いところ。その分、深堀りして書かれていて、豊富な事例をもとによく理解できる。確かに読んでみて大事だなと思える内容だった。
●安全な環境
安心感、帰属意識、アイデンティティが、チームのパフォーマンスにつながる。「安全」とあるが、何も起きない環境ではなく「安全な衝突」ができる環境をつくるのが良い。
近い距離で接し、帰属シグナルを送るのがよいとあるが、コロナ禍でリモートワークが一般的になった現在では、特に帰属意識が下がりやすくなっているので、リモート化でどう帰属シグナルを出せるかは考えたい。
●弱さの開示
弱さを見せ合うことで、チーム内で助けあう気持ちが生まれる。チームが正しくない方向に向かおうとしたときには、気づいた誰かが声を上げてくれるようになる。
ただ、飛行機の事故の例や、シールズの丸太エクササイズの話が出てきたが、追い詰められた状況だと、余裕がなくなり、弱みを開示することが心理的には難しいのではないか。弱みを開示する強さ、あるいはそれまでの日ごろの関係性構築がいるなー。
●共通の目標
サッカーを楽しみたいという目的は同じだというシグナルを送れば、フーリガンも事件を起こさなくなる。ピクサーは定期的なミーティングを開くことで、チームが道を見失わないシステムをつくった。
目指すところを明確にし、それを維持することが大事だ。
投稿元:
レビューを見る
最高のチームは「カリスマ性があるリーダーを採用していること」「優秀な人を集めること」で成り立つことではないということが事例や実験結果をベースに解説されている。主に帰属意識、コミュニーケーションの大切さが読み取れるような内容です。
事例が分かりやすく、個人的にはめちゃくちゃ刺さる内容で面白かったです。
投稿元:
レビューを見る
とても評判が良かったので、前々から気になっていた本。
読んでみたら、評判通りの素晴らしい内容だった。
これまで成果の出ているチームのリーダーと言えば、
強いリーダーがチームをぐいぐい引っ張っていくという
イメージを持っている人が多いような気がするが、
実際にはそうではなく、成果の出るチームでは、
①安全な環境をつくる
②弱さを共有する
③共通の目標を持つ
が共通しているらしい。
③はどこでも言われていそうなことだけれど、
①②は意外と感じる人もいるだろう。
①はグーグルの「プロジェクト・アリストテレス」でも言われたことなので、
興味のある人も多いと思われる。
本の中では、多数の実験やインタビューなどが取り上げられており、
①~③の重要性が理解できるようになっている。
たくさん事例が載っているので、
いくつかの事例は読み手にとってとても興味深いものになることだろう。
これからの新しいチーム・組織作りの参考になる本!
投稿元:
レビューを見る
人は生きていく中で全くの1人っきりということはなく、家族にしろクラブにしろ会社組織にしろ、常に他の複数の人々とともに行動する。つまり、何らかチームとして動く。ではどんなチームが目的のために強く成功するチームとなるのか。本書はアメリカで成功しているチームを分析し、最強チームの特徴を3つにまとめている。その3つの特徴とは、
・安全な環境(仲間としての高い帰属意識)
・弱さを共有(リーダーも含めた助け合い、全員参加のチームワーク)
・共通の目標
としてある。成功しているチームの具体例で、それらの特徴が分かりやすく紹介されている。また、「創造的であるチーム」と「熟練・習熟を目指す安定したチーム」とで分けた説明も試みている。
本書で説明されている特徴は自分の経験から言ってもとても納得できた。成功しているチームの特徴はこれまで自分のモチベーションを高く保てた組織、チームの特徴とよく一致した。その逆もしかり。自分でチームを率いる場合には、本書の内容を忘れないようにしたい。
投稿元:
レビューを見る
安全な環境を作る
- 帰属のシグナルを贈り続ける.
弱さを共有する
- 助けが必要と伝える. つながり、協力関係.
共通の目標を持つ
- 習熟 or 創造性. 計測する.
投稿元:
レビューを見る
チームで働く人の必読書。
「帰属のシグナル」という概念で、人間の集団における心理のほぼ全てを説明できてしまうことが分かる。
群れで生きてきた動物としての人間、という視点が入っており、これを読むと冗談抜きで人間の見え方が変わる。