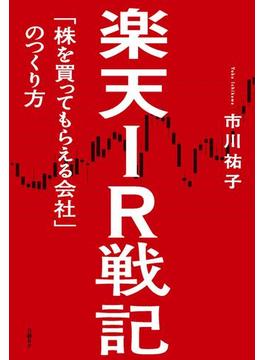- 販売開始日: 2019/06/14
- 出版社: 日経BP
- ISBN:978-4-8222-8968-3
楽天IR戦記 「株を買ってもらえる会社」のつくり方
著者 市川 祐子
「企業と投資家との対話の貴重なケーススタディ。最前線での奮闘の中に生きたヒントが満載。」 伊藤邦雄氏(一橋大学経営管理研究科特任教授) 推薦。見えない未来を信じ、変革を続...
楽天IR戦記 「株を買ってもらえる会社」のつくり方
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
「企業と投資家との対話の貴重なケーススタディ。最前線での奮闘の中に生きたヒントが満載。」 伊藤邦雄氏(一橋大学経営管理研究科特任教授) 推薦。
見えない未来を信じ、変革を続ける企業には、株式を活用した資金調達が欠かせない。「株を買ってもらう」ことこそが株式市場との対話の目的と信じ、約12年にわたり、楽天のIR(インベスター・リレーションズ)の看板を背負った実務家の記録であり、物語。
楽天初のIR専任者として著者が転職して3日目、楽天はTBS株取得を発表。取得費用の借金返済のための公募増資(株による資金調達)に巻き込まれ、調達に成功するも半年も経たずにライブドアショックで株価が半分となり、「ひとりIR」で修羅場を経験。
楽天の企業価値創造の仕組みを「楽天経済圏」と名付け、投資家との対話に取り組む著者に、金融事業に否定的な株式市場、震災、東証一部への市場変更などが待ち受ける。
前回公募から9年後、グローバル化した楽天のさらなる挑戦のため、チームで海外・国内の投資家からの資金調達を図る。
特別編として、コーポレートガバナンス・コード策定の起点となった経済産業省の企業報告ラボや、スチュワードシップ研究会でのエピソードを交えた「コーポレートガバナンス・コードと資本コスト」を収録。
「資本にコストがある」とはどのようなことか、企業の経営・財務・IRに従事する者は何を意識すべきか、ガバナンス改革の先にあるものは何か、平易な言葉で問いかける。
目次
- 第1章 TBSへの提案と財務危機
- 第2章 ひとりIR
- 第3章 暴落後、反転
- 第4章 楽天の理念とビジネスモデル
- 第5章 金融事業の毀誉褒貶
- 第6章 東日本大震災と直後の株主総会
- 第7章 一円ストックオプション導入とSR
- 第8章 東証一部上場と楽天イーグルス日本一
- 第9章 ヤフー・ショッピング無料化
- 第10章 IRの仕組み化
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む