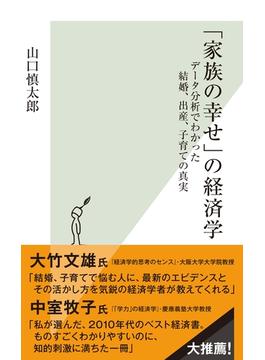統計や実験・調査結果をもとにした状況がわかる
2020/01/04 17:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:UMA1001 - この投稿者のレビュー一覧を見る
分析や予測には物足りないが、現状での状況把握には信頼できる内容
・男性の5人に1人、女性の10人に1人は生涯独身
・赤ちゃんの出生体重はその後の人生と大きく関わっている(健康、知能指数)
・働く女性の子供は低出生体重児になりやすい
・出生体重が10パーセント増えると、20歳時点でのIQは0.06高く、高校卒業率は1パーセント上がり、所得も1パーセント増える
・6歳児時点では知能テスト、先生の評価どちらを見ても、母乳育児で育ったほうが高い成績を上げている、しかし、その効果は長続きせず、16歳時点では差はなくなる
・育休3年制は無意味、1年がベスト
・給付金の充実よりも保育園の充実の方が現時点では大切
・4週間の育休取得はお父さんの所得を2パーセントほど下げている
・お父さんが育休を取得した場合、子供が16歳になった時の偏差値が1ほど上がっっている
・お父さんが育休を取ることで、夫婦で育児に関わり、結果として夫婦関係が良いものになっている
・お父さんの育休で離婚が1パーセント増えている
夫婦で過ごす時間が増え、嫌になるのが早まる、金銭的に低下、お父さんにストレス
・離婚率は1000人あたり17人程度
育休の経済学に集中すればよかった
2019/09/30 00:35
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マハラオ - この投稿者のレビュー一覧を見る
欧米に比べ日本のデータは、著者のいうとおり、「質量ともに劣っている」。その中で著者はドイツの研究をてがかりに育休3年制について政策提言を試みる。「海外の経験をそのまま当てはめるのはやはり危険」という至極まっとうな前提に立ちつつも同時に「無分別に改革をスタートさせてしまうのも危険」とのたまう。著者が前提とする予見は!)正社員を止めてはいけない、2)一歳児になれば母親の負担が軽減される、3)育休はキャリアの致命傷にならない、という当たり前の散点である。なにをいまさらという予想される指摘に対し著者の用意する回答は「論点をデータできちんと確認することは、間違いのない判断に必要」というものだ。ここからが本番。著者が経済学の理論を織り込んだ予測と称するものから引き出される結果は1)一年間の育休は母親の就業にプラス、2)育休3年制に追加的な効果なし、3)育休は3年もいらない、そして著者の結論は第3章4節の見出し「育休3年制」は無意味。一年がベストという断定である(ただしこれは編集部で付けた可能性もある。そうであっても著者がチェックしたか問われるところ)。1と2の典拠は海外の論文であるが3の育休3年不要論は著者の英文論文が典拠である。である以上典拠となる論文を解きほぐして解説するのが筋。単に「女性の出産や就業行動がどのように変化するかをコンピュータ上でシミュレートし、何が起こるか予測しました」と述べるだけでは読者を愚弄するもの。
投稿元:
レビューを見る
エビデンスベースの一般書が増えているの本当に嬉しい
母乳じゃなきゃ駄目とか迷信が老人が若者を苦しめる世の中に鉄槌を
今の日本で問われる家族の問題を優しく解きほぐしていく好著
ただ分析手法に興味を持つ身としては少しデータや手法を示してほしかったので-1点←論文読め←ごめんなさい
投稿元:
レビューを見る
最初はまあそうだろうなって内容から始まって。
マッチングアプリによって出会いの機会が広がるとかね、女性は男性に経済力を求めて、男性は女性に容姿を求める、とかね。( ˙˾˙ )チッ
以下、メモと雑感。ネタバレ含みますが、作品は楽しんでいただけると思います!
「母乳育児」に関する研究結果はとても興味深くて。結局、母乳の方がいいんじゃん、という残念な気持ちと、母乳育児がSIDSを減らしているという衝撃の事実!
ミルクで育った子どもと、母乳で育った子どもに、16歳時点での知能発達に差異が見られなかったとしても、母乳で育った子どもが、6歳時点での知能テスト・先生の評価がよいのなら、幼少期に自己肯定感をあげる一助になるかもしれない。
一方で、行動面で母乳育児の効果を認められなかったこと、知能発達の評価が長期的には有効でないという結果は、一部のお母さんを安心させる。
日本の男性の育休制度がとても素晴らしいということ。諸外国からの評価はとても高いのに、使う人がとっっっても少ないという現実。
父が育休を取ると、収入は減る。けれど、子どもが16歳時点で、育休を取らなかった父の子どもと比較すると、偏差値が1アップしている。生後1年間の親子のふれあいが、その後の長期にわたる親子関係に大きな影響を及ぼす。また、最初の、たった1ヶ月の育休で、ライフスタイルが変化して、家事と育児に使う時間が増える。
母の育休については、3年はとりすぎ。日本はちょうどいい。だから、父が育休を取って収入が多少落ちても、そこは母がフォローできるよね。
心理学社会学では、子を持つことが離婚につながりやすいと言われているけれど、経済学では夫婦関係が安定するという研究結果が出た。
どんな立場で論じるかによっても結論は違うんだ。
幼児教育の知能面に関する効果は8歳時点でほぼ消失。しかし40歳まで調査を続けると高校卒業率を上げ、就業率を上げ、所得を増やした。生保受給率、警察の逮捕率も減らす。問題行動を減らせるようになった!
それは犯罪を減らすことになるので、幼児教育をしたことで受ける利益が、本人だけでなく、社会全体の利益となる。
4大卒の母と比べて、学歴が低い(高卒未満)と、子育ての幸福度はマイナス、しつけの質もマイナス、保育園に通うことで、子育てストレスを大きくマイナスへ、幸福度をプラスへ。また、攻撃性と多動性も、大きくマイナスとなった。
個人的には、やっぱり母乳神話はほんとだったんだー、という残念な気持ち、
学歴が子育てに深く関係しているという裏付け。
幼児期に、心身の発達を満たしてあげること、それが約40年後に上記にあげたような効果をもたらすのであれば、費用対効果抜群!
医療費とか、生活保護費、収監費用の低下につながるわけだから、高齢化に伴って高齢者にかかるお金がクローズアップされがちだけど、やっぱり子どもにお金をかけないと。
保育園は、これだけ社会に寄与する存在で、それなのに、お給料が壁となって、保育園ができても保育士が集まらない。これだけ���人材を作り出す専門職であるにもかかわらず。それが、なんだかとても悔しい。
少子化なのに、待機児童がいるというこの国に、昨日からスタートした幼児教育・保育の無償化はどれほどの効果を生み出してくれるのか…
投稿元:
レビューを見る
昨今さまざまな情報が飛び交っていて何が真実か分からなくなるが、科学的に分析した情報から読み取れることは何か、ということを示してくれる本だった。日本語が明快で読みやすかった。
ただ、結局統計的な話というのは個人に当てはまるものではなく、あくまでも集団を見たときの話なので、このようなデータから冷静に判断する知識を得つつ、自分や家族の幸せは自分で選びとるしかないということが分かった。科学は解決策を示してはくれない。
投稿元:
レビューを見る
結婚、子育てについて気になる疑問を淡々とデータをもとに紹介してくれる本。
3歳まで育児に専念した方がいいのか、
粉ミルクより母乳で育てた方がいいのか、
などは子育てをしようとする母親にとってはとても気になる点。
それが、エビデンスと共に色々紹介されているのが良かった。
投稿元:
レビューを見る
結婚、出産、子育て(保育園、育休)、離婚について統計学的に分析し、何が真実で何が神話か解明した本。どの章からも読みやすく、世間で言われていることが統計的に真実かどうかを解き明かす経済学的視点に立った本。
・韓国のマッチングサイトでは、独身であることを証明するために証明書の提出が必要なものもある。
・大人ですら一度言われたくらいで行動を改められない。ましてや子どもに説明するのは大変。(それでも言葉で理解させることは大切。)
・離婚について
子どもの幸せという観点から考えても離婚の手続きを難しくすふよりは離婚が生み出す貧困の悪影響を避けるような社会の仕組みが必要。
投稿元:
レビューを見る
結婚、赤ちゃん、育休、イクメン、保育園、離婚の章立てがなされている。
新しい発見や内容と言うものは余り感じなかったが、ついつい感情論や経験則から来る逸話や話などに対して、論文などのデータを基に裏付けのある内容を示している事は自身の理解にも役立つように感じた。
離婚の章は、読む価値がある。これまで目に触れないような内容であり、新しい視点を得たような気がする。
投稿元:
レビューを見る
結婚や出産、子育てなどに関わる最新の研究結果から得られている知見を幅広く紹介してくれる本。特に子育てに関しては巷によく分からない情報がゴロゴロとしているので、そういうものに惑わされたくない人が読むといいと思う。
本書のタイトルは『「家族の幸せ」の経済学』だけど、私が感じた印象は「幸せになるための経済学」というよりは「不幸せを避けるための経済学」だということ。そして、これはけっこう大事なことだと感じる。
おそらく関心の高い人にとってはすでに知っているとか聞いたことのある情報も多いと思う。まだ子育てをしていない私でも知っていることは多くあったから。
でも多くの情報があって、特に家族や知人など近しい人からも(近しい人からこそ)情報が押し寄せる中で、毅然と自分たちなりの意思決定をするのは難しい場合もあるように思う。押し流されて「不幸せ」になってしまう人は多いのかもしれない。そういう時にこの本は強い味方になるのだと感じる。
帯にコメントを書いている中室先生の『「学力」の経済学』が出た頃から教育分野でエビデンスベースの本が増えてきたように感じててとても好ましい。エビデンスベースであるということでランダム化比較試験などの話に及ぶこともあり、政策提言などで終わるという構成の本も多いのだけど、この本はそれをやらずに個々の家族の話で締めています。著者自身の経験や感覚が語られることはあってもべき論はなるべく避けるようにしているように感じる。
何か意思決定のよすがを求めて読むと物足りないと感じる人もいるのかもしれないけど、私はこの本はこれで良いと思う。一人で抱え込まずに夫婦や家族でこの本について話し、「不幸せ」をさけられる人が増えれば良いと願いつつ。
投稿元:
レビューを見る
経済学の良心。もし私が高校生の時にこの本を読んだら、きっと経済学部を目指したと思う。
本書は結婚、出産、子育て、教育、離婚についての世界各国のさまざまな政策がどのような結果を及ぼしたのか、丁寧に明らかにする。
経済学とは、限られた資源(リソース)でいかにより多くの人をより幸せにできるか立案計画するための理論と根拠を追求する学問だ。といったような定義を読んだことがある。おそらく本書の帯に推薦文を寄せている大竹文雄さんの定義だったと思うが、まさにそんな本だった。
子供は母乳で育てる方がよいのか。
子供は3才までは母がつきっきりで面倒をみたほうがよいのか。
育休は長いほどよいのか。
本書は、豊富なデータから「そうとは限らない」という。
たくさんの国のたくさんの事例から、その調査が行われた時の状況や影響を与えそうな他の要因も考慮して、とてもとても慎重に、そう述べる。
赤ちゃんが一才までは母乳がよい影響を与えるが、長期的にはその影響は消える(ミルクと差がなくなる)。
子供が小さいうちは誰がか丁寧に面倒を見たほうがよいが、母親がよいとは限らない。母親が働けることまで含めるとプロの保育士の方がよい。
育休は一年くらいがよい。3年は長すぎてデメリットが多い(収入が減る、仕事に復帰しにくくなる、男女の役割が固定化される)。
などなど。
全ての結婚子育て中の人、考えている人、それから全ての政策立案者にお勧めしたい。
投稿元:
レビューを見る
諸外国の研究やデータが沢山紹介されていて、
結婚や子育てに関して、視野を広げる事の出来る一冊。
結婚や子育てに不安を抱えている方や、
子育てに日々取り組んでいて、
定量的な証拠が欲しい方に、
是非オススメです。
投稿元:
レビューを見る
◎目次◎
第1章――結婚の経済学
第2章――赤ちゃんの経済学
第3章――育休の経済学
第4章――イクメンの経済学
第5章――保育園の経済学
第6章――離婚の経済学
投稿元:
レビューを見る
内容のほとんどは研究の紹介だが、説明がわかりやすい
章立てが追いやすい
離婚の章がおもしろい(他の論文で読んだことなかった)
投稿元:
レビューを見る
経済学とタイトルがついてるが統計を適切に読む家族関係の諸問題の分析みたいな本だった
内容はデータに基づき的確な見解 なかには意外な見解もあり面白い
投稿元:
レビューを見る
ここでいう「家族の幸せ」とは、数多くの噂
や都市伝説めいたしきたりや行動を実行する
ことによりたどり着くことができるゴールを
表しています。
例えば「赤ちゃんは母乳で育てるべき」
「幼児教育は大切」などの、何が正解なのか
誰も分かっていないのに、何となく正論とし
て語られている習慣のことです。
これらの「噂」に対して、米国などのデータ
を駆使して極力真実に迫ろうと著者は試みま
す。
何と「男女の出会い」から「育休」「保育の
内容」まで研究対象になっており、まさしく
「家族」を学べる一冊です。