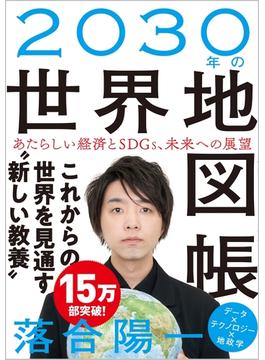「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発売日:2019/11/15
- 出版社: SBクリエイティブ
- サイズ:21cm/351p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-7973-9995-0
読割 50
紙の本
2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望
著者 落合陽一 (著)
2030年に向けてのビジョンを作るために必要なデジタル地政学の考え方とは。SDGs、GAFAM、中国、サードウェーブの世界を豊富な地図やグラフで俯瞰し、わかりやすく解説す...
2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望
2030年の世界地図帳
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
2030年に向けてのビジョンを作るために必要なデジタル地政学の考え方とは。SDGs、GAFAM、中国、サードウェーブの世界を豊富な地図やグラフで俯瞰し、わかりやすく解説する。池上彰との対談も収録。【「TRC MARC」の商品解説】
2030年の世界を見通すSDGs。これから2030年までに何が起こるのだろう。
未来を予測するためのデータには、様々なものがありますが、ひとついえるのは、これからの社会は今までとは全く違ったルールによって営まれるということ。
現在の世界はどうなっているのか、これから世界はどこに向かっていくのか。
SDGsの枠組みを借りながら、世界の問題点を掘り下げると同時に、今起こりつつある変化について語ります。
●テクノロジー×地政学でみる世界の勢力図
GAFAMによる世界支配を推進するアメリカ、一帯一路で経済圏を拡大しようとする中国、SDGsやパリ協定を通じてイニシアチブを発揮しようとするヨーロッパ、未開拓の市場で独自のイノベーションを生み出すサードウェーブ(インド・アフリカ)。多様化する世界を紐解けば、それぞれの地域に独自の戦略が根づいていることが見えてきます。ニュースをひとつとってみても、まったく違う視点で世界をとらえられるようになるはずです。
●一目で状況がわかる「地図」
全編を通じて「地図」を多用し、世界の状況が一目でわかるようにしています。
また、池上彰先生、大阪大学の安田洋祐先生、経済産業省の宇留賀敬一氏の対談も収録!【商品解説】
著者紹介
落合陽一
- 略歴
- 〈落合陽一〉1987年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。筑波大学図書館情報メディア系准教授・デジタルネイチャー推進戦略研究基盤代表。著書に「日本進化論」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
電子書籍
教えられることの多い本だった
2019/12/12 10:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いのぜい - この投稿者のレビュー一覧を見る
多面的な視点で書かれているので、参考になった。
紙の本
地図帳
2020/03/09 19:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なま - この投稿者のレビュー一覧を見る
話題になっている本だったので読んでみましたというか、読み始めたら内容が難しくて途中で諦めてしまいました。それでも興味のあるページは面白くて勉強になりました。
紙の本
世界の未来
2019/11/26 09:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
10年後の世界の状況についての一つの見方が、わかりやすく説明されていて、よかったです。世界地図が、見やすいです。
電子書籍
近未来
2022/02/22 19:38
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
それも、ほんの数年先ーです。アメリカをはじめ、台頭しつつある中国。そして、プーチン王国ともいえるロシア。これから、日本は、どうなるのか、どうすべきなのか……。
紙の本
視野が拡がる
2022/01/30 17:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とりこま - この投稿者のレビュー一覧を見る
SDGsについてよく目にするが、できた背景や世界がどのようにアプローチしているかなどデータや地政学を元に、分かりやすく解説している。
アメリカはトランプ政権で環境問題などに後ろ向きというイメージが強かったが、アメリカなりのアプローチがあることが分かった。
欧州でもアメリカでもない日本だからこそのアプローチがあると言うが、直接できること間接的にできることを見極め、一つの見方に偏らないことが重要なのかと感じた。また、空気に流され過ぎないことも重要で、それには自分でデータを調べ、自分で考えることが求められる。
紙の本
途中は少し間延びするが最後に納得
2020/01/08 23:04
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:UMA1001 - この投稿者のレビュー一覧を見る
・2035年前後には地価の大暴落の懸念、団塊世代がなくなり、子供世代が土地家屋の相続税をはらえずえ、多くの土地が売りに出されると予想される
・2000年時代はGAFAMに代表されるアメリカン・デジタルの時代、2010年代はチャイニーズ・でじたるのじだいえ、2020年代はSDGsがもたらすヨーロピアン・デジタルに時代か
・ヨーロッパ主導のルールと論理による支配