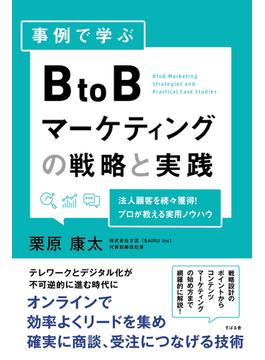投稿元:
レビューを見る
マーケティングの全体を俯瞰する本。
現状把握、顧客ヒアリングは優秀な営業であれば必ずしている事であるが、最初に手をつけるマーケターに必須の素養である事が分かった。
また、提案の階段を小さくする事もデジタルマーケティングへの落とし込みが必要な事が分かった。
優先順位として取りかかる順番としては受注に近い順番、オウンドメディアなどの構築は後回しという点は参考になった。
具体例とあるが、抽象化され過ぎていて、
イメージ想起がしにくい。
守秘義務があるので難しい部分ではあるが、具体例ではなく、一般例になっており、体感として身につくという感覚がない点が残念。
投稿元:
レビューを見る
お世話になっている会社の代表が書かれた1冊。良書。
当然ながら業務の中で聞く話が中心になっていたが、おさらいの感覚で読むことができとても勉強になった。現代のB2Bマーケティングであれば、この1冊があれば十分。手元に置いておきたい1冊。
投稿元:
レビューを見る
非常に基礎的な内容のため、これからマーケティングに取り組む人にはちょうど良いかもです。
ただケーススタディや事例が中心なので、少し他の本で勉強したことあるって人が復習がてら読むと良いでしょう。
正直Amazonの評価に少し騙された感が。。笑
各マーケティングフェースでの課題と解決策が詳しく事例的に載ってると思いましたが、もっと簡素なものでした。
投稿元:
レビューを見る
●流れ
・オンラインコンテンツの拡充/検討行動の前倒し
→ 営業担当に接触する前に57%の検討が完了。それまでにタッチポイントを築け
なければ検討の俎上にすら乗らない。
・B2Bの特徴(対B2C)
→ ・購買目的は課題解決。B2Cのような所有や体験要素は稀有。
・営業担当、という要素が基本的には経由するため「営業がカバーしやすい状態
でパスをできるか」というのが重要変数に。
・受注率は10-30%に落ち着く。単価も基本的にfixならばトップラインの最重要
変数は商談数(+ユニットエコノミクス)。
・情報の非対称性。B2Cならブロガーなり口コミが充実。B2Bは意識的に企業側
がコンテンツを創出しない限り、意思決定のハードルが高い。
==========================================================
●LTVとCAC
▶︎LTV/CAC > 3という目安。churnが3%、CAC回収期間が1年を想定か。
(参考:https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/136733
・成功する事業のタイプ(ピーター・ティール)
企業の成功には下記2つのみ。
①多額のCACを許容できる大企業・政府向けのサービス提供か、
②到達コストを劇的に抑えられるバイラルマーケティングを活用し、どの企業でも
利用するインフラ的なサービス(会計ソフトなど)を低い到達コストで実現.
--->マーケの死の谷:ACV(顧客の年額)が50-360万のビジネスはIPO到達せず.
(https://blossomstreetventures.com/2019/07/03/your-target-acv-25k/)
--->大手に250万以上 or 中小に50万以下でselfserveで提供するか.
▶︎CACは一定以下には下がらないという事実
効果的なチャネルはあれど、スケールさせる上では一定まで高騰する。
無視できないのが営業コスト。
▶︎上記の例外は下記。
①ネットワーク効果(slack,ベルフェイス)
:社内,取引先の利用者の拡大が利便性に直結。ユーザがユーザを呼ぶ。
②口コミ(識学、すごい会議)
:見込み客同士の積極的なコミュニケーション。識学は顧客の6割が紹介。
③既存顧客へのアップセル、クロスセル(Pardot,モチベーションクラウド)
:既存への拡販コストは新規獲得の1/5。
④強力なブランド(Apple, IBM , MS)
:Apple製品だから買う。ロクに調べもせずに買われる世界。
⑤他社が提供できないサービス(浜松フォトニクス)
:光電子倍増菅のシェア90%以上、のような類。
⑥第一想起、指名検索の獲得(コカコーラ・ラクスル・アスクル・SanSan)
⑦強力な販売代理店の存在(光通信、大塚商会など)
強力な営業力を持った代理店の活用。インセンティブはかかるが。
※VOCの補足できなくなる点には注意が必要。
⑧コンテンツマーケティング(インソース、WACUL)
※AIアリウストブログ(https://wacul.co.jp/pressrelease/aiw_launch/)
※インソース(自社サイトに13000ページ以上のコンテンツ、200以上のKWで
検索1位表示獲得)
▶︎LTV=業界とサービス属性でほぼ決まる��(帝国データバンク)
https://www.tdb.co.jp/trivia/index.html
▶︎LTV=①平均購買価格*②継続購買期間(or ③平均購買頻度)
①:中堅大手を対象にする、成果報酬(プロレド)、アップセル/クロスセル、
松竹梅の料金プラン(2:5:3の比率になりがち)
③:アップセル・クロスセル / CRMに注力(研修会社系)
②:オンボーディング強化、長い契約期間を用意、
中堅大手を対象にする(SMB:月次解約率3-7%、中堅:0.5-1%)
--->取引開始は困難だが一度開始すると継続性が高い.
④:業務への入り込み(switching cost)
⑤:データの蓄積(switching cost:心理的+事業インパクト)
==========================================================
●マーケティング設計
▶︎CVポイント設計
・施策/ファネル間の階段を滑らかにする/高ハードル(高単価)→ハードルを下げる
※無料トライアル、の前に資料請求のCTAを設置。社内稟議に対応。
※コンテンツ配信なら「更なるお役立ち情報の一覧資料、より詳細の事例を聞ける
セミナー、が正しいCTA。いきなり問い合わせしたい人はいない。
▶︎改善対策
1)リード数不足:CVに近いところからテコ入れ。
・認知 ② サイト訪問 ① CV ③ 商談 ④ 受注 ⑤ 継続利用
・バケツの穴を塞ぐ。LPのCVR:2%(min.1%以上)
・チャネル拡大は顕在化層→→潜在層の順番。
・受注./失注分析からTGT拡張を検討(※刈り取り済なら)
2)競合の参入によるCPA高騰・受注率低下
・競合が購買プロセスの前半(認知・理解フェーズ)に注力し、第一想起を
獲得している場合。
---> hot leadだとしても"当て馬"が多く受注率が上がらない
---> 特定seg(業種・業界)でいいので独占を目指す。
3)コンテンツマーケへの着手:受注に近いところからテコ入れ。
・認知 ⑤ サイト訪問 ④ CV ③ 商談 ② 受注 ① 継続利用
②:ROI説明、他社実績、競合他社比較、シェアNo.1など第三者評価、
自社役員などの経営ボード紹介、製品開発技術者紹介など。
③:最新の導入事例、課題解決事例やcase study、自社の専門性を伝える
ノウハウ記事、イベントセミナーの登壇実績、寄稿実績
--->当社と商談したい、話を聞きたいと思わせることが狙い。
④:サービス詳細、特徴、料金体系、導入事例、導入まで流れ、DLコンテンツ
--->CTA最適化が肝。
潜在層 (メルマガ登録、SNSフォロー、ノウハウ系セミナー申し込み)
準顕在層(事例系セミナー申込、ノウハウ資料DL、事例集DL)
顕在層 (資料請求、料金表・事例集DL)
明確層 (お問い合わせ、見積り依頼、製品カタログ請求)
==========================================================
●参考リンク
①The Digital Evolution in B2B marketing
file:///Users/kojiisaac.kamijo/Downloads/ceb-mktg-thinkb2b-presentation-150802124838-lva1-app6891.pdf
②B2Bサイト構築180のチェックリスト
https://sairu.co.jp/doernote/0170
③競合出稿状況確認
ahrefs:https://ahrefs.jp/
keywordmap��https://keywordmap.jp/
投稿元:
レビューを見る
マーケティングの前にLTVをきちんと考えましょう。
次にマーケティングはCVポイントを階層分けて用意しましょう。
これが型です。
投稿元:
レビューを見る
BtoBマーケの定石が学べます。
網羅的かつ顧客フェーズ別に施策の特性を紹介しているので、どのフェーズにどの施策を展開することが最善か考える頭を手に入れられます。
もっとも印象に残ったのは「上から下へ」=獲得確度の高い施策から実施することを提唱していることです。
投稿元:
レビューを見る
B to B企業向けのマーケティングの基礎的なナレッジが書かれている。本書は前半部分でマーケを構造的に解説し、効率よくかつ温度感を高めるオペレーションを紹介し、後半では実際のケーススタディを通して実践的な解決策を示している。他社のナレッジがよくわかる上に、実際の具体例も充実していて初心者でもよく理解できる著書。
投稿元:
レビューを見る
内容が薄過ぎる。。。
20分くらいで読み終わってしまった。
Amazonのレビュースコアが高かったのでポチってしまったが、超初心者向けの本。
投稿元:
レビューを見る
まず、マーケティング初心者(今はセールスしてます)のために用語の索引を巻末に載せて欲しかった。馴染みのない横文字の初見のオンパレードは辛い(笑)
あと、事例の紹介が主に無形商材(ソフトウェア)だったので、有形商材も当てはまるのかな、と少し疑問に思いました。
とは言え、BtoBマーケティングの基礎は抑えられていると思うので、読んでおいて損はないのかなと。マーケティング(上流)がやるべきことは分かった。新規リードを獲得し、そこから受注に至るまでの仕組みを構築すること。タイミングよく営業に顧客を渡す。
一方で営業の立場からすると、そこで受け渡された顧客に対するアクションの記載が欠如しているように感じた。仕組みがうまく構築できたら、あとは並のセールスでも売れるのかな?受注率は10-30%程度に落ち着くと言っていた。だからリード数を増やそうと。
マーケティングがうまくやってくれればセールスは普通でいいのか知りたい。
マーケティングの仕組み×SPINセリングの組み合わせが良さそうだけどなぁ。
投稿元:
レビューを見る
事例がさまざまあり、自社のケースも含まれたので、これを元に時間をかけても認知度を高めてゆける施策を提案してゆこう。 質より量なんですが、質を上司に認めてもらうプロセスも量と結果を出すしか方法はない!
投稿元:
レビューを見る
事例もセットで書いてあり体系的で分かりやすかった。
BtoBの領域では、顧客との情報の非対称性や、意思決定者が複数いて複雑なフローがあることなどを踏まえて、下記の意識が大事だと思った。
■リード獲得→受注までのフローの綿密な設計
→いきなり商談化することは難しいことを理解して、リードのフェーズを進めていくための施策考案
■オウンドメディア等で発信数を増やして顧客の信頼や安心を醸成するコンテンツの資産構築
→高額の意思決定において、リードとなる顧客はかなりの事前のリサーチをしている。その際に検討となる材料と安心を与える情報をしっかりと発信していくこと。
■顧客解像度を高めるためのヒアリングや競合他社分析。
→フロー設計において顧客に選ばれる理由や顧客の検討フローやタッチポイントを事実に基づいて仮説立てること。そして競合が今どのようなマーケティングフローでやっているのかをしっかりリサーチすること。大前提の3C分析は重要。
投稿元:
レビューを見る
これまで読んできたB2Bマーケ系、コンテンツマーケ系、マーケティング・オートメーション系、ウェブ・マーケ系などを読んでて「自己啓発系」に近い印象を持ってた。つまりどれも正論で、”まぁ、それできれば確かに成功するよねぇ~。1~2%くらいの人はねぇ~”というヒトゴト感というか、内容と生身の自分との距離を縮められる気がしてこなかった。
その感覚が本書のあとがきにドンピシャな例え話として記されていた。
ーーマラソン世界記録を見ると、人類はこの100年で1時間も短縮できた
という世界観。これに興奮できる人は読むべし、そして走り出せば良い。
投稿元:
レビューを見る
仕事で必要になったものの、この領域のノウハウがほぼ0なので読みました。
とてもわかりやすく、実践しやすい内容でやる気が出ました!
======|
・web上に営業を補完するコンテンツを事前に公開しておくことでリードタイムを短縮する
・コンテンツは「不要」「不急」「不信」「不敵」をそれぞれ解消できるコンテンツ
・売れるロジックの構成要素
問題提起
原因の深掘り
解決策の方向と結果
解決策としての商品紹介
信頼
安心
行動の後押し
・受注までの商談ストーリーのより入念な設計
・pcモバイルでもみやすい資料
・受注率は20〜30%に落ち着くことが多い
・ユニットエコノミクス:LTV÷CAC
・LTVが高ければ積極的なマーケティング投資ができる
・saasの死の谷:上場時のACV(顧客当たりの年間契約額)が50〜360万円の間に会社が存在しなかった
・上場できる規模までビジネスを成長させようと思ったら年間契約金額50万円以下でセルフサーブに近いサービスを提供するか、中堅大手企業向けに年間契約金額250万円以上のサービスを提供するかの二択しかない
・SMB(small and medium Business)、つまり中小企業向けに商品を開発した瞬間にビジネスのサイズが限定され、上場できる規模にはならない
投稿元:
レビューを見る
勉強になった!
・マーケティングで顧客とのコミュニケーションの質を大きく変えられるチャンスが増えている
・テレワークでデジタル化加速
・従来より多めのリード獲得、商談以外でオンラインセミナーやオンライン相談会に注力
・コンテンツマーケティングを充実させる(受注率をあげる)
・前半が認知と理解に、後半が情報収集や比較検討フェーズ
・ターゲットの属性値は?
どのような属性の企業に売れている?
売れてない?
売れたとしてもどれくらいの規模か?
製品に満足してくれているか?
★売れるロジック
問題提起
原因の深掘り
解決策の方向と結果→どんな課題を解決できる商品.ベネフィット
解決策としての商品紹介→料金.サービス.導入までの流れ.根拠.特長
信頼→事例
安心→FAQ
行動の後押し→資料請求、お問い合わせ、導入相談etc
投稿元:
レビューを見る
マーケティングを知らないので正直あまり内容が頭に入らなかった。
マーケティングに最も必要な事は
・ターゲットを明確に絞り
・その解像度を上げ
・データを分析して取り組むべき課題を明確にし
・それを高速PD CAを回していく
と言うことになるだろうか。
私はよくターゲットを忘れてしまう、もしくはターゲットが曖昧で仕事でつまずくことがある。
まずはターゲット、、そしてそのターゲットは何を困っているのか、何の課題を解消する必要があるのか、そしてその実現手段の良し悪しを判断する情報をしっかり取りに行きたいと改めて思った。
====
栗原康太(くりはら こうた)
株式会社才流 代表取締役社長
1988年生まれ、東京大学文学部行動文化学科社会心理学専修課程卒業
====
flier要約
https://www.flierinc.com/summary/2970