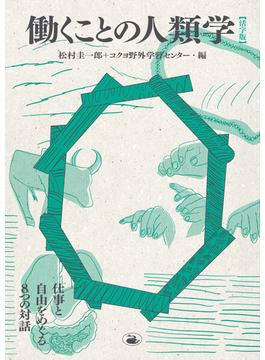「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発売日:2021/06/28
- 出版社: 黒鳥社
- サイズ:24cm/301p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-9911260-6-2
紙の本
働くことの人類学 活字版 仕事と自由をめぐる8つの対話
7人の文化人類学者がそれぞれのフィールドで体験した様々な「働き方」とは。仕事と自由をめぐる8つの対話を収録。ポッドキャスト番組で公開されたエピソードと、2020年11月開...
働くことの人類学 活字版 仕事と自由をめぐる8つの対話
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
7人の文化人類学者がそれぞれのフィールドで体験した様々な「働き方」とは。仕事と自由をめぐる8つの対話を収録。ポッドキャスト番組で公開されたエピソードと、2020年11月開催のイベントの内容を基に書籍化。【「TRC MARC」の商品解説】
文化人類学者が、それぞれのフィールドで体験した
知られざる場所の知られざる人びとの「働き方」。
それは、わたしたちが知っている「働き方」となんて違っているのだろう。
逆に、わたしたちはなんて不自由な「働き方」をしているのだろう。
狩猟採集民、牧畜民、貝の貨幣を使う人びと、
アフリカの貿易商、世界を流浪する民族、そしてロボット........が教えてくれる、
目からウロコな「仕事」論。
わたしたちの偏狭な〈仕事観・経済観・人生観〉を
鮮やかに裏切り、軽やかに解きほぐす、笑いと勇気の対話集。
ゲスト:柴崎友香/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理 /久保明教【商品解説】
目次
- ◼️巻頭対談
- ありえたかもしれない世界について
- 柴崎友香 + 松村圭一郎
- 【第1部|働くことの人類学】
- 貝殻の貨幣〈タブ〉の謎 深田淳太郎
- ひとつのことをするやつら 丸山淳子
- 胃にあるものをすべて 佐川徹
- ずる賢さは価値である 小川さやか
- 逃げろ、自由であるために 中川理
収録作品一覧
| ありえたかもしれない世界について | 柴崎友香 述 | 5−32 |
|---|---|---|
| 貝殻の貨幣〈タブ〉の謎 | 深田淳太郎 述 | 33−66 |
| ひとつのことをするやつら | 丸山淳子 述 | 67−100 |
著者紹介
松村 圭一郎
- 略歴
- 〈松村圭一郎〉文化人類学者。岡山大学文学部准教授。著書に「所有と分配の人類学」「うしろめたさの人類学」「文化人類学」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
文化人類学っておもしろい
2021/07/26 16:55
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:dsukesan - この投稿者のレビュー一覧を見る
ポッドキャストを元にした対談集なので、とても読み易いけど、内容は濃くて面白い!
文化人類学の物の見方も概要が分かり、かつ仕事や人間に対する見方を崩してくれる良書。これだけ、枠組みが違う世界があるということを知れて、ホッとするとともに嬉しさが込み上げてくる。文化人類学って、固定観念や規範を打ち破り、豊穣な世界を知り享受して、自分も楽になれる、新たな価値創造にも寄与する知的活動なのかもと思った。言葉が合っているかが分からないけれども、反骨とアナキズムに繋がるフラットな視座と思考に繋がるのかもしれない。そうして揺れながら見る見方の先に地域通貨やら、コミュニティやら、社会保障、セイフティネットのデザインといった社会のあり方、生き方、サステナビリティにつながる話も出て来るから面白い。
本当、ニマニマの止まらぬ読書体験。それは、自分の社会にある規範だけが絶対じゃ無いというところに、自由と笑があるアホになれるゆとりを感じられて安心を感じたからだと思う。
其れにしても、自分はこうした多様性の話が好きだと言うのに、他方で武士道とかそういうものも大好きでこだわっていて、ともすると他人に押し付けがちな自分とは何なのだろうと、大いに自己矛盾を感じたりもした。
続編もポッドキャストで企画されている様なので、聞いてみつつ、続刊が出たら購入したい。
以下、この本を読んで面白いと思った事柄をメモする。
・不確実な社会、環境、人間観に対して、自主自律しつつ繋がる人間関係が気持ち良い。『胃が違う』として、相手が自分の思い通りにならないことを仕方ないと受け入れつつ、関係は切れないという関係性は理想的。
・現代資本主義経済下での専門性の特化に対する『一つのことをする奴ら』という揶揄には、自分にも刺さり面白い。
・ルールを決めて、皆んなで守るのではなく、裏切られることも含めて都度判断していくバイタリティ。
・ルールに縛られることが少なさそうな社会を構成しているブッシュマンの自然資源コモンズの管理は、どの様にサステナブルなのか、調べてみたい。マタギとか、ネイティブ・アメリカンの様な狩における信仰などの形での保全ルールは無いのか?
・価値観や規範を他者と比較して、相対化することが文化人類学の醍醐味の一つと知る。この相対化というのは、南直哉の本で書かれていた、視野狭窄を避ける言う仏道の効用にも繋がると思った。
・確実性を前提とすると、努力が一貫して積み上がる右肩上がりの成長モデルが出来上がり、アカウンタビリティーと一貫性が重要視されて、それが保たれずに脱落すると死んでしまうというのは過酷で、日本社会にはそうした過酷さがあるということ。
・文化人類学の手法 エスノグラフィとデザイン思考が相性が良く、ビジネスや行政でも使えるとのこと。不確実な中で手探りでプロジェクトを進める手法として紹介されており、是非身につけたい。