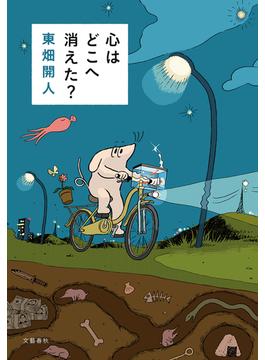1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ネコ - この投稿者のレビュー一覧を見る
人の心を読むことはできない、たとえ自分自身でさえも自分の心を知ることは難しい。人に語ることで、姿を現す心に気づいた時、感情が湧き上がる。そんな気持ちで読み進んでしまった。
投稿元:
レビューを見る
一つ一つは読みやすいエッセイなのだけれど、全体を通して見た時、カウンセリングとはこういうものか、と感じることができた。
というのは、自分が受けているカウンセリングに照らし合わせたから思う感想。
カウンセリングにおけるクライエントとして、自分の中では先が見えない闇の中で彷徨っているイメージだけど、おそらくカウンセラーからはこう見えていて、こういう気持ちでこういう反応をしてくれていたのか、と納得できる箇所が多くあった。
「心が一つ存在するために、心は必ず二ついる。」と本文中にあるが、本当にその通りで、もう一つの心が感じ、受け止めることで初めて心の形がわかる。そのもう一つの心役は多くの場合他者となると思うが、相手も人間なので心の形を教えてくれるだけでは済まず、傷つけたり変化させようとしたりすることも多々ある。そこを、純粋に心の形だけを教えてくれる、本人自身の変化を見つけてくれるのが、カウンセラーなのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
【あなたは心を見つけ出す。】今ほど心が蔑ろにされている時代はない。それはなぜかを解き明かし、心の在り処を探る。心を取り戻すための小さな物語が詰まった一冊
投稿元:
レビューを見る
心ってなに?どこにあるの?
それはぐにゃぐにゃで,
知識やなんやらで捉えられるものじゃない。
けど,それについて考えることはできる。
『心を見ることができるのは心だけだ』
ーーー
(かなり抜粋)
P90
「見られる」はふしぎだ。それは見張られていることでもあり,見守られていることでもある。
私たちは普段,自分の悪いところを隠して生きている...それだけじゃない。良いところも隠して生きている...そして,自分でもその存在を忘れてしまう。
それがあるとき,発見される。よく見てくれている人には,見えるのだ…そして,「見えている」と伝えられると,自分でも実感できる。
「見てくれている」これが貴重なのだ。それは幼い頃には比較的簡単に手に入ったけど,大人になった今ではめったに手に入らないものだ...もし,他者のいいところを偶然見かけてしまったら,率直に伝えると良い。それは幸福な瞬間なのだ。
投稿元:
レビューを見る
以前読んだデイケア本が面白すぎてびっくりし、こちらも手に取りました。臨床経験や自身の体験から考えたことを紹介されている中、
「根源的なことを問い続ける姿勢」が今とてもしっくりしました。
学問ではなく仕事での支援のことだけれど、長く続けていると「そもそもどうして」と立ち止まり振り返ることが減ってしまいよくないな、と感じていた折でもあり、意識的に考える機会を持ちたいと思いました。
投稿元:
レビューを見る
2021/09/09リクエスト 2
P86
孤独で先行きが見えず、方向を喪失している。
コロナがいつ終息するか分からないから苦しい。
それでも待つこと。無理に時間を動かすのではなく、時間の方が動くのを待つこと。なんだかんだで、それがメンタルヘルスの奥義だったではないか。
P110
物語は傷つきを核として産まれてくる。日々のカウンセリングもそうだ。クライエントが語るのは物語未満のお話だ。それはまだ生傷であり、痛みがあるから物語にはなっていない。核だけがむき出しになってきれぎれの話が散乱している。それを何度も語り直す。その時、生傷はかさぶたになり、薄い皮膚に覆われるようになる。物語るとは、傷を柔らかい皮膚で包み込んでいく営みだ。だから物語とは基本的に傷跡なのである。
P143
世の中にはお金で解決できる不幸がたくさんある。
と、同時に金で済まないことも多すぎる。金で済むことは楽やなぁ。本当にその通りである。
過去は変えられないし、失われたものは戻ってこない。だからお金でなく時間を使う。落ち込み、悲しみ、追悼する長い時間が、痛ましい過去を「私という歴史」の一部へと変えてくれる(こともある)
この著者の本は初読みだと思う。
読み始めてすぐ、文章上手い人だなあと思った。
ぐんぐんこちらに寄ってきて、引き込まれる。
そういう意味では、臨床心理士のイメージをいい意味で崩された。
以前、臨床心理士にカウンセリングに5〜6年かかっていた。
P222
終えると決めてから、時間をかける。終わりに向かっていく時間に現れる孤独を話し合うため。孤独はつながりによって解消されるだけが出口ではない。孤独であることを理解されることは、その孤独の形を少しだけ変えてくれる。孤独は持ちこたえることができ、味わうことができるものになる。人は必ず死ぬし連載も終わる。だからこそ生きているうちにたくさん話をした方がいい。それが良き終わりのために必要なことだと思うのだ。
ここを読んで衝撃を受けた。
カウンセリングにあんなに通ったのに私は何も考え方を変えることができなかった。そして消化不良だけが残った。
味方だと思っていたカウンセラーが突然辞めること、それを受け入れることができないまま終わってしまったから。
終わりに向けて、うまく出口に誘導されなかったような感じ。
身内を失い、血縁者とうまくいかず、さらにいろいろあり、今こそカウンセリングをずっと受けたいと思っていた。
この本は、まさに求めていた本だった。
たまたまブクログで知り、読んだが、本当にいい出会いの本になった。
大切に覚えておかないといけないこと、考え方を寄せていきたい部分がたくさんあった。
この著者の本を、他も読もうと思う。
どなたにも、おすすめです。
投稿元:
レビューを見る
東畑さんの本は、「居るのはつらいよ」「なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない」に引き続き3冊目です。
個人的には「なんでも見つかる夜に~」が好きで、本書は特にめちゃくちゃツボにハマるところがなく、薄い印象でした。雑誌連載をまとめた一冊だからなのか、著者が言うようにネタに困っていたからなのかは定かではありません。
東畑さんの本は面白いのですが、私が求めていた内容は「カウンセラーが臨床現場で考えた、こころについて
の洞察」みたいな、もっと深く潜り込むようなものだったので、本書のライトで日常と隣り合わせな感じは違うなと感じてしまいました。ところどころにエッセンス的に「ささる言葉」はあるけれど、バジーさんと同じく、弱いというか……。
賛否あるようなので、気になる方は書店でパラパラ内容を見てみて、「面白そうだな」と思えるのであれば、という感じです。
投稿元:
レビューを見る
令和版河合隼雄のような雰囲気。まえがきにあったようにかつて(90年代)は、河合隼雄をはじめとする心理学者の本が溢れ、事件が起きれば「心の闇」が語られていた。でも今は「心の闇」より「社会の歪み」。心理的な問題が起きていても、カウンセリングよりも、生活費の支給や労働環境を変えるなどの社会的経済的なケアが必要との認識に、社会が変わってきた。大人になったからわかる。確かにお金と生活基盤は超重要。でも、そんななかの、それでも、心を探して、心に寄り添い続ける著者のエッセイ集だ。時々軽妙すぎて読むのがしんどかった。
投稿元:
レビューを見る
心理学者のいろいろなカウンセリングのお話が聞けて良かったです。読んでいておもしろくもありながらいろいろ考えることができました。
投稿元:
レビューを見る
すごく心に沁みた…。
心は物語を求めている。
人の物語で癒される自分を発見。
筆者のカウンセリング受けたくなる。そして続編を期待したい。
投稿元:
レビューを見る
この本に載っている、1人ひとりの様々なストーリー(環境や状況)は、それぞれシリアスではある。
が、著者の巧妙でユーモアセンスある文章でクスっと笑わせてくれる。
なんだか、臨床心理士という人を身近に感じさせてくれた。(自分の中ではお堅いイメージだった)
話すこと・聞くことを仕事としているからなのか、内容は読みやすくて入りやすく、そして面白い。
堅苦しくないのも本書の魅力。
※2020年5月~2021年4月にかけて、週刊文春で連載した「心はつらいよ」をまとめたものとの事。
投稿元:
レビューを見る
色んな人の心を感じた時間でした。
そして、私の心も。
この本を読みながら、過去現在未来の私に想いを馳せました。
投稿元:
レビューを見る
週刊文春に連載されていたときもときどき読んで楽しんでいたので、こうしてまとめて読めてうれしい。連載開始がちょうどコロナの感染拡大とかぶっていて、それが週刊連載という形で瓶詰めのように保存されているのも貴重だし、そのなかから東畑さんが、パンデミックという大きな物語に吹き飛ばされた小さな物語=心を見つけようと意識したという序文も示唆に富む。そしてもちろん、河合隼雄に象徴される「心の時代」が、コロナ以前に終わりを告げていたという洞察も。そうか。「物は豊かになったが心はどうか」と河合さんは問うていたのに、現代は、物も豊かでなくリスクだらけ。だから心をどうこうするよりもまずまともに暮らせる環境をととのえることが先決、というふうにならざるを得ないものね。
各エントリでは「YouTube、安全なカプセル」が、前振りから事例(守秘義務があるから事例は基本的に数々の例をシャッフルしてつぎはぎしたものらしいけど)、考察、そしてちょっと自虐まじりのオチまでの流れが完ぺきですごく好き(笑)
そして何よりも「中学受験の神様」(大学院の教授のひと言が深い!)から「ピンク色の森へ」へ至る中学受験シリーズがすごくいい。児童文学みたい。危うくて紙一重で運がよかったという述懐もそのとおりだったんだと思う。そして児童文学にもそういう、紙一重の体験がたくさん描かれているんじゃないかと。それこそ河合隼雄さんが激賞していた『思い出のマーニー』だってそうだし。
投稿元:
レビューを見る
“不完全さを許せないと、私たちは人と一緒に居られなくなってしまう。”(p.105)
“「わかってくれない」は私たちの人生のデフォルトだと思うのだ。”(p.137)
“たとえば子どもが仮病を訴えているなら、エビデンスの提供を求めるのではなく、脚本に沿ってケア役を演じてあげる。心配してあげ、休養を取らせてあげる。こういうことだ。目には目を、演技には演技を。仮病を癒すのは、仮治療なのである。”(p.162)
投稿元:
レビューを見る
本当の自分とはなにか?
生きる意味とは何か?
私とは何か?
という問いには魅力があって人々は外界とはまた別の価値を内面に探し求めた。なにより臨床心理士は人気があった。
おおきすぎる問題は心をかき消す。それは抗えしがたい。
政府のことや、グローバル資本のことではなかった。もちろん、そういう大きすぎる物語も彼らの小さすぎる物語の遠景にはあった。だけど結局のところクライアントたちが語り続けたのは身の回りの小さなことであった。
自分で自分を責めることを超自我という。
多くの場合、現実は超自我よりマイルドなのだ同僚と顔をあわせない日々が続くとだんだん超自我の声が強くなってくる。心の中の上司が投影されるから学校や職場に行くのが億劫になるのはそのせいだ。
あいつが怖い、あいつがむかつくと考えぐるぐるかんがえるうちに心の中のあいつが肥大化していく。戦争を終らせるには直接会うしかない。
心の回復には時間が止まるフェイズがある。もちろんその前に環境を整えなければならない。経済的支援が必要な人危険な環境から離れるために一人暮らしが必要な人もいる。
そうやって暴風が収まると凪の時間が訪れる。そのとき私たちはふと我に返りぽつんと一人になるするとようやく、内省が可能になる。落ち着いて自分を考えることができるのだ。
必要なのは自分でなんとかすることではなく、人になんとかしてもらうことだ。不器用の頼れない娘と、不器用にケアすることしかできない母の間には何度も摩擦ができた。だけど摩擦とは二人が一緒にいられるように、互いの形を研磨することである。
金で済むことは金で済ませる。これはこれで人生の深淵を感じさせる名言
他者にもましてコントロール不能なのが自分の心、心は自分の所有物であるはずなのになかなか自分で止めることが難しい。こういうときは外在化と呼ばれる心理学の技法を使ってトリセツを作るとよい。
自分自身がまだちゃんと人生をいきていない。