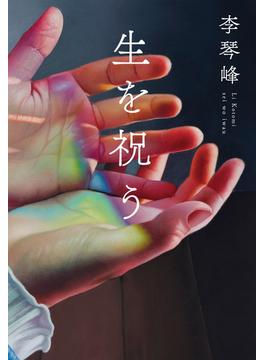自己決定もここまで来ると……。
2022/03/28 14:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
未来の日本、様々な科学技術の発達で、出生前に胎児に産まれてくるか否かを問う合意出生制度がある。出生の諾否を問われて産まれたとされる主人公は辛いことや失敗に直面しても、この世に産まれ出ずるのを選んだのは自分だからと自信を持っている。同性の配偶者との間に生殖技術で妊娠して、順調に月数を重ねている。
異性の配偶者を持つ同僚、制度ができる前に諾否を問われず産まれた姉の、それぞれの経験、そして自分のお腹にいる子どもの出生合意を調べる日が近付く。
命とは何か、自己決定、自己責任は出生時まで言えるのか?そんな問い掛けがある。
投稿元:
レビューを見る
残り3ページでまさかキャンセルを宣言するとは思わなかった。
胎児に生存難易度を伝えて「生まれますか?」と確認を取る。それを胎児は認識できるのか…?
いくら自分の意思で生まれたからといっても、人生の困難を丸ごと受容できるようになるわけではないんじゃないか?
先天的な障碍をもつ人は、これは自分が選んだことなんだ、自分が望んだ生なんだと「自分が選んだ」事実自体にも苦しまないかな。
どうしてもミスマッチは避けられないと思う。
それとも自分の意思で生まれていたら、主人公の言うように「それでもどんな挫折も耐えてやろうという気持ちになれたのは、この人生は他でもない、自分が選んだものだからだ。(p18)」というような心持ちになるのだろうか。
結果的にどうしても弱者が生まれにくくなるから、優生寄りの世の中に近づいていきそう。
子の「なんで産んだんだ」に対するパーフェクトアンサーになりうる法案。「お前が望んだからだ」と。
この世でよく言う「産んでくれて、ありがとう」は結果論なんだろうな。
なんだか作風が分かってきた気がする。
投稿元:
レビューを見る
自動運転や配送ロボット、そして胎内にいる胎児に意思を確認できるようになった近未来。
技術的にはわからないけれど死ぬ権利を唱えられてる今、生まれる権利が叫ばれてもおかしくはないなと思いました。
誰もが信じるよすがを欲していて罪悪感を無くしたい。
技術的にそれが叶えられても疑問を感じるってなんだか考えさせられました。
投稿元:
レビューを見る
割と淡々としていて、展開が読みやすい故に、登場人物達の交錯する想いが引き立てられているように感じた。
自分で選択できたこと、出来なかったこと引っくるめて引き受けるという態度が、生きるということ、(ある意味)大人のかたちの一つなのかなと思う。
投稿元:
レビューを見る
子どもは親を選べないということを「親ガチャ」というらしい。とすればこの小説は「産ガチャ」とでも呼ぶのか。
胎児が予定日の二週間前に自分で「産まれるかどうか決める」世界。
「アグリー」か「リジェクト」か。親は子どもの意思を受け入れなければならない、つまり子どもが「リジェクト」を選べばそれは「キャンセル」つまり堕胎するしかない。子どもの同意無くして勝手に出産することは違法であり将来子どもから訴えられることもある…って…これは、9か月以上の時間を共に生きてきた母親に突きつけられる恐怖の「拒否」である。耐えられるのか。自分なら…たとえそれが「法律」で定められたことだとしても自分の身体の中で成長し日々大きくなるさまを感じてきた「分身」による全否定に耐えられる気がしない。
同性間でも自分たちの遺伝子を持つ子どもを産むことのできる世界。女同士だから分かり合えているという錯誤。
ここから二人はどう生きるのか。
産まれる者の意思とは…。
誰でも時間と共に考えが変わることはある。生まれる前に自分の生を拒否した者が何十年後かに「生まれてきてよかった」と思うかもしれない。その逆もあるだろう。そういう機会を奪うこの世界。
じわじわとじっとりと根源的な恐怖がしみだす。「生を祝う」のか「生を呪う」のか。
投稿元:
レビューを見る
胎児の合意がない出産を禁止する「合意出生制度」が法制化された、近未来の日本の話。
子どもたちは「自ら選んで生まれてきた」事実が支えとなって、人生を受け入れることができる。
親たちは、自分たちのエゴで産んだという罪悪感から解放され、子どもの出生を晴々しく祝福することが叶う。
長らく続いてきた生の強制という重大な人権侵害は解消され、人類はついに生死に関する自己決定権を完全に手に入れた。万歳!
という社会が舞台だが。
とっくに成人してる自分でも、生と死を提示されて「さあ今この瞬間にどちらか選べ」なんて難しい。
恐怖と戸惑いに支配されて、やけっぱちになりそう。
自己決定権は確かに大事だ。個人の意思が尊重される世の中であるべきだ。
けれどそんな重い判断は、少なくとも私の手には負えない。
なにか大きなものに委ねている、という他力本願な気持ちでいるからこそ、今まで生き延びてこれた気もする。
そもそも、生と死なんて天秤にかけ得る?
チキンかビーフを選ぶのとはワケがちがうのに。
なんて疑念を抱くのは、私が令和の日本に生きてるから。
この物語の時代に生まれていたら、絶対的な正しさを感じていたと思う。
倫理観なんてそんなもの。
物語のなかでは、生まれることを拒否した子どもの母親たちが、悲しさや絶望や、言葉では表しきれない気持ちを慰め合うために密かに集い、だんだんと過激化していく。
正しさに口を塞がれた人々の痛みが迫ってきて、読んでて辛かった。
自分のエゴかもしれない。でも会いたかった。
我が子の意思を尊重したい。でもこの気持ちのやり場はどこ?
間違ってるけど、許されざることだけど、産みたかった。
制度側から見れば、この女性たちは「身勝手」「親失格」「子どもを所有物だと思ってる」愚かな存在だ。
当事者の心情との乖離がひどい。
正しい制度の暴力性を感じる。
この制度下だったら自分は生まれてなかったかも。
そう思ったときにゾッとしたのは、今の生を肯定できてるからだろうか。
意思によらず適当に流れ着く人生もあるけどどうだい、制度よ。
それも私の場合でしかないけれど。
投稿元:
レビューを見る
2021/12/11リクエスト 2
合意出生制度
出生強制罪の法理 民事裁判が起こされた話として、強制出生された子の安楽死費用を負担しなければならないこともある。
読んでいて、だんだん嫌な気持ちになったのは自分だけではないと思う。近未来が、こうなっていたら、子を産み育てることは、今の赤ちゃんができて嬉しい、元気に産まれますように、という大方の妊婦が思う感情はどこへ行くのか。
産まれた子が、辛い思いをしないように、自分を差し置いても大切に大切に、周りの嫌なもの危ないものからブロックする、あの気持ちはどうなるんだろう。自ら望んで生まれたのだから、自己責任、そんな放ったらかしの感じを受けてしまう。
そして最後にあの流れから、ラストは、全く納得できるものでは無かった。
あと、あの年齢で、自分のことをお姉ちゃん、と言うことに、とても違和感を抱いた。
自分としては、好きになれない作品でした。
投稿元:
レビューを見る
2021年12月
素晴らしかった。
作者の描く近未来は、技術の進歩と倫理観の進歩とがいびつなところが、現代社会のリアルな将来に見える。
現代社会でも出生前診断等はあるがそれは「育てやすさ」を考える親や社会という本人以外の都合だろうとある意味わりとさっぱり切り捨てられるかもしれない。でももし本人が生まれる前に決めることができるのだとしたらどうだろうか。生きづらさなんて誰が決めるのか。障がいや親の経済力の無さが「生まれてこないほうがまし」であるとしたらそれら本人じゃなくて社会の問題だろうと思う。
淡々とした語りのトーンがとてもいい。
投稿元:
レビューを見る
面白いか、良い作品かというよりも、とても好みの作品でした。『彼岸花が咲く島』も好みに合っていたので李琴峰さんの他の作品も読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
驚き、考え、納得したと、納得せざるを得ない…と言ったほうが良いのか。
近未来、胎児の同意が得なければ出産できないという
「合意出生制度」が法制化された。
出生を拒んだ胎児を出産した場合は、「出生強制」の罪に問われる。
衝撃的ではあるが、自身がその立場になったときどうするのか?
それ以前にこどもが欲しいという段階ですべてクリアにならないのか?
とかいろいろなことを思ってしまった。
投稿元:
レビューを見る
川上未映子の夏物語や、芥川龍之介の河童と通じる主題。社会・経済・健康・親子関係面などから算出した生存難易度が胎児に伝えられ、胎児がこの世に生まれることをリジェクトした場合には妊娠をキャンセルしなければならない出生合意制度が設けられた近未来の日本。難易度の1〜10の数値しか伝えられない中で胎児に選択を迫るのは、本当の自由意志の尊重とは言えないとか、そもそもこの世界のことを知らず、なぜその難易度なのかも分からない胎児は正しく判断できないとか、これは政府による思想管理だとか、この制度をめぐる批判はいちいちリアルで、やっぱり胎児の自由意志の尊重なんて無理だろ、と思うのだが、望んでいないのに生まれさせられることは無期懲役、という理論も尤もで、現代日本だったらそれは指弾されるだろうけれども私は合意なき出生への懐疑には共感できる。生まれてくるからには、親だけでなく子ども自身が望んで生まれてきた、という方が生を祝福できる、というのも本当にそうだなと思うし、逆に合意なき出生は、その子を呪いにかけること、というのも一面真理な気もする。この小説では殺意と同レベルに見做されている、親が産みたいという「産意」だけで子どもを強制出生すること、すなわちこの小説でいうところの殺人と同レベルの行為、が現代の出産、って思うと怖いことではある。これは極端だけれど、でも産むことは絶対的な善で、子どもは当然生まれてきたいものだし生きたいと思ってるでしょ、という現代の常識を相対化する意味で、すごく良いなと思う。
でも最初から何となく胸がざわつく小説ではあった。最後もなんか苦しい。
投稿元:
レビューを見る
胎児の同意なしには出産出来ない法律が存在する未来の話。
自分の意思によって生まれることを選択した人間は、自分の人生に責任をもてるんじゃないか…
そういう思想があってもいいかなと思わされた作品でした。
投稿元:
レビューを見る
胎児の出産同意なくして出産した場合に有罪扱いになる世界で、妊婦となった主人公が妊娠を機に、出産と向き合う話。
本書の世界線では、リベラルが過度に浸透し、胎児にまで自己決定権が付与され、胎児が母体にいる際に生まれてくる権利・生まれない権利を行使できる。仮想の設定ではあるが、自己責任論が求められる現代の延長でもあると思えた。
本書で印象的だったのは、人間が作った制度である以上、完璧な制度は無いという点だ。
投稿元:
レビューを見る
生まれてくる前に胎児によって意思の確認ができるように技術革新が起こった後の世界を描いている。
合意出生制度によって、親そして子供、周りの社会がどう変化したか。
時代や制度が変わったとしても、人間は自分が信じられるものを持つことが大事である、それを支えてくれる人や宗教などの存在が必ず出てくる。
特徴的だったシーンを以下に記載。
「どんな挫折でも耐えてやろうという気持ちになれたのは、自分が生まれることを選んだから。」
「自分の一存で子供を産みたいという、産意も誰にでもあり、殺意と同様に他者を意のままに操りたいという願望」
「生まれる前の命を絶つというのは恐ろしいこと、決定権といいながら殺めているのは人間の形ができたもはや子供である。」
「コンファームなんて制度が当たり前になっているが、昔を見ると女性が男性よりも知性が劣っているから選挙権がなかったり、国体の崩壊に繋がるから女性や女系の天皇が認められていないなど、今考えるとバカバカしいと思える考えがあった。」
「自分の考えの拠り所にするために、間違っているのは世の中だ、制度だって木津つかないために自分と違う意見を見て見ぬ振りをしている。」
「人生の初っぱなから自分の意思が無視されたという事実がこの子にとって一生解けない呪いになるかもしれない。私は自分の子供の出生に呪いではなくて、祝いを捧げたい」
「本当に大事なのは、自分の意思で決めることそのものじゃなくて、それが自分の意思だと信じ込むことなのかもしれません。重要なのは真実じゃなくて信念なんです。ある結果が自分の選択によるものだと信じることで、その結果を受け入れやすくするのが人間」
投稿元:
レビューを見る
ずっと誰にも話せずにいた思いを、この小説に言い当てられた。驚き動揺し焦り
ーーー安心した(朝井リョウ)