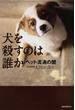紙の本
犬を飼うときは<家族>、捨てるときは<ゴミ>・・・。ゴミ扱いされた犬は、“冤罪”で死刑されるようなものである。
2010/12/07 13:09
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:星の砂 - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は、17年前に捨て犬を拾い、13年育てた経験がある。おとなしく愛嬌のある犬で、家族の癒し的な存在であった。だが、家庭の事情により、生活が一変。そんなある日、犬の体調が悪くなるものの、動物病院に連れて行く経済的な余裕がなく、治療もしてあげられず、何もしてやれないまま、死なせてしまった。それを、今でも悔やんでいる。そんな私が読むには、辛い一冊だったが、この本は、犬に係わるすべての人への、“警鐘”となるだろう。
第1章 命のバーゲンセール《「流通で「消える」1万4000匹」など》
第2章 「幼齢犬」人気が生む「欠陥商品」《「「8週齢」未満の販売を欧米は規制」など》
第3章 隔週木曜日は「捨て犬の日」《「命を奪う「住民サービス」」など》
第4章 ドイツの常識、日本の非常識《「98%に新たな飼い主」など》
第5章 動物愛護法改正に向けて《「「8週齢」が焦点に」など》
【巻末データ:主要自治体別 捨てられた犬の種類・犬にやさしい街は? 全106自治体アンケート】も載っている。
読めば読むほど、同じ日本人として、情けなく、悲しく、やりきれない思いに苛まれた。第1章に、「犬を捨てる身勝手な理由」を犬種ごとに集計した表が載っている。そこには、さまざまな理由があるなか、「犬の病気・けが・高齢」というのがあり、わが身を振り返った。私の場合、捨てはしなかったが、見捨てたようなものだから・・・。「犬が病気やけがをすれば当然、動物病院に連れて行かなければいけない」とある。もっともである。だが、「治療費は人間以上にかさむことがある」のも事実なのだ。
犬を安易に捨てることのできる構造に、身震いするほどの衝撃を受ける。ペットショップが衝動買いを促し、安易な気持ちで買い、安易な理由で犬を捨てる。そして、捨て犬を引き取り、殺処分をしていく地方自治体。無差別殺人そのものである。第4章のドイツの「犬の保護に関する規則」には、犬を飼育するためのルールを守らなければ、罰金が科せられる制度や、「犬税」などがある。安易に犬を飼うことへの抑止力にもなるそうだ。日本も導入して実施してもらいたい。しかし、このような制度でも取り入れないと命を大切にできない、というのも情けない。
著者は「私たち人間の取り組みが一日遅れれば、その一日で数百匹の命が無為に失われる。こんな理不尽なことを続けていいはずがない。犬たちの声なき声を拾えるのは、やはり人間なのだ」と、「殺処分ゼロ」が現実的に叶う日が来ることを願っている。
なお、11月27日の読売新聞に「民主党税制改正プロジェクトチームは26日、2011年度税制改正に向けた政府への提言集で、犬や猫などペットへの課税を検討課題とすることを求めた」という記事が載っていた。これが、“犬を殺す”ことの歯止めになればいいが。
紙の本
悲しい現実を変えていくのは私たち
2010/10/19 17:15
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:こぶた - この投稿者のレビュー一覧を見る
一年間に殺処分される犬の数は8万頭を超え、生後あまりにも早い時期親と引き離し、オークションで値段がつかない犬は流通段階で”消える”。
蛇口としての業者の問題、受け皿としての各自治体の問題、
そして安易に犬を買い安易に捨てる飼い主の問題。
それらが三位一体となって罪もない犬たちを殺処分に追いやっている現実。
殺処分される犬の種類、その理由、
犬に優しい自治体のデータまで添えられているこの本は
ショッキングであり
厳しい現実を突き付けているけれど
定点回収システムという捨て犬を公然と認めその後始末を行う
行政サービスに
おかしいということも
月齢が低いほど売れていく、
ペットショップでの販売方法やネットオークションでの
犬の販売が動菅法に違反していることに声をあげていくことも
普通の飼い主にもできることだ。
そしてなにより
犬を飼ったら長くても20年足らずの犬の一生に飼い主が責任を持つこと。
あまりにも身勝手な飼い主のために
命を奪われる犬たちの数が減ることが
弱いものに優しい社会ではないのだろうか
投稿元:
レビューを見る
どうして日本では年間30万匹もの犬猫が処分されるのか、ペット産業についてよく調べられていてわかりやすい。非常に参考になった。
可哀想と同情を誘う書き方でなく、冷静に現状を見つめているとこりが良い。
投稿元:
レビューを見る
ペットショップの犬はどうして常に変わっているのか、愛護センターが必要なのは市民ではなくペットショップかも?センターが無くなる日が1日でも早く来て欲しい。人間の身勝手さが憎い。
投稿元:
レビューを見る
日本全国で推定1230万頭ほどの犬が飼われているが、一方で、年間11万6千頭もの犬が自治体に引き渡され、うち8万4千頭が処分されているという。
本書は雑誌AERAに掲載された記事を元に大幅に加筆・修正したもの。
丹念にまとめられた巻末の自治体へのアンケートから、誠実な印象のある本である。
ただ、少々、結論ありきな感じがする。「かわいさ」を武器にしつけが十分でない幼犬を売り、勢いで購入した無責任な飼い主が飼いきれなくなって処分に走る。業者はまた、売れ残った犬を自治体に持ち込み、処分させる。『犬を殺すのは誰か』とタイトルは質問調だが、著者の中で答えは「もうけ重視の悪徳業者と十分な手立てを講じていない行政」であると結論が出ているのではないか。
そうした図式は確かにあるのだろう。しかし、業者への取材や衝動買いする飼い主への取材が十分であるようには思えず、それはあるのかもしれないけど、また別の図式もあったりしないのかなぁ・・・?という感が個人的にはぬぐえなかった。
殺処分ゼロに向けて努力している自治体の紹介やペット先進国ドイツのシェルター紹介などもあった。ドイツの事例を一足飛びに真似することは出来なくても、知ることで得られるものもあるだろう。
8万という数字は大きい。個人の手には負えないレベルだろう。動物愛護法改訂の動きもあるようだが、いい方向に進むことを願いたい。
*でも、「8万」は大きいけれど、飼われている犬全体の「0.7%」と思うと、大半の犬がモラルを持って飼われている、という見方も出来るのかもしれない。
*自分で犬を飼うときに、「保健所から」というのは少し考えたけれど、犬を飼うのは初めてだったこともあり、二の足を踏んでしまった。情報公開が進んでいるわけでもなく、敷居が高い感じがしたのもある。
*巻末の表によると、純血種の中では柴が飛び抜けて処分数が多く、(うちの犬も柴なので)胸が痛む。
*日本の動物愛護行政の歴史ってどうなっているのだろう。ちょっと追ってみたい気もする。
投稿元:
レビューを見る
アエラ編集部記者による渾身の取材記録。現状のペット流通の問題点が網羅的にまとめられており、一読して内容が理解できた。最終章では、愛犬政治家の名前や活動が紹介されているので、彼ら熱心で共通の思いのある政治家を応援することでも間接的に、ペットの殺処分問題に関与できる。巻末の<主要自治体別 捨てられた犬の種類>や<犬に優しい街は? 全106自治体アンケート>などの統計は、今まで知ることのなかった各地域性が見えてくる。地域のもうひとつの「顔」のようで、ある意味興味深い。ドイツのティアハイム愛護施設の例もでてくるが、国として比較した場合に、日本の生命倫理観や自然に対する考え方、他者への想像力、距離感など、ペットの問題は単一の問題ではなく、日本の抱えている問題の危うさを浮き彫りにするようだ。
昨今のペットブームにはどこか危うさを感じていたが、はたしてどれくらいの人が自分とは別個に生きる命に最後まで、まじめに向き合えるのだろう。「動物は命をもった私たちと同じ地球の仲間」である。動物の生命より資本の論理、市場主義を優先していいのだろうか。動物を売買する業者にもう一度、ペットの目をよく見つめて考え直してほしい。
意識を変えていかなければならない。
本の最後は次の文で締めくくられている。
「私たち人間の取り組みが一日遅れれば、その一日で数百匹の犬の命が無為に失われる。こんな理不尽なことを続けていていいはずがない。犬たちの声なき声を拾えるのは、やはり人間なのだ。」
投稿元:
レビューを見る
アエラ編集者が明かすペット業界の暗部。
日本国内での飼い犬の数が1232万匹(2009年ペットフード協会推定値)、それに対して2008年に殺処分された犬は84,045匹。 殺処分の多さに疑問を持った著者がペット業界の調査に立ち上がった。
多くの犬が殺処分される背景として、著者は「ペット業者」「飼い主」「行政」の問題を挙げている。
一番問題なのがペット業者(ブリーダー、ペットオークション業者、小売業者)。
営利企業である以上、利益を追い求めるのは当然のことであるが、商品は命ある生体。 完全に商品と割り切り、モノの様に生体を扱うのは由々しき問題である。 鮮度が落ちた商品(生後半年経ってしまった子犬等)は独自で処分したり行政に引き取らせたりするのがまかり通っている。 生まれすぎた子犬を間引くことによって高価で販売しようとするブリーダーも居るという。
そして、著者が一番問題視しているのが、ペットのオークションという仕組みである。 オークションという形態をとるが故に、売れる犬と売れない犬が歴然とし、売れない犬は必然的に闇に葬られる。 オークションを経由する流通では、その途中で1万匹以上がこつ然と姿を消すという。
二番目として指摘しているのが無責任な飼い主。 引越しで飼えなくなったり、犬の無駄吠え、噛み癖を理由に保健所に連れてくる飼い主が多々いるという。 ただ、その裏には安易にペットを買わせるペットショップが少なからず介在しているのも見逃せない。 犬の3~12週齢は社会化期と呼ばれ、子犬にコミュニケーション能力が芽生えて、周囲から様々な事を吸収していく時期。 その大事な時期を経験しないと情緒不安定な犬になったりするという。 動物は幼ければ幼いほど高く売れるので悪質なペットショップはこれを無視して販売する傾向がある。 結果として懐かない犬を排出し、飼い主によって手放されることとなる。
三番目としては行政。 ルーチンワークとして動物の殺処分を受けているため、これが前述のペット業者の格好の処理場所となっている。 殺処分数を減らすという努力がなされていなかったり、動物の痛みや恐怖を少しでも軽減させる殺処分方法を真剣に考える自治体はまだまだ少ないという。 この様な行政の体制が悪質ペット業者の温床となっている。 結局はペット業者を儲けさせるために、我々が税金を払っていると思うと行政の怠慢に思えてくる。
この問題を改善するには個人(飼い主)の意識UPと法整備しか無い。
現在の日本は緊急で解決すべき問題が多く、動物愛護の優先順位は客観的に見て高くないし、実際高くできないと思う。 ただ、そうは言っても国による法律の改正は地道に進めていって欲しいと願う。
投稿元:
レビューを見る
年間約11万頭の犬が保健所へ引き取られる。日本全国で飼われている犬約1200万頭の1%に相当、その多くが殺処分される。この異常な数字の原因についての、AERAの記者による2年間の取材レポートである。 流通・販売から殺処分までを「蛇口」と「受け皿」に例え、犬を扱うそれぞれの立場における常態化した問題を扱う。業者による無計画な大量繁殖、仔犬販売、飼主の衝動買い、無責任な遺棄、行政の限界、法の無作為など種々の問題点を明らかにしている。
投稿元:
レビューを見る
2008年度に全国の自治体に引き取られた犬の数、約11万匹。
そのうち、約8万匹が殺処分されたという事実。
(尚、平成22年度の殺処分実数は、犬5万匹、猫16万匹)
命有るものなのに、人間の欲望の対象とされ、商売の「物」として扱われて、最期には殺される形でこの世を去っていくペットの何と多いこと。
日本では、なぜこの様な理不尽な状態がまかり通っているのか?欧米のペット先進国と対比しつつ、日本のペット産業が抱える闇をあぶり出している。
問題の源泉は以下に要約出来よう
・ペットショップに大量の子犬を供給するペットオークションの存在
・赤ちゃんの子犬から育てたいと考える日本人特有の感覚
・ペット販売方法に対する法規制の緩さ
現在、動物愛護法の改正が議論されつつあり、夜20時以降のペットの展示販売は禁止される見込み。
出来れば、欧米同様に生後8週齢以下のペットの販売は早急に禁止されるべき。
さらに、狭いケージに何日間も入れられる現状の販売方法は、動物の尊厳を軽視するものとして、同様に禁じられるべきと考える。
安易にペットを飼うことが出来る現状が、責任感の無い飼い主を生み出し、結果として捨てられるペットを生み出すシステムと化しているのだ。ペットショップで犬猫を購入する飼い主全員が、この不幸な状況の存続に手を貸していると言っても過言では無い。
投稿元:
レビューを見る
広範囲に取材はされているようだが、それぞれの取り扱いは思ったよりも浅めで、内容的なヴォリュームもそれほどではない。
が、動物好きならずともおそらくは誰もがなんとなく嗅ぎとってはいるであろう、しかしなかなか直視しようとはしないペット流通を巡る闇の世界に明確に切り込んでいる。
売ったら仕舞い、と言わんばかりのペットショップのあり方。
本書で扱われている犬・猫ばかりではなく、アリゲーターガーがどこそこの川で見つかっただとか、在来種を駆逐しつつ蔓延る強力な外来生物たちが増殖した原因の一角にも、そうしたショップの姿勢が介在していることは明らかだ。
他にも、パピーミルやオークションといった、生体を売り物にする上では構造的に不可分な問題がつきまとうシステムが根強く残っていることも、この本は記述している。
店頭で売れ残った犬・猫や、無責任な飼い主たちが飼養を放棄した犬・猫が、まるで廃車をスクラップにするかのごとく、オートマティックに殺処分されている現状が間違いなくこの国にはある。
それも税金を使って。
売る側の良識の低さ、買う側の無思慮ぶり、そして商行為を規定する行政の立ち遅れ。
これらを鑑みるに、日本のペット業界はまだまだ恐ろしく未成熟であると断定せざるを得ない。
投稿元:
レビューを見る
動物愛護法について。
現在法整備中というのをはじめて知った。
ペットビジネス。
日本は本当に遅れてる。いてもたってもいられない気分になる。
投稿元:
レビューを見る
アエラで連載されていた犬の殺処分について、まとめた一冊。
本は、部屋にガスを入れて殺処分される痛ましい様子から始まるが、これらは決して目を背けてはいけない事なのだと思う。
本で取り上げられているのは犬の話だが、にゃんこ達の環境もほぼ同じようなものだろうと考えられる。
殺処分される家族(愛猫・愛犬)の姿なんて想像すらしたくない…。
制度の改正で事態を改善できるのであれば、愛護法の改正については注視していかないと、と思った。
投稿元:
レビューを見る
2013年55冊目。
飼われた犬のうち、100匹に1匹は自治体に持ち込まれ(捨てられ)、年間で持ち込まれた約11万6000匹のうち、約8万4000匹が殺処分されている(2008年度)。
そんな日本の捨て犬・殺処分を巡る各界の問題や取り組みを、犬の流通・小売り業界を「蛇口」、捨て犬の引き受けを行う自治体を「受け皿」として、構造的に捉えた本。
この社会問題の全体像が把握できる、とても優れた1冊だと感じる。
■8週齢以下の犬を家族から離して流通させることで、成犬時の問題行動を引き起こす可能性が上がり、捨て犬に繋がる。
■小売業者が飼い主に飼い始める前に検討すべき事項をきちんと説明する義務は動物愛護法第8条に明記されているが、衝動買いを狙う深夜販売やネット販売への規制はまだまだ。
■生体販売業におけるコスト削減は、すなわち動物への粗雑な扱いとなる。
■日本独自のオークションという仕組みが、参入障壁も低く、悪質なブリーダーの温床となっている。
■ドイツでは民間の動物愛護施設が「犬を探す際最初に行く場所」と認識され、年間25万人を呼び込むまでになっている(引き取り率は98%)
問題を構造的に捉えて、法律でできること、民間事業でできること、ボランティアでできること、一人ひとりができることを連携しながら実践していくことが大切だと感じる。
投稿元:
レビューを見る
犬猫を飼いたい人は店で買うのではなく、殺処分される犬や猫を引き取るように!
世の中には一定数のバカがいるのは仕方ないが、そのなかであとのことを考えずに犬猫を買うバカもいる。ペットショップは命ではなくエサや消耗品だけ売るようになればいい。
自分も拾った猫用のエサなどを買っているけど、それだけでもけっこうな金額になるはずだ。
投稿元:
レビューを見る
小学校や中学校から
こういう本を読ませればいい。
雑誌はこういう問題提起をたくさん、
じっくりやるべき。
田舎にはペットショップ無かったけど
親は犬を飼うなら保護犬がいいねと言ってた。
最初の犬は知り合いから、
次の犬は多分捨てられた迷い子の犬、
最後の犬は譲渡会でもらってきた。
また犬を飼いたいから、
保護センターに行きたいなぁ。