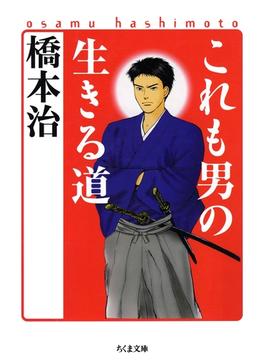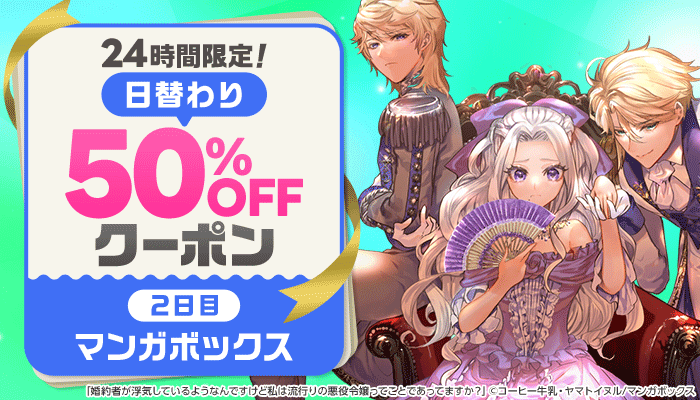これも男の生きる道
著者 橋本治
男にとって大切なのは、一人前になることです。それは、自分のするべきことはなんでもできること、自分のするべきことはなんでもすると覚悟して、なんでもすることです。もちろん、で...
これも男の生きる道
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
男にとって大切なのは、一人前になることです。それは、自分のするべきことはなんでもできること、自分のするべきことはなんでもすると覚悟して、なんでもすることです。もちろん、できないこと、わからないこと、知らないことを、素直に認めることでもあります。かんたんなようで、なかなか困難な、これが男の生きる道。男も女も、この本を読んで、一人前になってください。
目次
- 第1章 男には男の「自立」がある/第2章 日本の息子達が「自立」で悩むのは、日本の父親達が自立していないからである/第3章 「男の自立」とは、なれあいからの脱出である/第4章 大人の中の「子供」に学ぶ/第5章 「できない、わからない、知らない」を認めよう/第6章 男にとって重要なのは、「自立」ではなく「一人前になること」である/第7章 「成功への道」は遠く、そしてその道は、「なんだかわからないもの」である
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
一人前を目指そう
2020/01/02 20:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:dsukesan - この投稿者のレビュー一覧を見る
仕事も含めて、「できないのは、わからないから」「わからないのは知らないから」と著者は説く。それは、人間関係も含めて。
素直にできない、わからない、知らないを認めて、一旦落ち着くことを提唱する。出来ないことを認めるとは、すぐに出来るようになきゃならないというのも違うと言う言説に、少し安心。
家庭も、会社も社会も、人間の作るもの、どこかにとっかかりがあると信じて、恐れず、逃避せずに、一人前への道を粛々と歩みましょう。
始まりは”Idon’tknow.”
2005/06/21 00:48
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Tabby - この投稿者のレビュー一覧を見る
橋本センセイ、
「男がもっと率先して家事に参加するよう<自立>についての本を書いてくれませんか?」
というオファーに対し、
「その<自立>の定義自体がいささか違っているのではないか?」
と問い直すことから、この本は始まる。
ラディカルな問いを忘れないのが、いかにも橋本治らしい。
いつものように大切なことは、繰り返し繰り返し、これでもかというくらいくどく
語られている。議論が脱線することもしばしば。
その曲がりくねった議論の変遷をたどってみると、
【1.自立について】
男が自立できないのは、「父」がいないからなのだ、と。
橋本治にしては、普通の意見で面白くない。
【2.「わからない」「できない」から始める】
いつの間にか議論が脱線して、それこそ「わからなく」なってきた。
自立と「わからない」がいったいどういう関係があるのだろうか。
【3.「一人前」を目指せ!】
今までの議論はここで一気にチャラにされてしまう。
一人前になりさえすれば、自立は自動的に達成されるのだ、と。
これもいたって普通の意見だけれども、妙な説得力がある。
他人がしていることだから興味がない。そんなの簡単だよと思ってしまう。
そういう甘い態度に、橋本治は容赦なく冷や水を浴びせる。
つまるところ、一人前になる道のりのスタートは、生き方の難しさに対し、
「私は知らない」と疑問を発することにあるのかもしれない。
「自立」は男の目的か
2002/01/02 22:49
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とーも - この投稿者のレビュー一覧を見る
橋本治流の、一種の人生論の本。テーマは「男の自立」というコトバだが、実際の主張は「自立は単なる出発点であり目的ではない、大事なことは自分の頭で考えて行動する一人前の人間になることだ」という、まあ要約すればひどくありふれた、陳腐にさえ聞こえる思想である。
彼のこの種の本は、いつも論理の飛躍がかなりひどい(結論が間違ってるというのではないのだが筋道がたどりにくいのだ)。しかし、この本はややていねいに一歩一歩進めながら書いているので、筋を見失うことはない。ま、そのぶん、あの天衣無縫な持ち味が薄いとも言えるが。
しかし、同じ人生論の本ならば、やはり「絵本・徒然草」などの方がはるかに充実していて良い出来かもしれない。かれは何といっても、古典文学の「鑑賞」がもっとも得意で面白いのだ。長いメロディーの創意には乏しいが、他人のメロディーを借りて複雑絢爛な織物を創り出す編曲家の才能に通じるところがあるのかもしれない。