H2Aさんのレビュー一覧
投稿者:H2A

比類なきジーヴス
2018/05/04 21:52
ジーヴスもの第1弾
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これは執筆年代からいうと最初のものではない。しかしジーヴスとバーティ・ウースターものの翻訳がいちおう完結したシリーズ14巻の最初に出た巻である。バーティ・ウースターは有閑の青年で叔父の援助を受けて暮らしている。そのお付き執事がジーヴスでこの2人は時に諍いも交えて最高の名コンビを成す。この巻ではそのコンビがバーティの親友ビンゴ・リトルの縁談の世話をする連作短篇という形式。イギリス上流階級の滑稽で呑気で優雅な生活を垣間見せるし、実際ジーヴスとバーティのやりとりはかなり笑える。このシリーズが全部読めるなんで幸せだ。

いつかたこぶねになる日 漢詩の手帖
2021/03/09 15:07
須賀敦子の再来
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
漢詩に寄せた珠玉のエッセイ集。著者はフランス在住の女性詩人とのことだが、某読書界隈で話題になっていて、そういうことは珍しいが読んでみた。扱う漢詩は盛唐の大詩人の杜甫からはじまって王国維などの中国清朝の近代、さらに日本の平安時代の菅原道実から夏目漱石、幸徳秋水まで。詩そのものの詩風も多彩で食を題材にした杜甫の詩から思弁的だったり虚無的な内容まで漢詩の多彩さを教えてくれる。さらには漢詩以外の本も多数取り上げて古今東西縦横無尽にさらりと博識に語る。それでいて生活感あふれた内容も多いのでとっつきやすく読んで楽しい。かと思うとまた考えさせられる警句をいきなり出して驚かされる。手管を見せない天性の書き手。書店でそう見かけないためそう有名にはなりづらいだろうが、内容は素晴らしい。

地球の長い午後
2019/01/24 00:27
想像力の極限
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
はるか未来の地球。自転が止まり植物が支配する世界で人間は文字通り小さくなってかろうじて生き延びている。グレンという主人公もいるのだが、主役はやはりこの異様なこの世界そのものだ。いくらなんでもあんなやり方で月にまで行けてあいまうのはどうだろうと思っても想像の限りを尽くしているのでこの世界に幻惑される。ポンポンがうっとうしいとか、あの生意気なキノコ(アミガサダケ)の野郎は何なんだとかどんなにけなしても、そうした短所の数々はこの異世界そのものの存在感に圧倒される。そして結末で語られるこの世の黙示録のような終末ビジョンにもやられてしまった。オールディスはこれ一作でも名を残すにちがいない。

夜の果てへの旅 改版 上
2022/03/27 21:58
呪詛という行為
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
フェルディナン・バルダミュは衝動的に志願兵となり、戦場に送られる。そこは無意味に人が死に、死地においやられ苦痛を被らされる場所。負傷して帰還して療養施設に隔離されても理不尽な目に逢い続け、やがてアフリカに渡りさらにアメリカに行きつく。どこへいってもバルダミュがみるのは汚物まみれの見にくい人間の姿。巻の終盤でかすかに善意を見いだすが、それも振り切って帰国を決意するところで下巻へ。暗澹とした内容だがこのどこか飄々とした語りはドンキホーテ譲りだろうか。
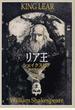
リア王 改版
2021/05/02 22:14
悲劇の典型
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
筋書きや内容については訳者の福田恆存の解説を読むのが最善。リアの気まぐれのような領土配分はいきなり狂気を感じさせるが、その並外れた情念が周囲の人物たちに渦巻く悪意を攪拌して、わずかな善意も押し流して、なにもない場所に行き着く。以前ローレンス・オリヴィエの映画を観たことがあったがそれは大分ストーリーを刈り込んでいたように思う。原作は(月並みな表現だが)その複雑さ、深刻さ、スケールの大きさで別格。個人的には道化の存在が悲劇の中にアクセントを生んでいて、その小唄も見事に韻を踏んで訳されている。訳者の短い解説も的確で重みがあって素晴らしい。

暇と退屈の倫理学 増補新版
2021/04/24 16:57
「退屈」の博覧会
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
暇と退屈のメカニズムについて論じた長編論考。堅苦しくなく著者の生の声も時々聞けるので飽きずに読め通せる。といっても決して安易な流行本とはちがう。身近なテーマが意外なほど深く掘り下げている。ハイデッガーの退屈への考察、3つの形式についての考察が全体の背骨のようにになってたびたび参照される。そこに古今の様々な学際的な知見を参照しながら議論を進めていく過程がおもしろい。著者は誰かひとりの議論に寄りかからず、部分的に肯定しても結論部分はなかなか認めようとしない。それでも倫理学と言っている手前、「結論」をつけてはいるが自身で言っているように、そこに超越的な策など示されない。そこにがっかりする向きもあるだろうが、私はそこに至る探求の道筋こそスリリングに感じた。また、人間の「本来の姿」という概念に対する著者のはっきりとした拒絶の姿勢も自分には好ましい。
大抵は、「増補新版」に付いている増補された部分は余計でつまらないことがほとんどだと思うが、この本は増補された書き下ろしの論考も充実しているのも稀少。

火星年代記 新版
2020/11/29 22:11
旧版で持っています
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ハヤカワSF文庫に収録される前のNVに入っていた旧版を持っている。火星に押し寄せる地球人たちと火星人の物語は、そのまま新大陸に押し寄せてアメリカ人になったヨーロッパ人の焼き直しのよう。ここには「詩情」としかいいようのない情感があって、繰り返される人間の物語がほんとうに叙情的に描かれる。火星人の残した廃墟でバイロンの詩が連想されたり印象的な場面がいくつもあってその感動は忘れようがない。終幕の『百万年ピクニック』で映し出される「火星人」の姿を目にする。訳文にもリズムがあってブラッドベリの世界をちゃんと日本語に移し替えられていて素晴らしい。

冷血
2019/01/24 00:04
大人になった天才作家
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
カンザス州に住むクラター家がある日全員惨殺されたという実話を元に構成。犯人はペリーとディックの2人。この2人の視点と、その犯人を追う警察側のほか事件の大勢の関係者を小説として描いた。事実だけを素材にしているので本来はノンフィクションだ。しかしカポーティによって選び出され再構成され小説としても十分に読ませる。犯人であるペリーには尋常でない共感を持っていたのではないか。理不尽な犯行動機を自供する場面はこの小説の核心部分で鬼気迫るものだが、そうした悲惨な事件を起こした当事者であるにも関わらず、ペリーに勧善懲悪的な正義感を振りかざす気にはなれない。ペリーとディックは「12人の陪審員」の証人の見守るところで絞首刑に処せられ、この地域の平安が戻ったと語られると、この2人の死も結局は社会のための生贄として供されたとわかる。実在の事件の取材という制約があるにも関わらず、これだけの小説世界を創り出し定着させたカポーティはやはり素晴らしい才能の持ち主だった。読んだのは旧約版。

現代思想入門
2023/01/21 21:19
入門の入門
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
デリダ、ドゥルーズの章だけでも読む価値ありだと思う。目から鱗だった。音声中心主義、差異、とかそういう解釈があるのかと今さら納得。無意識のもんだいにもそんなに関心あったわけではないが、ドゥルーズにおいてどういう意味があったのか少し蒙が拓いたような気がする。これほどくだいて書けるのも著者の地に足のついた理解のおかげ。それから終章のポスト・ポストモダンもおもしろく読んだ。

山田杏奈セカンド写真集「BLUE」
2022/05/24 19:08
水着はないけど
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ある出演映画を観てから、他の出演作を何本か観た。表紙はずいぶん大人びた表情だが、無邪気さと賢さが同居したような不思議な雰囲気をまとっている女優。スレンダーで華奢だが色気も感じさせる。水着などはないが素材も抜群で女性の写真集としては上質。

夜の果てへの旅 改版 下
2022/05/03 17:44
夜明けでも心の中は「夜の果て」
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
アメリカから帰国したバルダミュは途中で放棄しかけた医学を修め、パリ近郊のランシー街で医師として働く。戦場からアフリカ、アメリカと目まぐるしく駆け回った前半とは対照的にごく狭い舞台の中で人間たちが蠢く。ますます救われないことが確実になる人間の姿。陰鬱さはさらに色濃くなりともに歩んできたロバンソンの最後を看取ったところで物語は唐突に終わる。セーヌ川で朝を迎えたのに心の中は闇につつまれたまま、バルダミュは言葉を失う。再読しても虚脱状態のようになりそう。多少距離は取れたつもりだけれどこの作品の持つ毒性はやはり強い。

ジオラマボーイ☆パノラマガール
2022/02/10 20:09
バブル期の傑作
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
映画を観てから読む気になった長篇漫画。映画版が意外なほど忠実にこの原作をなぞって、一方で巧みにアレンジしていたことがわかる。原作の方は1989年というからバブル全盛期の作品。当時の生活風景を写しているので古めいて感じる部分も確かにあるが、この作品はそれにとどまらない今でも驚くような新鮮さがあってとてもおもしろい。

君は永遠にそいつらより若い
2022/01/14 23:50
ホリガイとイノギ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
青春小説のような題名からはちょっとかけ離れた成熟した内容。これがデビュー作だとすればこの作家は異質。トラウマものだが、この小説は独自で新しい。言葉選びがおもしろいとか洒脱だというのとは全く違う資質。

理不尽な進化 遺伝子と運のあいだ 増補新版
2021/09/12 16:55
進化論をめぐる言説
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
進化論を軸にして、種の99.99%が絶滅してしまう絶滅論争と、適者適存を巡る社会一般の「進化」概念の誤用、悪用と、ドーキンスvsグールドの一方的な論争、「説明」と「理解」に代表される知の2極(科学と歴史)へと話題は広がる。著者の親切そうな人柄を反映してか、著述も丁寧に説明するので晦渋さはなくて親しみやすいし、気ままに別の話題が繰り出されて脱線したり、煩わしさも少し感じた。しかし無駄話も含めて視野が広くおもしろい内容だった。進化論というより科学をめぐる哲学本、というのが実態ではないかと思う。

パルムの僧院 改版 上
2021/08/22 09:34
最初は少し我慢も必要
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
舞台はイタリア。いきなりナポレオン軍に従軍してした挙げ句に主人公ファブリスは無鉄砲に次々に失態をやらかす。混乱したままの冒頭100ページぐらいまでは挫折しそうだった。それでも塔に幽閉されて以降のクレリアとの恋愛関係になっていくあたりから俄然おもしろくなる。それに平行して流れるジーナとモスカの大人の関係が地下水脈のようにこの小説を支えている。スタンダールの理知的で自由な人間観も、この夢のような小説に結晶している。ネットで見ると主人公が無鉄砲だから嫌いと言った意見も多いが、この無茶ぶりも含めて逆に小説の魅力だと自分は思う。


