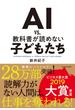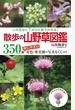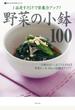あられさんのレビュー一覧
投稿者:あられ
2018/05/02 04:26
AIというものには何ができて何ができないか、人間との違いは何か。
24人中、22人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
新井先生のような研究者さんが、このような形で最新の研究成果と知見を広くシェアしてくださることはとてもありがたいです。自分でも以前高校生と接して「何だ、これは」と思ったことがあるのですが、新井先生の大規模な研究・調査でわかったことと符合しています。
「~以外の…(リンゴ以外の果物、のような)」の「以外の」が読めていないとしか考えられない、というくだりには、ぞっとしながら「ああやっぱり」と思いました。そして、そのことについて大人たちの一部が「不必要に難しい文章を読ませて学生を混乱させている」的に反応するということには、ひたすらぞっとしました。まずは大人が、人の話、聞けよ……ということですよね。「教科書が読めない子供たち」は、大人の鏡です。文科省が数学の「行列」をどう扱っているのかというところでは、文字通り、目を疑いました(私が読み間違えているのだと思いました)。
また、AIというものには何ができて何ができないか、それはなぜなのかという説明が、これまで読んだAI関連の書籍の中で最もはっきりしていて、わかりやすかったです。根拠のない幻想を振りまく夢物語ではなく、こういう冷静な説明が、もっともっと広く読まれるようになるべきです。
その上で「人間には何ができるのか」を建設的に考えていかねばならない。実際、ワープロやパソコンの時代になって「漢字なんか書けなくったっていい」という極論がさほど極論に見えなくなっている現実にも、人間は冷静に対処できています。そういう意味で、希望は持てる本です。が、ぼーっとしていては希望すら持てない。そういうことではないでしょうか。
電子書籍で購入。紙の本での感覚でマーカー引いてメモ(コメント)書いてたら、hontoのリーダーでマーカーの数の上限を超えてしまいました(マーカーの上限なんて、あるんですね……それじゃ基本、小説のように読み流すものにしか使えないです)。

【アウトレットブック】シュガー ぼくはネコである
2017/06/27 05:07
しばし、彼らとネコの生活の中へ……
17人中、17人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ページをめくっている間は時間を忘れる本です。
フランスのバンドデシネ(コマ割りマンガ)。
コマ割りは、1ページに4×6の24個の正方形が基本で、
コマの枠線を超えて縦横無尽に時間と空間が展開し、
家の中や街路を飛んで歩く猫の視線を再現しています。
ストーリーは、セルジュとアンの若いカップルの家の猫(たち)の物語。
最初にいた特別な猫、ティムと不幸な形で別れ、
次に飼った子猫、ジェフとはほんのつかの間で別れることとなりましたが、
次にアンの弟がもらってきた雑種の黒猫は長い時間をともにしました。
シュガーと名づけられた子猫の冒険の日々、
セルジュとアンの時間(子どもが生まれます)、そして……
造本もおもしろく、印刷もきれいです。
アウトレット本で購入しましたが、汚れなどなく、きれいな状態で
とてもよい買い物ができたと思います。
2019/10/30 14:48
ポイントは調味料
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
紙の本を持っていたのですが、姉のところに行ったまま戻ってこないので、セールになっていることだし、電子書籍で買いました。電子より紙のほうが使い勝手はよいのですが、電子版をタブレットやスマホに入れておけば、見たいときにいつでもさっと参照できて便利です。電子版は目次は細かく指定されていますが、マーカーをつけたり全文検索したりはできません(基本的に、紙の書籍を画像データ化してあるだけ)。
この本のレシピの優れているところは、まるでデパ地下で売っているような、ありきたりでないサラダが、近所のスーパーで買えるありふれた素材の組み合わせで、自宅で作れる、という点です。
決め手は調味料の使い方で、巻頭にまとめられている「人気の定番ドレッシング20」を使いまわすだけでも毎日の食卓に変化を出せます。レモン果汁やマスタードを感覚で使えるようになると、家で作るものもデリっぽいおしゃれな感じになりますね。
サラダなので基本的に素材にはあまり手を加えないレシピが多いのですが、レンコンを素揚げしたり、ピーマンを焼いたりして使うという「ひと手間かける」系のレシピもあります。うまく作れれば、パーティーのときなどはそれがよいかも?
本体は8つのパートに分かれていて、Part 1は「デパ地下人気サラダ」、Part 2は「エスニックサラダ」、Part 3は「和サラダ」、Part 4は「ごちそうサラダ」、Part 5は「ランチサラダ」、Part 6は「おつまみサラダ」、Part 7は「ホットサラダ」、Part 8は「フルーツサラダ」という分類です。Part 4は「サラダ」と呼ぶのは無理があるように感じますが(「メインのおかずと付け合わせ野菜」だと思います)、他が充実しているので気になりません。
巻末には「食材別インデックス」があり、「かぶが安かったから大量にあるんだけどどうしようかな」というときは、「かぶ」で見ればよさげなレシピがぱぱっと見つかるようになってます。
2019/05/26 18:59
花だけでなく実でも探せる
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
同じシリーズの『散歩の花図鑑』を紙と電子版で所有しており(レビュー投稿済)、良い感じだったので、こちらも電子版で購入しました。
構成は本書も『花図鑑』とだいたい同じで、「目次」で季節ごとに分類され、「写真目次」では黄色系、赤系など花色で分類されていますが、同じ要領で果実・種子の色からも探せるようになっています。編集はかなり手間がかかったのではないかと思います。
掲載されている植物ですが、確かに街中で見かけることはほとんどないにしても、山まで行かずとも、都内でも等々力渓谷や石神井公園のようなところ、あるいは団地の敷地内でうっそうとした茂みになっているようなところで見かけるようなものもけっこう入っています。シュンランなど、野生のものを見る機会はなくても民家の玄関先などに植えられているのを見る、という花もあります。シャガやクサノオウ、ホタルブクロ、オオバギボウシなどは、私は日常生活の中でわりとよく見かけるのですが、確かに、コンクリの割れ目から生えているような植物ではないかもしれません。
実際に見たことがなくても、この本で写真を見て「かわいい花だな、いつか現物を見てみたな」と思う花々もたくさんあります。ハナネコノメ、セントウソウなど。
花が小さいもの(数ミリ単位)が多く、写真は電子版で大きく拡大表示できるのが楽しいです。
以前、白いフワフワした綿毛だけが目立っていて、何の植物かわからないものがあったのですが、果実・実の写真目次の「白系」のところにその植物らしき写真があるので、その植物の解説で花の時期を調べて再度確認に行ってみたいなと思っています。

きのう何食べた? 1 (モーニングKC)
2019/04/25 19:54
ドラマ化を期に、電子書籍を入手
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
10年ほど前に友人が「おもしろいよ」と貸してくれたマンガ。
当時「これはすごいなー」と夢中で読んだのですが、
書籍を増やす気になれない時期だったので買いはしませんでした。
今回ドラマ化されたのを見て、
改めて読み返したくなったので、電子書籍で入手しました。
ドラマはドラマでよいのですが、
「淡々とした日常の中にすっと入ってくる隙間風」のようなものの表現は、
マンガの描写のほうが私には伝わってきます。
特にシロさんと両親の間の空気感。
ドラマで「説明調のセリフ」で読まれると、マンガで再体験したくなります。
でもドラマだと、その両親の間にもいろいろあったであろうことも
説明なしでも伝わってくるんですよね。役者さんってすごいな、と。
そんな感じで、しばらくはドラマにあわせて読んでいくかなと思っています。
2007年にすでにこういう表現があったこと、今思うと驚きですよね。
2018/07/17 13:21
漠然と「野菜はヘルシー」というだけでない実用的レシピ集
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
野菜だけ、または野菜とじゃこやベーコンといった食材を使った一品料理のレシピ集。「菜の花のからしあえ」や「ラタトゥイユ」、「きくらげの卵炒め」のような定番から、「大根の葉と納豆のあえもの」、「大根とパプリカの洋風なます」のような創作料理っぽいものまで、レパートリーを広げてくれる実用的なレシピが多数掲載されています。調理手順は2ステップか3ステップでまとめられています。
肉など脂肪分が多く含まれる食材はあまり使わないレシピが多いです。「小鉢」なので、そうがっつりした食材は使わないです。
本のコンセプトが「栄養力アップ」で、第1章が「栄養成分で選ぶ」、第2章が「症状別」(冷え性、胃腸のトラブル、骨の強化、など)と大枠で整理されています。「油で調理するからβ-カロテンの吸収率もアップ」というように、料理名の脇にそのレシピと栄養のポイントが簡単にまとめられています。(油と栄養素のことは家庭科で習うはずなのですが、「油を使わないのがヘルシー」と短絡している方には向かないレシピ集かもしれません。)
家族の食卓に何かもう1品……と考えている方だけでなく、一人暮らしで、栄養が偏っているから何とかしなくちゃと思っている方にぴったりだと思います。調理の基本は特に説明されていないので、ある程度慣れている方向けです。

図説英国ティーカップの歴史 紅茶でよみとくイギリス史 増補新装版
2020/02/29 17:43
立派な研究書
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
イギリスの陶磁器(主に磁器)の歴史を、「ティーカップ&ソーサー」に絞り込んで解説してくれる立派な研究書です。しかも美麗写真多数。ストーク・オン・トレントなど現地訪問もされていて、情報量がとても多く、読み応えたっぷりです。
お茶の器だけでなく、お茶そのものについての解説もたっぷり入っていて、お茶の産地としてイギリスに重視されていた中国との関係や、お茶と庶民との関係(当初、お茶は上流階級にしか手の届かないような高級なものでした)も書かれていて、単に「美しいボーンチャイナの写真を眺めてうっとりする本かな」と思って手に取っただけだったので、驚きました。嬉しい驚きです。
あえて難を言えば、ここ20年ほどに起きたイギリスの製陶産業の激変っぷりを、1ページ分でよいのでカバーしていただけていたら、と思いました。例えばミントンはとっくの昔に別の製陶会社の傘下に入っていましたが、その後も経営の統廃合が続き、2020年の現在ではもうブランドとしても存続していません(2015年にブランド廃止)。イギリスの製陶は、産業丸ごと博物館入りしてしまったような状態にあります。イギリスでは日常に近すぎて特に誰も関心を払っていないかもしれませんが、そういうなかで、日本でのこのような立派な本が比較的安価で出版されたのは、すばらしいことだと思います。関係者各位に敬意を表します。
![リンネル 2018年 12月号 [雑誌]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/29314415_1.jpg)
リンネル 2018年 12月号 [雑誌]
2018/10/23 06:01
充実の内容と付録
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
付録目当てでの購入です。
メインは去年と同じくムーミン×Marble SUDのポーチ。去年はキャンバス素材で4点でしたが、今年はエンボス加工の合皮素材で3点です。一番大きいのはB5版が入るサイズで、クッション素材が使われているので、タブレットに使えそうです。小さいのの1つ(四角い方)は背面がティッシュケースになってます。一番小さな半月型のは小銭入れにぴったりです。いずれも作りはしっかりしていますが、素材の経年劣化が進むとヒビが入るかもしれません。
ほか、ムーミンのシール(ぷっくりしたもの)と付箋がついています。個人的には、ニョロニョロの姿が見当たらないのがやや淋しいです。
本誌は北欧特集。陶芸家のリサ・ラーソンを招いての座談会などが掲載されています。リサ・ラーソンとアストリッド・リンドグレーン(童話作家)はとても仲がよかったそうです。それと、今でこそ「憧れの福祉国家、北欧」のイメージが定着していますが、リサ・ラーソンが働き出したときはまだまだ女性は大変だったということが語られていたりもして、読み応えのある記事です。
というわけで全体的に充実した内容です。興味がある人は、売り切れる前に入手を。
2018/05/29 08:54
「わかり合えそうな同種ほど……」
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「わかり合えそうな同種ほど
わかり合えないことのダメージが大きい
同種は私の世界を脅かす
近寄らない
臆病なのだ」
……という事情で好戦的な猫。
それが「私という猫」だという。
野良として生きる「猫」は、同種の猫たちとも深く関わろうとしない。
それが変化を見せる。
人間を題材にして書いたら、きっととてもシリアスになること。
でも流れるように変化していく。猫だから。
そうして作品は、猫たちの中へとはいっていく……
猫を可愛く描こうとしていない、力のある絵が気になって、
普段マンガはあまり読まないのですが、買ってみました。
主人公の猫、その子供たち(親離れしたものたち)、
ボス猫、美しっぽと呼ばれる猫、
見た目は怖いが中身は乙女な猫、
人に飼われている猫、人に捨てられた猫……
キャラの立った猫たちの織り成す猫社会の物語。
職場の近く、ビルの立ち並ぶ街で猫たちが声を張り上げているのが
ときどき聞こえます。
そこにいる猫の中には、人間の姿を見るとパニクって逃げるのもいれば
餌をもらうときだけ出てくるのもいるし、
かわいがってくれそうな人にはすりすりしてくるのも、
旺盛な好奇心を隠せずカバンの中に顔を突っ込むのもいます。
ひょっとしたら、立ち並ぶビルのすき間で展開されているのは、
こういう物語なのかもしれません。

ねぎのレシピ
2017/10/21 20:24
うまみ野菜・ねぎ
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ないと困るねぎ類ですが、使い切るのが大変です。長ねぎを1束買っても使い切れず、万能ねぎも使い切る前にしおれてきてしまい、たまねぎは一度買うと2ヶ月もつ……何よりレシピがマンネリなのですよね。
そういうとき、ねぎ類だけに特化したこのレシピ本はお役立ちです。長ねぎで30種類以上、万能ねぎとたまねぎがそれぞれ20種類以上のレシピが掲載され、最後に「ねぎみそ」、「ねぎ塩」のような調味料のレシピが添えられています。レシピは和風・洋風といった分類なく掲載されていますが、何となく主菜・副菜・汁物・ごはんものがグループ化されて並べられており、よい編集だと思いました。
長ねぎを単に素焼きして塩とオリーブオイルでいただくレシピを魚焼きグリルで作ったところ、料理らしいことは何もしなかったにもかかわらず、うまみたっぷりでとてもおいしくいただけました。私が料理下手なだけかもしれませんが、あまりいじくり回さないほうがおいしくなるお野菜なんですね。ところどころ掲載されている一言コラムみたいなの(フライパンの使い方のコツなど)も役立ちます。
食材についてのうんちく系解説がなく、ストイックさを感じさせるようなレシピ本です。電子書籍化もされていますが、紙の本は使われている紙の素材感もよく、気分にゆとりができるような本です。

江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統
2018/09/22 19:09
4年後の視点から
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
もう4年になるのですね……今年(2018年)、同じ著者で別の出版社(筑摩書房)から『オカルト化する日本の教育 江戸しぐさと親学にひそむナショナリズム』という新書(ちくま新書)が出たので、改めて発端となった『江戸しぐさの正体』も読み直してみました。
「江戸しぐさの正体』は、「江戸しぐさ」なる虚構(フィクション)を丹念に検証し、その始祖である芝三光という「反骨の知識人」(というか「ちょっと独特なおじさん」)や、芝氏亡き後に芝氏の思っていなかった方向に「江戸しぐさ」を広めて・広げていく越川禮子氏、そこに飛びついてきたNPOや自称「保守」的教育関係者といった人びとがどういう思想を持ちどう行動してきたかを丁寧に述べて、1人のいわば「江戸マニア」の脳内にだけ存在していた架空・虚構の「江戸」が、いかにして「歴史的事実」に仕立て上げられていったかがよくわかる力作です。
一方で、越川氏が「江戸しぐさ」に関わるようになる前にはまっていたアメリカの先住民(アメリカ・インディアン)にまつわる言説のことは、『江戸しぐさの正体』ではあまり踏み込んでいません。
「ホピ族のおしえ」、「先住民の叡智」的な「インディアンもの」が書店の売れ筋だった時代は確かにありましたから、著者の原田氏にとっては、越川氏が傾倒した思想の内容は説明するまでもない自明のことだったのかもしれませんが、「アメリカ・インディアン」と「江戸」がなぜつながるのか、『江戸しぐさの正体』ではいまひとつつかみきれませんでした。
その点を補っているのが、4年後の2018年に出たちくま新書の『オカルト化する日本の教育』です。「先住民」性の持ち上げという現象について知りたい方にはこちらも併読をおすすめします(原田氏の元々の研究分野もそちらですよね)。
『江戸しぐさの正体』の内容は、大筋のところは、『オカルト化する……』の最初の章に含められていたので、2018年の今から読むなら、『オカルト化する……』ではいまひとつ具体的でない個々の「江戸しぐさ」の奇妙さ、珍妙さについて知るために『江戸しぐさの正体』を読む、という流れになるかもしれません。
いずれにせよ、「『江戸しぐさ』は直ちに教育現場から追放すべきである」という2014年の著者の明確な主張が、4年後の2018年になってもなお繰り返されねばならないというのが、日本の現実です。むしろ、事態はより深刻化している。
『江戸しぐさの正体』は、「トンデモを笑う本」として楽しんで終わらせてはいけない1冊でしたし、出版から4年後の今もそういう存在であり続けています(残念なことに)。
194ページから引用します。
「フィクションを現実にあった事柄として教えるのは、結局虚偽である。虚偽に基づいて道徳が説けるものだろうか。……また、虚偽によって人々を自分の主張に誘導するというのは、ファシストがよく使う手口である。『江戸しぐさ』の実在は虚偽だと知りつつ、自分の考える道徳に教え子を誘導するのに便利だから使うというのは、ファシズムに抗するどころか教師がファシストに近づく第一歩になりかねない」
これは2018年の今、さらに切実になっていないでしょうか。
2018/05/14 04:03
とても楽しめる短編集
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本でも大変話題になったドゥニ・ヴィルヌーヴの映画『メッセージ』(原題はArrival)の原作「あなたの人生の物語」をはじめ、全8編から成る短編集。
個人的に一番好きなのは表題作ですが(映画化されたストーリーもよかったですが、映画ではかなり脚色されています)、「七十二文字」のどんどん展開していく感じも好きです。「地獄とは神の不在なり」での、いわば西洋のオーソドックスな精神世界にひとひねり加えた物語も楽しめましたし、「バビロンの塔」の折り畳まれてぐるっと戻ってくる感じも小説を読む体験の楽しさを改めて示してくれています。「顔の美醜について : ドキュメンタリー」は、設定は(今のところ)現実離れしているにせよ、妙にリアルです。
この「妙にリアル」という印象は、全体的に共通しています。「妙に」というより「奇妙に」というべきかもしれませんが。
翻訳は、公手成幸さん(表題作と「理解」)、嶋田洋一さん(「七十二文字」)、古沢嘉通さん(「人間科学の進化」、「地獄とは~」)と、浅倉久志さん(上記のほかの3篇)。
著者のテッド・チャンはたぶんきっとものすごく凝り性の人なのだろうなと思います。1篇1篇エッジが立っていて、どれを読んでもそれぞれ違うふうに楽しめますが、共通しているのは「知的」であるということ。決して小難しく書かれているわけではないのですが、自然と集中して読むことになるので、本を置いたとき、ふと「ああ、頭使ったなあ」という感覚になります。

常備菜 2 冷蔵庫から出してすぐにおいしい、ごはんに、お弁当に役立つ、作りおきおかず111
2016/11/20 19:36
安心のレシピ本
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
地元の文教堂さんでもずっと平積みになっている「常備菜」のレシピ本、第二弾。
第一弾は「よくある定番の常備菜」が多かったのですが、
第二弾はより新しい感じがします。
難しいことをしようとしていないのは第一弾も第二弾も同じで、
外食で出てくる「かきのオイル漬け」のような一品が、案外簡単に自分でも作れます。
レパートリーの幅がぐっと広がりますよ。
ある程度料理をしなれている人で、今から「常備菜」本を買おうかなという人は、
5年前に出た第一弾より、こちらがおすすめです。
逆に、料理をあまりやらない人は、まずは定番を作れるように、第一弾がおすすめです。

このあとどうしちゃおう
2016/11/20 11:53
「死」を受け入れるために
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
いくつになっても、親しい人、身近な人の「死」を受け入れることは難しいものです。
私の祖父が他界したのは何年も前のことですが、それでも難しいものです。
お通夜・葬儀は、親戚と久しぶりに再会したりして騒いでいるうちに終わってしまい、
「死」が実感されるのはその後です。
そういうときに、こういうノートが発見されたら……と考えるだけでも、癒しになります。
ヨシタケさんのあたたかみあふれる絵柄と、おじいちゃんの俗っぽさが合わさって、
実に秀逸な絵本です。
個人的には、「歌の上手い神様」が最高です。

英語類義語活用辞典
2020/01/26 02:03
古典的名著
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
名著です。同時に古典的です。そういう「古典的名著」の価値が分かる人ならば、そういうものとして書棚に置いておいてぱらぱらめくれば、めくるたびに新たな知見が得られるでしょうが、単に「名著」という評判だけを聞いて実用的な本を求める人には、残念ながら、向かないと思います。
自分がこの本を使えるかどうかを判断するには、340~342ページのstandardとcriterionの解説を見てみることをお勧めします。偶然ですがまさにこの項が「基準」となる一冊です。例文も含め、この項目が理解できれば、この本は書棚に常備しておいて損にはならないでしょう。
ただし、約40年前の本ですから(オリジナルが出たのは1979年。文庫での再刊は2003年)、今の社会の中でのことばの実態・リアルさとはずれてしまっているところもあります。40年前のさまざまな言葉の語感を知らない若い世代の方には、あまり向かないかもしれません。例えば「エキサイトした新聞記者」のような、今は廃れてしまったような言葉遣いがなされている箇所があります(全体から見ればごくごくわずかですが)。
それでもなお、そういった移ろいにかかわらず確固としてぶれずにいる部分もことばには多くあります。例えばidleとlazyの違いの簡明な解説(200~201ページ)がその一例で、これは一度読んだらしっかりと頭に入るようなスッキリした解説です。他方でpowerとstrengthの違い(276~278ページ)は、年月を経て読者の側の知識が増えたころに再度読み直すと、さらに知見を広げることができる深い解説です。
この本で引用されている英文と解説を見て、「これが書かれた当時はこうだったのかもしれないが、今はどうなのだろう」と思ったら、インターネットで調べればよいでしょう。最所フミさんの時代は得られなかったような道具とリソースを、私たちは日常的に手にしているのですから。
電子版も出ており、紙版より安く買えるようですが、この本はまず紙版を入手して、「ぱらぱらとめくってみる」、「通読してみる」という使い方をした後で、必要なら検索自在な電子版を買うようにしたほうがよいでしょう。最初から電子では、この本の長所は引き出しづらいし、何よりユーザーとして使いづらいのではないかと思います。