ナミさんのレビュー一覧
投稿者:ナミ
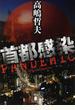
首都感染
2016/11/26 10:20
良き意味での“サムライ”の話でした。
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
良き意味での“サムライ”の話でした。素晴らしいの一言。ただ、少々気になる点を挙げるなら、中国が悪者過ぎる(まあ、実際にそういう国なんだから仕方ないが)ことと、日本が格好良すぎるというか、現実にこんな“サムライ”がいないだろうというのが悲しい。
確かに、新型インフルエンザのパンデミックを扱ったものではあるが、それに対する態度が正に毅然としており、理想的な“サムライ”の姿勢のように私には見えたのである。現実に、このような致死率が異常に高く、変異速度の早い(耐ワクチン型のウイルスが速やかに出現してくる)ウイルスがパンデミック(感染)を引き起こしたなら、このような既然とした政策を実行できる人物が複数いなければ日本は全滅してしまうだろうな。いやはや、怖い作品でしたが、毅然としたヒーローの格好よさと、それを取り巻く人間物語に感動させられました。
高嶋哲夫の作品は、『ミッドナイトイーグル』(2003)で注目し、その後『M8』(2004)、『命の遺伝子』(2007)などかなり読んでいるが、ハズレのない秀作揃いでした。

収容所から来た遺書
2016/11/26 10:33
感動しました。
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
感動しました。前半は、むしろ淡々としたソ連での抑留生活の描写であり、ソ連の理不尽さや仲間を売ってでも自分は助かろうとする同じ日本人抑留者へのいきどおりを感じる程度であるが、後半になるとそのような逆境の中でも正義を信じて自分らしい生き方を貫き通した主人公・山本幡男の強さに涙を誘われる。そして、そうした生き方に賛同し、それを支えた同胞たちの努力にも敬意を表したい。山本幡男が呼びかけたアムール句会に集まった人々を観ると、優れた軍人は優れた文化人でもなければいけないとつくづく感じさせられる。さて、山本幡男なる人物像は下記のとおりであるが、むしろ共産主義思想家で、かつロシア文化にも造詣の深かった山本が、「反共」「反ソ」思想の持ち主として過酷な戦犯としての抑留生活を強いられたことに時代の矛盾・不幸を感じると同時に、ソ連型共産主義=スターリン体制の異常さを伺わせる。
なお、著者である辺見 じゅんはむしろ歌人として有名な人らしいが、本書を読む限り綿密な取材を通じて素材を完全に消化し、それを再構成することにより物語性も兼ね備えた“ノンフィクション小説”に仕上げており、小説家としての実力もかなりのものとみえる。残念ながら、2011年9月21日に逝去している。

闇に香る噓
2019/03/23 22:51
緻密な構成に裏打ちされた謎が謎を呼ぶ展開に脱帽です。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
緻密な構成に裏打ちされた謎が謎を呼ぶ展開に脱帽です。人格自体を特定することが困難な満州残留孤児(引き揚げ者も含む)を対象とし、更に謎を解明すべき主人公を視覚障害者とすることで、謎を更に根深いものとして描くことに成功している。周囲で起きている事象を的確に認識・判断することの困難さから、主人公がどんどん疑心暗鬼に陥っていく心理描写も凄い。そして全編を通じて貫かれる国を超え、家族愛すら超越した人間愛に感動でした。中国側からみたら何を日本を美化してるんだと言われそうですがね。こんな人達がもう少し沢山いれば戦争なんて亡くなるだろうになあ。いや、そんなことより単なる推理小説としても実に素晴らしい出来でした。流石、第60回(2014年)江戸川乱歩賞受賞です。

すべてがFになる The perfect insider
2017/09/23 12:26
またも一気読みに近い面白さでした。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
またも一気読みに近い面白さでした。真賀田四季博士と西之園萌絵との不思議な緊張した面会場面の後、犀川博士と萌絵との奇妙なコンビのやりとりを経て、一気に不穏な殺人事件へ導入。あとは密室殺人事件を中心に謎解きだが、謎解き過程を科学的・哲学的議論でオブラートに包んで読者の推理する楽しみを最後まで残している。確かに、謎解きのヒントは各所にちりばめられてはいるのだが、決定的なヒントが見つからない。萌絵がかなり良い線までの謎解きを細目に出していくのに対して、主役の犀川博士は最後まで殆ど自分の推理を明かさないやり方はちょっと狡い気もするが、読者の推理する楽しみを最後まで残すという意味では仕方ないのかな。そして、最後で一気に謎が解き明かされるのだが、674:『笑わない数学者[3]』同様、真犯人がどうやら消えてしまうという謎めいた終わり方である。
<以下、蛇足>本作品の初出は1996年というから私がWin95を導入して、インターネットを始めた時期である。よって、PCに対してWS(ワークステーション)という言葉?機械?(笑)が出て来りして時代を感じさせる。その当時、VR(バーチャルリアリティ)は20年位先の技術として考えられていたが、天才科学者にとっては既に基本構想は描かれていたのであろう。本作品では、極めてリアルにVR装置が登場し、活用されているのである。先見の明に感服。

ロスト・ケア
2016/12/09 09:21
高齢者問題を取り上げた作品は多々あるが、本作は綺麗ごとでは済まない現実的視点から出発し、遅れている高齢者対策という社会問題にまで切り込んだ問題提起をも含むものとして興味深い。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
注目の新人登場です。高齢者問題を取り上げた作品は多々あるが、本作は綺麗ごとでは済まない現実的視点から出発し、遅れている高齢者対策という社会問題にまで切り込んだ問題提起をも含むものとして興味深い上に、推理小説としても面白い構成となっていることが注目される。2013年の第16回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。次作『絶叫』(2014年10月、光文社)も楽しみです。
物語は、関係者個人の行動を時系列的に追う形を取っており、高齢者大量殺人犯も<彼>という形で早い時期から登場し、煙草から抽出したニコチンを注射する殺害方法はもとより、対象者の選定方法・基準や、生活環境を克明に調査したうえでの実行方法まで明かされる。これでは推理小説としても面白味は半減してしまうのではと思われるが、いえいえ、まずその動機・目的、<彼>とは誰か、どういう経緯でこの「完全犯罪」が露見して<彼>が捕まるのか本作の肝である。<彼>に関しては、中盤辺りで極めて怪しい人間として介護事業所長・団啓司が登場してきて、<彼>の車・外見などの状況証拠から99%犯人と思われてくる。しかし、この手のお話の例にもれず、それでは余りにも単純すぎる。そこで気になりだすのが、かなり早い時期から主要な役割も無いのに登場し続ける所長・団と同じ介護事業所職員・斯波宗典であるが、どうにも犯人像と結びつかない誠実な真面目人間なのである。一方、本作の主役である検事・大友秀樹がひょんなことからこの高齢者大量殺人事件に気付き、犯人をも割り出してしまうのが中盤から終盤への結節点である。終盤では、ある高齢者宅の鍵を複製した人間がいることに気付きその犯人を明らかにするため介護事業所職員・斯波宗典が張り込みを始めることで、犯人=所長・団という推理が確定してしまうのだが、何と、検事・大友秀樹が割り出した犯人は職員・斯波宗典であった。さて、このどんでん返しが実に用意周到でやられたって感じです。まあ、狡いとも言うか。(笑)さて、ここで終わってしまえば実に良く出来た推理小説でしたで終わってしまうのだが、犯人・斯波宗典の犯行動機・目的が本書の価値を非凡なものとしている。本書では登場人物がそれなりの役割を持って配置されており、冒頭からの登場順では、まず<彼>は当然犯人であり、次いで羽田洋子、斯波宗典=<彼>、佐久間功一郎(大友に事件のヒントを与える役割)、大友秀樹(検事)であり、介護事業所長・団啓司はかなり後での控え目な登場である。(この辺りにも気づくべきであった。)
でこの登場人物配置は、本作の主題である高齢者大量殺人の意味を問う、検事・大友秀樹と犯人・斯波宗典とのその動機・目的の意味を問う熾烈な戦いを描くことにあったのである。出番の少ない羽田洋子は被害者親族の気持ちを代表する役割として配置され、ある意味で事件によって救われたという思い、実際に人生を再出発させることが出来るという形で現実的矛盾を表出する。死刑という罰は確定しつつも、その罪を認めさせることが出来ない検事・大友秀樹が辿り着いた犯人・斯波宗典の真の目的とは、私の直感を要約するなら「救いのない高齢者対策に一つの解決方法という壮大な物語を作り問題提起をしていくこと」となる。このことを、著者は福音書のキリストが息絶える場面の記述を引用して表現している。(361P)
結末の是非に関しては緒論あって当然であるが、推理小説としても強烈な問題提起の書としても一級品であることは間違いない。

パラダイス・ロスト
2016/12/07 10:34
期待を裏切らない面白さでした。注目したいのは、3話「追跡」である。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
期待を裏切らない面白さでした。短編であるので要点が明確だし、読んでいても集中力の続く内に完結するのも良い。さて、シリーズ3として注目したいのは、3話「追跡」である。イギリスの新聞記者であるスパイが、D機関の“魔王”こと結城中佐の実体に迫るのだが、逆に結城中佐の罠に嵌ってスパイとしての自分の身分を暴かれてしまい、もっとというより最悪の事態として、これまで日本国内で作り上げてきたスパイ網(アセット=資産)情報まで奪われてしまう。多分、結城中佐の側では、彼が周囲を嗅ぎまわり始めた瞬間から彼を無力化すると同時にアセットの“乗っ取り”を画策したという筋書きと推測した。彼は、限り無く結城中佐の実体に肉迫したと思うのだが、それに目を奪われてもっと大きなゲームに敗れたと言ったところか。あのジョン・ル・カレが膨大な紙面を使って描き出す世界を短編で楽しませてくれるのだから堪らない。
更にもう1作は4・5話「暗号名ケルベロス 前・後編」である。まず、珍しく120ページだから中編と言うべきことと、その内容である。要は、アメリカから日本へ向かう客船の中で、ドイツのエニグマ暗号の秘密を解き明かすため日本へ向かう英国情報部員とD機関の戦いが主題なのだが、そこへエニグマを盗むために忙殺された船員の妻が敵である英国情報部員を殺害するという横槍が入ると筋書きである。結局、D機関員の鋭い推理で犯人は捕まるのだが、その際、自決を覚悟した妻から“幼女”と“愛犬”を託されてしまう。存在しない存在であることを旨とするD機関員にとって、現実の存在である“幼女”と“愛犬”を託されるということは大変なことである。今後の展開が気になる。なお、本編では、欧州での第二次世界大戦が熾烈さを増しつつも、日米開戦はまだでアメリカも参戦していないという微妙な状況下で、大西洋航路と参戦国間の交流が途絶えている中で唯一残った交流路である太平洋航路の微妙な状況が描かれている点が興味深い。
さて、この『ジョーカー・ゲーム』(2011)でスタートした短編集は、『ダブル・ジョーカー』(2014)で終わったと思っていたのだが、どうも好評につき [ジョーカーゲームシリーズ]として継続されるようである。既に4作目である『ラスト・ワルツ』(2015年1月、角川書店)が発刊されている。なお、ウィキペディアでは、本シリーズを「D機関シリーズ」と称しているので私もそれに倣うことにする。

古代日本の超技術 あっと驚くご先祖様の智慧 改訂新版
2016/11/17 10:01
日本人の素晴らしさを改めて認識させてくれる秀作。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本人の素晴らしさを改めて認識させてくれる秀作。無機材料工学専門で永らく半導体結晶の研究に従事してきた著者が何故こんな本を書いたのかと不思議に思って読み始めたのだが、優れた研究者というのは鋭い観察眼・広い好奇心・様々な知識を総合的に駆使しうる能力において優れているのだなと感心させられた。研究の関係で訪問した先々でその国特有の技術=“技”に着目し、それを自らの趣味?と結びつけて科学・技術的に追求した結果が本著書であった。
著者はまず、五重塔の心柱の耐震・耐風機能につき解析し、続けて「木」だけで石よりも長持ちする建築物を実現してきた「木の文化」「木の文明」の素晴らしさを説くとともに、木の加工技術の優秀さを現代の半導体結晶の表面加工技術との対比で説明する。ついで、木造建築物の耐用年数を更に高める役割を果たす「瓦」の特長を解明し、更に、1000年以上も朽ちずに使用可能な釘の材料である「たたら鉄」から、世界に類を見ない「折れず、曲がらず、よく切れる」を実現した“日本刀”にまで及ぶ。更にはひょんなことから関心を持った奈良の大仏の銅の産地や、銅の鋳造方法まで話は広がり、終いには、縄文時代の代表的装身具であった翡翠装飾品の“穿孔技術”の素晴らしさを現代の穿孔技術との比較で明らかにする。
こうした一連の話の展開は、全て著者の鋭い観察眼・広い好奇心・様々な知識を総合的に駆使しうる能力に裏打ちされているのだから面白くない訳がないのである。いやはや、驚きの一冊でした。
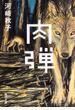
肉弾
2020/09/27 13:35
一青年の成長を自然界と人間との関わり合いの中に据えた力作。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
一青年の成長を自然界と人間との関わり合いの中に据えた力作。特に後半の自然のなかで生き抜くための戦いと、青年の成長過程の描写は手に汗握る迫力。文系出身の著者が自然の成り立ちや野生動物の生態などもしっかりと勉強した姿勢には、羊飼いを止めて専業作家に転向した気概が放射されていて好感が持てる。動物と人間の両方の視点からの作風で登壇した作者。更に自然、動物に切り込んだ作品に期待したですね。

首都崩壊
2017/12/11 11:04
東京大地震による首都崩壊と単純に考えていたが、主題は一歩進んで「首都移転問題」に道州制まで絡めた日本再構築の話でした。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
東京大地震による首都崩壊と単純に考えていたが、主題は一歩進んで「首都移転問題」に道州制まで絡めた日本再構築の話でした。その後押し材料として、東京直下型大地震を用いたのはちょっと気に入らないけど、必要性は認識しつつも、各人各様の思惑で遅々として進まない物事を一歩進めてみる為の引き金としては仕方ないでしょうね。更に、世界支配の野望を秘めて暗躍を続ける中国の動きを適切に絡め、今や車の両輪となっているアメリカと日本の関係を描いて見せた、ある意味で日本再生小説とでも言えようか。
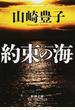
約束の海
2017/12/11 10:52
現実を冷徹に見据えた社会派作家として気になっていた著者の未完遺作。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
現実を冷徹に見据えた社会派作家として気になっていた著者の未完遺作。1988(昭63)年7月23日の“なだしお事件”が題材ということで、自衛隊の存在を問う話かなと思ったが、著者が残した全3部からなる「構想メモ」を見て、もっと深い内容だと知った。それは、著者の執筆にあたって」(2013年7月)に明確に記載されている、「戦争をしないための軍隊」(378)という思想である。89歳という高齢と、疼痛症(筋筋膜性疼痛症候群)という難病を抱えながら、実に難しい問題に正面から立ち向かった著者の熱意に頭が下がります。是非、完結した作品を見たかった反面、この問題は日本国民全てが考えるべき問題であり、巻末に収録された<『約束の海』、その後;P-383~P-411>という、山崎プロジェクト編集室&秘書:野上孝子氏などがまとめた、今後の構想予定から自分なりに考えてみる方が良いのかも。
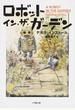
ロボット・イン・ザ・ガーデン
2017/09/25 08:12
ポンコツロボット“タング”と無気力駄目男“ベン”の珍道中から思わぬ結末に発展していく面白さ。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ポンコツロボット“タング”と無気力駄目男“ベン”の珍道中から思わぬ結末に発展していく面白さ。前半は少々冗長でイライラしたが、後半は一気読みでした。構成は大きく3つに分けられる。ポンコツロボット“タング”の登場で既にきしんでた家庭が崩壊、離婚して珍道中に出た導入部。徐々に、タングの謎が明かされて家族として生きることを決意する中間部。そして、旅を通じて成長したベンが、人生再生の手掛かりを得ていく結末部である。子供の成長と、それに伴う親の成長の物語とも重なって見えて来る。前半部は4点かなと思ったが、読み通して5点とした。
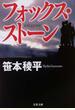
フォックス・ストーン
2017/05/24 09:04
空間的広がりの大きさ、複雑に構成された壮大な謎に満ちた物語に魅了されました。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
空間的広がりの大きさ、複雑に構成された壮大な謎に満ちた物語に魅了されました。日本からアメリカへ、そして主要な舞台であるアフリカへと収斂していく物語は驚くべき謎に満ちている。我々が知る機会の少ないアフリカの紛争事情は実に興味深い。アフリカという地域事情を背景とする壮大な陰謀は緻密に計算された構成で、その謎解きも魅力である。初めの内は過去の人として語られるボブ・ショーニングが、物語が進むにつれて重要なピースとなりはじめ、最後にボブ・ショーニング=“ケープフォックス”=オコネル刑事という複数の存在としてパズルの最終ピースになる結末は見事である。ただ、「アフリカ人のためのアフリカ人による理想国家を作る」というボブ・ショーニングの一見正しい理想と、その実現のための方法論との齟齬が何時、何処から狂い始めたのかが気になりました。山岳関係を得意とすると誤解していた笹本稜平の初期の探偵?スパイ?陰謀活劇?として期待した作品でしたが、期待以上の面白さでした。

絶叫
2017/05/24 08:52
壮絶の一言。
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
壮絶の一言。保険金連続殺人事件だが、そこに至る家庭の不幸、一度捕えられたら抜け出せない闇の社会の描写に圧倒される。主人公:鈴木陽子は憎むべき存在の筈なのに、何故か憎めない。陽子は、結局、完全犯罪を達成して別人として生まれ変わる。逃れられない宿命に囚われた一人の人間が社会の闇から抜け出して再生する、成功物語として読める為だろうか。犯罪は悪いことだと思いつつ、つい陽子に拍手したくなる結末でした。
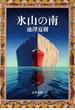
氷山の南
2016/12/07 10:11
氷山曳航計画の話かと思ったら、どうもアイヌ系一青年:ジン・カイザワが大人に成長していく哲学的物語でした。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
氷山曳航計画の話かと思ったら、どうもアイヌ系一青年:ジン・カイザワが大人に成長していく哲学的物語でした。大半は氷山曳航計画を担うシンディバード号の船内とその乗組員と曳航される氷山“箱船”との話であるが、後半でオーストラリアの原住民アボリジニの青年:ジム・ジャミンジュンとのグレゴリー国立公園での日常が描かれる。哲学的・精神的物語はあまり私の得意ではないのだが、氷山曳航計画や曳航される氷山“箱船”の話は具体的で興味深いし、氷山曳航計画に反対する拝氷教集団“アイシスト”は謎めいていて緊張感を与えている。しかし、これといって大事件が起こる訳ではないのだが、しっかりとした展開で全く飽きさせない。394:『真昼のプリニウス』(1993)では、「どちらかというと哲学的な話に収斂してしまい、徐々に退屈さを感じざるをえなかった。」ということで低評価だったが、本作で俄然名誉挽回でした。「理系知識を加味した哲学的評論」を強みとするらしいこの著者も注目株です。

女ことばと日本語
2016/11/28 09:56
流石、学者の著作だけあって面白さに加えて参考になる情報がてんこ盛りでした。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
流石、学者の著作だけあって面白さに加えて参考になる情報がてんこ盛りでした。古代の宮廷の詞や女房詞、遊里などで使われた遊女語など言語学的な流れは当然であるが、「女ことば」が本当に定着・意識されるようになるのは江戸時代からであり、その後の流れ、特に戦中・戦後の時代背景の中で「女ことば」に対して、政治戦略的な観点から新しい意味づけがなされていく過程の分析は実に興味深いものであった。たかが「言葉」と思っていたが、その深い意味に実に驚かされた。「女ことば」があるという世界にも珍しい言語である日本語の素晴らしさとして、小説においても会話者が男であるか女であるかが明確に判るという指摘には目から鱗でした。末尾の方でそうした観点から小説論にも触れているのも面白かった。

