読人不知さんのレビュー一覧
投稿者:読人不知
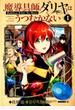
魔導具師ダリヤはうつむかない 1 ~Dahliya Wilts No More~ (BLADE COMICS)
2021/12/16 02:04
コツコツ努力を重ねるものづくり系異世界転生
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まず表紙絵で、異世界ファンタジーっぽいのにドライヤーがある……? と困惑。内容を読んで納得。
前世知識は魔導具開発のヒント程度で、チートなし。
主人公のダリヤが失敗とそれを乗り越える努力、周囲の助力を重ねてものづくりにコツコツ取組む姿にグッときました。
父の親友の息子トビアスと婚約。双方の親が良かれと思った縁組だったのに……
自分の低身長コンプレックスをやんわり主張してダリヤにヒールの高い靴を捨てさせ、人前で酔うとみっともないからと飲み会に参加させず、怪我をされると外聞が悪いからと自由な研究開発を抑制し、化粧品を捨てさせ、元の赤い髪を地味な色に染めさせ、服も地味なものに変えさせる。
少しずつ、少しずつ、真綿で首を絞めるようにダリヤの自由と笑顔を奪ってゆく。
茹で蛙系DV野郎。
それがトビアス。
逆にトビアスは、ダリヤと共に在る為に何を変えたのだろう。
その後も次々飛び出すクズ野郎エピソードに変な笑いがこみ上げてきました。
よいこのみんなは男女問わず、リアルでこんなゴミに引っ掛からないように、ダリヤがされたのと似たことをされたら、さっさと逃げましょう。
トビアスと浮気相手以外の登場人物が、みんないい人なのが救いです。
騎士ヴォルフレード、よく生きてたな……
自分の道は自分で照らす。ダリヤさんの人生に光あれ!

四畳半神話大系
2019/11/04 01:14
幾度繰り返そうとも変わらない芯がある
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人生は選択の連続です。
人は誰しも「あの時、あちらを選んでおけばよかった」と後悔と共に選択の誤りを振り返る瞬間があります。
本書には、「あの時、あちらを選んだ」分岐ルートが幾つも登場します。
どのサークルを選んでも、関わるメンツはどのルートでも同じ。
関わり方の程度や種類、立ち位置が変わっても、主人公の「私」の性格や行動原理が変わらない為、なんともアレな展開は避けようもなく。
実は「私」の目を通して見た小津君こそが主人公なのではないかと錯覚する程、小津君の活躍と関与、影響力は大きく、これこそが運命の出会いと強力な縁(えにし)であって、分岐ルートに見える選択肢の数々は、ほんの些末事に過ぎなかったのだと掌の上で転がされた気分になります。
全体を通しで読んで、再読すると、人の縁の奇妙な力に思いを馳せたくなる多重構成です。
読めば読む程、主人公のアレな性格が浮き彫りになり、悪縁奇縁に絡めとられた周辺人物たちの幸せを祈らずにはいられません。

拾い猫のモチャ 1 (KITORA)
2018/12/24 20:46
猫飼いの幸せが詰まった一冊
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ツイッターで連載を追っている猫四コマ。
にゃっとしてニヤっとする猫飼いあるあるが詰まった幸せな一冊。
どこが好きって全体ですよ。
モチャの仕草や表情のひとつひとつが、在りし日のウチのコに重なって懐かしい気持ちになりました。
四コマの一本一本が実話かと思うくらいリアルで、どこからウチのコを見てたんだろうと思うコマもありましたが、この漫画はフィクションです。
オスの三毛猫モチャはどこにも居ませんが、毛皮の色は違っても、猫好きのみんなの心に住む大切なあのコの化身かもしれません。

古武術の発見 日本人にとって「身体」とは何か
2017/04/15 03:27
二方向から「身体」を再認識する対談集
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
武術研究家の甲野氏と「バカの壁」などの著書で知られる解剖学者の養老氏の対談集。
ふたつの観点から、身体感覚を読み解く。
専門的な話題が多いが、対談集なのですらすら気軽に読み進められる。
明治維新後、西洋式の鍛錬や洋服の導入などにより、日本古来の体捌きが廃れて久しい。
服装による動作の制限など、何気ない変化が身体の動きを変え、心身をも変えてゆくなど、ハッとさせられる気付きが多い。
稽古で組み上げられた型を敢えて崩し、再構築した体術。
スポーツの世界では、単一基準での評価に特化した強力な動作が評価される場面が多いが、日々の生活など実際の必要に迫られる場面では、そんな単一の力が求められることは、ほぼない。「単線の物差し」では測れない成果の綾について、考えさせられた。
例えば、足の遅い人でも人混みに紛れ、他人との衝突を回避して移動できれば、追跡者の速度を落とし、自分の姿を隠して逃げ切ることができる。この状況では、百メートルを九秒で走る脚力は必要ない。生きる為には、総合力が必要だとの想いを得た。
宮本武蔵など剣豪の逸話や現代でスポーツ化した武術からも身体性の変遷を読み解き、腰を痛めない介護の動作など、現代の生活を楽にするヒントも与えてくれる温故知新の書。

命売ります
2021/10/13 00:58
SAN値が削られる三島由紀夫のエンタメ作品
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
次々と現れては消えてゆく登場人物が、誰も彼も常軌を逸した癖者揃い。
勿論、主人公の羽仁男もその一人で、物語は何となく電車内で死んでみる試みから始まる。
死を試みた経緯も筋が通っているようでいて、納得したが最後、読者が人として終わりそうな危険な色を帯びる。
死に損なった羽仁男は、景気のいい会社を辞め、新しい商売を始める。
それが「命売ります」
客たちの「他人の命の使い途」の異様さ、その値段も様々だ。
金と女に不自由せず、生命を売りに出し、危険を顧みない非日常の大冒険。
中高年男性の夢を詰め込んだようなハードボイルドな展開に様々な毒が忍び込む。
一見なんの繋がりもないようでいて、実はある一点で繋がる。次第にその糸と意図が見えてくる様がミステリ的で味わい深い。
本筋とは関係ないが、学生服姿の薫少年の言動が幼く、小学校高学年くらいの子かと思いきや、高校生だったことに驚かされた。
時代的に金持ちのボンボンの平均像なのか、敢えて幼く描かれたのか不明。
現在では差別的な表現なども散見されるが、作品が描かれた時代背景を読み取る為、出版社の判断で敢えて残してある。
読む際には、それを念頭に置くと昭和中期の空気感を味わえる。

天使の囀り
2019/07/28 20:09
ダイエットに最適な夏向きホラー
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ジャンル的には「パラサイト・イヴ」などのサイエンスホラーが好きな人向けだと思います。
本作では、ホラー映画にありがちな、「危険とわかっている所に何故か突入して案の定……」な展開の理由が、後半で明確に解き明かされ、成程と納得すると同時に背筋が凍りました。生理的嫌悪感的な意味で。普通のホラーとは一味違う、捻りの効いた恐怖。
人によって恐怖の根源が異なることで、物語に奥行きが与えられ、恐怖カタログ的な趣があります。
劇中に登場するギャルゲの主題歌の歌詞など、細部まで丁寧に作り込んであり、日常部分のリアリティがより一層、身近な恐怖に思いを到らせます。
私はこれを読んで、少し痩せました。
お肉はよく焼いて食べましょう。
食中毒の啓発書としても使える夏向けのホラーです。

全電源喪失の記憶 証言・福島第1原発 日本の命運を賭けた5日間
2019/07/25 23:31
最後のひとかけらの瓦礫が片付くその日まで
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
あの時、何が起こったのか。
本書は、政府の調査結果や東電の発表とは違った角度から、福島第一原発事故の経緯を読み解くカギになる。
実名でインタビューに応じた人々の証言を元に、あの時、現場で何が起きたのかを語るドキュメンタリー。
現場の尽力、福島や他の地域の人々が何を為し、何を成し遂げたのか大変よくわかった。
人・地域・仕事・責任……そんなキーワードで繋がれたヒューマンドラマでもあるが、フィクションではなく、現実に起きた出来事で、まだ何も終わっていない。
現場の社員や協力(下請け)企業、東電とは無関係の建設会社までもが、命懸けで未曽有の事象と戦った。
あの時、一旦は現場を離脱して戻った協力企業関係者がショベルカーで獅子奮迅の活躍をしなければ、高濃度に汚染されたと知りながら手作業で瓦礫を撤去し道を作った現場職員が居なければ、二号機に留まり手動で冷却装置を作動し続ける地元の東電社員が居なければ、二号機も爆発していたと知り、納得と同時に背筋が凍った。
同時に、協力企業の社員が普通の靴で地下に突入し、高濃度汚染水でベータ線熱傷を負ったことや、三重の建設会社がポンプ車の提供を申し出てから長時間待機させられたこと、ポンプ車の現場到着後の東電対応など、「東電にあらずば人にあらず」などと揶揄された残念な経緯も浮き彫りに。
当時の政府と東電本店の詳細な対応を知り、虚偽報告をしてでも冷却を続行させた吉田所長の胃の痛みが自分にも伝わった。
新聞で読んだが、通しで読むと更に状況がわかりやすくなった。
連載時にあった多数の図はかなり減らされたが、その分テキストが増え、読み応えが増した。
まだ、事故の終息作業は続く。
最後のひとかけらの瓦礫が片付くその日まで、ずっと読み継がれて欲しい一冊。
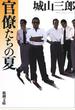
官僚たちの夏 改版
2018/12/08 23:27
温故知新で今を考える材料に
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
昭和三十年代の金融業界を巡る経済小説。
霞が関の官僚、政治家、銀行員、記者などが情報戦で駆け引きの攻防を繰り広げる群像劇です。
最近、ブラック企業が何かと取沙汰されています。
この作品を読むと、ブラック企業の経営陣や管理職は、昭和三十年代のノリのまま思考停止しているのがわかります。
家庭を顧みず、休日はなく、深夜まで働いた後、更に政治家宅で打ち合わせ……それが、勤め人の「勤勉で仕事熱心で正しい姿」とされていた時代です。
それに付き合わされて、深夜から早朝にかけて宅飲みの酒肴を用意させられる議員の妻もいい迷惑です。
これに文句を言わないのが「良き妻」とされた時代でもあります。
仕事最優先で家族は顧みられず、尊重もされず、仕事に巻き込まれて非常識な時間に迷惑を掛けられても、文句を言うことさえ許されません。
仕事を失えば存在意義を失うところまで「自分=仕事化」していた世代の悪しき側面が如実に描き出されています。
因みに、作品が描かれた時代には、これらが美徳とされていました。
時代や世相が変われば、同じ作品でも美徳が底なしの悪徳に変わる好例です。
作中で唯一人、官僚の片山氏が、定時で仕事を終えて余暇を楽しんで仕事の能率を上げると提唱し、自ら実践していますが、作中では浮いています。
官僚の片山氏は「不真面目な奴」のレッテルを貼られ、出世コースから外され、他の登場人物からは冷ややかな目で見られています。
現代の価値観からすれば、片山氏はとても有能な人物ですが、この時代はそうではありませんでした。
現在、働いている方は、片山氏以外の登場人物の台詞に注目してください。
上司や経営陣から、ひとつでも言われたことがあれば、その会社は要注意です。
人事部に一人でも、風越氏のような人物がいれば、社内の風通しが悪くなり、不正や腐敗の温床を醸成しかねません。
発言者が同僚ならば、会社のブラック化を推進し、同調圧力でまともな人材を圧し潰す「ブラック人材」です。
作中の時代から高度成長期にかけてモーレツ社員だった人たちは、仕事以外の全てを擲って突っ走り続けました。
現実の社会で、未だに会社に籍を置くこの世代の人々は、若い世代から「老害」と呼ばれがちです。
退職後は往々にして、家庭内で「濡れ落ち葉」や「粗大ゴミ」と化し、家庭の収入源でなくなった途端、熟年離婚を申し渡されることも珍しくありません。
「終身雇用」が定年退職までの幻想だったと気付かず、自らを「単なる収入源」以外に価値のない存在にしてしまった人々です。
作中の時代にはまだ、頑張れば頑張った分、見返りがありました。
しかし、その社会の未来にある「現在のリアル」は、皆さんがご承知の通りの有様です。
古きを温ね新しきを知る。
本書は、悪い意味での「昭和のニオイ」を感じ取るガイドブックになることでしょう。
これから就職活動に臨む学生さんや、転職をお考えのブラック企業勤めの皆さんに読んでいただきたい一冊です。

記者ハンドブック 新聞用字用語集 第13版
2017/03/26 21:01
情報リテラシーを高める為に、記者志望者以外にも読んで欲しい一冊
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、共同通信社及び提携する地方紙の新聞記者たちが、記事を書く際に使用するマニュアル。
つまり、新聞の書き方の本。
紙の新聞を取っていない人でも、ポータルサイトなどで、新聞社から配信されたニュースを目にする機会は多い。
どのような観点から世の中の出来事を掬い取り、どのように記事として文章化しているのか、見出しに籠められた意図や、紙面での掲載位置による情報価値の判断基準を知れば、以前とは違った観点からニュースを読み解けるようになる。
特に、若い世代の方々に読んでもらいたい一冊。
単位や国際機関の一覧など、便利な表もついている。
ネットでの検索も、予備知識を持った上で調べれば、より速く正確に良質な情報に辿り着けるようになる。
作家志望の方にとっては、ニュース部分を描く際の参考書として、重宝するだろう。

おまわりさんと招き猫 1 あやかしの町のふしぎな日常
2021/12/31 20:09
ゆるくて懐かしいかつぶし町の日常
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
かつぶし町の四季折々の出来事。
ゆるくて懐かしい雰囲気の空気が、居心地よさそうで好きです。
笹倉さんの泰然自若とした大物っぷりがいい味出していて安心感があります。
柴崎先輩は家族全員こうだったんだろうか……それならそれで、きちんとしたご家庭なので、同級生に揶揄されたことをコンプレックスに思わなくてもいいのにと思います。
現実の世界でも、真面目であることを揶揄する風潮が存在しますが、理解に苦しみます。
本来、社会の秩序を保つ長所であるはずなのに一部の人々からは、当たり前のような顔で欠点として貶され、真面目できちんとルールを守る人々が人格否定までされるのは何故なのか。
個人的に「愛想がよくて手癖が悪くルールを破る人」と、「無愛想で真面目な悪事を働かない人」が居れば、後者と人付き合いしたいですし、前者とは極力関わり合いになりたくありません。
「ノリが悪い」ことは、いじめや、犯罪レベルのルール違反より悪なのかと。
おのりさん…お互い一生忘れられない初恋&失恋だけど宝物になりそうな思い出。それもまたよし。
願っていた形とは違うけれど、これからずっと一緒に居られるのは、これもまた幸せの形だなぁと、ちょっと切なくて、でもあたたかな気持ちになれました。
町の住人が誰一人として、おもちさんの動画を撮ってネットに出さない辺りがかつぶし町の居心地の良さのひとつなんだろうなぁと思いました。
何のかんの言いつつ春川くんもそういうコトをしない。この居心地のいい空気を壊さない暗黙の了解。守りたい日常が共通認識として存在する町。
ちょい怖だけど幻想的でワクワクする行列。笹倉さんの態度に納得。おもちさんが一緒なら大丈夫な安心感。
笹倉さんが「彼ら」の間でちょっとした伝説の存在になっているのが流石の貫禄。
わだつみの岩のエピソードは、信仰の本質に触れていて、成程と納得。
小槇巡査とおもちさんのご縁は、一体いつからのものなのか。
自分の憧れの人の背中を追い掛け、夢を実現させてその先まで考えられる小槇巡査。きっと定年退職する頃には、満足のゆく仕事ができる筈。
柴崎さんにとって、あの件は神頼みレベルでハードル高いとは…強く生きて欲しいです。

魔導具師ダリヤはうつむかない 2 (BLADE COMICS)
2021/12/16 02:07
魔導具師は笑顔を生み出す素敵な職業
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
副ギルド長のガブリエラさんは神!
トビアスだけでなく、浮気相手もなかなかアレなお嬢さんのようで、割れ鍋に綴じ蓋の模様。
敢えて人目のある場所でそんな事情を声高に叫ぶマウンティング。でも、騎士ヴォルフレード君のお陰で逆に恥をかいた模様。人を害するのではなく、自分の幸せだけ見ていればいいのにねぇ。
騎士ヴォルフレードの難しい立場にちょっとしんみり。
魔道具系武器の話で盛り上がる二人。開発者とユーザで視点は違うけど、意外と気が合うかも。
オズヴァルド店長、意外とタフな精神の持ち主。
本編を読んでから、カバー下の四コマを読むとニヤッてなります。
魔道具の原理の説明も読みやすく、世界観の理解に一役買って、登場人物たちの暮らしが見えてくるのが面白いです。
父カルロの生前の善行が色々な人から少しずつ知らされて、暗くなりかけたダリヤの道を照らしてゆくのが素敵。
眼鏡があってもなくても、ダリヤはダリヤのまま。
眼鏡があってもなくてもヴォルフレードも同じ人。
眼鏡を捨てて得た自由と、眼鏡を得て手に入れた自由の尊さは同じ。
魔導具師は一見、地味な職業だけれど、必ず誰かの役に立って笑顔を生み出す素敵な職業。
製品のその先に生まれる笑顔を糧に前を向いてひたむきに努力する姿に元気をもらえました。

職業としての政治 改版
2021/08/08 19:28
民主主義の原点と責任を知る手掛かり
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書が出版されたのは、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、ソビエトやドイツで革命が勃発した時期である。
マックス・ヴェーバーが講演を行った時代背景を頭に入れてから読むと、かなり尖った発言であることが窺える。
前半は、皮肉と具体例を交えた政治史。欧州と米国の政党と議会の成立過程が語られる。
日本の国内政治に関しては、民主主義の導入過程や目的が全く異なる為、あまり参考にならないが、国際政治を見る上では、現代でも有用な資料と言える。
二十世紀前半の系譜を繙くことで、各国政府や首脳陣の選挙前の動き、選挙対策としてテコ入れする政策や、どこを向いて政治を行うかなど、見通しを立てる一助になるだろう。
後半は、書名通り、政治家の資質を語る。
現代の日本でも通じる……よく考えれば「当たり前のこと」が、政治家と、彼らを選ぶ有権者に向けて語られる。
その責任が立脚する根拠と、対象とするものは何か。
信仰などに立脚する心情倫理と、現実に即した責任倫理。
心情倫理の結果に対する無責任性と、信条と信条に基づく「絶対正義」の追及は、現代のインターネット上などで繰り広げられる炎上騒動を彷彿とさせる。
責任倫理では、人間の欠陥を考慮に入れ、自らの行為の結果に対しては責任を認識するが、世の中には責任を負いきれない重大な結果があちこちに転がる。
政治と権力は切っても切れず、国民を守る為には、右の頬を打たれても、左の頬を唯々諾々と打たれてはならないのが国際政治の世界の不文律である。
侵略から自国民を守る為には、少なくとも、右の頬を打った手を払いのけるだけの武力が必要である。
どこまでを「正統な暴力」と看做し、どこからを「倫理に悖る暴力」とするか。
その線引きは、一部の政治家ではなく、彼らを選出する有権者の良識に懸っている。
政治を他人事目線から自分自身と関係のある事柄として見る為の手引書。

復讐と法律
2020/08/23 05:43
「復讐なんてバカな真似はやめるんだ!そんなコトしても死んだあいつは喜ばない!」に対する答えが全て書いてある本
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
復讐の本質と、その抑止に関する問題の根源を取りまとめた論文集。
A「復讐なんてバカな真似はやめるんだ!」
B「お前に何がわかる?」
A「そんなコトしたって死んだあいつは喜ばない!」
媒体を問わず、フィクションでありがちな状況。
A類型の登場人物は、現代の劇中では好人物として描かれやすい。
本書には、復讐の発生機序や、「私人による復讐」が「公権力による刑罰」に置き換わる過程を「刑法進化」として取りまとめられている。
最古の原稿は百年近く前、最新でも五十年以上前に書かれた遺稿集である為、現在の理論や価値観にはそぐわない部分もあるが、大筋に於いて研究資料として、充分な機能を果たす。
民事法についても少し述べてあるが、著者の急逝により、刑法に比べると内容は薄い。だが、後学に道筋を遺した功績は限りなく大きい。
世界各地の膨大な資料を繙き、復讐の概念や、復讐が規制される過程がわかりやすい。
大抵の国や民族では、物々交換や貨幣制度の成立と、社会の集権化が進むにつれ、復讐が「治安を乱す私闘」と看做され、規制される。
しかし、日本では明治維新後の刑法制定まで、完全に廃止されなかった辺り、ガラパゴス感がある。
仇討ちを完全に廃止する為の法整備の過程や、条文の表現に関するやりとりも興味深い。
本書を読めば、復讐の主目的が、死者の魂の慰撫ではないとわかる。
復讐を抑止するには、賠償もしくは、加害者への処罰が必要である。
A類型の登場人物は好人物として描かれやすいが、刑法が成立する過程を知れば、解釈が一変する。
賠償や処罰を充分に行わず、単に被害者や遺族らの復讐を制止する行為は、却って社会秩序を乱す悪行で、Aはいい人どころではなく、加害者の加担者に過ぎない。
現在、違法行為に対する世論の厳罰化傾向が強まりつつあるのも、これに由来するのではないか。
本書を読めば、現代の「加害者の人権を擁護したい人々」が、被害者や遺族に対する充分な賠償もなく、死刑廃止や刑罰の軽減などを要求しても、容れられる筈がないことがわかる。
古代には、復讐避難所に逃げ込んだ犯罪者は、奴隷化、あるいは労働を課され、賠償金を準備する猶予を与えられた。また、犯罪者の親族や友人などが、代わりに賠償金を用意する時間稼ぎにも使われた。
加害者の更生を云々する為には、それ以前に被害者への救済が成されなければならない。
賠償なき許しは、やった者勝ちをもたらし、社会秩序が保たれなくなる惧れがある。
現代の日本では、民事訴訟で被害者や遺族に対する損害賠償が確定しても、刑法犯が支払を踏み倒す傾向が強い(殺人・傷害致死事件は約70% 2000年 法務省調べ)。
古代よりも、被害者や遺族の人権保護が後退した、と言わざるを得ない。
それ対する社会の違和感が、厳罰化を求める声となったのではないかと思った。
また、本書を読めば、フィクションに於けるアウトローが「へっへっへ…俺たちゃアウトローなんだぜ」などとイキっている場合ではないことがわかる。
古い時代、加害の賠償を行わない者に対して、共同体が行った最終制裁が「法外(outlow)」措置で、アウトローは、法による保護を外された者であり、謂わば「生命の価値を失った者」である。
一般人や被害者、被害者の遺族らが、アウトローを殺害してもお咎めなし、または、共同体の秩序維持の為、殺害を推奨される。
本書を読めば、復讐ジャンルのフィクションを見る目が変わる。
法史に興味のない方や、創作活動をする方々にもオススメの一冊。

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。
2019/07/22 01:59
ニコニコ学会を紙の本にしたようなノリ→基礎研究の視点が身近に
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
軽妙な語り口で紹介される鳥類学者のお仕事の日々。
お勉強だけでなく、漫画なども適度に楽しみつつ学者になった人なのだなぁとわかるネタのちりばめ方で、面白く読めました。
その面白さに目を奪われそうですが、鳥類や基礎研究が置かれる厳しい状況、山積みの課題もまざまざと突き付けられ、考えさせられます。
どんな課題があるのか。
本書を読むことが、無関心からの脱却の第一歩になる筈です。
一般人の自分にできることは限られますが、取敢えず、無理のない範囲で町内の清掃をしようと思いました。「できることから、少しずつ」をみんながやれば、大きな力になるでしょう。
まずは、他人事ではなく、身近な鳥に自分のこととして目を向けるだけでもいいと思います。「自分が住む場所は、この鳥が住める環境なんだ」という自覚。
鳥類学者のお仕事と言われても、うまく想像できませんでしたが、予想以上にハードでした。
無人島の調査でハエが口に入る……何となく宮沢賢治の「よだかの星」を思い出しました。メンタル面でもハードモードなフィールドワーク。
鳥だけではなく、鳥を取り巻く環境全体をひっくるめて、場所だけでなく、人間の経済活動、社会活動も鳥が生きてゆくための生態系に少なからず影響があると再確認。見えないところの繋がりを見せてくれる一冊でもあります。

コミケ童話全集 1
2019/07/22 01:37
同人者あるある×お馴染みの童話
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最初に見たのが石油王の話で、ツイッターで追っていましたが、紙の本が手に入ってよかったと思えたシリーズです。電源なくても読める幸せ。
同人あるあるネタで容赦なく繰り出される濃いギャグがツボ入りました。
マッチ売りの極限状態に、なんとなくわかりみ。
浦島太郎のカメの存在全てに腹筋崩壊。
三匹の子豚&借金取り、赤ずきんのネタが何か好きです。
>「誰だお前!」
>「おばあちゃんです!」
この流れにワロタ。
ラブコメで借金をチャラにする契約。
発想が超シュール。部下、今まで気付かんかったんかって言う。
というか、クソブタさんちの玄関めっちゃ広いので、実は豪邸に住んでる?
笠地蔵&桃太郎のおじいさんたちの困惑にうっすら申し訳なさを感じてみたり。
でも、おばあさんたちが楽しそうでなによりです。
コミケや同人を知らない人も、このおじいさんたちと同じスタンスで見ると、身近にいるこれ系の趣味の人たちを見る目が変わって、一緒に(状況を)楽しめるようになるんじゃないかなと思いました。


