Pattoさんのレビュー一覧
投稿者:Patto
紙の本

紙の本なっとくする演習・電磁気学
2024/05/14 12:31
本書が少しでも希望を与えてくれそうな気がする
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
著者は、電磁気学が難しい理由を次のように説明している:
<電磁気学は難しいというのは定説。専門家の間でもよくパラドックスが話題になる。
電磁気学をわかり難くしている第1の理由は、電磁気学を構築する論理体系をはっきり理解していないこと。電気に関する現象の根元は電荷にあり、この電荷にはクーロンの法則による力が働く。マックスウェルの方程式は電磁気学の基礎方程式だが、実は、クーロンの法則から出発し、何段かの論理的ステップを経るだけで、マックスウェルの方程式に行き着く。
第2の理由は、電磁気学には複数の法則が独立して存在すると考えられていること。たとえば、クーロンの法則から得られた結果が、アンペアの法則と矛盾するように見えることがある。これはパラドックスだ。
第3の理由は、変位電流。変位電流という考えが存在していること自体が、電磁気学を不透明にするのに最も寄与する。世界的に知られた有名大学が編集した電磁気学教科書に、明らかに正しくない図が載せられていることからも理解できる。>
なるほど・・・、高級な悩みですな。
私などは、電磁気学で使われている数学の難しさを第1の理由に挙げたいくらいだ。
専門家たちも電磁気学に悩んでいるのだからといって、すねていても始まらない。
電磁気学を学ばなければならない現実がある。
電磁気学の勉強で悶えている私に、本書が少しでも希望を与えてくれそうな気がする。
期待している。
話は脱線するが、本書の Coffe Breakにおもしろい話が紹介されている。
<「ベクトルと”3次元の複素数”」
複素数の写像を利用すれば、電気力線や等電位戦を簡単に描くことができる。このとき、「電気力線の面積密度は電界の大きさに比例する」という条件が、自動的に満足されているのがすばらしい。このように、ベクトルである電界の性質は、微分可能な複素数で表すことができる。
(この部分は文章表現に問題はないが、何故かレビューに書くと「レビュー内容に使用できない文字が含まれています」という警告が出るので省略せざるを得ない。hontoの検閲はレビュアーの投稿意欲を削いでしまうのではないか?省略した部分を知りたい人は、本書を読まれたい。)
これに対して、ベクトル量である普通の電界はE(x, y, z)と表され、3個の変数をもつ。そこで、もしかりにw=x+jy+kzというように、新たな”虚数”kが発見されれば、新しい複素関数f(w)は3次元の電界の役割を果すかもしれない。
(後は略)>
このコラムを読んで、自分の高校時代を思い出した。私は数学の先生たちに「3次元の複素数」について質問したことがある。突然ロバが口を利いたようなものだ。驚いた山口祐司(仮名)先生は、つまらない「複素数の定義」をていねいに説明するだけ。大八木順之助(仮名)先生は、オレが説明できて君がわかればすばらしいけどな・・・、と情熱的に語った。江波戸三好(仮名)先生は、そういうことは大学へ行けばわかる、と逃げた。ところが、我われ男子生徒のアイドルである榊和恵(仮名)先生は、質問をしっかりと受けとめて何やら説明して下さったが、その内容はすっかり忘れてしまった。ひょっとしたら、 「ハミルトンの四元数」にも触れられたかもしれない。それはともかく、榊先生は「あなたはもっと現実的になって、普段の数学の成績を上げることが先決ですね」と優しく諭してくださった。数年前、「榊先生が数学の学習指導に関する研究で博士号を取得されたぞ」とマドンナを巡るライバルの友人から知らせが届いた。榊先生は、私のような出来の悪い生徒の指導に心を痛めておられたようだ。
紙の本
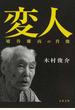
紙の本変人埴谷雄高の肖像
2024/06/14 11:18
埴谷雄高談「自分の小説はわかる人がいないし、わからなくて当然」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「最晩年 古澤和子さん(家政婦)」がいちばん参考になった。
古澤さんは、1996年1月6日から翌年2月29日の臨終まで、埴谷雄高氏の住み込み家政婦として付き添った。
埴谷氏の病状が1月以降悪くなったが、2月に良くなる兆しが見えた。
その頃の埴谷氏は古澤さんにこういうことを話したという。
<あなた、ちょっとここへ来てください。僕は間もなく死にますから、今、お礼を言っておきます。聞きたいことがあれば何でも言ってください」。他の方にもよくおっしゃっていました。
どの本を読めばいいのかを伺うと、「自分の小説はわかる人がいないし、わからなくて当然なので、読むなら対談集を読んでください」「仲間に囲まれて自分があったので、仲間のことをよく書いたつもりです。仲間のことはよく知ってほしい」。>
埴谷氏は、他人が『死霊』をわからなくて当然だ、と言っている。
他人に理解されないようにして『死霊』を書いているという意味だろう。
だから、多くの評論家たちが書いた「死霊論」は、埴谷から見て「的外れ」に思えただろう。
私が『死霊』を理解できなくて当たり前であり、それを知って安心した。
因みに、鶴見俊介氏がこういうことを書いている。
<晩年に入って、埴谷雄高に、もうろくの兆しが見えた。
そのもうろくは、これまで自分自身に起ったことをつとめて書かないようにしてきた戒めを、緩くする。
彼は一人の文学者に、自分の言うことを書いてもらうことにした。
《昨年(1996年)の2月頃、「白川君、君が僕のことを一番よく知っているのだから、僕の最期を見とどけて欲しい。物書きに最期まで見届けられた作家はこれまでいないので、それをぜひお願いします」と言われた。》(白川正芳『始まりにして終り―埴谷雄高との対話』文芸春秋、1997年)
1997年2月19日、埴谷雄高が87歳で亡くなるまで、白川正芳は1年余り毎日のようにその家に通い、数百時間にわたってテープに話を採り、その日のことを家に戻って記した。
もうろくは、自分に起った古い出来事を、老年のその時・その時の状況に基づいて、一挙に照らし出すことがある。これまでの60数年の埴谷雄高の著作よりもはっきりと、白川との対話録に、埴谷自身に映じる埴谷の過去の筋道が見える。
例えば、台湾で育った頃のこと、日本内地の家系上の出身とのつながり、それらが、初期の埴谷が自分に許さなかった語り口で、そのもうろくのゆえに明らかになった。>(鶴見俊介『埴谷雄高』講談社、2005年)
鶴見しによれば、埴谷氏の「もうろく」のおかげで『死霊』がわかりやすくなった、ということらしい。
以上の他に、埴谷 雄高 (著)、NHK (編集)、白川 正芳 (編集)『埴谷雄高独白死霊の世界』(NHK出版、1997年)も『死霊』理解の参考になる。
古澤さんの話に戻すと、埴谷氏の体の調子は、2月を無事に過ごし、3、4、5月が一番良かった。
6月頃は寂しがるようになった。
変化は7月頃。
<梅雨時は昼から外が薄暗い。すると「側にいてください。側にいてくれればいいんです。心臓の悪い者は夕暮れ病といいまして、側に誰かいないと寂しくなるんです。1分でいいんです」とおっしゃった。>
<夜中に目が覚めると「どなたかいますか?来てください」とおっしゃる。「どうしたんですか?」と応えると、「あなたですか。いるならいいんです。確認です」とおっしゃり、ベッドに戻られる。と思うと戻ってすぐにまた「誰かいるんですか?いませんか!」と叫ばれる。そんなことが一晩に何度もあった。>
埴谷氏は、「独り死にゆく者の孤独」と戦った。
ご冥福を祈る。
紙の本

紙の本奇抜の人 埴谷雄高のことを27人はこう語った
2024/06/13 11:01
埴谷雄高談「自分の小説はわかる人がいないし、わからなくて当然」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「最晩年 古澤和子さん(家政婦)」がいちばん参考になった。
古澤さんは、1996年1月6日から翌年2月29日の臨終まで、埴谷雄高氏の住み込み家政婦として付き添った。
埴谷氏の病状が1月以降悪くなったが、2月に良くなる兆しが見えた。
その頃の埴谷氏は古澤さんにこういうことを話したという。
<あなた、ちょっとここへ来てください。僕は間もなく死にますから、今、お礼を言っておきます。聞きたいことがあれば何でも言ってください」。他の方にもよくおっしゃっていました。
どの本を読めばいいのかを伺うと、「自分の小説はわかる人がいないし、わからなくて当然なので、読むなら対談集を読んでください」「仲間に囲まれて自分があったので、仲間のことをよく書いたつもりです。仲間のことはよく知ってほしい」。>
埴谷氏は、他人が『死霊』をわからなくて当然だ、と言っている。
他人に理解されないようにして『死霊』を書いているという意味だろう。
だから、多くの評論家たちが書いた「死霊論」は、埴谷から見て「的外れ」に思えただろう。
私が『死霊』を理解できなくて当たり前であり、それを知って安心した。
因みに、鶴見俊介氏がこういうことを書いている。
<晩年に入って、埴谷雄高に、もうろくの兆しが見えた。
そのもうろくは、これまで自分自身に起ったことをつとめて書かないようにしてきた戒めを、緩くする。
彼は一人の文学者に、自分の言うことを書いてもらうことにした。
《昨年(1996年)の2月頃、「白川君、君が僕のことを一番よく知っているのだから、僕の最期を見とどけて欲しい。物書きに最期まで見届けられた作家はこれまでいないので、それをぜひお願いします」と言われた。》(白川正芳『始まりにして終り―埴谷雄高との対話』文芸春秋、1997年)
1997年2月19日、埴谷雄高が87歳で亡くなるまで、白川正芳は1年余り毎日のようにその家に通い、数百時間にわたってテープに話を採り、その日のことを家に戻って記した。
もうろくは、自分に起った古い出来事を、老年のその時・その時の状況に基づいて、一挙に照らし出すことがある。これまでの60数年の埴谷雄高の著作よりもはっきりと、白川との対話録に、埴谷自身に映じる埴谷の過去の筋道が見える。
例えば、台湾で育った頃のこと、日本内地の家系上の出身とのつながり、それらが、初期の埴谷が自分に許さなかった語り口で、そのもうろくのゆえに明らかになった。>(鶴見俊介『埴谷雄高』講談社、2005年)
鶴見しによれば、埴谷氏の「もうろく」のおかげで『死霊』がわかりやすくなった、ということらしい。
以上の他に、埴谷 雄高 (著)、NHK (編集)、白川 正芳 (編集)『埴谷雄高独白死霊の世界』(NHK出版、1997年)も『死霊』を理解するのに参考になるようだ。
紙の本

紙の本詩人 西脇順三郎
2024/06/10 11:52
感覚脱落者の萩原朔太郎が西脇を評し、情念に於て感覚脱落症的なところがある、と言って鋭く西脇の本質を突いた
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「ポエ爺(ポエジー)」こと西脇順三郎は愉快な詩人だった。
本書の「西脇順三郎回想」という章は愉快なエピソードで一杯だ。
● 西脇には超俗・非凡な天才性がいつも閃いていたが、意外に平凡で通俗な一面もあり、これが30年間の歳月、僕を歓喜の頂上に押し上げたり、困惑のどん底に突き落したり、反撥の断崖に立たせたりした。
西脇は複雑な人格を持った人だった。彼の内面はアポロン的明るさとディオニソス的破壊性とが、いつも全速力で往来していた。大胆不敵と小心臆病という真反対の性格が、たえずせめぎ合っていた。俗っぽさがあまりにも子供っぽいので、それはやがて超俗の趣を呈することもあった。その通俗と超俗の距離は大きく、そこを彼は大きな振子のように行ったり来たりしたが、彼自身もそうした性向、体質をいささかもてあましていた。人間は自我という存在の、手のつけようのない強さや脆さやわからなさに困惑し、悩み、憤り、悲嘆に暮れ、人生に疲弊するのかもしれない。>
● 西脇は人間が職業を持つこと、実業につくことを忌み嫌い、呪ったとまで書いている。志に反して講壇生活を60年近く送ったが、彼は生業として大学教授をしたにすぎず、実のところ教育するとか、後進を育成するという意識は薄く、好きな者は勝手にやっていろ式だった。だから大学という組織体の中で、彼の自由が奪われたことも多くあったろうし、それが彼自身の言葉によれば「近代人の憂鬱」の源泉であったかもしれない。彼は集団からはいつも一人孤絶した島で、一人だけのポエジーという旗を振ったり、昼寝をしたりしていた。
● 西脇は古今東西の文藝・芸術に対して該博な知識と教養の持主とされている。・・・だが彼は少くとも学問の成立の基本的条件である方法論がなかったし、理論を組織体系化することを嫌った。想像力の飛躍が大きく、卓越した直観力は発揮するが、理論の肉付けや方法の手続きや裏打ちを無視した。だから実証や証明のない全く彼独自の感性の赴くままに、小気味のよいほどに論評の対象を裁断した。
● 昭和12年、萩原朔太郎が西脇を評し、情念に於て感覚脱落症的なところがある、と言って鋭く西脇の本質を突いた。そして当の萩原自身もまた西脇に劣らない感覚脱落者であって、萩原もまた現実に対して弱く、西脇同様、虚に対するとき詩魂が高揚する一面があった。意想奔逸とでもいうべき感性高跳びが詩文のあちこちで行われ、詩的言語に稀有なる内実を二人とも与えている。
● 客観的観察や学問的静態化を全く顧みないところに、この詩人らしい固有の、良くも悪くも独断と偏見が溢れ出ている。だからT・S・エリオットを評して、詩人は冗談交じりに「エリオットはソバを食べたことがないから、いい詩が書けない」とか「エリオットはガンモドキを食べたことがなかったから、気の毒なことをした」と言った。
● 人命・地名は詩の中に活用された。中桐雅夫は「ナカキリコ」、田村隆一は「タミューロー」、鍵谷幸信は「カジノヤ」、那珂太郎と諏訪優を合わせて「ナカスワ」と神々にされた。
もっとあるが、この辺でやめる。
著者の鍵谷氏は、「想像力の飛躍が大きく、卓越した直観力を発揮する」西脇に師事して翻弄され、きちんとした研究をすることができなかったのではないか?
植草甚一氏との共編で『コルトレーンの世界』というモダンジャズの本も出しているから、そういう心配が起る。
残念ながら、鍵谷氏は、西脇に「30年間の歳月、歓喜の頂上に押し上げられたり、困惑のどん底に突き落されたり、反撥の断崖に立たされたりした」せいか、59歳位で亡くなってしまった。
ご冥福を祈る。
紙の本

紙の本柄谷行人『力と交換様式』を読む
2024/06/09 16:13
柄谷氏のお写真を拝見すると、お元気そうだが、時の流れを感じてしまう
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
栗本慎一郎氏の『鉄の処女―血も凍る「現代思想」の総批評』(1985年)の「4「二重緊縛」に悶える柄谷行人」という章に、柄谷氏について詳しく書いてある。
そして、その章末に掲げられた柄谷氏のプロフィールが大へん愉快である。
<柄谷行人:本名、善男。1941年兵庫県生れ。神戸の名門、灘中・高から東大経済学部卒。同大学院英文科修士課程卒業。文芸評論家、法政大学第一教養部教授。主著に『マルクスその可能性の中心』、『日本近代文学の起源』、『隠喩としての建築』等。大学では英語の先生である。中沢新一によると「柄谷さんの英語ってヒドイでしょ」ということだが、たしかに講義中に辞書は何度も引くし、割合いい加減にやっているという印象を受ける。外国語を学ぶことの意味を「反動的」なまでに強調し続けてきた人にしてはどうなんだろうな。二枚目であり、女子学生にも人気がある。本人も割とその気なのか、便所で頭をけんめいに直している姿を見られている。マユツバな話だがアメリカに男の恋人がいるともいう。内向的で自閉症的な性格とちょっと酷薄な政治的な性格が共存していてつき合いにくそうな人だという。
上杉清文による注釈:変型本位を探究。不可能と聞いただけで濡れてきちゃう学者肌とか。>
柄谷氏のことを知らない私が、何だかよく書けているように思えてしまうのは、栗本氏が上手だからだろう。
そういうわけもあって、申し訳ないが、柄谷行人氏の本をほとんど読んでいない。
ところが、ずっと柄谷氏は頑張っておられたのだ。
最近、柄谷氏のご健在ぶりを知り、本書を手にしてみた。
私の頭のレベルではわからないから、評価の星★の数はいい加減になる。
チラッと読んだことがある、『畏怖する人間』のほうがわかり易く感じるほどだ。
帯の柄谷氏のお写真を拝見すると、お元気そうだが、時の流れを感じてしまう。
そういうわけで、上記の若き日の柄谷氏のプロフィールを思い出したのである。
本書に関係ないことを書いたことをお許し願う。
今後も永く健筆を振るってください。
紙の本

紙の本IC産業最前線 日米決戦・現場からの報告
2024/06/08 17:21
「協同電子技術研究所」という会社
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、日の丸半導体が80年代の狂騒状態に向って始動した状況を活写している貴重な資料である。今は「兵どもが夢の跡虚」。
それはさて措き、70年代に「協同電子技術研究所」という会社が存在した。以下は、大学の先輩から聞いた話に基づいている。
協同電子技術研究所はユニークな半導体メーカーだった。もともとソニー、日本ケミカルコンデンサ、東光など6社が共同経営する会社としてスタートし、後に東光の完全子会社になった。
協同電子技術研究所の本社と相模原工場は、小田急相模原駅に近い閑静な住宅街の中にあったが、やがて相模原工場に見切りをつけ、会津工場を建てた。
相模原工場はダイオード、トランジスタ、パイポーラIC、ハイブリッドICを担当し、⇒「相模東光」⇒閉鎖と変遷。
会津工場はCMOS ICを担当し、⇒「会津東光」⇒1980年モトローラとの合弁化⇒1982年モトローラに全面売却して「モトローラ会津事業所」と変遷。
1999年に「モトローラ会津事業所」はテキサス・パシフィック・グループに売却され「オン・セミコンダクター」となる。
相模原工場には、『CMOS最新応用技術特集』(日刊工業新聞社、1973年)に「わが社のCMOS」を寄稿する優秀なエンジニアもいたが、問題の人材もいた。
例えば、ソニーから来た技術幹部は、自社の能力を顧みずに液晶電子腕時計の事業化を企てが、試作品の社内販売で頓挫。日立中研から秘書同伴で来た化合物半導体の専門家は、亀の甲羅を焼いて占っていたという。彼女に会えなくなるので会津工場への転勤を拒否したバカ者もいたらしい、等々。
中川康造氏の『日本の半導体開発』によれば、1971年頃、就活中の山下博典氏は通産省から協同電子技術研究所を斡旋されたが断ったという。その会社の内情が複雑で、とても手を出す気になれなかったからだ。
それから、中川氏の『東芝の半導体事業戦略』によれば、1975年9月に鈴木八十二氏は東光が4KビットのダイナミックCMOS・RAMを開発したことを知った。鈴木氏は東光さんはやるなと思ったが、パワーが大きいことが致命傷になって伸びないだろうと感じたそうだ。
以上の変遷の中で、協同電子技術研究所のエンジニアたちは、東光の半導体部門(埼玉事業所)に移るグループ、モトローラに移るグループ、その他の半導体メーカーへ移るグループに別れた。
エンジニアたちは東光、モトローラ、TI、キャノン、クラリオン、諏訪精工、セイコー電子工業、日本プレシジョン・サーキッツ、シャープ、オムロン、東京三洋、IBM、スタンレー電気、日立、サンケン、ミツミ等々へ移ったので、協同電子技術研究所は半導体業界の人材供給源であった。
こんな話を聞いた。会津東光から諏訪精工(セイコーエプソン)に移った人は経営幹部まで出世したが、目まぐるしく経営が変転したようだ。2000年7月にTIの聖地「鳩ケ谷工場」を買収して液晶ドライバICの製造会社「エプソン鳩ヶ谷」とするが、今はマンションになっている。2001年にIBM野洲事業所の半導体製造部門と合弁会社「野洲セミコンダクター(YSC)」を設立し、2006年6月にYSCを完全子会社化したが、翌年2007年3月にYSCをオムロンに売却した、という具合だ。もう一つ、モトローラ会津事業所から部下を引き連れてアナログデバイセズ日本支社長になった人は、お客の評判がよくなかったらしい(営業マンから聞いた話)。
結局、2009年に東光の半導体部門は「旭化成エレクトロニクス」に売却された。そして2019年に東光本体は村田製作所に吸収されて「埼玉村田製作所」となった。大田区雪谷にあった東光本社は今は跡形もない。これで協同電子技術研究所の残り香は完全に消失した。
紙の本

紙の本IC産業大戦争 急成長市場をねらう企業群
2024/06/08 17:18
「協同電子技術研究所」という会社
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、日の丸半導体が80年代の狂騒状態に向って始動した状況を活写している貴重な資料である。今は「兵どもが夢の跡虚」。
それはさて措き、70年代に「協同電子技術研究所」という会社が存在した。以下は、大学の先輩から聞いた話に基づいている。
協同電子技術研究所はユニークな半導体メーカーだった。もともとソニー、日本ケミカルコンデンサ、東光など6社が共同経営する会社としてスタートし、後に東光の完全子会社になった。
協同電子技術研究所の本社と相模原工場は、小田急相模原駅に近い閑静な住宅街の中にあったが、やがて相模原工場に見切りをつけ、会津工場を建てた。
相模原工場はダイオード、トランジスタ、パイポーラIC、ハイブリッドICを担当し、⇒「相模東光」⇒閉鎖と変遷。
会津工場はCMOS ICを担当し、⇒「会津東光」⇒1980年モトローラとの合弁化⇒1982年モトローラに全面売却して「モトローラ会津事業所」と変遷。
1999年に「モトローラ会津事業所」はテキサス・パシフィック・グループに売却され「オン・セミコンダクター」となる。
相模原工場には、『CMOS最新応用技術特集』(日刊工業新聞社、1973年)に「わが社のCMOS」を寄稿する優秀なエンジニアもいたが、問題の人材もいた。
例えば、ソニーから来た技術幹部は、自社の能力を顧みずに液晶電子腕時計の事業化を企てが、試作品の社内販売で頓挫。日立中研から秘書同伴で来た化合物半導体の専門家は、亀の甲羅を焼いて占っていたという。彼女に会えなくなるので会津工場への転勤を拒否したバカ者もいたらしい、等々。
中川康造氏の『日本の半導体開発』によれば、1971年頃、就活中の山下博典氏は通産省から協同電子技術研究所を斡旋されたが断ったという。その会社の内情が複雑で、とても手を出す気になれなかったからだ。
それから、中川氏の『東芝の半導体事業戦略』によれば、1975年9月に鈴木八十二氏は東光が4KビットのダイナミックCMOS・RAMを開発したことを知った。鈴木氏は東光さんはやるなと思ったが、パワーが大きいことが致命傷になって伸びないだろうと感じたそうだ。
以上の変遷の中で、協同電子技術研究所のエンジニアたちは、東光の半導体部門(埼玉事業所)に移るグループ、モトローラに移るグループ、その他の半導体メーカーへ移るグループに別れた。
エンジニアたちは東光、モトローラ、TI、キャノン、クラリオン、諏訪精工、セイコー電子工業、日本プレシジョン・サーキッツ、シャープ、オムロン、東京三洋、IBM、スタンレー電気、日立、サンケン、ミツミ等々へ移ったので、協同電子技術研究所は半導体業界の人材供給源であった。
こんな話を聞いた。会津東光から諏訪精工(セイコーエプソン)に移った人は経営幹部まで出世したが、目まぐるしく経営が変転したようだ。2000年7月にTIの聖地「鳩ケ谷工場」を買収して液晶ドライバICの製造会社「エプソン鳩ヶ谷」とするが、今はマンションになっている。2001年にIBM野洲事業所の半導体製造部門と合弁会社「野洲セミコンダクター(YSC)」を設立し、2006年6月にYSCを完全子会社化したが、翌年2007年3月にYSCをオムロンに売却した、という具合だ。もう一つ、モトローラ会津事業所から部下を引き連れてアナログデバイセズ日本支社長になった人は、お客の評判がよくなかったらしい(営業マンから聞いた話)。
結局、2009年に東光の半導体部門は「旭化成エレクトロニクス」に売却された。そして2019年に東光本体は村田製作所に吸収されて「埼玉村田製作所」となった。大田区雪谷にあった東光本社は今は跡形もない。これで協同電子技術研究所の残り香は完全に消失した。
紙の本

紙の本量子で読み解く生命・宇宙・時間
2024/06/08 11:09
「コペンハーゲン解釈」は好かないので、これでボーアやハイゼンベルグに「ざまあ見ろ」と言えそうだ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
よくわからないのにこう言うのは妙だが、吉田伸夫氏の『光の場、電子の海』を読んでから、私は吉田氏が言うことを信用する。
本書は小冊子だが、『光の場、電子の海』と同様に、あるいはそれ以上に難しそうだ。
とりあえず、宣伝のために「帯」や「カバー」に書いてあるキャッチコピーを読んで済まそうと思う。
<たった一つの事実で全て解決する。
量子の世界の4大謎
1.歴史は分岐し、パラレルワールドが存在するのではないか?――多世界解釈
2.「人が見る」という行為は、現実世界に物理的作用を与えるのではないか?――観測問題
3.量子には一瞬で空間を超えて情報が伝わるテレパシーのような力があるのではないか?――量子もつれ
4.生と死、二つの状態が重なった猫を作ることができるのではないか?――シュレディンガーの猫>
<生命、宇宙、時間。物質や光の最小単位・量子は、これらのあらゆる現象と関わりを持つ。だが量子には謎が多く、その正体さえ判別できず、《粒子であり波である》と矛盾した説明がされている。本種は《粒子ではなく波である》という結論から出発し、事象の解明に挑む。>
本文にも少し目を通してみると、終りに近い部分にこう書いてある:
<アニーリングマシンは組み合わせ問題しか解けず、しかも、必ずしも最適解は得られない。計算速度も、ゲートマシンのように圧倒的に速いわけではない。ただし、すでに実用段階にある点で優位にある。
一方、ゲートマシンは、論理演算で解けるすべての問題に対応でき、うまく動けば、スピードはアニーリングマシンとは比べものにならないほど速い。しかし、実用化までの障害は大きい。現在は、いくつかのグループが開発した小型マシンを使って、役に立つかどうかの実証実験が進められている。
組み合わせ問題に相当する課題は実社会に数多くあり、アニーリングマシンの有用性は揺るがない。ゲートマシンは、しばらくの間、研究者のオモチャ以上のものではないだろう。>
<初期の量子論が、物理学者のみならず哲学者の関心を引いたのは、物理現象を論じるのに人の役割が無視できないという形で理論が構築されていたからである。人間がどのような観測を行うかによって、物理的な状態が左右されるという見方であり、人間から独立した客観的な物理的実在が厳然と存在するという自然観を否定するかのようだった。かつては、ボーアやハイゼンベルグらが行ったこうした哲学的な議論がもてはやされたが、現在ではあまり重視されない。>
<ハイゼンベルグらの議論では、人間による観測が物理現象の帰趨を左右する。しかし、想像を絶するほど広大な宇宙の中で、塵のような惑星にへばりついて生きる人間がそれほど重要な役割を演じるとは、ちょっと考えにくい。干渉の有無によって量子論的な過程を区別する立場は、私が知る限り、量子論の最も合理的な解釈である。>
<超ひも理論は、厳格に定めらた数学的枠組みを出発点とし、そこからひたすら数式をいじくるような研究しかできない。実際の物理現象から多くの知見を得る道を断ったことで、超ひも理論は行き詰まり、次第に顧みられなくなった。>
「ゲートマシンはまだ研究者のオモチャ以上のものではない」
「ボーアやハイゼンベルグの哲学的な議論は現在あまり重視されない」
「広大な宇宙の中の塵のような惑星にへばりつく人間が物理現象の帰趨を左右するとは考えにくい」
「超ひも理論は行き詰まり顧みられなくなった」
とは愉快である。
「コペンハーゲン解釈」は好かないので、これでボーアやハイゼンベルグに「ざまあ見ろ」と言えそうだ。
紙の本

紙の本電子立国日本を育てた男 八木秀次と独創者たち
2024/06/07 12:52
物理学関係者にとっても一読に値すると思う
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「八木秀次」と聞いてもあまりピンとこないが、「八木アンテナ」は時々耳にする。
調べると、八木アンテナは、1926年に電気通信学者の八木秀次が宇田新太郎と共に開発し、地上波テレビの受信用アンテナとして多く使われている、と説明されている。
日本ではなく、世界が八木アンテナの価値を認め、第二次世界大戦で連合軍がレーダー用に八木アンテナを使用して日本軍に甚大な被害を与えたのだ。
さらに、本書によって、八木アンテナの発明だけでなく、阪大物理学科の創設、湯川の中間子論完成に寄与等の、八木の幅広い活躍がよくわかる。
しかも本書は、いきなり、愛人の菊代さん(八木の秘書)との生活という、八木の生臭い面の描写から始まる。
菊代さんは、「文化勲章の科学者八木秀次博士、秘書のマンションで急死」「老科学者が15年も別居を続けた理由」などと雑誌に書かれることを恐れたという。
だから本書は、堅苦しい内容だが、けっこう気楽に読めるということだ。
それにしても、やはり立派な業績を上げる人は「その方面」もお盛んなのである。
それから、「あとがき」には、本書が八木中心に書かれた理由が書いてある。
<私は連載(「日米半導体産業30年」という記事)が終ってから、量子力学の日本における開拓者であり、素粒子物理学の創始者である湯川秀樹と朝永振一郎の生涯にわたる交錯を書きたいと思った。まず湯川サイドの取材が相当に進んだところで、思わぬ方向転換をすることになった。八木秀次という科学者が急に浮上してきた。
八木と湯川の関係は、八木が阪大物理学科を創設した時に、湯川が八木を頼って京大から阪大講師に転じたことから始まる。八木は湯川を庇護し、湯川は八木の鞭撻のもとに中間子論を完成する。だが、そんな八木と湯川の関係は伝えられることがなく、湯川のノーベル賞受賞の陰に八木の尽力があったことは、今ではまったく忘れられている。> (概要)
本文でもこう書いてある。
<八木が湯川を叱責したことが、核力の暗闇をさ迷う湯川を解決に向けて踏み出させた。朝永振一郎まで引き合いに出して、なぜ論文が出ないのか、もっとしっかり勉強しろ、という八木の痛烈な面責が、湯川の中に宿意を生んだが、その一方で、湯川をして大胆な仮説の構築へと踏み切らせる後押しになった。> (概要)
本書には、湯川・朝永の他に、寺カン(寺沢寛一)、菊池正士、坂田晶一、武谷三男、伏見康治等々の多くの物理学者が登場し、彼らのエピソードがいろいろ紹介され、大へん興味深く読める。
例えば、寺カンは阪大物理学科に自分の派閥を作るために尽力し、菊池は阪大の「戦時科学報国会」で中心になって大暴れしたという。
竹を割ったような気性の菊池は、「聖戦」の時流に乗って歯止めが効かなかったという。
つまり、現代の「右翼過激派学生」のようだったらしい。
私の叔父から聞いた話だが、そういう菊池も、戦後の大学闘争が盛んな頃に東京理科大学の学長だったが、コソコソ逃げるようにして、なかなか学生の前に姿を現さなかったそうだ。
本書は、そういうアホみたいなエピソードばかりではないから、物理学関係者にとっても一読に値すると思う。
紙の本

紙の本ソニー失われた20年 内側から見た無能と希望
2024/06/06 12:11
出井伸之氏以降のソニーは「名声願望」「贅沢三昧」「明日への迷走」 等の「経営ゴッコの会社」という表現がピッタリするようだ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大へん興味深く読んだ。
参考になった箇所をいくつかピックアップしてみる(要旨):
<創業からずっとソニーは技術の会社だった。世界へ進出し、日本企業に先駆けて海外で株式を公開し、世界のソニーになり、保険会社や映画会社を持つ、日本でも稀な業態の国際企業に発展した。それが、出井が社長に就任する頃から、組織と制度をいじくる経営ゴッコの会社に変った。
ソニーの制度改革の歴史と本音の目的
1994年 カンパニー制の導入(技術者の懐柔と隔離)
1995年 ストック・オプション制度の導入(米国式経営の模倣による宣伝)
1997年 取締役会の改革と執行役員制度の導入(外様理系の隔離と組織階層化への布石)
1998年 報酬委員会と指名委員会の設置(将来の企業私物化への布石)
1999年 ネットワークカンパニー制の導入(上級役員の懐柔と権限の拡大)
2002年 アドバイザリーボードの設置(ホールディング会社設立への布石)
2003年 委員会等設置会社への移行(組織階層化と企業私物化の完成)>
<アメリカへのリベンジを目指したソニー創業者の時代が終わり、高学歴社員によるソニー経営が始まった。現場での労働を嫌い、未知への挑戦を嫌うような高学歴社員で占められた今のソニーに、かつてのベンチャー精神は甦らない。
出井の過ちは、出井流のソニーのガバナンス改革と委員会等設置会社への移行であり、それは経営の監督と執行の分離を目指すもの。経営の監督ができる者は、経営の執行が出来なければならないが、それを分離した。
すなわち、経営の監督をしているつもりなのに経営のことがわからない人や、経営の執行をしているつもりなのに経営のことがわからない人が、偉いポジションにつくことになった。ソニーを知らない社外取締役に、企業戦略や法令順守などわかりようがない。
社長時代の出井は、執行機能を社内の執行役に権限委譲して、取締役がその執行役を監督するという具合に、経営の監督と執行の機能を分離した。執行役の任免権限は取締役会にあるから、ソニーの事業は、ソニーを知らない外部の人間に操られている。
経営を監督できる人が監督し、経営を執行できる人が執行することが重要だ。人間の問題を置き去りにして、組織と数字の話ばかりしている――それが出井時代から続いているソニーの問題だ。>
<人は俊英だから俊英であり、秀才だから秀才である。ただし、俊英(秀才)以上の人でなければ、誰が俊英(秀才)なのかわからない。従って、苦し紛れの現実では、誰にでもわかる学歴に頼って人の能力を判断する。(現実を見ると)東大に入る目的は他人との差別化であり、他人との差別化を目指す人間が量産される。東大生の問題点を極論すれば、無意識に他人を人間だと思わなくなる。そういうエリート集団では、組織が機能しない。
ソニーが犯した最大の過ちは、盛田昭夫が確たる意思で自分の後継者を2人育てなかったこと。本命と二番手の2人だ。
大賀が犯した最大の過ちは出井を後継者に選んだこと。後継者は選ぶものではなく、育てるものだ。>
<ソニー経営者の終戦時の年齢と特徴
井深 +37歳 諦観(自由への歓喜→技術開発)
森田 +24歳 復讐(米国への凱旋→市場開拓)
大賀 +15歳 自失(自我への模索→名声願望)
出井 +7歳 飢餓(物質への羨望→贅沢三昧)
平井 -15歳 飽食(明日への迷走→無為無策)>
出井伸之氏以降のソニーは「名声願望」「贅沢三昧」「明日への迷走」 等の「経営ゴッコの会社」という表現がピッタリするようだ。
それでもまだソニーは持ちこたえているのだから、私は妙に感心してしまう。
紙の本

紙の本人生の経営
2024/06/06 10:41
何だか「京のお公家さん(まろ)」の「朝廷での世渡りの術」ようではないか
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
アマゾンのマーケットで、本書について、一つのインパクトのあるレビューを見つけた。
これ以上に要領を得たレビューはないと思う。
だから自分のレビューを書く気がなくなってしまったが、その代りに、謹んでここにそのレビューを転載させていただく:
<コネ入社、コネ出世、無能であるがたまたまコネでソニーの社長になり、凋落のA級戦犯である上、長期政権で私利私欲に走った財界のプーチン、習近平である著者があまりにまともなことを書き綴っており、只々驚くばかり。立ち読みで十分。>
そのレビューを書いた人にお礼を申し上げる。
他人のフンドシを使って澄ましているのも気が引けるので、少し自分のコメントを書いてみる。
おかしな考えではあるが、ソニーの出井伸之氏と日本電産の永守重信氏を比べると面白い。
ネット上で「ブラック企業」と呼ばれている日本電産の創業者である永守氏は、会社にとって重要な「怒り役(叱り役)」をしっかりと果たしているので、一部の人たちに「ベルサイユのナマズ」と呼ばれている。
出井氏の場合はどうだろうか?
本書は「キャリア指南書」だから、「経営」ではなく「キャリアアップ」のハウツーについて書いてある。
「キャリアアップ」について説明を要さないだろうが、こういう説明がある:
<キャリアアップは、自分の能力、地位、市場価値が現状よりも良い状態になること。キャリアアップは抽象的な言葉でもあり、人によってさまざまな捉え方がある。>
「キャリアアップはさまざまな捉え方がある」のだから、出井氏は本書で、煌びやかではあるが、一般性に乏しいようなハウツーを自由奔放に書いている。
日々中小企業で喘いでいる私は、照れ臭くて、マネができそうもない。
どちらかと言えば、永守氏の泥臭い話の方が、屁の音のように、自然に耳に入って来る。
永守氏の話に比べると、うまい言葉が見つからないが、出井氏が書いていることは、何だか「京のお公家さん(まろ)」の「朝廷での世渡りの術」ようではないか。
因みに、原田節雄氏は 『ソニー 失われた20年 内側から見た無能と希望』の中で次のように述べている(要旨):
<創業からずっとソニーは技術の会社だった。世界へ進出し、日本企業に先駆けて海外で株式を公開し、世界のソニーになり、保険会社や映画会社を持つ、日本でも稀な業態の国際企業に発展した。それが、出井が社長に就任する頃から、組織と制度をいじくる経営ゴッコの会社に変った。>
< アメリカへのリベンジを目指したソニー創業者の時代が終り、高学歴社員によるソニー経営が始まった。現場での労働を嫌い、未知への挑戦を嫌う高学歴社員で占められた今のソニーに、かつてのベンチャー精神は甦らない。
出井の過ちは、ソニーのガバナンス改革と委員会等設置会社への移行であり、それは経営の監督と執行の分離を目指すもの。経営の監督ができる者は、経営の執行が出来なければならないが、それを分離した。
経営の監督をしているつもりなのに経営がわからない人や、経営の執行をしているつもりなのに経営がわからない人がエラくなった。
人間の問題を置き去りにして、組織と数字の話ばかりしている。それが出井時代から続いているソニーの問題だ。>
<ソニー経営者の終戦時の年齢と特徴
井深 +37歳 諦観(自由への歓喜→技術開発)
森田 +24歳 復讐(米国への凱旋→市場開拓)
大賀 +15歳 自失(自我への模索→名声願望)
出井 +7歳 飢餓(物質への羨望→贅沢三昧)
平井 -15歳 飽食(明日への迷走→無為無策)>
出井氏の本と原田氏の本は相互補完的のようだ。
紙の本

紙の本失われし自我をもとめて
2024/06/05 18:57
処分しようと思ってページをめくってみたら、良さそうな本であることに気がついた
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
だいぶ前に、たまたまブックオフで値段が安かったので購入した。
別に悩みがあって本書を手にしたわけではない。
最近、処分しようと思ってページをめくってみたら、良さそうな本であることに気がついた。
大変失礼な扱いを本書にしてしまったことを反省している。
本書のカバーに、次のように出版社が宣伝文句を書いている:
<本書は、人間の問題を扱って、心理学書の表相性もなく、哲学書のもつ晦渋さもなく、著者の臨床心理家としての鋭い観察が、哲学・文学などの豊かな叡知に裏打ちされて、わかりやすい筆致で綴られている。ことに現代の孤独・不安の分析は見事で、思わず自我の深淵を覗き見るような感慨に誘われる。悲劇感の喪失、時間体験の意味、プロメテュース的人間など、そして人格の統合、自我実現、存在への勇気を説いてやまない。>
読んでいる途中であり、よくわからないことも多くあがるが、その宣伝文句の通りのように思われる。
例えば、こういう箇所がある:
<・・・自己断罪の人は、神が自分をこんなに苦しめ、罰しなさるからには、自分もなんと重要な存在であることかと、それをきわめてしばしば示そうとする。
このように、過度の自己断罪は、かえって内に隠れた尊大さをとりつくろうための衣となっている。自己を責めることによって、自惚れを克服できると思っている人々は、「自己を軽蔑する人間は高慢な人間に最も近い」というスピノザの言葉を熟考してみる必要がある。>
「私は無神論だから関係ない」では済まされないような、痛いところを突くご指摘ではないだろうか。
身の回りを見ると、自分もそう見られているだろうが、やたらと謙遜する人が意外と頑固で意固地である場合が多いように思える。
紙の本

紙の本失われし自我をもとめて
2024/06/05 18:55
処分しようと思ってページをめくってみたら、良さそうな本であることに気がついた
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
だいぶ前に、たまたまブックオフで値段が安かったので購入した。
別に悩みがあって本書を手にしたわけではない。
最近、処分しようと思ってページをめくってみたら、良さそうな本であることに気がついた。
大変失礼な扱いを本書にしてしまったことを反省している。
本書のカバーに、次のように出版社が宣伝文句を書いている:
<本書は、人間の問題を扱って、心理学書の表相性もなく、哲学書のもつ晦渋さもなく、著者の臨床心理家としての鋭い観察が、哲学・文学などの豊かな叡知に裏打ちされて、わかりやすい筆致で綴られている。ことに現代の孤独・不安の分析は見事で、思わず自我の深淵を覗き見るような感慨に誘われる。悲劇感の喪失、時間体験の意味、プロメテュース的人間など、そして人格の統合、自我実現、存在への勇気を説いてやまない。>
読んでいる途中であり、よくわからないことも多くあがるが、その宣伝文句の通りのように思われる。
例えば、こういう箇所がある:
<・・・自己断罪の人は、神が自分をこんなに苦しめ、罰しなさるからには、自分もなんと重要な存在であることかと、それをきわめてしばしば示そうとする。
このように、過度の自己断罪は、かえって内に隠れた尊大さをとりつくろうための衣となっている。自己を責めることによって、自惚れを克服できると思っている人々は、「自己を軽蔑する人間は高慢な人間に最も近い」というスピノザの言葉を熟考してみる必要がある。>
「私は無神論だから関係ない」では済まされないような、痛いところを突くご指摘ではないだろうか。
身の回りを見ると、自分もそう見られているだろうが、やたらと謙遜する人が意外と頑固で意固地である場合が多いように思える。
紙の本

紙の本世界がドルを棄てた日 歴史的大転換が始まった
2024/06/02 18:40
田中氏を「陰謀論」と呼ぶなら、そういう「陰謀論」なら読んでも損はないと思う
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
田中宇氏は、2004年に出した『アメリカ以後』で「日本が米ドルを買い支え、買い取った米ドルで米国債を購入し、アメリカの財政赤字を補填しているが、日本はそれでよいのか?」と問いかける。
それから5年後に出した本書で、書こうとしたことの一つは「米国の上層部には、金融危機を悪化させ、米国の覇権を崩壊させようとしている人々がいるように感じられる」こと、それから「彼らの目的が何であるかを考察する」ことである、と述べる。
そして今度はアメリカにこう問いかける:
<米国投資銀行リーマン・ブラザーズ破綻後、世界は基軸通貨としてのドルを棄てざるを得なくなった。なぜ米国はドルの価値を引き下げるような、財政赤字の急増や金融破綻の黙認を続け、ドルに象徴される自国の覇権を自滅させているのか?>
アメリカは「金融危機を悪化させ、米国の覇権を崩壊させようと」した」。
例えば、金本位制の崩壊という1971年の「金ドル交換停止(ニクソン・ショック)」、ドル安・円マルク高を決めた1985年の「プラザ合意」等を行った。
シロウトの私も、そういう自滅的な行為をする「アメリカの目的」を知りたいと思う。
本書の「第3章 覇権の歴史と多極化」は「200年の近現代史を解読し直した壮大な歴史論になっている」と田中氏は述べる。
「国際的談合体制」「軍産複合体」「隠れ多極主義」「軍産英イスラエル複合体」等という作業仮説を使って近現代史の流れを分析し、「アメリカの目的」を考察する。
当否はさて措き、その考察はなかなか面白く、説得力がある。
昨今、「ディープステート」が流行っている。
本書が出た2009年頃は、「ディープステート」は一般的に使われていなかった。
馬渕睦夫氏によれば「ディープステート」とは次のようである(要旨):
<WASPに代りアメリカのエスタブリッシュメントの座を仕留めたグローバリストからなる左派ユダヤ人社会のこと。主要メディアを傘下に収めて世論を操作し、ドルの発行権を独占することで金融を支配し、CIAなどの情報機関を配下に置いて世界の裏社会と通じ、軍産複合体という軍需産業と多国籍企業を握って彼らのビジネスの便宜を図り、ネオコンというイデオロギー政策集団を使って世界戦略を遂行した。アメリカの実権を握り世界に影響力を及ぼし始めたのは、100年前のウィルソン大統領の時代だ。>
田中氏が言う「金融危機を悪化させ、米国の覇権を崩壊させようとしている人々」は、「ディープステート」にほぼ該当するようだ。
今でも田中氏は「ディープステート」という用語を使っていないから、エライ。
横着者の私は「国際金資本」、「ユダヤ金融資本」等というような用語があるのに、新たに「ディープステート」を持ち出す必要はないだろうと思う。
「ディープステート」は、「陰謀論」の本でよく使われているようだ。
「金融危機を悪化させ、米国の覇権を崩壊させようとしている人々」が「国際金融資本」でも「ディープステート」でもよいが、彼らが易々とシッポを出すとは考え難い。
確かな証拠もなく彼らの所業を論じると、「陰謀論」の誹りを受けることになる。
田中氏はある会合で「ぼくは陰謀論者です」と言ったそうだが、それはイロニーに違いない。
田中氏は、可能な限り、註として典拠を示している。
それでも田中氏を「陰謀論」と呼ぶなら、そういう「陰謀論」なら読んでも損はないと思う。
話題は少し古いかもしれないが、本書は本質的な部分を論じているから、そういう意味で、今でも古さを感じさせない。
これから田中宇氏の他の著書も読んでみようと思う。
紙の本

紙の本森有正の日記
2024/05/31 17:04
「漱石文学は最大の問題の一歩手前で停止し、ごたごた言っているたわごと」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
読んでいる途中であるが、一言二言記しておきたい。
著者の佐古純一郎氏の言葉よりも、本書に引用されている森有正氏の言葉に惹きつけられる。
● 漱石文学
<露伴は日本的伝統によって貫いた。だから可能性を残していた。鴎外、漱石、荷風は伝統へ戻って行った。しかし戻る道の無意味さが判った僕はどうすればよいのか。たとえ絶望的に見えても前進する外はない。>
<三島由紀夫は自分でも知ることのできない超越性に憬れながら絶望的に閉ざされた自分のちっぽけな世界に耽溺していたのだ。根本において芥川龍之介の場合と同じだ。太宰治も有島武郎も皆そうだったのだ。この基礎の中に構築された文学が根源的に不毛なことは明らかである。>
<漱石文学の特色(というか欠点というか、長所というか)は、最大の問題の一歩手前で停止することである。それは作者にも作品にも当てはまる。あのドストエフスキーのつき抜けていくゆくところがない。そして、この限界は実に重要である。この限界をこえたところに、精神は精神としての意味をもって来るのである。存在は存在の意味をもって来るのである。この限界は「日本」ということとぴったりと一致する。その意味では見事な文学である、といえる。ここで「生きること」と「日本」とが完全に一致している。しかし生きることは、従って文明は、日本より大きい筈だ。・・・この限界の内部でごたごた言っていることは全部たわごとである。>
「漱石文学は最大の問題の一歩手前で停止し、ごたごた言っているたわごと」とは、森氏の「日本人であること」の厳しい自覚の言葉であろうが、驚きを禁じ得ないご指摘である。
● 円環的復帰
<遥かに行くことは、実は遠くから自分に帰って来ることだったのだ。これは僕に本当の進歩がなかったことを意味してはいないだろうか。それとも本当に僕の「自分」というものがヨーロッパの経験の厚みを耐ええて、更に自分を強く表わしはじめたのだろうか。今僕はこの質問に答えることができない。これに答えるにはおそらく数十年の歳月がかかるだろうからである。ただ僕は、自分の中に一つの円環的復帰がはじまったことを知るのである。よかれあしかれ、これが自分だというもの、遥かに行くことは、遠くから自分に帰って来ることなのだ、ということである。そしてこの遠くから帰って来た自分は、旧い日本に帰ったのではなく、自分に帰ったのだ。>
<一つの生涯というものは、その過程を営む、生命の稚い日に、すでに、その本質において、残るところなく、露われているのではないだろうか。僕は現在を反省し、また幼年時代を回顧するとき、そう信ぜざるをえない。この確からしい事柄は、悲痛であると同時に、限りなく慰めに充ちている。>
森氏の「生涯というものは、その稚い日に、すでにその本質が露われている」という言葉は、モーリヤックの下記の言葉と一見よく似ている:
<完成すべきものは、青年期の終りで、すべて我々の中で形を造ってしまうものだということを感じていた。我々の青春の戸口で、勝負はすでに決ってしまうのだ。それ以上には何も進まない。ことによったら、少年時代からもう決まっているかもしれない。外に出るよりも以前に我々の肉の中に埋っている、かくかく、しかじかの傾向は、我々の体の内奥で成長をとげ。我々の青春の清純さと合体する。そして大人になると、突然、”怖ろしい花”を開くのだ。>
だが、モーリヤックの言葉には「(肉体の不可避な運命として)幼年期、少年期の美しい相貌は、突然、内部からの罪によって腐敗し始める」という含意があり、森氏の言葉にはそれがない。
