hiroさんのレビュー一覧
投稿者:hiro
紙の本
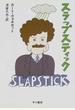
紙の本スラップスティック または、もう孤独じゃない!
2001/05/09 22:57
スラップスティック
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
カート・ヴォネガットの小説に共通して読み取れる、ちょっと憂鬱になるような諧謔、皮肉、ペシミズムといった特徴が、この小説にもある。時に時間や空間が錯綜し、複雑極まりなく読みづらい小説であっても、「もう1度読もうかな」と思ってしまうのは、そんな中にもどこかホッとするような、人のあたたかさや優しさが描かれているからだろう。「見るべき物もない汚い世の中だけど、こんな良いところもあるんだよ」という作者の声が聞こえてきそうだ。そんな穏やかなあたたかさが、この小説にもあると思うのだが、どうだろう。
紙の本

紙の本ループ
2001/05/09 22:49
ループ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「リング」「らせん」と続いた3部作の完結編。1作目の「リング」を読んだ時は、不幸な超能力少女の怨念がビデオテープに宿り、それを見た者を呪い殺すという発想に少なからず衝撃を受けた。少女の過去を暴く謎解きの興味と、呪いによる死期の迫った主人公の追いつめられた心理描写の巧みさで一気に読ませる、一級のエンターテイメントだと思う。次作「らせん」では、主要なテーマが前近代的な「呪い」から、極めて先端的な科学の分野であるウィルスやDNAへと転換する。この変化はまた、1作目で注目された「貞子の呪い」の単なる続きではない、全く新たな分野に挑戦した作品としての位置を明確にしていて、好感を持ったものだ。
そして完結編としての「ループ」。結論から言えば、「読まない方が良かった」というのが正直なところだ。「らせん」以後の混沌とした世界を、どのように収束させていくのか(あるいはどれだけ混沌が深まるのか)という興味で、首を長くして待った完結編だったのに……。発想の更なる転換、飛翔と言えば言えるのだろうが、これは「呪い」から「ウィルス」へという発展とは、少しレベルが違うのではないか。私には困難な問題からの逃避のように、思えてならない。
紙の本

紙の本審問 下
2001/04/28 23:29
魅力的な人達
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
検屍官シリーズ11作目。一作ごとに事件の複雑さ、人物描写の奥深さが増してくるようだ。前作「警告」の続編という事になりそうだが、事件の関連で言えば9作目「業火」さらには8作目「接触」にまで遡れるから、本当に長大な一連の事件と言うことになる。1作目から読むのでなければ、せめてそのあたりから読むのであれば、本書は一層面白く読めるだろう(勿論、単独の小説としても間違いなく面白い)。
主人公ケイ・スカーペッタは、作を追う毎にスーパーウーマン振りを発揮しているが、苦悩をも深くしていく。単なる「勧善懲悪・めでたし、めでたし」的な小説でないところが、このシリーズがこれだけ長く多くの人に読まれる所以だ。それ以外の登場人物も、同じように成長し、人生に疲れ、人間味を増していく。読む者にとっては同じ時を生きる友人のように思えてくるのが、これだけ長く続くシリーズ物の良い所だと思う。作中人物と一緒に苦悩し、正義感に燃え、年をとっていくのである。
本作では犯罪の精緻さもさることながら、人物描写の点でこれまで以上に、深く掘り下げられている。レギュラー陣のこれまで語られなかった意外な一面や、人物を取り巻く環境の変化など、シリーズ中の画期的な作品になっている。長年に渡りキャリアを積み上げてきた検屍局長の辞職といい、今後の新たな敵となる犯罪組織の登場を思わせる終わり方といい、主人公達の活躍がこれからも長く続きそうな期待を持たせてくれるのが、この「審問」だと言えそうだ。
紙の本

紙の本20世紀言語学入門 現代思想の原点
2001/04/28 23:08
20世紀言語学入門
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
詩や小説と言った文学、思想や社会学と言った人文科学に興味のある人であれば、それらに形を与える言語その物に惹かれた経験が一度はあるのではないだろうか。日頃から読書することの楽しみに通じていればなおのこと、私達にその恵みを与えてくれる「言語」の学には抗しがたい魅力がある。思想や哲学にしても、様々な思索は言語によってなされるところから、「現代の思想は、言語という基本要素をやっかい払いしうるどんな超越的立場もありはしない」という立場に立って、本書は20世紀の言語学の流れを概観している。
民俗学や社会学等、様々な分野の学問が相互に影響しあって現代の言語学が形作られ、それがまた思想や哲学に還元されていく様は、知のダイナミズムを感じさせる。本書はそれを初心者にも理解できるように、ある時は単純化し、またある時は身近な比喩を用いてわかりやすく概説してくれる。これから本格的に学ぼうという人にとっても、格好の入門書になるのではないだろうか。
紙の本
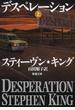
紙の本デスペレーション 上巻
2001/04/14 17:40
デスペレーション
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
選ばれた者達が邪悪と戦う。「IT」を思わせるような筋書きではあるが、そこはキングであればこそ、そんなことは全く気にさせず一気に読ませる。異様な警官が旅行者を暴力的に拉致していく冒頭で、読む人に今流行のサイコ・ホラーかと思わせながら、やはりそれだけではすまさないところもキングの小説らしい。
この小説では、特に神と救済といったテーマが扱われている。ただ単に「弱い人間を助けるだけではない神」という、キングの解釈も興味深いところだ。
紙の本

紙の本ハンニバル 下巻
2001/04/02 18:58
「え、何で?」という感じ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これまでのトマス・ハリスの小説の例に漏れず、これは絶対に面白い。面白さの一つは、まず、ディテールの見事さだと思う。詳細なリサーチのもと作品を仕上げることで有名な作者だけあって、実にリアルな描写が続く。例えば冒頭、クラリスらFBIが麻薬犯の取り締まりに向かう場面。何人もの男がひしめくバンの荷室に大量のドライアイスが何故か積まれている。エンジンを止めたまま張り込まねばならず、エアコンが使えないとすれば、少しでも空気を冷やすために積むというのは成る程と頷ける。それでも室内に染み着いてしまう体臭と汗の匂い。これはもう、実際に体験しなければ書けない場面なのではないだろうか。またレクター博士の趣味に関する部分。これなども生半可な知識ではこれ程説得力のある小説にすることはできなかっただろう。作者の広範な興味と知識が伺える。
更に面白いのは、怪物レクターの意外に人間的な面が垣間見られるところ。悲惨な過去が語られる中でみられる、幼い妹への追慕の情は切ない程だ。また団体旅行の旅客機の中で、同乗者に悟られぬようそっと食べようと楽しみにしていたフォションのランチを、隣の子供に見つかりあげざるを得なくなる、ちょっと微笑ましい姿。単に`怪物’としての恐ろしい姿だけではなく、より人間的な面が描かれているのが興味深い。反対に博士を捉え、拷問・殺害しようとしている面々はどうだろう。司法省の大物、大富豪、誘拐屋、保安官代理といった人達。何れも出世や富、復讐や血に飢えた人間だ。レクターのように人間は食べなくても、余程`怪物’なのである。この対比がまた、面白い。
ただ一つ、「う〜ん」と唸って首を捻るのが、結末の部分だ。法とそれが定める正義。それを追求し行動の原則にもしてきた前作からのクラリスにして、この結末。「え、何で?」と言う感じだ。まだ読んでいない方は、ぜひ御一読を。
紙の本

紙の本取り替え子
2001/04/01 12:02
「取り替え子」に思うこと
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
伊丹監督の自殺はまだ記憶に新しいところ。実際の義弟に当たる作家の書く小説であり、また登場人物の人間関係も(名前こそ違っているけれど)事実に即したものだとすれば、小説としての興味よりも謎めいたスキャンダラスな事件への興味がより刺激されるのではないか。しかしこの小説は、当の自殺に対してされた論評や世間一般に抱かれた疑問に対する作者の反論・解答ではなく、あくまで大江健三郎の小説(フィクション)である。伊丹氏の自死に大きな衝撃を受けたのは事実だろうが、この小説はその経緯を跡付けるのがテーマではなく、その死あるいは回復不能な衝撃からの復帰・新生を描いている。これは作者の小説に一貫して流れるテーマだろう。主人公と義兄の、共に創造的な仕事をする2人が、同じようにこれまでの仕事に対する悔いやこれから先の困難・不安を抱いたとき、つまり同じように人生の壁に突き当たった時の、対処の仕方のモデルとしての2人の違いに、この小説のテーマがあると思う。
書評欄で安原氏は酷評されているが、終章のセンダックの引用については、全く同感だ。またこの終章が主人公の妻を中心にして語られている点にも違和感を覚える。これまでも作者の小説には女性(母)的な力は色濃く出ていた。所々に登場する主人公の妻にしても、四国の谷間を背景とした母的な力に結びついていたように思う。「魂の再生の物語」という背景があったわけだが、今回の小説ではむしろ兄との関係で生きてきた存在として行動している。これは読む方としては弱い印象を受けざるを得ないのではないだろうか。いずれにしても、小説の内容はもとよりこの本の体裁は、学生時代よりずっと愛読してきた一ファンとしては、少し寂しい気持ちがした。
