月乃春水さんのレビュー一覧
投稿者:月乃春水

みみをすます
2005/04/22 00:20
朗読、音楽、イラストの相乗効果。澄んだ荘厳な詩の魅力が最高に生かされている、すごい本!
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
谷川俊太郎さんの一編の詩が、長新太さんのイラストと、ご本人の朗読、ご子息である谷川賢作さんの音楽、英語の翻訳と朗読で再編成されています。
聞いてみて…
思わず泣きました。
『みみをすます』は、わたしにとってこの本で初めて知った詩です。
初めてが「耳から」でよかった…
はからずしも、幸運な出会いになりました。
わたしの住んでいるところは田舎で、ずいぶん昔から人が住んでいるようです。
古墳もあるし、土器が出土したりしています。
近所には杉や竹林があります。
子どもと散歩に出かけ、ゆったりと歩きながら、竹が揺れ、笹の葉が風にそよぐ音を聞いていると、なんだか厳かな気持ちになリます。
昔の人たちもこの音を聞いていたんだなぁ…
それぞれ様々なことを思いながら生活していたんだなぁ…
その気持ちがこの『みみをすます』に、澄んだ、荘厳な詩として表現されていた…
衝撃!を受けるほど、感動しました。
朗読は日本語のあとに英語。
英語は音が小さくなっているので、それこそ耳をすまさないと聞えません。
これは演出なんでしょうか…
音楽は、効果音といってもいいかもしれません。シンプルな分、詩の朗読を凛と際立たせ、内容にまで深く沁みこんでいくような効果があります。
さらに、長新太さんの絵が素晴らしい。
橙と黄色の暖色のクレヨンで描かれていて、一見、いたずらにさらりと書いたように見えますが、じつは詩の本質をずばり表現しています。
これぞ巨匠の技でしょう。
一編の詩の魅力が最大限に活かされて存在している…
すごい本です。
たとえば病気療養中の人や、産後間もない人へのプレゼントにもいいのではないでしょうか。
初めて出会う方も、かねてからご存知の方も、この詩を、この一冊を通じてぜひ堪能していただきたい。
そう強く願います。
【月乃春水 ツキノ・ハルミ 本のことあれこれ】

はるがきた
2012/04/04 06:15
なかなか来ない春を待ちわびた人の提案と行動。「自分にできることをする」という素敵な見本。春先に読みたい絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『どろんこハリー』シリーズで有名なジーン・ジオン&マーガレット・ブロイ・グレアム夫妻による絵本です。1956年の作品ですが、日本では未訳で2011年に初お目見えというわけです。
春を待ちわびている街とそこに住む人々のものがたり。
2012年も寒い日が続き、なかなか春らしくならない。そんな気候だったのでなんともぴったりでした。
「はるは まだ こないのかしら」
街は灰色、街路樹は枯れ枝。はるはまだ、どこにもみあたらない。
人々は街の色とおなじように、暗くて沈んだきもち。
通りを歩いていた男の子が、いいことを思いつきます。
「ねえ!どうして はるを まってなきゃ いけないの?
まってなんか いないでさ、ぼくたちで まちを はるに しようよ!」
近くにいたおとなたちは男の子の説明を聞き、たちまち笑顔に。
そして おばさんがこう言うのです。
「さっそく しちょうに そうだんしましょう! さあ、みんな てつだって!」
次の日から、街の人たちは行動開始です。
さて、なにをするのでしょう…?
じっくりとご覧あれ!絵本のページもみるみるうちに色づいていきます。
けれどもその晩、雨が降り…
その後の変化はさらに見ものです。
このおはなしでわたしが素敵だなぁと思ったところは2つあります。
ひとつは、男の子の提案をおとながまずは聞く、ということ。
子どもだからと、聞く前にシャットアウトしたりしないんです。
ふたつめは、自分たちにできることをしよう、という態度。
寒い寒い、と言って春を待っているいるだけではなく、動き出すんです。
突拍子もないと言えなくもないアイディアですが、すぐに実現させようと動くことはとても大事なこと。それを許可した市長もすごいですね。
「自分にできることをする」という素敵な見本がここにあります。

うできき四人きょうだい グリム童話
2012/03/16 15:49
正真正銘のハッピーエンド。ホフマンの絵が持つ魅力で引き立つグリム童話
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
2012年は、ドイツでグリム童話が初めて出版されてから200周年だそうです。
フェリクス・ホフマン画によるグリム童話はいくつかあるようですが
わが家にもあり、お気に入りなのが『おおかみと七ひきのこやぎ』。
おはなしは、わたしも幼い頃から親しんでいますが、ホフマンの絵が素晴らしい。
大袈裟に描かれているわけではないのに、それぞれ個性があふれ出ているこやぎや妙に色気のあるおかあさんやぎ。そして景色の美しさ。
巧み、というのとはちょっとちがう気がしますが、なんともいえない魅力があるのです。
しかしこの『うできき四人きょうだい』はストーリーも知りませんでした。
偶然手にして、中表紙の四きょうだいの姿に釘づけです!
四人の息子をよその土地にいって仕事をおぼえてくるようにと送り出した父。
きょうだいは四つの道をそれぞれ行き、別れます。
それぞれが出会った人は…?
弟子になって身につけた仕事は…?
四年後、四人は再会し、それぞれの腕前を父親に披露します。
そこへ王さまのおひめさまがりゅうにさらわれたというニュース。
無事に連れて帰ったものにはおひめさまを嫁にやろうというおふれが出ます。
「いまこそ、うでのみせどころ」と旅立つ四人きょうだい。
おひめさまは海の上の岩てのてっぺんにいました。
ところが、りゅうがおひめさまのひざをまくらに眠っている…
このシーンは見どころがあり!
四人はそれぞれ身につけた得意分野を活かし、おひめさまを救い出します。
おわりはめでたし、めでたし…なのですが、えっ、こういう終わりかたですか!?と、肩すかしをくらった気がしました。
この場合、王様が賢い、というべきでしょうか。
正真正銘のハッピーエンドとなっています。
それを象徴するかのようなラストシーンも印象的です。
グリム童話×ホフマンの作品、これからも読み進めてみたくなります。

きみたちにおくるうた むすめたちへの手紙
2012/02/28 04:47
バラク・オバマ&ローレン・ロング、ふたりの父親によるすべての子どもに捧げられた願いは…アメリカの歴史を変えた13人を称え、子どもの持つ可能性を教えてくれるメッセージ絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
アメリカ合衆国第44代大統領のバラク・オバマがふたりの娘に向けた手紙です。
この絵本でオバマ大統領はアメリカの功績と、アメリカを形づくる理想を語ります。
アメリカの歴史の中で大きな変化をもたらせた13人の偉大なアメリカ人を称えています。
元気いっぱい歩いて行くふたりの娘たちが絵本の左側に描かれ、
右側には、偉人たちとその功績が描かれています。
それを見上げている子どもは、その人の子ども時代の姿でしょうか。
まるで未来の自分を見上げているようにみえます。
ページをめくるたび、子どもたちが増えていきます。
アメリカの偉人たちの功績を語ったあと、最後に自分たちの娘に話を戻し、
彼女たちの才能と可能性を指摘しています。
しってるかい?
きみたちの なかにも おおきな ちからが ひそんでる、ってことを。
きみたちも かがやく ひとに なれる、ってことを。
みらいを つくるのは きみたちだ、ってことを。
これは、自分の子どもだけに向けたメッセージではなく、アメリカそして
世界中の子どもたちに向けられたものでしょう。
イラストは、子どもの本の作家・画家として活躍しているローレン・ロング。
ふたりの息子の父親だそうです。
バラク・オバマとローレン・ロング、ふたりの父親による、すべての子どもに捧げられた願い。
共通しているのは「子どもたちに自分の可能性を知ってほしい」ということです。
紹介されているのは以下の13人です。
ジョージア・オキーフ ─ 大きな花や動物の骨の絵で知られる画家
アルバート・アインシュタイン ─ 相対性理論を唱えた物理学者
ジャッキー・ロビンソン ─ メジャーリーグ初のアフリカ系選手
シッティング・ブル ─ 北米先住民スー族の大戦士
ビリー・ホリデイ ─ 多くの名曲・名唱で知られるジャズ歌手
ヘレン・ケラー ─ 視覚と聴覚を失いながら活動した社会福祉事業家
マヤ・リン ─ ベトナム戦争戦没者慰霊碑を設計した中国系の建築家
ジェーン・アダムズ ─ 貧困をなくすために努力した社会事業家
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア ─ 公民権運動の指導者
ニール・アームストロング ─ 月面を初めて歩いた宇宙飛行士
シーザー・チャべス ─ 農場労働者の人権を守ったメキシコ系の運動家
エイブラハム・リンカーン ─ 奴隷解放宣言に署名した大統領
ジョージ・ワシントン ─ アメリカ独立戦争を戦った初代大統領
日本で2011年7月に発行されたものですが、「ローレン・ロングさんから
震災によって今も大きな困難に直面している日本の子どもたちに向けたメッセージ」が寄せられています。
最後はこのように締めくくられています。
この絵本が国境をこえて、日本の子どもたちにも
なぐさめや勇気やはげましや希望をあたえることを私は願っています。
そして日本の子どもたちにも、困難を乗りこえる力や、
すばらしい生き方をするための力が、自分の中にもあると
気づいてくれるよう願っています。
子どもたちのみならず、おとなも勇気づけられます。

ぼくがあかちゃんだったとき
2012/02/21 08:03
誕生日に父が息子に話す、はじめて会った日からきょうまで。繰り返し語りたい、成長のエピソード。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
6歳の誕生日を迎える日。パーティーのためたくさん料理をつくるおとうさんが、ぼくに生まれてからこれまでのことを話します。
浜田桂子さんのこれまでの絵本『あやちゃんのうまれたひ』では、母が娘に、生まれたときのことを話していましたが、
こちらは「ぼく」が語り部。父と子の会話がとても素敵なんです。
おかあさんは、やってくるおじいちゃんとおばあちゃんを迎えに行っているところ。
おとうさんとぼくはふたりきりです。
おとうさんが、ぼくをひざにのせて、にこにこして 言います。
「おおきくなったなあ。
あの ひから 6ねん たったんだなあ」
「あの ひって?」
「きみに はじめて あった ひさ」
おとうさんは、ぼくがあかちゃんだったときの話をはじめます。
このおはなしのおもしろいところは、
ぼくが観客として、あかちゃんだったころの自分をながめているところ。
いまの自分と比べているんです。
おかあさんも ひるま ねむるんだ。
なにしろ よなか、きみに
しょっちゅう おっぱいを あげるからね。
そこで おとうさんの でばんさ。
りょうり せんたく、どんと まかせとけってね。
描かれているのはとっちらかった台所。
おとうさん、料理本と首っ引きです。
あ、なべがふいてる!手に持ったおたまからも、シチューがたれてるよ。
ぼくは
ねえ、おとうさん。
だから おとうさん、
りょうりめいじんに
なったんじゃない?
ぼくの おかげだね。
…たしかに。子どもの成長とともに、おとうさんも進歩したんですね。
簡単なようですが、おとうさん自身が意識して行動しないとできることじゃありません。
おかあさんも、全部自分でやってしまうのではなく、おとうさんにやらせてあげないとね。
夫婦お互いの協力あってこその、変化ですね。
はじめてわらった日、おしめをかえるとき、はじめての熱。
おとうさんとぼくの様子はコマ送りのように描かれているものもあり、
まるで映像を見ているようです。
うごきだし、たち、あるく。
ぼくも当時の自分ににエールを送り、いまのぼくとおなじになったと喜びます。
元気いっぱい、好奇心にあふれてうちの中のあらゆる物を出すぼくの姿。
いまのぼくはびっくり!
最後のおとうさんのことば、そしてぼくの返答がとても素敵です。
待ち焦がれたあかちゃんが、いま年月を経てここにいる。
成長してくれて、ほんとうにうれしい、ということ。
いま、ここにいる、子どもという存在に対する肯定です。
それを祝い、振り返る日。
その日が誕生日、ということですね。
表紙はぼくが1歳の誕生日。
ケーキにたてたろうそくをさわろうとしているぼく、
あわててとめるシーンが切り取られています。
おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃんも勢揃い。
きょうと同じお祝いの日です。
子どもが生まれてからこれまで大きくなってきてからのエピソードは
子どもが小さいうちは誕生日ごとに、または子どもがせがんだらいつだって話して聞かせたいな、と思います。
母親ではなく父親から聞くと、ひと味もふた味もちがうのでしょうね。
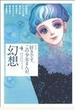
好きです、この少女まんが。 4 (KCDX)
2012/01/26 10:57
少女漫画家により厳選され、テーマ別に編集された傑作・名作アンソロジー。豪華です!
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
表紙とタイトルに惹かれ、読んでみました。
「好きです、この少女まんが。」という傑作・名作集のアンソロジー第4弾。
このシリーズのコンセプトがこれまた素晴らしい。
1. 10代~ベテランの「描き手」である少女漫画家85人が自薦他薦を問わず厳選
2. すべての作品にプロの目から見た少女漫画家からのセレクトコメントつき
3. さまざまな年代の製作委員(少女漫画編集)が実際に全てを読み、全員一致で高評価
4. 年代別ではなくテーマ別で区切り、母娘で読み継がれる不偏の不朽作
5. 出版社という少女漫画界の垣根と常識を超えた作品集
(講談社コミックプラス「好きです、この少女まんが。」より)
『幻想』がテーマの4巻、収録作品は
吉田秋生 きつねのよめいり(よしまさこ選)
いくえみ綾 My dear B・F(みやうち沙矢選)
森川久美 君よ知るや南の国(宮島葉子選)
阿部律子 アルカディアの少年(英洋子選)
美内すずえ 泥棒シンデレラ(秋元奈美選)
耕野裕子 地上の一点(桐島いつみ選)
名香智子 気のふれた(中山星香選)
わたしが知っていたのは『My dear B・F』のみですが、いつ読んでも泣けてくる名作です。ここに収録されていてうれしい!
どの作品も、読後に「ふぅーっ」とため息が出ます。
読後のため息というのは、いい作品に出会ったときのしるしみたいなもの。
こころに残る作品である保証書ともいえるかもしれません。
アンソロジーというのは、漫画に限らず小説も、わたしはとても好きなのですが、とにかくこの企画はすごい。
選者の熱いコメント&イラストがあるからなおさら、作品の素晴らしさを共有し、味わうことができるように思います。
他のテーマも読んでみたくなります。
それから現役の少女たちがこのまんがを読んでどう感じるのか。
そんなことも気になります。

シロナガスクジラより大きいものっているの?
2011/07/13 13:39
大きく壮大な「宇宙」のおはなし。比較と比喩がおもしろく、想像することを可能にする絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「ふしぎだな?知らないこといっぱい」シリーズの一冊。
地域の親子読書会で、小学6年生に選書した絵本です。
「絵を見るだけじゃなくて、ちょっと頭の中で想像してみてね」と読み始める前に言ってみました。
タイトルが印象的です。いったい何のことが書かれているのか、と思いますよね。
シロナガスクジラそのものではない、とは想像がつきますが。
「宇宙」のことが書かれているんです。シロナガスクジラは大きさの基準です。
最初に文字だけのページがあり、この本には宇宙のこと、そして大きなもののことが書かれていると説明があります。
まずここで、途方もない数について、あらためて認識させられてしまいます。
どのくらい大きな数か、ということの例として挙げられているのは「数を数える」ということ。
100まで数えるとだいたい1分かかる。
1000まで数えると12分くらいかかる。
100万まで数えると、1日に10時間数え続けたって、3週間はかかる。
10億まで数えるなら、毎日12時間数えつづけても、50年以上かかる。
…そんなこと、考えてみたこともありませんでしたが、なるほど、そういうことなのか。
わたし自身が、はぁ~っとため息つきながら納得してしまいました。
おはなしは、シロナガスクジラの大きさの説明からはじまります。
そばにいるのは、ゾウ、ライオン、馬。大きさの比較として、さらに観客としての役割もあるかな?読者といっしょになってシロナガスクジラの大きさに驚いているようです。
シロナガスクジラは尾びれのところだけでも、地球上のたいていのいきものより大きい。
そんなに大きなシロナガスクジラをものすごーく大きいびんに、100ぴきずつ入れたとして…
そのびんを、ふたつずつ、またまたものすごーく大きな板の上にのせたして…
その板を、10枚重ねて、もうびっくするくらいの高さにまでつみあげたとしても…
エベレスト山の上にのっけてみたら、こんなに小さくしか見えないんだよ!
と、大きいはずのシロナガスクジラ入りのびん(板に乗せて10枚重ね)がとても小さく描かれています。
ページをめくるたびに、大きくなったり、小さくなったり。
読み手は、絵本を横から縦にしたり、また横に戻したり。驚きも高まっていきます。
シロナガスクジラ→エベレスト山→地球→太陽→アンタレス→銀河→宇宙
と、大きさの比較は続きます。
伝え方がとってもおもしろいんです。
地球を袋に入れたり、太陽をオレンジと見なして箱詰めしたり。宣伝文句までついています。
途方もないほどの大きさが、可笑しなたとえのおかげで、想像ができるようになる。
これってすごい!
最後は、宇宙の大きさについて、本当のところはまだわかっていない、と締めくくられていますが、文章はこんなふうに書かれています。
「だけど、すくなくともこれだけはわかったよね、
うちゅうは、シロナガスクジラより、
うんとうんと大きいってことがね。」
これは4月のおはなしタイムで読んだのですが、最中にマグニチュード6.3のかなり大きな余震があり、読むのを一時中断しました。
揺れがおさまり、続きを読み始めたのですが、ざわざわしていた子どもたちも、すーっと本の内容に入り込んでいきました。
誰もが経験したことのない規模の東日本大震災から、まだ1か月しか経たない時期。
揺れると、怖い!と縮こまってしまいます。子どもに限らず、おとなだって。わたしは余震のたび頭痛が起きていました。
でも、この本は、縮こまってしまった気持が大きく、大きく、広がっていきそうな壮大なおはなし。
ちょうどいいタイミングだったかもれません。
深呼吸して、空を見上げたくなります。
からだや気持がなんだか縮こまってきてしまったら、またこの絵本を開いてみたいと思います。

コウモリのルーファスくん
2011/07/01 15:04
現状を変えたいコウモリのルーファスくんがやってみたことは…不思議とこころに残る、ウンゲラーの絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
コウモリのルーファスくんのちょっとした冒険と出会いの物語。ウンゲラーの1980年の作品です。日本では1994年に一度出版されたようですが、今回は今江祥智さんによる翻訳です。
いつだって灰色と黒の「夜の色」の世界で暮らしているルーファス。
ある夜、野外映画会でカラー映画を見かけます。はじめての色に驚いたルーファスは、いつもとちがうことをしてみます。次の日の朝、眠らずに、目をこじ開けて起きている。朝日の美しさにみとれ、まぶしいくらいの、色にあふれた世界にみとれ、憧れます。そこで、ルーファスがやってみたことは…
わかる、わかる。自分にないものに憧れて、新しい世界をのぞいてみたくって、ちょっと無理してやってみる。いざ、変身!そんなときのウキウキした気分といったら…。なんだか身に覚えがあるような。
変身してみてご機嫌だったのに、ひどい目にあってしまったルーファス。
チョウのコレクター、タータロ先生の庭に落ちてしまいます。幸福な出会いでした。タータロ先生のおかげでルーファスは回復し、ふたりは友だちになります。
ある日、ルーファスはタータロ先生と映画を見ていて、洞穴が恋しくなります。
結局のところ、元いた場所に戻るのですが、ふたりの交流は続いていきます。
全体的にさらりと描かれているのですが、不思議とこころに残るものがあります。
特にタータロ先生とのふれあいがとてもいい。先生の手当て、しぐさに感じられるのは愛、なんです。
自分にちょうどいい居場所や行動。そこに落ち着くまでには、冒険も必要です。
ルーファスもたいへんなおもいをしましたが、タータロ先生と出会えたのは、外の世界に踏み出したおかげなんですから。
憧れて、やってみたけれど、なんか、自分に似合わないことしちゃったな、なんてこと、ときにはあります。失敗して痛い目にあっても、得たものはきっとある。そんな気づきにも、なぐさめにもなりそう。
子どもはもちろんですが、おとなにも読んでもらいたい絵本です。

おこだでませんように
2011/06/14 18:41
いつも怒られてばかりの「ぼく」が七夕さまの短冊に、こころを込めて書いたおねがいは… おとなとして揺さぶられる名作絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「おこだでませんように」とは、小学1年生の「ぼく」が、七夕さまの短冊にこころを込めて書いたおねがいです。
いつもおこられてばかりのぼくの気持が伝わってくる、七夕にもぴったりな絵本です。
ぼくがうつむいて、石をけっている姿、
「ぼくは いつも おこられる。
いえでも がっこうでも おこられる。」
という文章で、おはなしははじまります。
家で妹と遊んでやったらわがままを言って、怒ったら泣いてしまう。
ぼくはおかあちゃんから怒られる。
おかあちゃんのことばと、それに対するぼくの理由や気持もあわせて書かれています。
けれどもぼくはそれを口に出しては言いません。
黙って横を向き、何も言わずに怒られる。
そのときの表情は表紙にもなっていますが、ぐっとおもいを閉じ込めて、耐えている横顔です。
学校で怒られたこと、家で怒られたこと。
エピソードが書かれていますが、読み手にはふたつの感情が交差します。
あぁ、それなら怒られてしまうわね、という親や先生と同じ立場で納得するおもい。
そうなのか、そういう事情や気持があっての行動なのか、と「ぼく」によりそうおもい。
どないしたら おこらへんのやろ。
どないしたら ほめてもらえるのやろ。
ぼくは「わるいこ」なんやろか、と悩み、夜も怒った顔がちらついて眠れないほどなんです。
七夕さまのおねがいを、学校に入学してから教えてもらったひらがなで、ひとつずつ、こころをこめて書いた短冊が、見開きで大きく書かれています。
これがタイトルにもなっている「おこだでませんように」
「ま」は鏡文字、反対になっています。
机の上にはおしりを噛んだあとのある鉛筆と、切れちゃった消しゴムもあります。
ぼくが小学生であることは、おはなしの最初のイラストからもわかるのですが、1年生だというのは、後半になってはじめてわかります。
1年生だからこそ一生懸命に、まちがえているけれど、書いた文字。
願いの強さ、ひたむきさが際立ちます。
「ぼく」がクラスで一番最後に出した短冊をじっと見た先生の反応は…
そして、先生から夜、電話をもらい、長いこと話をしたおかあちゃんは…
これが、ほんとうに素敵。おとなとして、まちがっていたことを認め、きちんと謝ることは、日常のあわただしさにまぎれて、なんとなくスルーされがちなことかもしれません。それでは、ほんとうはいけないのだ。そう思います。
七夕さまにお礼を言って、笑顔でふとんに入る「ぼく」。こころからうれしそうな、無邪気な笑顔です。
これは6年生に「おはなしタイム」で読んだ絵本です。
親子読書会で選書しているのですが、低学年に、ではなく、あえて高学年に。その理由は読んでみて、教室の空気を感じてよくわかりました。
「ぼく」の感情の動き、そして親や先生の反応も、客観的にわかる年頃なのでしょう。これまでになく、集中して聞いて、感じ入っている雰囲気がありました。
同じ日、図書ボランティアの活動があったので、この絵本を持って行き、参加した母たちに見せたところ、「ぼく」が自分の子どもに思える、など、ぼくの気持と登場する母の行動があいまって、反省と感動の声が聞かれました。
おとなが揺さぶられる絵本なのです。
関西弁は聞きかじりなので、読みにくいところもあるのですが、「ぼく」の感情がとてもよくあらわされていることばだと思います。標準語だったら、印象が変わってしまう気がしました。
読み手として、願わくば、関西出身の人が読んだ朗読DVDなどがあるといいな、と思います。
多くの人に届いてほしい、名作絵本です。
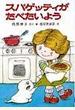
スパゲッティがたべたいよう
2011/06/13 09:05
おばけ×おいしいもの。なんだかそそられる、人気のシリーズ第一弾。おばけのアッチと女の子のエッちゃんのやりとりが見もの。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「小さなおばけ」シリーズの第一弾です。小学1年生の三男と読むおはなしを探していて、これはどうだろう?と読んでみたら、親子ともにとても気に入りました。
おばけ×おいしいもの。
どちらもなんだかそそられますよね。
おいしいものが大好きな、小さなおばけの男の子、アッチ。町いちばんの高級レストランの屋根裏に住んでいます。
ごちそうのいちばんおいしいところ(かなり個人的好みも入っているところがおもしろい。「えびフライだったら、かりかりしたしっぽ」とか。)だけ横取りしてしまう、いたずらなおばけです。
そんなアッチと人間の女の子、エッちゃんとの出会いが描かれています。
おいしそうなにおいに誘われて、ひとりでスパゲティをつくっているエッちゃんのうちにやってきたアッチ。
エッちゃんをこわがらせて、スパゲティを頂戴しようとするのですが、エッちゃんは動じません。
あまりにエッちゃんが怖がらないので、ついに姿をあらわします。エッちゃんとアッチのやりとりは見ものです。
自立しているエッちゃんはとっても素敵。アッチに対してのはたらきかけも、ほんとうにいいかんじ。おとなもこうありたいものです。
スパゲッティの歌もついています。ラップ風に読むとおもしろい。
そうして、アッチがスパゲィティをおいしくつくれるようになるところでおわります。
エッちゃんがかしこまった様子で出来上がるのを待っていますよ。
こんなふうにアッチとエッちゃんはなかよしになって、アッチはお料理するのも大好きになったんですね。
このシリーズはたくさんあって、勤めている図書館で返却されてきたのを見て知りました。
シリーズがごっそり借りられて返ってきたり、リクエストされていたりしているので、わたしも出会えたというわけですが、たしかに、これは次から次へと読みたくなるおはなしです。
文章は、声に出して読むのがとても心地いい。三男は、まだ自分では読まず、読んでもらうのを聞くのが好きですが、自分で文字をどんどん読み進める子にもよいのではないかと思います。
絵もかわいらしいのですが、女の子っぽくなりすぎていないので、男の子にも向いています。
これからシリーズを少しずつ、親子で読み進めていきたいと思っています。
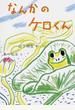
なんかのケロくん
2011/01/22 19:15
いつも「なんか」を求めて外に出て、うちに帰って「なんか」がわかる。かえるのケロくんとママの親子のあたたかいおはなし。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
いつも「なんか」と言っているかえるのケロくんのゆかいなおはなし。
なんかほしい
なんかしたい
なんかうれしい の3話が収められています。
かえるの子ども、ケロくんは「なんか」が口ぐせなので、みんなから『なんかのケロくん』と呼ばれているんですって。
おやおや、どこかで聞いたことのあるセリフです。うちの三男(6歳)もよく言うんです、「なんか」って。
ケロくんは、はすの葉っぱの上でお昼寝して、目が覚めたとたんに「ねえ、ママ。なんか」
ママとのやりとりがなんだか笑えます。
「なにが ほしいの?おやつなら さっき たべたでしょう」
「おやつじゃ ないもの、なんか ちょうだい」
「なんかじゃ わかりません。なにが ほしいのか はっきり おっしゃい」
「だって、ぼく なんかが ほしいんだもの」
おかあさんはケロくんにふうせんガムを1枚わたし、
「それじゃ、これでも かみながら なにが ほしいのか かんがえておいで」
と言うのです。
…なにか、はっきりとはわからないんだけど、なにかがほしい。
そういう気分、おとなだってありますよね。
すぐに結論は出ないから、こうした猶予が与えられるのはいいですね。
ふうせんガムをふくらませながら歩いていると、ケロくんはかまきりのおにいさんに会います。
ふうせんガムをつりざおと交換し、次はかにのおばさんに会い、また交換。次はかめのおじいさんに会い、最後にはママの元へ帰ります。
ケロくんのほんとうにほしかったものは…?
ケロくんがほしい「なんか」を求めて外に出て、だれかと出会い、うちに戻る。
そうして、ほんとうにほしかったものをみつける。
3つのおはなしはおなじパターンで進み、終わります。
最初の語り手が読者に話しかけるのもとてもいいかんじ。
あべ弘士さんが色鉛筆で描くケロくんや動物の生き生きした様子、はすの葉っぱ、くきがぐーんと伸びている姿。どれも生命力や躍動感みたいなものが感じられます。それがすごくいいんだよなぁ…大好きな絵です。
子どもひとりでも読める本ですが、これはやはりママが子どもと読むのがいいのではないかと思います。読み聞かせたママこそが、ほんわかしてしまうおはなしなんです。
『「なーんか、なんかよみたい」ときにはケロくんのおはなし』という帯の文句も最高!
ぜひとも続編を望みます。
<ブログ> 産後の読書案内

あそびにおいでよそらまめくんのおうち
2011/01/08 13:56
360度にひろがるそらまめくんワールド!サービス満点、たのしく遊べる立体しかけ絵本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
子どもたちに大人気の「そらまめくん」の立体しかけ絵本です。
表紙を開いて背表紙とあわせてマジックテープで留めます。するとそらまめくんとその仲間たちのいるはらっぱのできあがり。
そらまめくんのふわふわベッドはもちろん、なかまたちのベッド、あさつゆの池もあります。さらにすべり台やぶらんこも!
ピーナッツくんのおうちはかなり大きくてびっくり。はじっこにはうずらの親子もいます。
そらまめくんたちの立体人形もあるんです。手で持ったり、差し込んだりして遊べます。
基本ポーズのほかにおやすみポーズ、「わーい おや?」「うひゃあ」なんていう感情をあらわすポーズも。
しかけ絵本定番のめくったり、引っぱったりするところもあります。
どんぐりコップやお花などのかわいい小物がポケットにはいっていたり、ミニ絵本もついている、という徹底ぶり。うれしくなっちゃいます。
絵本の中の世界が立体になり、360度に広がるそらまめくんワールド。自由自在に遊ぶことができます。
わが家の息子たちも夢中になり3人で遊んでいました。
このしかけ絵本だけでも遊べるのですが、やはり本を読んで、そらまめくんと仲間たちのおはなしを知ってからのほうが何倍もたのしめるかと思いますよ。
そらまめくんのベッド
そらまめくんとめだかのこ
そらまめくんのぼくのいちにち
そらまめくんとながいながいまめ
<ブログ> 産後の読書案内

愛情日誌
2010/11/20 19:13
恋愛、結婚の先にある夫婦と小さい子どものいる日常。現代の夫婦小説の最高傑作!
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
恋愛し、結婚し、子どもが生まれた夫婦の日常、セックスについて描いた「現代の夫婦小説」最高の傑作!です。2004年刊行の単行本『愛情日誌』と2006年刊行の『夏の力道山』の中から「おでかけ」「愛情日誌」「夏の力道山」が文庫にまとまったものです。
登場人物は3作とも同じ家族が中心です。映画監督で時々俳優もする夫、明彦。学生時代の友達と五人で編集プロダクションをやっているわたし、豊子。
三十四歳、三十六歳で出産。子どもは四歳の昇太、二歳の宝子。
1作目は土曜日、夫婦でラブホテルに行く、タイトル通りの「おでかけ」に至るまでの夫婦の暮らしぶりが会話も交えて詳しく描かれています。
朝、朝食と夕食の支度をしながら、起きてくる昇太にパジャマを着替えさせ、(やってあげるのではなく、服を自分で選ぶのに、話しながら根気強くつきあう)、けんかをはじめた兄妹をしかり、夫婦は険悪なムードに。ケンカの朝は、恋愛の成れの果て、という感じがする、という豊子のつぶやきが胸を打ちます。
「なんでこうなっちゃうのかな。好きな人と結婚して、その人の子どもを産んで育てて、自分で働いて、まぁお金の心配もなくて。ひとつひとつの事柄を取り出して考えると、どこにも問題はない。でも、わたしの現実は、ぷんぷん怒ったり、夫に優しい言葉も掛けられないような毎日だ。(略)こんなこと嫌だな。」
家で仕事をする時は、九時には眠り、三時頃むっくり起きる豊子。
「わたしは子どもを産んだら原始人になっちゃったの」
(これってわたしも似たような生活パターンなので笑ってしまいました。)
豊子の明彦に対する気持は
「好きだけど、好きの種類が違うのだ。前は首にしがみいて「うわぁ、好き好き好き」という感じだったけど、今は後ろをどこまでも付いて一緒に歩いていきたいという好きなのだ。」
「愛情日誌」は「おでかけ」のその後。「久し振りにしたら、なんだかぱっとしなかった。」とはじまります。豊子の場合は「わたしはね、ちんちんの安定供給より、日々の親切の方が嬉しいんです」。
夫婦の会話も、深刻過ぎず、どこかとぼけた風情があるのがたのしい。温かい愛情が底辺にあります。
豊子のつぶやきに深く共感する、母である女性たちは多いのではないかと思います。たとえばこんな。
夜、こんな風に寝ている子どもたちを見ると、わたしは決まって朝顔の苗を思う。テレビの教育番組で見たシーンだ。早廻しに撮った映像で、苗は蔓をぐるぐる伸ばして、ずんずん大きくなっていった。この子たちは、一体いつ、こんなに大きくなったのだろう。わたしも、あの苗の映像のように、子どもたちが大きくなっていく瞬間を見てみたい。わたしたちの体には、時間が魔法の粉のようにまぶされている。宝子の髪は肩よりも長くなり、昇太の歯が抜け、明彦のちんちんはぐったりし、わたしの発情期は去ってしまった。(P115)
ずっと一緒にいるということは、相手の体の記憶が、自分の体に移り住むということだ。体のことだけじゃない。一緒に過ごしてきた時間が、層を成して、お互いの成分になることだ。(P115)
写真などには残らない、ささいな瞬間が、わたしの成分になっていく。小さな事どもを忘れたくないと思う。(P115)
3作の中でいちばん長い「夏の力道山」は、「煙草を吸う人に効く」といって明彦に普段飲む錠剤にマカを追加して渡しているシーンからはじまります。この「マカ」はストーリーのちょっとしたアクセントになっています。
夫婦の友人や仕事のパートナー、後輩、得意先の奇異な人も登場します。豊子の仕事や人への向き合い方、考え方も描かれていて、親近感が増しました。
きょうも豊子は電動自転車をうんしょ、うんしょと漕いでいるのかなぁなんて想像すると、わたしも元気が湧いてきたりして。
大変な話も挿入されています。豊子の通っている、自宅で鍼灸治療院を開業している女性の瀬川先生が語る、自身の子どもができたきっかけ、出産直後の話、女性が子どもを持って働くこと、セックスレス、そして再度の妊娠。
人の人生にいいとか悪いとか、正解も不正解もないけれど、これを聞いて(読んで)どう思うのか。語りあってみたい気がします。
子どもが生まれたあとの夫婦のセックスレスについては、NHKでも放送されたり、雑誌の特集などでもみかけることがあります。「問題」としてひとり歩きさせるのではなく、小さな子どものいる暮らしの現実の中で、明彦と豊子それぞれの事情や気持とからめて描いているこの小説の手腕はお見事。架空の話とは思えず、豊子の物語はわたしたちみんなの物語でもあります。
文庫版のあとがきで、作者の夏石鈴子さんの書かれていることにも、とても共感しました。
夫婦がうまくやっていくには、相手に対する思いやりは欠かすことはできないだろう。もしかしたら、この思いやりという中に、セックスという要素もちょこんと入っているのかもしれない。セックスはあればいいけど、なくても、また別な絆が生まれてくるのではないか。長く一緒に暮らしていく夫婦には、「夫婦生活」というよりも、夫婦であるという「夫婦活動」こそが必要なのではないか。(P225)
日々成長していく子どもたちのいるなかで、状況は移り変わり、自分やパートナーの気持もゆれたり固まったりしながら変化していく。
毎日があわただしく、バタバタしてくたびれきってしまうけれど、休んで気を取り直し、さまざまな事情と折り合いつけながら、なんとかうまくやっていきたい。
そんなふうに、夫婦や家族のありかたについて、自問自答したり、夫婦で話したり、友人同士で話したりして、よりよい道を探している人は、わたしも含めて多いのではないかと思います。
そんな試行錯誤のお伴になるのがこの小説です。
詩人の平田俊子さんによる解説「幸せ、あります」は、この小説におもわず引きずり込まれ、五十嵐豊子に共感した目で書かれていて、これまたとても魅力ある文章になっています。
<ブログ> 産後の読書案内(本のことあれこれ)

天才柳沢教授の生活ベスト盤 The Red Side
2010/10/10 08:34
名盤!初めて手に取るには最適。いかにして「天才柳沢教授」が現在に至るのか…?じんわりと堪能できます。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『天才柳沢教授の生活』のベスト盤です。
「感動はいつも熱くて、静か。」「世界に心をふるわせる短編13話を収録。」という帯の言葉に惹かれました。
が、なによりも、以前から気になっていた漫画なのに手に取る機会がないままでしたので、これはいい!と、見つけて即座に飛びつきました。
1988年から「モーニング」誌に掲載された全211話からの傑作選です。
収録作品は
「縛られて」 第134話
「飛行機男」 第74話
「想い出がよみがえる時」 第31話
「桃太郎のいる風景」 第77話
「私という少年」 『天才柳沢教授の冒険』(第4話)
「その表情の向こう(前編)」 第96話
「その表情の向こう(中編)」 第97話
「その表情の向こう(後編)」 第98話
「あなたを知りたい」 第99話
「ソネット83番」 第102話
「夏の思い出」 第104話
「校庭を見ていた少年」 第181話
「おとうと」 第121話
巻頭に「主人公・柳沢良則とその家族。また、その頻出する人物について。」の簡単な説明があるので、わたしのように初めて読むという人でも、すんなりとストーリーに入っていくことができます。
この本では、柳沢教授のこれまで、歴史を垣間見ることができます。
どのようにして、柳沢良則という人が現在のようになったのか?
少年時代のエピソードは特に印象に残ります。
ところで、読み終わるまで気がつかなかったのですが、これは「The Red Side」。
もう一冊、「The Blue Side」もあるんですね。
まさにThe Beatlesのベスト盤と同じわけで、だからこその「ベスト盤」(「版」ではなく)。
こんなタイトルづけ、選りぬかれた作品の並び順の妙といい、存分に堪能できました。
じんわりと、こころの深い部分が揺さぶられます。
青盤も、すぐにでも読まなければ!
<ブログ> 産後の読書案内(本のことあれこれ)

だるまさんの
2010/10/02 05:04
だるまさんのからだの一部が…?笑いがはじけちゃう!あかちゃんからたのしめるシリーズ第2弾。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
かがくいひろしさんの「だるまさん」シリーズ第2弾。
短い手にメガネを持っているだるまさんが表紙です。ちなみに足もあるんです。
「だ る ま さ ん の」と、片足で立ち、左右に傾いているだるまさんの姿がひと文字ずつに描かれています。
ページをめくると…「め」(目)
ぎゃははーっ!と笑っちゃう。
次はまた、「だ る ま さ ん の」
このときのだるまさんの姿に注目。ページをめくると出てくるひと文字、つまりだるまさんのからだの一部がもうわかるようになっています。
からだの一部はわかっても、その描き方は奇想天外。
「そう来たかー!」と叫んじゃう。
最後は「ふふふ」と笑っちゃう仕上がりです。
だるまさんの疑問、問いかけに子どもはすぐに答えます。「ないっ!」
3作のシリーズものですが、どれもこれも存分に楽しめます。
あかちゃんでなくとも大丈夫。
試しに小学校の昼休みの図書室に持って行ってみたら、5年生の子が友達とページをめくり、そのたびにはじけるような笑いが飛び出していました。
だるまさんといったら、完全に?置物なわけですが、こうして手足を与えられ、いきいきと動きだし、おもいもよらぬ展開が待っている。
こんなわくわくする絵本、おとなも見ずにはいられませんよ。
■だるまさんが (書評があるのはこちら)
■だるまさんの
<ブログ> 産後の読書案内(本のことあれこれ)

