健忘さんのレビュー一覧
投稿者:健忘
| 10 件中 1 件~ 10 件を表示 |

武士道 改版
2004/02/01 23:27
日本人の道徳とはこういうものだろう。
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最近、「道徳」なる言葉を聞くことが多い。「国民の道徳」という本も出ているようである。そもそも道徳とは何か、人が生きていくために、最低必要な倫理、というものではなかろうか。その道徳、日本ではどのような形で、昔から教えられていたのか。その答えを記しているのが、本書であろう。著者はご存じ、新渡戸博士。といっても、最近の若い人になじみがなければ、5千円札のおじさん、である。
本書は新渡戸博士が、ベルギーの法律学者、ラブレー氏に、日本は宗教教育無くして、如何に道徳教育を施すのか、と質問され、自分の道徳教育の根本理念は武士道にあり、と感じて書かれたものである。本書では、武士道の基本に、仏教の諦観、神道の教義、儒教の教訓があると見る。この三者が一体となって、日本の道徳概念が形成されたと見ている。その道徳概念は、封建制度に培われ発展した。ここまでくると、それは男性中心社会の道徳理念ではないかと反論もでようが、博士は、第14章“婦人の教育および地位”という一章を設けて、封建制度の下においても、婦人の教育と地位も武士道の中に組み込まれたもので、決して婦人の地位は低くなかった、と述べている。このあたりは、本書が外国人向けに英語で書かれたことと、婦人が外国人であった博士らしい論述でもある。博士は、日本の道徳教育の形を広く海外に示し、日本の文化への理解を広め、日本の道徳は武士道だと主張した。ここに本書の最大の貢献があると思う。
本書を読んで、人の情とか倫理といった基本的なことは、現代でも共通の問題だと思った。しかし、これらの問題は、決して学校教育の問題ではなく、家庭教育の問題であろう。博士も武士道が学校やそれに類するところで教えられたとは言っていない。昨今の道徳教育論議は、学校に道徳教育を導入するしないといった議論である。日本では道徳というのは、人の道という考え方であった。それを学校で教え、評点いくつ、というのは、まったく本末転倒であると思う。そう言った、日本の道徳とは何か、という問題を再考するのには、本書が一つの教科書となると思う。これが本当の“国民の道徳”だろう。

非対称情報の経済学 スティグリッツと新しい経済学
2004/05/19 00:37
情報の経済学がわかる。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
2001年度のノーベル経済学賞は、アカロフ、スペンス、スティグリッツの3氏が受賞した。受賞理由は「非対称情報下の市場経済」の経済分析に貢献したことによる。この理論、昨今、情報の経済学として流行っている。要約すれば、市場において、情報の完全性が成立しない場合、具体的には、中古市場や保険など不確実性が存在するときの経済分析である。この不確実性という状況が80年代以降、経済のグローバル化の拡大とともに注目されてきた。その状況を分析する経済学として、受賞したのであろう。
本書は非対称情報の経済を、伝統的な経済学の限界を指摘することから解き明かしていく。そして、伝統的な理論である完全競争市場では、市場の失敗や貧困問題の解決などの経済問題は生じなくなる、と述べる。ここに現実とのギャップを見て問題を提起し、完全競争市場の前提となっている“情報の完全性”を非現実的な前提だとして、非対称情報の世界での市場経済を解説している。その過程で、非対称情報の経済学を構築した3人の経済学者のうち、スティグリッツ教授の理論を紹介している。本書の特徴としては、従来の情報の経済学がどちらかというとミクロ理論を中心に論述されていたのに対して、マクロ理論の領域にも踏み込んで、失業問題や賃金の下方硬直性、貸し渋り問題なども非対称情報の経済学で分析しているのは目新しいところだろう。また、昨今、議論されている、コーポレートガバナンスの問題やモラルハザードの問題も論述されている。
本書は大学一年生などに解説したものを、ビジネスマン向けに通勤電車で読めるように書き下ろしたという。確かにこの手の本の中ではやさしい部類だと思う。しかし、3章までと4章以降ではレベルが違う。4章以降はどちらかというと経済学をある程度マスターした人が読むと良いと思う。このようなレベルの違いはあるにしても、この分野の入門書としてはお薦めの一冊だ。
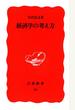
経済学の考え方
2000/07/12 13:04
経済学の大家が書いた近代経済学批判
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
近代経済学というと数学が出来ないとダメだという考え方がある。これは何故か?経済学が、完全情報のもと合理的な計算可能性を持つホモエコノミクスなる人間を前提に理論構築されているからである。ここから、ある制約条件の下目的関数の最適化という問題を解く、と言うのが近代経済学だ。この解法過程に数学が使われる。このようなモデルを「一般均衡理論」と言う。このモデルを現実の経済分析にあてはめ、計量モデルなどを構築しているのが、現在の経済分析だ。
このモデルよく考えると、完全情報を持ち、合理的な計算可能性を持つ人間でないと説けない。これは現実的ではないぞ、と気がつく。ここが近代経済学批判となる。このモデルの非現実性と非人間性を近代経済学の大家が、アダム・スミスから最近の経済理論までの流れに沿って解説しながら、切々と述べたのが本書である。
ここで切々といったのは、宇沢氏といえば戦後日本の経済学を世界的水準に高めた大家である。その人が、このままでは経済学はダメになると血みどろの戦いをしている様が本書の随所に現れているからだ。宇沢氏は「ジョーン・ロビンソンの経済学」の章において「(経済学は)現実とはまったく無縁の、抽象的な世界で形式論理のみを追うか、あるいは特定の産業ないしは政策的立場を弁護する議論が横行している」と述べている。この現実と無縁な世界にいってしまった経済学を本来の「理論と実証」の学問に戻そうと主張するのが本書である。
本書の最終章で宇沢氏が提唱する、不均衡理論と社会的共通資本の理論は読み応え十分だが、理論のレベルが高く相当の経済学の素養が要求されるのがちょっと残念だ。しかし、本書の様な新書版で経済学の全貌が鳥瞰できるのは他にない。

印象派美術館
2004/11/28 13:51
読める印象派美術
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は500ページ弱の印象派百科事典といっていいだろう。図版が大きく見やすいこと、解説が平易であることが素人には助かる。
前半は、印象派が何故生まれたのか?という点に力点を置いている。印象派というのは、若手の画家が絵を売るために、共同出資会社を作り、そこが主催して展覧会を開いた、この一連の展覧会の作品が後に印象派と呼ばれたようだ。
後半は印象派の画家たちが大物になっていった、その後を第3部「輝ける日々」と題して画家と作品を解説している。第4部に「印象派の影響」と題して、印象派が世界の美術にもたらした結果を要約している。我々が目にすることの多い、黒田清輝“湖畔”なども印象派(日本の印象派)なのだそうだ。その他、梅原龍三郎、安井曽太郎なども紹介されている。さらに本書の冒頭に、印象派の四大要素というのがあり、これはステレオタイプ化しているという言い方も出来るが、印象派の特徴を要約したものとしては秀逸だと思う。
四大要素とは、
「光のざわめき」代表作:ルノワール“ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会”
「瞬間をとらえる」代表作:モネ“ひなげし”
「同時代、近代都市パリの光景」代表作:マネ“鉄道”
「色彩の輝き」代表作:ゴッホ“ラ・クローの収穫風景”
となっており、作品と結びつけて特徴を解説する、読む前にテーマを提示する、こういう方法が美術の勉強方法として正攻法かどうかは別にして、良いアイデアだ。また、写真を趣味にして、スナップを撮っている身としては、この四大要素、スナップ写真のテーマにも繋がる思いがする。もっとも印象派の時代は写真の台頭期であったことも影響しているかもしれない。
印象派の展覧会は日本で人気があり、毎年どこかで開かれているが、美術史や印象派の総合的な解説書を読もうと思うと良い本がない。本書は専門知識を持たずに平易に読める解説書としてお薦めしたい。

戦略的金融システムの創造 「1930年代モデル」の終焉とその後にくるもの
2004/05/31 01:00
金融システムから分析した日本経済と90年代後半からの金融危機
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
90年代後半から“金融危機”という言葉が、経済問題のキーワードとなっている。この金融危機の原因は、資産デフレによるものとするのが多くの識者の見解である。ここでいう、資産デフレとはいわゆるバブルの崩壊である。バブルの崩壊が不良債権を生み、銀行の貸付債権が焦げ付き、銀行経営が成り立たなくなる。そこから金融危機が発生する。というシナリオだ。ここで、チョット止まって考えてみると、バブル前は銀行経営は順調で、バブルを生んだような貸付は行われず、優良会社と銀行の持ちつ持たれつの関係で、経済が順調に機能していた。それが、何故、不良債権を生むような貸付が行われ、銀行の経営を圧迫するまでになったのか。何故、銀行の経営が圧迫される前にそれを阻止できなかったのか。こういった見方に立って、金融システムを分析したのが本書である。ポイントは、従来の金融政策が、ミクロとマクロのミスマッチを起こしたこと、従来の金融システムは1930年代に形成されたモデル(30年モデル)であり、経済の不安定性・不確実性に対応するには問題があった、という2点である。具体的には、ミクロとマクロのミスマッチは、金融危機で銀行に対する特融などの手段で流動性を供給したとしても、不良債権の処理などにより、金融市場の流動性は増加せず、国民所得の増加には繋がらない。30年モデルは経済の安定性が確保できており、情報の非対称性が少ない状況ではうまく機能するが、自由化が進み銀行業務の多様化が進んだ今日では、機能不全に陥る。 このような視点から、金融システムを分析し、金融危機の経済分析を行った。読み進むと、30年代モデルの形成から崩壊、90年代後半からの金融危機の分析と、広範な範囲をカバーした論文集となっている。金融危機の経済分析と金融危機の本質、という2点に関していえば、第5章「金融システムと経済および金融の安定」を読めばいいと思う。ここで、日本の金融危機は資産デフレではなく、債務デフレだ、という極めてすぐれた分析がなされている。それは、80年代以降、日本の企業の資金調達が多様化し、過剰債務の企業が増加した。そこにバブルとその崩壊が生じ、過剰債務を持つ企業は返済することを優先し、投資や新規事業の構築が遅れ、経済の停滞をもたらし、デフレになる。金融機関も過剰債務を解消させ、不良資産の発生を未然に防ごうとする。ここに貸しはがしや貸し渋りといった問題が生じる原因がある。ミクロ的には企業の価値を維持し銀行の経営を最適化するが、マクロ的にはデフレーションの原因になる。まさにミスマッチを生じている。このような状況の下でBIS規制や金融の自由化・国際化が一方で急務になり、これに対応する金融システムの構築が出来ていなかったため、経済の不安定性が増す。このような分析をもとに、著者は新しい金融システムとして、ナローバンク構想を含むシステムを提唱している(第7章)。これは“決済サービス銀行”と“投資サービス銀行”に銀行の機能を分離し、リスクの分散を図ろうとするものである。現実問題として、日本の場合、都市銀行、地方銀行、郵貯、信用金庫系など多様な銀行形態を統合することが出来るか、という疑問はあるが、ミクロのリスクを分散し、マクロの安定性を重視する政策のための構想としては面白い。
本書は現在の経済問題を一番ホットな金融危機という視点から分析した好著だと思う。

ぶつぞう入門
2004/02/01 23:33
初めて仏像に興味を持ったらこの本。肩が凝らずに読めます。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
仏像をたずねてなどの題名の仏像入門書は枚挙にいとまがない。多くは偉い学者さんか高名な僧が書いている。これらの本は、紹介している仏像の縁、作者、製作年代など決まり切ったことを述べていて、読んでいてつまらない。そこで、本書は素人が仏像を見るとこうなる、と書かれた。著者は柴門ふみ女史、漫画家である。
本書は“ある日突然仏像と恋に落ちた”という、柴門女史の仏像探訪記である。その女史を上手くのせて、これを書かせたのが、「オール讀物」の編集部。この企画、初手から女史の漫画家としての腕、絵の才覚を見込んでいる。見た仏像それぞれに女史の絵が描かれている。これが本書の一番の見所であろう。この仏像の中で、女史がナンバーワンに挙げているのが、円成寺“大日如来(坐像)”である。この像、土門拳も古寺巡礼(写真集)に載せていて、土門の撮った写真が顔だけなのに対し、女史の絵は坐像であり、このあたり、仏像案内としてはその全体像を知ることができる。その像の評も“若者の自信に満ちたエネルギーが伝わってくる”と本格的である。また、この像は、女史も述べているが、かの運慶が20代の時に製作した像である。従って若者のエネルギーはピッタリの評だろう。一方、土門は“藤原時代彫刻の温和さを残しながら、運慶その人のよう”と評している。ここで土門評との比較すると、女史は、運慶が貴族好みの定朝様のお手本をなぞっただけの仏像に異議を唱えた、“所信表明”と述べており、過去の仏像写真に述べられた評などと比較して本書を読むのも面白い。また、女史の描いた仏像には、“反町”とか“菜々子”などの似顔絵評も付き、これも頷かせる。
本書は気軽に読めて、内容は濃く、京都・奈良のかなりの範囲におよぶ仏像探訪記として書かれている。仏像入門としてはお薦めである。

中・高校生のための朝鮮・韓国の歴史
2016/02/29 23:26
隣の国の歴史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
朝鮮、韓国というのは日本の隣の国です。歴史の知識は皆無でした。これがこの本を読んだ感想です。本書は朝鮮史を神代(朝鮮にも神代がありました)から現代まで解説してくれます。オンドルが渤海の文化の名残であることなどは本書を読むまで知りませんでした。日本の歴史教育がいかに欧米偏重かということもあらためて感じました。
朝鮮の歴史・通史を読むことで、朝鮮の王朝は数百年単位のスパンで交代していることも判ります。朝鮮史というと、古代の白村江の戦い、近代の朝鮮併合と朝鮮戦争しか知らなかったことも痛感しました。
著者も朝鮮を近くて遠い国と述べています。朝鮮の歴史が日本人に知られていないことを嘆いています。
拉致家族の問題や慰安婦問題は今も日本と朝鮮韓国の懸案です。お互いの理解を深めるためにはお互いの歴史文化を知ることから始めるべきだと思います。
本書は平易に書かれている朝鮮史です。一読をお勧めします。

ユーロ破綻そしてドイツだけが残った
2013/11/17 14:21
EUの欺瞞
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
EUというのは政治経済システム文化までも統合しようという、ある意味で暴力的なシステムだと思っている。
本書はEUの経済、特に金融面に焦点を当てて、その構造的な問題点を分析している。強いドイツが何もしないと、EUは結局崩壊すると言うことが良く理解できる。財政を各国毎に任せ、金融のみ統合し、グローバルな金融統合による、利益を強いものが享受しようというのがEUだ。ここにEUの欺瞞を見る。
財政と金融は経済の両輪、実物面の政策が出来ない金融だけでは経済政策の舵取りは出来ないことを教えてくれる。今の日本への警鐘としても読めると思う。

統計学
2013/11/17 14:12
数値事例が豊富
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
統計学の教科書は、数式の羅列か算術統計に毛の生えた位の教科書か、数理統計への入門書で良い本が少ない。
本書は算術統計から数理統計への橋渡し的な教科書で、数値事例を使って丁寧に解説している。
経済学の学部生で数理統計の専門書を読もうとする人、計量経済学の入門としての統計学を勉強する人にお勧めしたい。また、日本には、Takeshi Amemiya「Intoroduction To Statictics and Econometorics」のような本がないので、計量経済学の本格的な教科書を読む前の本としては、良いと思う。
| 10 件中 1 件~ 10 件を表示 |



