sfこと古谷俊一さんのレビュー一覧
投稿者:sfこと古谷俊一

クトゥルー神話事典 新訂
2001/02/16 16:39
クトゥルー神話世界の散策のお供にどうぞ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
クトゥルー神話についての知識を整理するのに、もってこいの事典『クトゥルー神話事典(1995年刊)』が、文庫になりました登場しました。学研の1990年のムック『クトゥルー神話大全』に掲載されていて重宝した辞典などの原稿に増補したもののようです。
作品別索引を入れて455ページと厚めとはいえ、文庫にできるサイズなりの文章量ですけど。広汎に現代の作家の作品に至るまでの関連作品について押さえることができ、クトゥルー神話の入門のお供に、最適だと思います。
クトゥルー神話の成立と現状への経緯を要領よくまとめた序文も有用ですし。
出典作品を明記してあるため用語辞典は、眺めるだけで神話体系の概観が見えてきて、自分なりの話を作ってみたくなったりします。
発表年代別に1980年までの主要作品を整理した作品案内は、読書案内としてのみならず、神話作品のパターンを認識するのに便利な一口解説つき。
現代日本の作家まで含めた作家名鑑は、神話作品の多様さを示し、また作者単位での作品案内ともなっています。
最後にあるクトゥルフ神話世界内の歴史年表も、労作です。

食の体験文化史
2001/02/16 08:55
古代日本の食を探るエッセイ第一弾
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中公文庫の「日本の古代」シリーズの監修者による、古代日本にからめた食い物についてのエッセイ。食と生活・文化・地域性・政治・習慣などを絡めて、古墳時代あたりを中心として語っています。
エッセイだけあり学説というには飛躍しているネタもありますけど、これも含めて古代日本ファンタジーの素材にも便利そうだな、と思いました。
河内日下や鹿島の蓮が仙薬として把握されていたとか、氷室の歴史とか、料理人の地位の高さとか。むろんその手の情報がメインの本を探したほうがいいんでしょうけど、楽しく読めました。

世界の建築 イラスト資料
2001/02/16 08:51
ヨーロッパ歴史建築の中身を見る
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
イラストでの歴史的建造物の外観と平面図・断面図を、縮尺つきでたくさん載せてある本です。
1896年に発行されたフレッチャー著『建築史』の、大正八年の邦訳の押絵と用語集より抜粋し現代の用語に改めたもの、だそうです。
基本的には西欧のものがほとんどなのは残念ですが、中世ヨーロッパ風で遊ぶときにはたいへん便利だと思います。同宿尺での類似建造物の平面図の比較あたりは、自作するときにもとても便利です。これだけたくさんの縮尺つき地図のある本は、私は他に知りません。
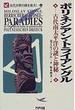
ポリネシアン・トライアングル 古代南太平洋の謎と神秘
2001/02/08 21:36
ポリネシア民族の網羅的入門
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ハワイ、ニュージーランド、イースター島を頂点とする南太平洋の領域、ポリネシアの人々の歴史と暮らしについて概説した本です。古代とか書いてありますが、近年までの話題が入っていたりします。
航洋民族ポリネシア人の生活、習慣、信仰、政治体系、航海術、食物などについて書かれております。われわれ日本人にとってはたいへん理解しやすいものも多く、相違や同一点が興味高いと思いました。
西洋や地中海沿岸、中国の一時期以外の各地の生活については、わりと知らない人が多いの。それ以外の世界の人々について知るのは役にたつかと思います。これを読んでいても、近くのミクロネシアやインドネシアではどうだったのだろうかとか、色々と知りたくなりました。

ゲルマン民族・二つの魂 「最初のドイツ人」生と闘いのミステリー
2001/02/08 21:21
初期ゲルマン民族の由来と文化を解き明かす
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ゲルマン人の誕生の経緯から、ローマとの戦い、そして考古学的知見を駆使して古代ゲルマン人の生活までを扱っている、啓蒙書です。戦後ドイツで、ゲルマン民族にたいする誤解を解くことを目的として書かれた本だそうで、一般向けだから網羅的でやさしくて、かつ冷静な視点で当時の考古学の成果(沼地から発掘された遺骸の研究とか)を生かして書かれています。副題は『「最初のドイツ人」生と闘いのミステリー』。
ゲルマン民族の素性(巨人塚をつくっていた農民と、アーリア遊牧民の混血であること)から書き起こし、ローマとの戦いとその経緯とゲルマン人の実像を生活・習慣・思想などからとか交互に記述しています。
よく知られて居る北欧神話の体系なるものが実際には比較的最近になって組み立てられたものであるとか、蜂蜜酒の作り方などの古代ゲルマン族の生活習慣などについての記述が、大変興味深く読めました。当時の実際の身長、女性の立場、服装や髪型、信仰や住居などにも触れられていて、創作などの参考にするのにも便利です。一般向けの読み物ですから、データを検索するのには向いていませんけど。

トールキン指輪物語事典 普及版
2001/02/06 21:36
指輪物語を読み終えた人への副読本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1994年12月翻訳発行の『トールキン指輪物語事典』(B5でした)が版形を変えて安価に入手できるようになりました。帯を見ると映画に合わせようということでしょうか。
『ホビット』『指輪物語』『シルマリルの物語』(上、下)ほかのトールキンの関連著作から抽出された用語について整理して解説されている、まさに百科事典です。まず歴史を概説した部分があり。そのあと地理、社会、動植物、伝記(人物)について、それぞれ辞書順に紹介が書かれています。
索引には項目ごとの出典作品がどの本かが明示されているのですが、項目の本文のほうには出典の記載が無いのは、すこし残念ですね。
全体としては、良く纏まっており。かつて『指輪物語』などを読んだ記憶をよみがえらせてくれます。こいつはこんなやつだったっけ、などと認識をあらたにすることもあって、久しぶりに『指輪物語』も読みたくなりますね。
『指輪物語』を読んで楽しかった人、指輪物語世界で遊ぼうという人はむろん、架空世界を作成する人が参考にするためにも、手許においておくと便利な一冊だと思います。

アイザック・アシモフの科学と発見の年表 コンパクト・サイズ
2001/02/05 17:16
手軽な値段で入手できる発明発見の科学史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これはコンパクトサイズの廉価版ですが、大部のほうと内容的には同一だと思います。
科学技術史上重要な発明・発見について、年代順に豊富な解説を交えて整理した辞典的な書物です。索引を入れると546ページありまして、たいへん内容豊富となっております。項目数は1500くらい。近現代の発明発見が過半数です。
最近の知見からいえば変だとかいったものもありますし、ミスか見落としか古い通説を採用しているものもあります。また現代に続く発見というものを重視しているので東洋などでの発明発見が軽視されている傾向は強いなどの癖もあります。なにかの調査に使う時には、できるならクロスチェックはしておいたほうが良いのは確かです。

ウマ駆ける古代アジア
2001/02/04 03:45
紀元前の馬の利用の利用史を要領よく解説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
紀元前、鐙(あぶみ)が発明される時代まであたりの馬の利用史を要領良くまとめたもの。多数の資料に言及しているのに、かなり読みやすくできているという感じですね。発掘資料などをもとに数値的にもきっちりとしているのと、イラスト・写真が多数あることが、イメージしやすくて便利です。
騎馬と車馬の二大利用法の起源についての最新の知見から書き起こし、メソポタミア・エジプト・ヒッタイト・殷から漢までの中国などでの、馬の軍事利用における利用法の変化などについて書かれています。
こんな感じで近代あたりまでの馬の利用史なんかあると面白いでしょうね。

江戸の宿 三都・街道宿泊事情
2001/01/24 16:25
江戸時代の宿の実情と変遷を概観する入門書
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
江戸時代の宿についての入門書籍です。江戸時代の宿場の成立・ありかた・建築、旅行者の種類と泊まり方、宿の経営のあり方など、宿に関るいろいろな話題がまとめられています。
題名には江戸のとありますが、これは江戸時代のということでして。良くあるような江戸や東海道だけの話ではなく、上方はむろん、九州や北陸、琉球や蝦夷地などの情報もあり、たいへん興味深いものとなっています。とくに大型の都市内の宿については江戸の宿自体はほとんど出てこないで、上方の史料が中心のようですね。
江戸時代の日本に限らず、宿のあり方、意義というものについて考える上で、たいへん役に立つ内容だと思います。
市場と宿は密接な関係がある、商人宿の庭から発展して市場を生んだ事例もあるあたりを見ますと。宿が商人の荷物も引き受ける場であったというのは、私の意識から抜け落ちていたようで。そういやそうだようなと再認識。宿は都市にも必須であり、商売だけでなく、役所に用のある人間が宿泊するという需要もあるものだ。というあたりも、街道の宿場町の宿についてしか書かれていない本だけを読んでいては、思い当たらないことだと思います。
また、信仰の旅のためにとの村々の対応の産んだ、善根宿(余裕のある人、奉仕の心のある人が家を宿として提供する)から合力宿(村の成因から集めた金で運営される無料宿)、そして旅人立ち入り禁止への推移というのは。無償持ち出しで運営されていたものが、悪意の利用者、コストの負担を理解しない利用者の増大により。負担で倒れたりするインターネットとの類似性を感じてしまいました。

粋なゲーマー養成講座
2001/01/05 23:13
TRPGコンベンションの諸問題とその対処
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
TRPG(テーブルトークRPG)サポート雑誌「ログアウト」での連載を単行本にしたもので、多少の改定と連載後の反響をもとにした補足的な章が追加されています。
実用的なコンベンションでの問題行動とその対策について、リプレイ風に軽くまとめて、コラムや用語解説で補足もしてあります。中級者養成のための企画としては珍しく単行本化されたもの……といえるでしょうか。
プレイスタイルの変化、ひとくくりにできない初心者の実態、日常だけで遊んでしまえる状態の管理、シナリオに参加しようとしないプレイヤー、発言できなくなるプレイヤーへの対処、身辺を清潔にすることの必要性、キャラクターの性格重視の暴走などについての話題が出ています。TRPG.NETのTRPG座談会をはじめとした掲示板などでもよく出る話題に絡んだ内容も多く、いずこでもおなじ問題が出てくるのだろうなと痛感します。
ただし、善意の熟練者による問題、サークルでのGM(ゲームマスター)強要の問題、持ち回りによるインフレ現象、どう行動して良いのかわからないプレイヤーへの対策、などなど書かれていない問題も多数あります。特にコンベンションではなくて内輪のサークル内で発生する問題については記載が少ないといえるでしょう。そこは続刊に期待……したいところですが、さすがに掲載誌が無くなっているので辛いですね。

トンパ文字 生きているもう1つの象形文字
2000/11/03 22:02
かわいい絵のような文字たち
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中国奥地にて現在も利用されている、漢字でない象形文字の紹介本。本文は日本語と英語で対訳風に併記されています。
トンパ文字とは中華人民共和国の雲南省の、ナシ族と呼ばれる少数民族が使用している、絵画的要素をとどめた象形文字です。もともとトンパと呼ばれる宗教者が経典を記録するために用いた文字だったそうです。もともと漢字などの世界の諸文字も、宗教者が独占する神秘の道具である時代が長かったわけですけど(ヨーロッパの紙が普及するまでもそうでしたし、太平洋やマヤなどでも同様でした)、比較的近年まで宗教者が利用していていまも残るというのは、けっこう珍しいのかも知れません。
ほぼ半分はカラーベージで、トンパ文字の伝説や占いにおける用例や、ナシ族の生活についてなど、簡単にまとめられています。ほぼ紙面の半分が写真であり、かわいらしい色つき象形文字が、なかなか楽しげです。
もう半分はモノクロで、トンパ文字の対訳辞書になっています。これがあればトンパ文字で文章が書ける……かも知れません。
この本をみていると、まだまだ世界には知らない文化があるのだなという感慨とともに、あまり記号化のすすんでいない古い形態の象形文字の面白さなどが伝わってきて、なんとなく幸せな気分になります。

軌道エレベータ 宇宙へ架ける橋
2000/10/26 05:59
軌道エレベータの入門書の決定版!!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
軌道エレベータ! 宇宙への掛け橋! SFマニアであれば、これだけで本の内容が理解できるでしょう。……が、私の観察と実体験から推察するに、SFファンでさえも軌道エレベータについてまったく知らない人間は多いようなので、ちょいと説明しときましょう。
まず静止衛星を思い出してください。これの説明まではしませんが、ようするに赤道上で地上と相対的に静止してみえる位置にずっといる衛星です。この静止衛星から上下(地球側とその反対側)にバランスをとって糸状のものを伸ばしていきます。それでも相対静止していることには変わりありませんね。では、この糸を地上に届くまで伸ばしたら、どうなるでしょうか。重心は静止軌道にあることにかわりがなければ、そのまま安定してしまいます。そして、糸を伝ってしまえば静止軌道、さらには脱出速度を得て他の惑星へ飛び立つことが簡単にできる……これが軌道エレベータ、究極の宇宙への交通手段です。
『軌道エレベータ』では、この軌道エレベータの歴史的経緯や技術的問題点について、わかりやすく説明してあります。また、材質に大きな技術的進歩を要する古典的な軌道エレベータ以外にも、最近発案されているスカイフックのたぐいなどについても簡単に解説してあります。
近未来から遠未来まで、リアリティのある技術背景を持った宇宙SFを、さらに楽しむために。手元においておきたい一冊です。
(初出:日刊TRPGニュースメール 語り部日報のTRPGのための読書案内)

コスチューム 中世衣裳カタログ
2001/04/29 21:47
中世ヨーロッパの衣服について軽く入門するには便利
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
見開き2ページで、昔の人の職業別の衣装をつけた姿の時代による変遷を簡単に解説した本です。
正面もしくは斜め前からの図と、各部の拡大図および簡単な解説によって紹介しています。他には冒頭には貫頭衣などの衣服の基本構造の分類に関する説明が、巻末には服飾用語と索引が用意されています。
副題は中世となっており、たしかに三分の二ほどは中世からルネッサンスのヨーロッパの衣装となっています。残りにはローマやギリシャ、および東洋や世界各地のメジャーな衣装なども含まれています。
いわゆる中世ヨーロッパ風世界の衣服の概略や用語について、入門的に把握するためには役に立つと思います。小説などで名前を出して描写する参考に程度であれば、十分でしょう。しかし本格的にイラストを描く参考にするのであれば、もう少し高価な、細かい図版や後ろ姿なども書かれた書籍のほうが役に立つと思います。

図説日本呪術全書
2001/02/04 03:48
日本の呪術についての便利な情報源
5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ハードカバーで461ページに、日本の各種の呪術をつめこんであります。
図版も充実しており、一冊で呪術の情報がまとめてえられるので費用対効果も高く、なかなかに便利です。ただ、辞書的な利用をするには重大な難点があります。索引がないのですよね。これがたいへん残念です。
なお、この本で扱われている呪術とは、儀式などによって、不幸を追い出したり、幸福を呼び寄せた、他人を呪詛したりするという、現世利益を得るものだと思って良いでしょう。
あと、この本では信仰の概念や各種の用語についての細かい解説があるわけではなく、あくまで呪術としてどのようなものが存在するかがずらっと並べられています。そのため、ある程度の用語や信仰についての基礎知識がないと分からないところも多いかもしれません。

よみがえる文字と呪術の帝国 古代殷周王朝の素顔
2001/08/06 16:45
殷周時代の世界認識
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
発掘・伝来している古代中国の書物や銘文を、天文学などと照らし合わせて年代を検討し。その過程で採用した仮説から「後の史書では覆い隠されている殷周時代の世界認識や制度」を提示した本です。
繰り返して同じことをぐるぐると書いている部分があるとか、他の説の支持者への私信めいた挑戦のようなものが新書としては多すぎるなどはありますが、提案されている論は面白いものだと思います。
他の説とどちらが正しそうなのかなどは良くわかりませんが。文字を呪術の道具として用い、権威を作り上げていた古代社会という概念は魅力的です。
文字を記録の道具として理解し多用している現代人、特に識字率が高い時期の長い日本人にとっては理解しにくいことではありますが。文字の呪術性は長い間、世界中で存在したものですし。そのあたりの違和感や概念の違いを理解して歴史を考えるというのは、たいへん楽しいですよね。

