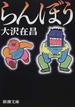はや父さんのレビュー一覧
投稿者:はや父
| 4 件中 1 件~ 4 件を表示 |
紙の本論争・中流崩壊
2002/04/22 00:25
必読の一冊
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書で論点となっている「階層の固定化」というのは、私自身の実感としてはハッキリ有ると思う。以前籍を置いていた会社(いわゆる大企業だった。まあその中でも小さな方ではあったけれど)と、現在在籍している地方公共団体との間での違いを感じる。両者ともに、管理職まで到達すれば本書でホワイトカラー被雇用上層(「W雇上」と略されている)に位置付けられるのであろうが、構成層には明確に違いが有ると感じられる。そしてそれは親の代からの継続性を伴っているように感じられるところも有る。
また自分の出身大学においても、そこは元々地方出身者が多いというイメージの有る学校だったが、自分が大学生活を送った平成の始めには既に首都圏出身者が多いという印象を受けた(ハッキリしたデータを見たわけではないが。いや、予備校サイドのデータであったかもしれない)。それも大きな会社に勤めている親が多かったような気がする。
そんなことが、この問題に対する自分の実感と問題意識のようなものとしてあった。
さて、本書はここ2、3年程流行している(以前から定期的に流行の波は来ていたようであるが)「中流が崩壊してしまったのではないか」あるいは「新しい階級社会が到来するのか」という事をめぐる議論の主な小論をまとめて掲載したもの。
現時点でのこの論争の火付け役は、橘木俊詔氏の『日本の経済格差』(岩波新書)という98年刊行の本のようである。次いで、『不平等社会日本』(中公新書)を著した佐藤俊樹氏や、「学力低下問題」を扱う苅谷剛彦氏などがいて、それぞれの論点で論争が展開されている。これらが展開される一つのきっかけとして、『中央公論』と『文芸春秋』の両誌が2000年5月号でこのテーマを特集し、それを受けた各新聞などを含めて論争が展開されたとのこと。そういえば、幾つかは当時新聞で読んだ記憶がある。本書は新書であるので、当然の事ながら『日本の経済格差』や『不平等社会日本』などの書物自体は掲載されていないが、それに対する批判や反論などは掲載されている。
本書のメリットだが、最初に中央公論編集部による「論争を交通整理する」があり、98年の橘木論文から01年3月までが分かりやすくまとめてある事。1.所得分析(経済学)、2.世代間の地位再生産(社会学)、3.世代間の学歴再生産(教育社会学)と分類してあるのは、この本を読み進めるのに分かり易くしてくれたし、今後他の本などでこれらの論点を追っていくのには非常に参考になる。
デメリットは、当然の事であるがこの一冊でカバーできる範囲は狭い。新書にそれを求めるのはないものねだりであるが。ただし関連文献の掲載は「論争を交通整理する」だけでは分かりづらく、できればもう少しわかりやすいものを用意してもらえれば有りがたかったと思う。
各論争は基本的に、ジニ係数やSSM調査などといったデータに基づいて行われている。それぞれデータの取り上げる部分や読み方の違いにより、立場の違いが発生しているようである。ただどちらかと言うと、佐藤氏や橘木氏などの「階層の固定化」或いは「中流層崩壊」(この二つは全然違う事のようであるが確実にリンクしている)を唱える側は、それほど大きくは無いデータを取り上げているような観がある。それに対する批判側は、全体を語るには狭すぎる領域を取り上げているように見える。
私自身の現在の感想は、社会が確実に変化していて「階層の固定化」、つまり世代間の階層移動の可能性が減じて来ているイメージを多くが共有してきており、それにより社会のシステムが崩壊する予兆のようなものがきざしてきている、というものである。大袈裟かもしれない。しかし予兆である今のうちに、「機会の平等」についての社会的コンセンサスを作る努力をする必要があるのではないか、と感じた。
紙の本堤防決壊
2002/03/30 01:45
そして、全てはベタになってしまった、のか
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
女性誌『クレア』連載の「吠えろ! 俺たち」をまとめた2冊目。1冊目は『隣家全焼』。ナンシー関のクールな認識に、さらに冷水をぶっかけるような町山広美という感じで、主にメディア上に象徴的に現れる世間の風潮を、切りに切る。その感覚が大変気持ちよい。
ナンシー関のこの形式の本としては、大月隆寛との本よりも、一段とさえを感じて、こちらの方が面白いと思う。しかし、前作に比べると切れ味が鈍ったような感もある。こういう形式に、こちらが慣れすぎたのか。
けれど、どうもそれよりも自分を含む世間の座標軸(の様なもの)がさらに「しょーもない方」に行ってしまったからではないか、という感じもする。それは連載最終回、99年10月号での町山広美の次の発言がとても納得できてしまうところに良く現れていると思う。「連載始めた頃は私たち、「流行っているから好き」っていう人たちの存在にとまどっていたけど、3年たってそれが普通のことになっちゃった。「流行ってないから好きじゃない」って感じだもん、今は」。
そして、全てはベタになってしまった、のか。
紙の本らんぼう
2002/03/24 00:43
型は強し
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大沢在昌の作品は、どれも大変読みやすい。私も結構な冊数を読んでいるが、今だかつて、読みづらいなあとか思った事は無い。もちろん、貶している訳ではなく、エンターテイメントとして素晴らしい事だと思う。
さて、そうはいっても、大沢本は軽くて読み流せるものばかり、と言う訳ではない。大沢在昌の作品には2系統有ると思う。それを読後感で分けると、あっさりとしているものとずっしりとしているもの、の2種である。新宿鮫シリーズの多くが後者に属し、この本などは前者に属していると思う。この前者に属するようなものには、他に、日本一不幸なサラリーマンのシリーズやら、『悪夢狩り』やらまあたくさん有る。
それでこの前者の流れの印象だが、特に型にはまっている印象が強い。もちろん、ミステリー全般がそうだし、特にハードボイルドは、型の小説でも有るとは思うが(もちろん、古いハードボイルドの型ではなく、色々幅を広げた後の型、である)。
さて、この作品について。この作品は「痛快なマンガである」と思う。後者の流れの作品の中でも、特にマンガのような型を感じる。それでも、とても良く出来た型であるから、痛快に感じるのだと思う。最凶にして最強な主人公達が、ひたすら悪人達を叩きのめす、そのことに、特に理屈は無い。最終章で描かれているように、クビになって警官で無くなりさえしなければ、どうなったって構わない、というもの。
それだけ、では有るのだが、とっても楽しく読みきることができる。特に強いストレスを感じているときなどにお奨め。少なくとも読んでいる間だけは、間違い無くスカッとします。
紙の本知恵と意欲が生きる社会福祉「経営」 規制緩和なんか怖くない
2002/04/05 11:24
今後の社会福祉について考える手がかりにはなる。しかし疑問を感じつつ読んだ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、現在の日本においてほとんどの業界と同じく「規制緩和」の大波が押し寄せる福祉業界に対して、積極的な「経営」によって来るべき民間企業との「自由な競争」を生き抜いて行こうと呼びかけるものである。本書の発行日は'99/5/10であり、はじめて「措置制度」が改正となった児童福祉法の改正施行日である'98/4から約一年経過の時点である。つまり「規制緩和」の確実な第一歩が踏み出された段階である事を意味する。
さて、本書は全体的に非常に平易で、一つ一つがなかなか分かりやすい説明となっているが、まとまりがイマイチな印象を与える。本書の全体の構成は四部構成となっている。
「第一部 ついに始まる営利企業との自由競争」では、戦後の社会福祉の歴史の説明の後、「規制緩和」で市場原理による競争により事業者の自由な入退室が起こり、それが消費者の利益につながると説明する。そして競争によってつぶれて困る老人ホームなどは、入所者を保護する制度を公益法人によって作ればよいとの提言がされる。
この部分は市場に対する考え方が素朴すぎるのではないか。儲かる可能性のある仕組みも、介護保険という制度を創設して市場化したからであるはず。しかし介護保険の対象は高齢者であり障害者や児童は含まれない。児童は絶対数があるし、現在の核家族という状況からも儲かる仕組みの構築は出来るかも知れない。けれども障害者はどうか? 措置制度が支援費支給制度という契約制度に転換するが、儲かる仕組みは考えられないと思う。
また施設は密室になりがちで、行政の検査については現在よりも詳しいものが要求されるはず。参入規制を撤廃したら、質の確保のために出口の側で充分な検査が必要だからである。だがそういった論点は本書にはないが、密室になりがちな施設の特性を考慮して、自由化した後の福祉業界の質の維持を図るためには、不可欠な議論であると考える。
さて「第二部 社会福祉法人の組織改革の要諦」は法人の理事の問題点、つまり現状の理事はボランティアでありどこまで責任を問えるのか、と問い掛ける。そして、市場での競争においては意志決定のタイミングが大切であり、そのためには民主的組織では対応できないと説明する。その先行例として農協、生協をあげている。
第二部は概ね納得できるが、社会福祉法人の将来像についてもう少し話を聞いてみたい。
続いて「第三部 庶民と中小企業の経営学」では、社会福祉法人は規模からして中小企業に当たるとして、中小企業の実態紹介をし、中小企業は適正利潤でなく過大利潤を目指さないと生き残れないと訴えている。
最後の「第四部 自立と自己責任の社会福祉経営に向けて」では、「業界の常識」と「社会の非常識」の対比をし、また社会福祉法人に民間活力を感じないという厚生省社会援護局長の発言に対し、内容に異論はないが監督者として一番の責任者のはずが、今更何を言っているのだとする。これは非常に共感できた。そして、措置制度がなくなれば意識が変わり、その事により主体は消費者に移る、また対象者・分野別縦割りの解消により福祉も普通の消費活動になるとする。しかし本当にこのように変わるものなのか、疑問が残る。
この後、3者の先進事例を紹介し、最後に経営のための10か条をあげている。
さらにあとがきで、役所はコストで価格を考えるがそれは子供の考えであるとする。しかし今でも施設職員の給与などは非常に低い水準であり、どうなのか。障害者福祉は利益が出る仕組みを作れない、ならば質は悪かろうが行政がやらないと無理ではないか。
全体に強く疑問を感じながら読み進んだ。ただ、そのような考え方の違いを感じながらも、本書によって私も改めて今後の社会福祉について考える手がかりにはなった。
| 4 件中 1 件~ 4 件を表示 |