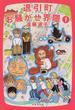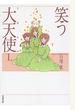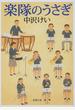homamiyaさんのレビュー一覧
投稿者:homamiya
2004/09/06 02:10
家族っていいなあ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
モコは町屋に住む小学校3年生の女の子、めちゃめちゃ好奇心旺盛でわんぱく盛り。
くにたち物語は、このモコちゃんの成長物語。
1巻ではモコちゃんというより、その一家にまつわるエピソードが中心となる。
のんびり屋のお父ちゃん、元気なお母ちゃん、優しいじいやばあ。
隣に越して来た男の子、ポチとその家族。
モコちゃんが元気いっぱいに活躍し、周りの人に暖かく見守られているのが、とてもほのぼのとする。
小さいころ、自分もこんなワガママを言って叱られたりしたなあ、といつの間にか、モコちゃんを見守っている自分に気づくでしょう。
1巻では、ポチとケンカした同級生の母親と、モコちゃんの母親の対決シーンが印象的。
「私は娘を信じる。娘の選んだ友達であるポチも信じる。
でも子供はウソをつく、ただそれを鵜呑みにして罪を他人になすりつける親にはなりたくない」
「子供が非を認めて謝って丸くおさまってる所へ親が口を出すんじゃない」
こんな母親に愛情いっぱいで育てられたら、娘はグレようがない。
ラストのじい・ばあとのふれ合いのエピソードもよいですが…切なくて泣いてしまいます。
家族っていいなあ。と素直に思える本です。
2004/08/29 18:30
ほのぼのコメディ〜
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
退引町に住む個性豊かな人々が織り成す、どたばた・ほのぼのコメディ。
遠藤淑子はどたばた・ほのぼのを描くのが実に上手い。
絵は上手くないと言われているが、あまりプロっぽくないタッチがほのぼの感を増しているようで、私はけっこう好きな作家。
退引町お騒がせ界隈は、その原点のような作品。
元々は花とゆめコミックスの「退引町1丁目15番地」と「退引町お騒がせ界隈」で、前者のすべてと後者の一部が収録されている。
短編集だが、どの話にも毎度おなじみの住人達がどの話にも出てきてアットホーム感がある。
豪華なフランス料理や、味わい深い会席料理ではなく、今日はお惣菜みたいな本を気軽に読んでホッとしたいな〜という時にオススメ。
紙の本笑う大天使 第1巻
2004/02/17 02:08
川原泉の最高傑作
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
川原泉の作品には独特のテンポがある。
読者は、「川原節」とも言うべきセリフまわしにいつの間にかハマりつつ、しかしストーリーではほろりとさせられたりする。
この魔術のような川原作品の最高峰が「笑う大天使」だ。
良家の子女を対象に幼稚園から短大まで一貫した教育システムを誇る聖ミカエル学園、由緒正しい名門女子校。それは「大天使(アークエンジェル)の乙女達」と呼ばれるお嬢様たちの集う「綺羅の空間」である。
ミカエル学園の高等部に、3人のお嬢様がいる。
この3人は実はお嬢様のなりそこないだ。
ぞんざいな言葉遣いに、粗雑な動作。
しかし、他人によく見られたい見得の強い3人は大きな猫をかぶって、普段は至って清楚なお嬢様。ふとした事からお互いに猫をかぶっていることが発覚し、仲良くなり、そこから様々な事件に巻き込まれたりするのだが…。
前半はこの3人やその家族とのやりとりや巻き込まれる事件の成り行きにハラハラしつつ、3人の性格や環境がつかめてきた後半ではさらにそれに深入りするようなエピソードになる。この後半のエピソードが珠玉だ。
家族の絆、親しい人の死、友情…といったものが実にさりげなく、しかし印象的に描かれている。
川原泉は人を見る目がとにかく温かいのだろう。
何でもないようなシーンでもこの著者にかかると何とも言えない温かい雰囲気になるのだ。
少女マンガは苦手だという男性もこの作品は一度読んでみてほしい。
紙の本楽隊のうさぎ
2003/03/23 03:29
ブラス!!ブラス!!ブラス!!!
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
引っ込み思案の中学生・克久は、入学後、ブラスバンドに入部する。先輩や友人、教師に囲まれ、全国大会を目指す毎日。少年期の多感な時期に、戸惑いながらも音楽に夢中になる克久。やがて大会の日を迎え……。
ストーリーは背表紙に書いてある上記のあらすじそのままで、それ以上のことは何も無い。実に平凡でありがちな感じがするが、本の良さは、あらすじだけではないのだという事を改めて感じた本だった。
この本には、リズムがある。
ブラス!!ブラス!!ブラス!!!
例えばこれは第四章のタイトルだが、県大会を目指して、寝ても覚めてもブラス!という夏を送る部員達をとてもリズミカルに表わしている。
わかりやすくリズムのある言葉に導かれて、読み手も克久と共に色々な気持ちを味わい、大会の日を迎えられるのだ。
心を灰色に塗り固め、学校で何も感じないようにしていた入学当初から、部活に入り、個性豊かな同級生や先輩とのやりとり、親とのやりとり、初めての大会で味わう敬虔ともいえる舞台、学年が上がってまた部活三昧の毎日、2度目の大会。
学生時代の部活というのは不思議だ。プロというわけではない。お金ももらわない。しかし、半ば強制力みたいなものもあり、時間をかけて同じ面子で何度も練習をすることになる。みんなで一生懸命がんばって何かを作る、と言葉で書くと何だか陳腐だが、そこから得られるものはなかなか他の時期・場所では得がたいものだと思う。
「うまい演奏や深い演奏はできても、こんな真剣な音は今しかできない」
と克久の先輩が言ったように、それを克久が「温かな生き物の体を抱きしめるように解った」ように、それは経験した人にはわかるのだろう。
そして、本を読んでその経験を疑似体験する読み手にも、わかるような気がするのだ。
登場人物もいい味を出している。
私のお気に入りは、1人は部活顧問の森勉、通称ベンちゃん。
音楽に燃える、クレイジーな先生で、指揮者でもある。部員達は彼の悪口を言い出すと止まらないが、ほかの先生と違って、ベンちゃんの悪口は言えば言うほど楽しくなる。そんな先生だ。この先生は、部活を通して「他者と比べては生まれないような質のプライドを生徒たちの中に作り出してしまう」すごい先生だ。学校でこんな先生に出逢えたらいいなと思わせるキャラクターだ。
もう1人は克久の胸に住む、うさぎ。裃をつけてはっはあと頭を下げたり、歌を歌ったりする。このうさぎが克久の成長に一役買っているのだが、ふつーにこういううさぎが登場するあたり、作者の遊び心と、そのウマさに感心する。
紙の本返事はいらない
2003/01/22 02:41
宮部みゆきらしい短編集
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
宮部みゆきの本を読むと、著者の一貫した考え、というか哲学のようなものが伝わってくる。
それは、非常に「きちんとした」「まっとうな」考え方で、著者の人柄が出ているのだろうなあと、いつも思う。
この短編集には、そういう「宮部みゆき」らしさがよく出ていると思う。
恋人に対してそう望んでいたくせに、「自分に合わせすぎている」と理由をつけて別れを持ち出す男。
クレジットカードで多大な借金を抱える女性、購読する雑誌は、
『喫茶店やレストランやブティックを、現実にあるものよりずっと美しく洒落た感じに写して載せている。ジャケットの色、スカートのライン、週末にボーイフレンドに連れて行ってもらう店の名前まで、懇切丁寧に指導し…紙面の向こうから語りかけてくる。こうすれば幸せになれる。こうすれば美しい人生があなたのもの』というもので、“都会”に、“都会らしい生活”にあこがれ、借金とも思わないでクレジットでお金を借りて、この雑誌の言う「幸せ」を手に入れようとする。
若くない女性が、若い女性に嫉妬する。
「私はついていないのだ」と、思うようにならない人生を、他人のせいにして生きていくオールドミスの女性もいる。
宮部みゆきは、こういう人々を本の中に実にリアルに登場させる。
そしてまた、彼らとは対照的な、「まっとうな」人々を登場させ、「まっとうでない」人々を「否」であると感じさせるのだ。
こんな事を、あからさまに書かれたら、いかにも道徳的な感じで楽しくない物語になりそうだが、宮部みゆきが書くと、決してそんな風にはならず、とにかく読み進めるのが楽しくて、あれよあれよという間に読み終えてしまう。この短編集でも、ちょっとしたヒントから事件の犯人がわかったり、鮮やかな犯行手口だとか、ミステリーとしての魅力も十二分である。
紙の本秋の花
2003/01/08 11:00
傍らに置いておきたい本です
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
女子大生の母校の後輩が屋上から転落して亡くなった。それは事故? 自殺? あるいは…??
というストーリーだが、上の一文から想像されるようなミステリーでは、ありません。
謎解きは非常にゆっくりだし、解かれてみれば、「何だ、そんな事か」という程度。
味わって欲しいのは、その過程で、が出会う出来事、考える事、友人や謎解き役の噺家・円紫さんからの言葉…そういう一つ一つが、水が染みるように読む人の心にじんわりきます。
“紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る”
という古今集の歌が、あるお菓子の箱に書いてあったという話がでてくる。
後で、が円紫さんを自分の生まれ育った町に連れて来ることになるのだが、そこで円紫さんのこのセリフ。
「もう何年かすると、あなたもきっと誰かをここに連れて来るのでしょうね。そして自分の歩いた道を教えてあげる。そのとき、誰かは、>と思うでしょう。一本の木、一本の草までね」
は体がしびれる。
読んでた私もしびれました。
思わず、本を閉じて反芻してしまいました。
北村薫の話は、決して美しいだけの物語ではない。
人の嫌な面や弱い部分も書かれているし、眉をひそめるようなつらいシーンもある。
ドラマチックに、都合のよい事だけが書かれているのではなく、物語のあくまで一部分として、上述のような珠玉のシーンが登場するのだ。
実人生だって、よいことばかりではないけれど、悪いことばかりでもない、そして時には円紫さんの言葉のような心ふるえる出来事もある。
北村薫の本は、それを思い起こさせてくれます。
「秋の花」は、北村薫の「空飛ぶ馬」「夜の蝉」に続くと円紫さんシリーズの一つだが、それぞれ
独立した話なのでこれだけ読んでも問題ありません。
が、この本を読んだ人は、魅力的な登場人物や北村薫をもっと味わいたくなり、きっと他の本も手にとってしまうでしょう…。
紙の本燃えつきるまで I lost myself when I lost him
2002/12/27 14:09
とてもリアルな恋愛小説でした
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
読み始めて1行目で、「別れないか」とくる。
その後は、別れを決意した恋人への未練、恋人の新しい彼女への嫉妬、ストーカーまがいの行動…と、実にわかりやすいストーリーなのだが、これがすごくリアルなので、ありきたりな感じがせずに読める。
31歳の働く女が、職場で「女を捨ててる」と言われても笑って流せるのは、結婚を約束した恋人がいるから。
恋人との結婚を視野に入れて人生設計を立てている時に別れるということは、恋人を失うだけでなく、人生を失うに等しい。
私は31歳で恋人にふられた事はないけれど、こういうのはすごく想像できる。31歳に近づきつつある「女」だから。主人公の感情や行動がいちいちリアルで、「わかって」しまう。
こんな失恋をもし自分がしたら、友達に何と慰められても立ち直れないだろう。
(主人公も、彼のことをあきらめてしまえばいいのに、という事はイヤというほどわかっているのに、人に何と言われても気持ちがどうにもならない)
その時、どうしたらいいのか? この話を読んでおくといいのかもしれない。
もっと年若い人や、男性が読んだらまた違う感じなのかもしれないけれど、同年代くらいの女性には共感できて、また、勉強になるのではないかと思われる。
何の理由もなくても恋は冷める事もあるし、何年つきあっても心変わりもあり得る。愛は愛というだけで永遠ではあり得ない、という事を知って、いい恋ができる女になりたいなあ、と思う。
ところで、女の失恋モノってよくあるけれど、男の失恋モノってどんな話になるのだろう?
紙の本幕末遊撃隊
2002/08/29 13:50
幕末のサムライのお話、生きた歴史です
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
時は幕末、“サムライ”伊庭八郎の物語。
池波正太郎の「その男」とかなり話が重なっているようだ。人は寝て食べて飲んで、好きな女を抱ければそれでいいんだ」といった幸せ観も「その男」と共通する。
共通しないのは、「その男」の主人公は明治維新で床屋になったが、伊庭八郎はあくまで「微衷を尽くすのみ」と官軍に抵抗するのをやめず、戦って死んだ点。単なる剣術バカではなく、時代の潮流が変わった事も理解しながら、でも、このような転換期には冷静に戦いを止める人も、続ける人もどちらもいていいのでないか、と自分は続ける側にまわる所が非常に印象的。それでいて最後まで涼やかな印象なのがすごい。
歴史は、年表上の出来事ではなく、その時代に生きて動いた人々の必然の結果。この本のように「生きた歴史」を読むとそう思う。
遊女・小稲とのロマンスは泣ける。勝手にいなくなって戦死しようとしている男が「金を工面してくれ」と言ってきて黙って出せる小稲がすごい。出させる男もすごい。
紙の本スキップ
2002/06/26 10:08
たくましい女性像
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
17歳の女子高生・真理子が昼寝から目覚めると、42歳の自分になっていたお話。といっても、この物語はSFではない。SFではないのでこの不思議の理由は全く解明されない。真理子はただ、現実を受け入れて、乗り越えてゆく。42歳、夫と娘がいる、自分の職業である高校教師の仕事、両親が既に死んでいる事実。著者は男性であるのに、実にあざやかに、これらの事実に直面する17歳の少女の心を描いている。
青春まっさかり、まだ将来は「夢」でしかない少女が、突然、職も決まっていて、夫もいて(しかももうだいぶオジさん)、何より女性として「若さ」を失ってしまうショックはどれほどのものなのだろう。当然真理子も悲嘆にくれる。けれど、彼女は本当にたくましい。この「たくましさ」は豪快さではない。ぶつかった問題に泣き、悩み、よく考えて、自分なりの答えを出して行動で示していく。こういう女性のしなやかなたくましさを書かせたら北村薫は天下一品だ。
最初、真理子は教え子の少年にほのかな恋心を抱く。この恋の行方が17歳の真理子の「たくましい成長」を語る一つのハカリになっている。この恋の行方は読んでからのお楽しみに。
何て事はないが、北村薫らしくて、私が好きなシーン。
真理子の夫が、自分の妻の中身が17歳に戻ってしまった事実を知り、でも妻への愛情は変わらない事を示す場面。娘の美也子が
「坊主憎けりゃ袈裟まで」
と言う。
「好きな人の心が17歳でもやはり好きだ、という事なのね」
という意味なのだが、敢えて逆の「憎けりゃ」という表現を使う所が、一見控えめで、でも派手派手しく「愛」を語られるより、よほどしみじみと印象づけられる。
2002/06/19 18:21
ロマンティシズムの極み!
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
不老不死で、人の血や薔薇の花から生気を吸い取って生きるヴァンパイア、「ポー」と呼ばれる一族。人目を避けて、人々の時の流れから置いていかれる孤独感を抱えて、一族の1人である少年・エドガーは生きてゆく。ちょっと昔のヨーロッパを舞台に、エドガーや彼が出会う人々とのドラマが透明感あふれる細い線で描かれている。
ポーは遺伝で増えるのではなく、普通の人間が、ポーに血を吸われ、かつ、ポーの血を与えられた時に、その人間もポーとなる。
エドガーは幼少時、育て親がポーである秘密を知ってしまい、その秘密を守らせられるために、エドガー自身もポーにされてしまう。普通、ポーとなるのは成人してから。成長しない事がバレやすいため。少年のままポーとなり、時を止められてしまった彼は、ひとところに長くはいられない。成長しない「少年」ゆえに、時の流れに置き去りにされる孤独感は人一倍強い。
エドガーが誰かを愛しても、成長しない彼は置いていかれてしまう。置いていかれない為には、その者もポーにするしかない。それは、その者に、自分と同じ孤独感を与える行為に他ならない。
エドガーは作品中で決して多くは語らない。むしろ無口な方である。が、エドガーの哀しみは切々と心にしみてくる。
…などと思ったのは大人になって読んでからで、子供の頃に母の本棚にあるこの作品を読んだ時には、美しい人々が綺麗な舞台で、何だか美々しくてロマンチックな事をやってる、薔薇を育てて生きるヴァンパイア?? わーすてきー、くらいにしか思わなかった気がする。
全体的に、詩的で美しい雰囲気の作品である。