斉藤 律子さんのレビュー一覧
投稿者:斉藤 律子
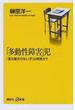
「多動性障害」児 「落ち着きのない子」は病気か?
2000/12/28 12:17
行動療法,薬物療法,環境改善のバランスを説く多動性障害の説得力ある解説書
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
集中力に欠けたり,じっとしていられないなどの症状を併せ持つ「注意欠陥多動性障害」(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorders)は,ここ数年で言葉自体が徐々に浸透し,原因や対処についての情報も増えてきた。しかしこの症状はどこまでが正常で,どこからが異常か判断しにくいうえ,国によって認識や対処方法もさまざまなため,今の日本の社会や日本人という体質,気質に対して,何がいちばんい良い方法なのかはわかりにくい現状がある。
そのような中で,発達障害の医療に携わる小児科医師が記した本書は,多動性障害に悩む多くの親子のストレスを軽減させてくれる良書といえる。著者は子どもの自尊心を大事にしながら,生活上の具体策を提唱し,それを補う形で薬の摂取を勧めている。あくまで行動療法と薬物療法のバランスを重要視する説は,多動性障害の子どもの9割がリタリンなどの中枢神経劇薬を服用している米国の極端な対処療法に警鐘を鳴らすだけでなく,子どもの永い将来にわたって身体に及ぼす薬の影響や,親子関係などを見通した方法論として,十分説得力を感じさせてくれる。
その説得力の背景には,現場医師ならではの「多動性障害の原因」と,リタリンなど「薬物の効果と副作用」に関する記述の詳しさがある。医師という立場だと,どうしても生理学的な部分に偏りがちだが,本書では社会変遷や脳内部に異常を見出す歴史的経緯も踏まえたうえで,今なぜ多動性障害が増えているように感じるのかをわかりやすく解説している。また,薬物療法の事例や服用の意味,他国との比較などから,薬に対して相対化された見解を持つことができる。広い視野とニュートラルな観点で捉えられた本書は,多動性障害を理解する上で非常にバランスのとれた必読書といって良いだろう。
(C) ブッククレビュー社 2000
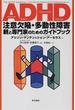
ADHD注意欠陥・多動性障害 親と専門家のためのガイドブック
2000/10/05 00:15
ADHDを概括的に知るための入門書。国内の診断,治療機関や国内サイト,関連書籍などの資料も掲載
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
動きが激しく,何度言ってもすぐにどこかへ行ってしまう。いたずらがひどく,お友達とも遊べず,一人で暴れ回ってしまう。大きな声で一日中騒がしくしゃべり続けている・・・。幼少期のお子さんを持つ親なら,このような子供の抑えきれないパワーに閉口することも多いだろう。しかし,本書はその度合いを超えた,子供も大人もコントロールできないADHD(注意欠陥・多動性障害)についてまとめられたものである。自分の胸の内にしまい込んで悩むよりも,専門家による基本的な知識を身につけることで不安を取り除きながら,今後の対処を冷静に考えるための入門書と言える。
ADHDに限らず,欧米を中心に読書障害や学習障害などがここ10年でマスコミに取り上げられたり,診断や治療方法が一段と進んだこともあって,何か新しい「欧米型のヒステリー性の病態」と誤解している人も多いが,そうではない。症状自体はいつの時代でも存在しているものの「現代社会という枠組みの中」ではやや浮き上がってしまう,特徴的な一連の症状を示す症候群としてとらえられている。
日本国内でも学級崩壊やキレる子供についての問題視が高まる中で,ADHDをはじめ,関連病態の情報が多くなってきた。その中で言えば,本書は英国の書籍のため,薬物治療などの医学的治療や心理学的治療がどれくらい国内の事情と合っているのか,はかりにくい部分がある。また,子供の事例がほとんど掲載されていないので,本文の抽象的な病態表現からは,なかなか不安要素を拭うまでに至らないのではないだろうか。
ただ,国内の診断,治療機関や国内サイト,関連書籍などの資料が掲載されているので,それらを有効に使い,さらなる情報収集をすることが可能である。本書で基礎概論を知り,巻末の情報から次なる対処を考えるための手引き書として利用したい。
(C) ブックレビュー社 2000

パソコン徹底研究4級 パーソナルコンピュータ利用技術認定試験のための 2001年版
2001/05/22 18:18
パソコンの基礎概念と基礎技術を効率よく習得できる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
パーソナルコンピューター利用技術認定試験は,パソコンが日常生活やビジネスに浸透するなかで,企業などの産業分野や教育現場で,より有効に使いこなせるようになるための技術習得の目安として,その有用性が認識されているものである。本書はそのなかの4級受験者のための参考書だ。
4級はパソコンを使いこなすための基礎技術を獲得するもので,本書ではワープロソフトや表計算ソフトによるデータ作成,データベースソフトの利用,インターネットによる電子メールなどを行うための知識や基本操作についてまとめている。
最近では機種によって非常に簡単に操作できるものが多いが,マシンを動かすよりも少し難しい基礎概念を知ることで,パーソナルコンピューターの基礎動作の習得に深みがでるよう構成している。受験者だけでなく,一般読者にもお奨めの基礎習得テキストである。
(C) ブックレビュー社 2000-2001

学生のための初めて学ぶIT(情報技術)
2001/05/22 18:17
現役の高専教師が学生向けにIT(情報技術)の基礎知識を解説。一般も見落としがちな関連知識が身につく
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
IT(情報技術)を,あたかもビジネスシーンでのゴールドラッシュを見るかのようなはしゃぎぶりから,企業も社会もようやく地に足のついた技術理解へとシフトしてきている。そのような中で,より機転の利くIT技術者を育てるための解説書として,高専の学生向けに作成されたのが本書だ。ビジネスや生活にITを取り込むとどうなるかなどについての専門書は多くあっても,情報工学科の授業に適したテキストを目にすることはあまりなかった。
そのニーズに対応するべく,本書は授業を実際に体験している現場の先生によって,学生が身に付けなければならない基礎から応用までが,整然とまとめられている。技術の重要性が声高に言われ,それらを学ぼうとする人々も増える状況で,本書の内容のような基礎知識は,学生のみならず一般読者にも必要不可欠のものである。最新情報が飛び交う分野だが,21世紀をリードする産業技術の基礎を学ぶにはもってこいの解説書である。
(C) ブックレビュー社 2000-2001

図解ヒトゲノム 激変する世界
2001/05/22 18:17
ヒトゲノム(全遺伝情報)の最新動向を,極めてビジュアルに分かり易く解説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
雑誌NEWTONの別冊は,自然科学の幅広いテーマを豊富なイラストなどとともに平易な解説でまとめられたシリーズとして定評がある。本書は,その中でも,1990年代後半あたりから最も動向が注目されているテーマの1つ「ヒトゲノム」(全遺伝情報)について,現状と可能性を探ったものだ。
これまでの研究経過や将来の可能性については,次々とニュースが飛び交うヒトゲノムだが,日々研究成果が発表され,新たな人体のなぞが明らかになっていく状況では,このような情報誌で最新動向をつかんでおきたい。
ヒトゲノムについては主に解析バトル,病気の治療法や新薬開発などの展望が主なニュース内容だが,本書は,リアルなイラストと研究者たちの姿を頻繁に登場させることで,類書が多いこのテーマの解説をいっそう臨場感あふれるものに仕立てている。巻末では,ヒトゲノム解析の基礎知識をおさらいできるよう配慮されているのも助かる。
(C) ブックレビュー社 2000-2001

図解ヒトゲノムのことが面白いほどわかる本 遺伝情報の解読で何がどうなるのか!?
2001/01/07 18:15
社会現象としてのヒトゲノムと,今後の研究をわかりやすく解説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ヒトゲノム解読速度ナンバーワンを誇っていた米国の一企業,セレラ・ジェノミクスといえば,ヒトゲノムのイメージをビジネス色の強い存在として世界中に印象付けた企業だ。また,常に研究とビジネスを効率よく連動させるすばやさに驚かされた反面,営利追究の行き過ぎに世界中から非難を浴びた渦中の企業でもある。80年代後半と90年代は,そのような企業動向とゲノムの可能性に沸いた時代だった。本書はそんな騒動の一部始終と,次に展開されるヒトゲノム研究やビジネス構想についてまとめられたものである。
ところで,さまざまなテーマが多数の図版とともにわかりやすく解説されている「2時間でわかる図解シリーズ」の一冊である本書は,何度文字だけで説明されても混乱をきたしてしまう用語群「ゲノム」「遺伝子」「DNA」「染色体」などの関係性がクリアに図式化されている。また,混乱しやすい専門用語や造語を欄外解説してあるのも理解しやすい。用語や研究工程が複雑でいくら関連書籍を見ても難しい「ゲノム」のようなテーマでは,本書のようなスタイルのものを入門書としてまず一冊目に読んでおくとよいと思われる。
世界的に加速するヒトゲノム研究の今後については,研究内容を俯瞰する形で解説されているが,多くの遺伝子関係の書籍ですでに述べていることが多く,やや深みに欠ける。前半が社会現象としての興奮が伝わってくるので,後半も研究最前線や研究者の課題や問題点などについてもう少し踏み込んだ内容がほしかった。しかし,「これほど知ることのすばらしさ・面白さを教えてくれる科学技術はかつて存在しなかったと思う」と筆者も述べているとおり,「これから」のヒトゲノム研究動向は目が離せない。次々配信されるゲノム関連ニュースに対する「免疫」を備える意味で,手軽に読み進められる好著である。
(C) ブッククレビュー社 2000
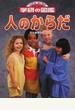
人のからだ
2000/12/28 12:18
身体の神秘がリアルに実感できる,子ども向け人体図鑑の決定版
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
多くの子どもにとって図鑑は「世界観が広がる玉手箱」である。精密な写真やイラスト,仕組みの解説,人類の壮大な計画や計り知れない歴史まで,そのスケールは知識欲を満たしてくれる。子どもたちはここで自分の興味の行方を模索し「お気に入り」の巻を繰り返し見続けるが,とりわけ自分の身体の仕組みがわかる人体ものは人気が高いという。
本書はそんな図鑑の製作で長年の実績を持つ学研から出版された,ニューワイドというシリーズの人体図鑑である。かつて一世を風靡(ふうび)した前「学研の図鑑」シリーズの同タイトルと比較をすると,前作が生理学的な要素に絞られているのに対し,本書は現代社会が及ぼす人体への影響までも包括されており,内容の幅が広がっている。また,新しい写真が多く掲載されていることや,最新医学情報がわかりやすく盛り込まれていて,自分の身体と今を生きることをリアルに直結させることができる。
(C) ブッククレビュー社 2000

目で見る食品カロリー辞典 市販食品&外食編2001年最新版
2000/12/28 12:18
外食中心の女性にうれしいカロリー図鑑
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
普段忙しいために外食や市販食品を摂取することの多い女性にとって,ダイエットをする際のカロリーコントロールは至難の技である。最近では商品にカロリー表示をしているものが増えてきたものの,表示のないものも多く,商品を前に購入を迷うことも少なくない。本書はそんな状況下の人にうれしい,1200点もの市販食品と外食,コンビニ・ファーストフードなどの最新のカロリーをまとめたハンドブックである。
各食品は「アイス」「アルコール飲料」「インスタント麺」のようにグループごとにまとめて「あいうえお」順に並べてあるのと,各コンビニエンスストア,各ファミリーレストランごとに商品やメニューのカロリーが表示されているので,とても見やすく利便性が高い。巻頭の「タイプ別・やせるコツ」というワンポイントアドバイスからは,自身の太る原因が明確に浮かび上がってきて,自分にあった方法論を模索することもできる。
(C) ブッククレビュー社 2000
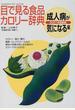
目で見る食品カロリー辞典 成人病が気になる編2001年最新版
2000/12/28 12:17
生活習慣病を防ぐための身近なカロリー手引書
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
成人病は中年以降のものだから関係ない−−そう考えていると,あとで痛い目に合うのではないかと思えるほど,最近の食事情やライフスタイルは「黄信号」が点滅している。10代でも肥満や高血圧,コレステロール値の高い人が増え,20代女性に至ってはダイエットのしすぎで骨密度が低下してしまう。このままでは老化速度が速まるばかりで,長寿国もいずれは下降線をたどるかもしれない。そうならないために,本書を利用しながら,いま一度自分の食事内容を見直すことをお勧めしたい。
栄養のバランスだけでなく,塩分や糖分,脂肪分のコントロール,ビタミンなどの採り方についてアドバイスが掲載され,後半部分には和食,洋食,中華・韓国風料理,主食,コンビニエンスストアの食品,ファーストフードのカロリーが,インデックス式に検索できるようになっている。忙しい人でも次の食事からでもすぐに利用できる,ヘルシー食生活への近道となりそうな1冊である。
(C) ブッククレビュー社 2000

高脂血症を予防し、血液をサラサラにする献立と料理120品 心筋梗塞、動脈硬化を防ぎ、血管をしなやかにする!
2000/12/28 12:17
抗酸化作用を高めるための手軽なレシピ集
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ここ50年ほどのあいだ,欧米食の増加やライフスタイルの変化によって,日本人の身体も欧米化してきた。そのおかげで動脈硬化や心臓病が増え,そこへ前首相が脳梗塞で他界した件も重なり「抗酸化作用」を高めるための食事内容や,生活習慣の見直しについていっそう関心が高まっている。
本書はそのような読者の要望にこたえた「血液をサラサラにする」ためのレシピ&メニュー集である。著名な心臓外科医の監修と,医療と直結した栄養指導のキャリアを誇る管理栄養士によるレシピからは,適正なエネルギーとバランスのとれた栄養を考慮した1週間のメニュー例をはじめ,不飽和脂肪酸や抗酸化ビタミン,食物繊維の上手なとり方などが的を絞って紹介されている。健康管理に気遣う毎日の食生活に欠かせない,手軽で便利な献立集といえる。
(C) ブッククレビュー社 2000
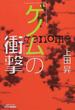
「ゲノム」の衝撃
2000/12/28 12:16
日本のゲノム研究をスピードアップするためには,産学官の連携が課題
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ヒトゲノムの解析について,日本は欧米に遅れをとってしまった−−そんなイメージが定着している昨今だが,いったいなぜそうなったのか,そもそも日本のゲノム研究はどのように進んできたのか。本書はそんな疑問が一気にわかる,国内のゲノム研究の経緯と産業動向をまとめたものである。丹念な取材に加え,ゲノム研究の第一線で活躍している研究者のインタビューも間にはさまれており,課題や問題点,成果などがクリアに伝わってくる。
ところで欧米では,ビジネスチャンスを多分に含んだこの研究の達成のための近道として,産業と研究者と国−−いわゆる産学官の連携プレーの形を成熟させてきた。しかし日本では,この産学官のバランスが悪く,立ち遅れの一因となっていることが随所から感じられる。この問題は他の分野の研究においても同様に危ぐされるもので,研究活動の構造に対する警鐘ともなっている。
しかし最近では巻き返しを図って,多くの研究成果をあげていることも事実だ。本書では,毎日の新聞では追いきれない,各企業や研究者による医療,食品,情報技術などの有意義な研究内容が多数紹介されていて,研究現場を一望することができる。また専門家たちのインタビューからは,期待の裏側に存在する多くの課題や問題が指摘され,地に足のついた研究進展を理解することができる。
それにしても,特許戦争が繰り広げられる中での研究がいかに大変かは,一般人には計り知れないものがある。印象深いのは,これだけ速さが求められる研究でありながら,バイオインフォマティクス(生命科学の研究に情報技術を活用すること)の予算,人材が足りていないということだ。ヒトゲノムの解析の遅れを教訓に,産学官の連携が発揮されるかどうかが,本当の意味での次の段階での成果につながっていくだろう。
(C) ブッククレビュー社 2000

脳外科医だからできること
2000/12/28 12:16
脳外科手術数全国一の医師による,32年間の奮闘記
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は脳外科手術数全国一の医師による,32年間の軌跡を綴った手記である。脳外科という現場であるが故に,たくさんの生死の瀬戸際を見つめてきた著者は,脳死判定や臓器移植をとおして「死生観」「医師のあり方」を思索し,医師としての人間性をいかに高めるかを追究している。
また,エッセイの合間の「脳外科一口メモ」というコラムには,脳外科のかかり方や,良い医師とめぐり合うためのヒントが掲載され,患者への思いにあふれた気配りがされている。どれだけ医療技術やインフォームド・コンセントが向上しようと,結局患者は医師の人間性によって救われる部分が大きい。本書はそんな患者側の思いに応え,日々鍛錬し続けている医師の真摯(しんし)な姿勢に触れることができる。手記であるためいささか個人的すぎる記述もあるが,医療事故が多く医師や病院に幻滅するなかで,病の折にはこのような名医に出合いたいものだと思わせる一冊である。
(C) ブッククレビュー社 2000

目で見る食品カロリー辞典 おかず・素材編2001年最新版
2000/12/28 12:16
カロリーを見ながら「食べながらダイエット」の基本を実践
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ダイエットの基本は適度な食事と運動に尽きるが,その「適度」の見極めが難しい。特に食事を見直す際に,ついストイックになりすぎたり偏ったりして,リバウンドや体調不良を経験している挫折者も多いのが現状だ。そのような失敗経験者は,ぜひ本書を利用して「きちんと食べながらダイエットをするとはどういうことか」と基本に立ち返ることをお勧めしたい。
本書はダイエット方法論はほんの巻頭で説明しているだけだが,少ない文字量の中にもやせるだけではなく,健康的できれいになることも兼ね合わせたアドバイスが掲載されている。その上で主内容である素材やおかずのカロリーを把握すれば,確かに食事とうまく付き合っていけそうな気がしてくる。これまで素材のみのカロリーが掲載されたものはあっても,自分の食べたおかずがおおよそどれくらいのカロリーか一目でわかるものはなかったので,とても便利で手軽な1冊といってよいだろう。
(C) ブッククレビュー社 2000

元気がでるサプリメントの本 お肌が気になる、ダイエットしたい、毎日疲れぎみ、冷え・肩こり・便秘・疲れ目・生理痛……なんとかしたい! そんなあなたに必要なサプリメントは?
2000/12/28 12:15
サプリメントを効率よく摂取できる,お役立ちハンドブック。美容・現代疾患,生活習慣の改善など目的別に
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
栄養のバランスとカロリーを考えて食事のコントロールをしても,どうしても補いきれない微量栄養素。それらをサプリメントで摂取するときに,何をどれくらい,そしてどう取ったらよいのか−−本書はそのような疑問を持つ人々にお薦めしたいサプリメント図鑑である。「美肌になりたい」「ダイエットをしたい」「疲労を軽減したい」「冷え・肩こり・便秘・生理痛を治したい」「ストレスから開放されたい」など,美容・現代疾患,生活習慣の改善のための目的別お薦めサプリメントが紹介されていて,自分の状況に応じて検索することができる。またどのようにサプリメントを取れば効率よく栄養素が摂取できるか,ワンポイント・アドバイスが掲載されているのもうれしい。
このように成分や目的,価格などからおおよそ自分に合ったものを選ぶことができる一方,摂取方法によってはまったく効果がなかったり,それどころか害になることもあるなどの注意点を補う記事が少ないのが残念だ。また,本書はあくまで商品紹介と購入のためのお役立ち情報がメインなので,「現代女性の食生活やライフスタイルから,どう食事をとり,どうサプリメントで補うか」という部分に関する医師や管理栄養士のアドバイスがなく,説得力に欠ける。そこが欠落すると個人の感覚のみでサプリメントを摂取するしかないため,いささかサプリメント至上主義的な印象を受けざるを得ない。
ただ,商品購入のための情報は多様に紹介されていて,単に商品を選ぶだけであれば非常に楽しい読み物となっている。ショップやカタログ,インターネットなどで商品情報をさらに得て,自分なりに商品比較をした上で必要なものを必要なだけ摂取すると心がけていれば,本書は力強いサプリメント・バイブルとして活躍してくれることと思う。なによりも,若い女性のヘルシー・ケアのための意識改革に一役買いそうな一冊である。
(C) ブッククレビュー社 2000

ウイルスの正体を捕らえる ヴェーロ細胞と感染症
2000/12/16 21:15
ウイルス解明とワクチン製造の立役者,ヴェーロという不死の細胞のすべてを解説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
目に見えない細菌やウイルスは,時に歴史の事件として名をとどろかせ,衛生事情が良くなろうとなるまいとその都度環境に合わせて発生し続ける厄介な代物である。しかし,知らず知らずのうちに忍び寄る死の恐怖を尻目に,研究者たちはいかにしてそれらの性質を解明し,救世主ともなるべき効率のよいワクチンを作り上げてきたのか−−。本書は細菌やウイルスの正体を探りながら,ウイルスの性質解明やワクチン製造に多大な貢献をなした「ヴェーロ」という不死の細胞について解説されたものである。
ところで,専門家以外ではウイルスや細菌とは何かと聞かれても,その違いや人類への悪事を説明できる人はほとんどいないだろう。著者はウイルス学の先端を走ってきた筋金入りの研究者であるにもかかわらず,そのような専門的な知識を一般読者にもわかりやすく平易に解説している。しかも,地球史というスパンの中で細胞とは何か,いかにして地球上に細胞ができたかなど,微生物の歴史をもひもときながら知的好奇心を十分満たす筆致でまとめられている。
ヴェーロ細胞においては,これほどウイルスの性質を明らかにし,ワクチンを安全にしかも大量に生み出した「ウイルス解明の立役者」はほかにはないと感じさせる驚きの不死細胞である。またそれが日本で生まれたというから感慨深さもひとしおだ。ポリオから人々を救うために生まれたヴェーロ細胞は,その後ラッサ熱,エボラ出血熱などの診断に使われ,またジフテリア菌や大腸菌O-157の解明にも利用されている。その研究過程は想像以上に大変なものだが,研究者の飽くなき追及とヴェーロ細胞の活躍ぶりからは,日本の科学者の研究魂がひしひしと伝わってきて,現代を生きる私たちを支えてくれていることに改めて気づかされる。
(C) ブッククレビュー社 2000


