川村 卓さんのレビュー一覧
投稿者:川村 卓
| 7 件中 1 件~ 7 件を表示 |

中盆 私が見続けた国技・大相撲の“深奥”
2001/02/09 17:09
初心者にとっては、大相撲の裏入門書にもなりうる“良心的な暴露本”
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
実業団で鳴らしていた板井が、22歳の初土俵から史上最速の5場所で十両に駆け上がっていく出世物語は痛快。しかし、ほどなく八百長仲間に取り込まれていく。
星の貸借システムの実態は読んでのお楽しみだが、基本的には1勝借りたら1敗しなければならず、ガチンコに強くないと昇進も地位の維持もおぼつかない。板井によれば、八百長常習の千代の富士はガチンコでも最強だったという。幕内在位54場所、最高位小結の板井もその意味では実力者であり、八百長調整役の「中盆」を勤めたからには“人望”もあったのだろう。
若貴兄弟らガチンコ派の台頭により八百長派が衰退するなか、1991年9月場所を最後に廃業した板井の軌跡は、バブル期を泳いだ男の一典型ともいえる。板井のシニカルな語り口を活かしつつ、恨みつらみを抑えた構成(鵜飼克郎)は堅実で、専門用語や人物などの注記も行き届いている。初心者にとっては、大相撲の裏入門書にもなりうる“良心的な暴露本”だ。
読了後、大相撲への興味や愛着が以前より増したことを正直に告白しておきたい。

武学入門武術は身体を脳化する
2001/02/09 17:06
門外漢にとっては現実世界での生き方指南の書として読むことも可能。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
4年前に都内の某書店で開催されたプロレス・格闘技本ブックフェアの売上トップは、なんと『唯脳論』(養老孟司著)だった。格闘技、ことに武道・武術系には、技法解説ではなく、思想、哲学、身体論などと近親性を示す著作が少なくない。
稽古を通じて精神対肉体の二元論が超克されるというイメージ、あるいは「身体=脳」といった表現が違和感なく受け入れられる文化圏が確実にある。著者がこちらを正視している表紙にはちょっと緊張してしまうけれど、「往(い)なす」をキーワードに、格闘技的な対立・対抗の次元を超えた身体のあり方を種々の逸話を交えながら説いていく本書の姿勢は懇切丁寧で、神秘主義等とは無縁。
ふと立ち止まりたくなるような言葉にそこかしこで出会うこともでき、門外漢にとっては現実世界での生き方指南の書として読むことも可能。著者はわかったつもりの“つもり”を戒めるが、気軽に勝手に遠慮なく柔軟に読んでしまう読者をどうか許したまえ。

果てなき渇望 ボディビルに憑かれた人々
2001/02/09 17:17
筋肉美を競う世界を通じて、人間という不思議な生き物の諸相が鮮烈に浮かび上がってくる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
競技としてのボディビルは、健康管理やダイエットのための運動までを含む広義のボディビルとは別世界だ。細部に分けると300を超える各筋肉をくまなく鍛え上げ、力強い厚みと繊細さを備えた立体感を実現するためには、才能と素質に恵まれた人でも10年以上を要するという。もはや“マッチョ”と揶揄して済むような対象ではない。
かつて三島由起夫をコーチした人の回想から始まる本書は、コンテストに生きるビルダーの生活を追い、筋肉美の追求と“女らしさ”との間で性差の問題にも向き合わざるをえない女子ビルダーの内面に迫る。さらには、ドーピング検査がきびしい日本とは違い、公然とドラッグが使用されているアメリカのプロビルダーの仲間入りを夢見て、副作用覚悟でステロイドを使いながら異形への道をめざす日本人ビルダーの慄然とするような日常が紹介される。最終章には、健全な生涯スポーツとしてのボディビルに取り組む高齢者ビルダーが登場。
筋肉美を競う世界を通じて、人間という不思議な生き物の諸相が鮮烈に浮かび上がってくる、読みごたえ十分のノンフィクションである。
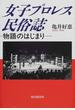
女子プロレス民俗誌 物語のはじまり
2001/02/09 17:14
花も実もあるシュートなプロレス本の誕生だ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
プロレスを観客の存在抜きに語ることはできない。客層の劇的なまでの変化とリンクしながら今日に至っている女子プロレスはとくにそうである。
女子プロレスを広く芸能ととらえ、その興行形態に民俗学的なアプローチを試みるだけでもユニークだが、それは本書の一面にすぎない。一人のファンとしてコアなファンたちの行動に密着するだけでなく、女子プロレスラーとしての自意識のありようをアジャ・コングに、また一人前の女子プロレスラーになっていくプロセスを天野理恵子(現カルロス天野)に直接問いかけ、彼女たちから生きた言葉を引き出したように、接近戦にも強さを発揮。その上で、従来のプロレス論を踏まえつつ、やる側と見る側の相互に関係し合うメカニズムに迫っていく展開は、どこよりもプロレス会場を自らのフィールドワークの地と定めた著者ならではの説得力をもつ。
メディアとの影響関係、ジェンダー、ルーツとしての女相撲など、本書の中で掲げられている諸課題が今後どう解き明かされていくのか、早くも次作に期待を抱かせてしまう、花も実もあるシュートなプロレス本の誕生だ。

吾輩は「黒帯」である 日本人拳士ロンドン道場痛快修行記
2001/02/09 13:16
例の五輪柔道の“誤審”騒ぎを冷静に考えるためのヒントにもなる好著。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
少林寺拳法を1年半ほど習った林青年は、語学留学先のロンドンでもさっそく現地道場の門を叩いた。日本国内ではたいてい1年ほどで初段に昇進する。林青年も黒帯だったが、英国では「ブラックベルト」は特別視され、試しのパンチまでが飛んでくる扱いだ。今までどおりに練習を続けたかっただけなのに、頭一つ大きな連中を指導するはめになった著者は、「はからずも、ふたつの精神文化がぶつかりあう最前線」に立たされる。
“月謝を払って習う以上、弟子は師匠と対等”がジョーシキであるような、デモクラシーの本場にして多民族が共存する都市での、文字通り体を張っての異文化交流の日々。軽妙洒脱に語られるエピソードの数々は読む者をまったく飽きさせないばかりか、あやしげな“カンフー”や“ジュージツ”までが跋扈する地球の裏側の「武道」のあり方を鏡にして、私たちの先入観や誤解をも映し出す。「もっとも武道を理解していないのは、実は日本人ではないのか」との指摘は鋭い。例の五輪柔道の“誤審”騒ぎを冷静に考えるためのヒントにもなる好著。

猪木語録 闘魂伝書世紀末篇
2001/02/09 13:13
「信者」には溜飲が下がる待望の“伝書”。非「信者」にもエキサイティングな“言葉の猪木プロレス”。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
現役時代の後期には体が理念についていかず、言葉倒れの印象を免れなかった猪木だが、引退によって肉体的制約から解放されたことで思う存分“猪木らしく”振る舞えるようになり、再び影響力を強めつつあるように見える。
いつも会場を沸かせる「元気ですかーッ!」「ダーッ!!」は猪木の道化的な一面にすぎない。“「闘い」はあるが「プロ」としては欠落した部分がある『PRIDE』と、表現としては「プロ」ではあっても「闘い」が薄れて魅力が失われている新日本を含めた「プロレス」の双方をつなぐ”との抱負など、自らが直接かかわるビジネスや小川、藤田などのレスラーに関するコメントはもとより、「格闘芸術」「シュート」「命懸け」「プロフェッショナル」等々の命題についてしゃべりにしゃべる猪木。
その饒舌にはもともと定評があるが、時に不可思議な飛躍をはらむ論理展開がいかにももっともらしく感じられるのも、猪木ならではの呆れるばかりの説得力というほかない。「信者」にとっては溜飲が下がる待望の“伝書”であり、非「信者」にとってもエキサイティングな“言葉の猪木プロレス”だ。

猪木詩集 馬鹿になれ
2001/02/09 13:06
何事も必然にしてしまう魔力が「アントニオ猪木」という人、否、“運動体”にはそなわっている。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1998.4.4の引退セレモニーで、
「この道を行けば/どうなるものか−−迷わず行けよ/行けばわかるさ」とやって観客を驚かせた猪木がついに出した詩集。
何事も必然にしてしまう魔力が「アントニオ猪木」という人、否、“運動体”にはそなわっている。作者が「猪木」であることの意味が内容に先行してしまうのは仕方ないが、作品それぞれはシンプルながらなかなか堂に入っており、よくあるタレント本の水準をはるかに抜く。
「悲しみを心に集めて/真夜中に/泣いてみた」(泣いてみた)や「本当の自分も/笑ってた−−/それくらい/馬鹿になれ」(馬鹿になれ)のような劇化したモノローグもあれば、飢餓のソマリアに取材した「悠々と空を舞う禿鷹(はげたか)に向かって/俺は腹の底から叫んでいた/「ばかやろうっ!」/この絶叫(こえ) 地球の果てまで響け」(生き地獄)といった猪木らしい言葉の配置と見得、「シルクロードをバイクで疾走した夏/砂漠に見た蜃気楼のように/夢はどこまでも/俺を誑(たぶら)かす」(蜃気楼)のような作者の生の内実をうかがわせる一節もあって、生半可な読みとばしを許さない。
「詩人猪木」はたんなるシャレではなかった。
| 7 件中 1 件~ 7 件を表示 |


